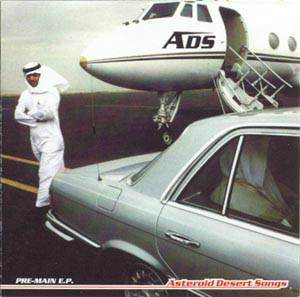これは待望の、と言っていいだろう。サンズ・オブ・ケメットの元一員、最近ではザ・スマイルのメンバーとしてのほうが有名かもしれないが、UKジャズ・シーンを支える俊英ドラマーが初のソロ・アルバム『Voices of Bishara』をリリースする(ちなみにハロー・スキニー名義ではすでに2枚アルバムを発表済み)。レーベルは〈Brownswood〉で11月4日発売。
ちなみに、『Voices of Bishara』というタイトルは先日亡くなったチェリスト、アブドゥル・ワドゥドの77年のファースト・アルバム『By Myself』にちなんでいる(レーベル名が〈Bisharra Records〉)。やはり彼の影響力は大きいのですな。
この秋注目の1枚、チェックしておきましょう。
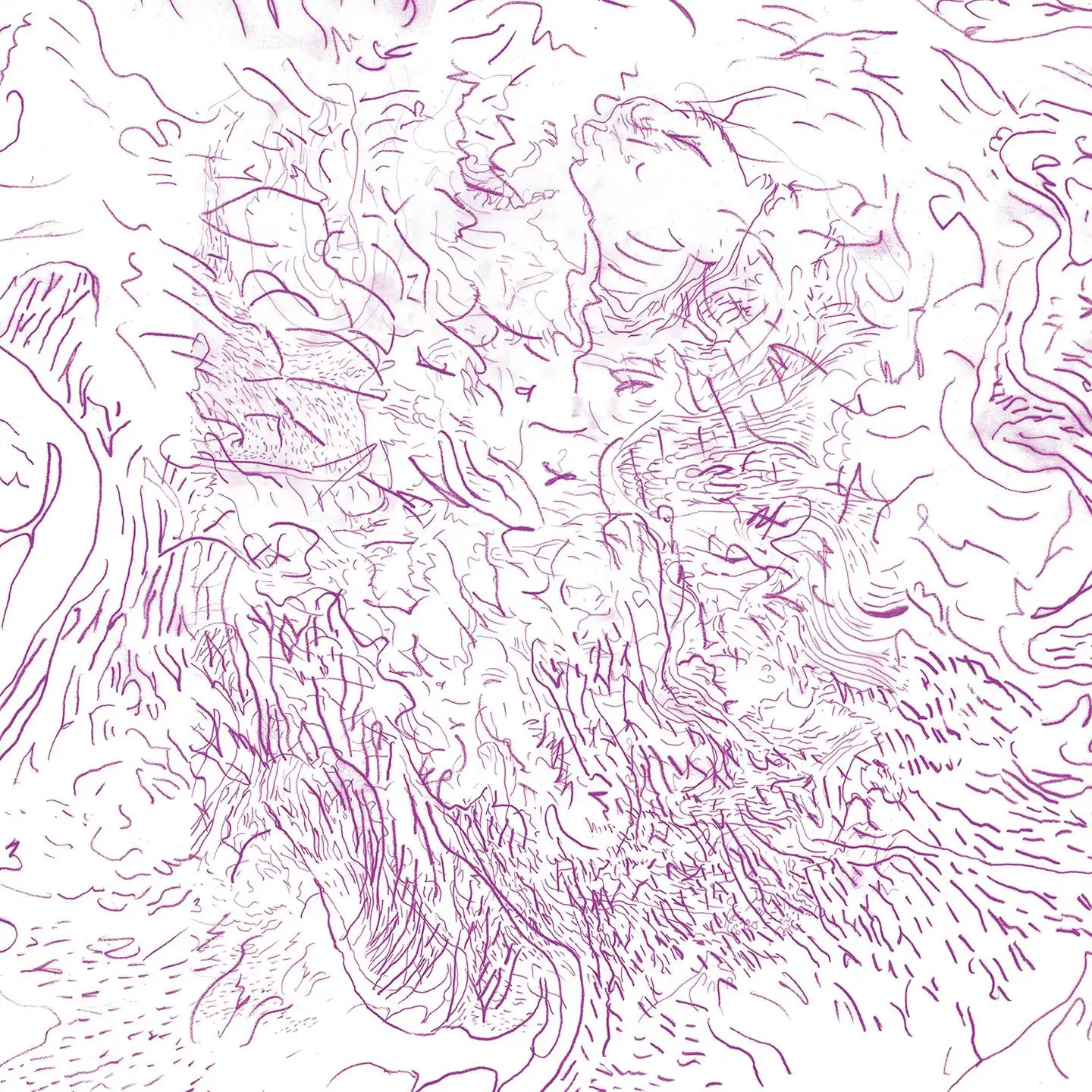
Tom Skinner
トム・スキナーが自身名義では初となる
アルバム作品『Voices of Bishara』を発表
レディオヘッドのトム・ヨークとジョニー・グリーンウッドと
共に組んだバンド、ザ・スマイルやシャバカ・ハッチングスの
サンズ・オブ・ケメットでの活動でも知られる鬼才ドラマー!!
このレコードは、不正直さと偽情報が増加する時代に、コラボレーションとコミュニティを通して、何か真実のものを世に送り出す試みである。"Bishara" とは良い知らせをもたらす者であり、このアルバムに参加するミュージシャンは、私にとって非常に大切な存在で、この考えを尊重し、集団で暗闇が広がるところに光を広げるのである。 ──Tom Skinner
ドラマーでありプロデューサーでもあるトム・スキナー。レディオヘッドのトム・ヨークとジョニー・グリーンウッドと共に組んだバンド、ザ・スマイルやUKジャズの最高峰と言われるロンドンを拠点に活動するテナー・サックス奏者シャバカ・ハッチングスのサンズ・オブ・ケメットでの活動でも知られる鬼才が、トム・スキナー名義では初となるアルバム『Voices of Bishara』を発表! 新曲 “Bishra” が公開されている。
Tom Skinner - Bishara
https://youtu.be/B5CbxJu2cAY
本作は星の数ほどあるレコーディング・セッションを編集し、タフで魅力的な新しいサウンドを実現した無駄のない美しいアルバムだ。タイトルは、スキナーが隔離期間に繰り返し聴いていたチェリスト、故アブドゥル・ワドゥドの超レアな1978年のソロ・アルバム『By Myself』にちなんでいる。ワドゥドのアルバムは彼自身のレーベル〈Bisharra〉から自主リリースされたもので、スキナーの作品タイトルではアラビア語の綴りを使用しているが、どちらも同じ意図、意味を持っている。それは「良い知らせ」または「良い知らせのもたらす者」と訳される。
『Voices of Bishara」はトム・スキナーがロンドンのブリリアント・コーナーズで行われたセッションにミュージシャンの友人たちを誘ったところから始まった。このレギュラーイベントは、クラシック作品をフル再生し、それに対して即興で応えるというシンプルな形式をとっている。その夜は、ドラマーのトニー・ウィリアムスが1964年にリリースした作品『Life Time』に焦点を当てて行われ、彼と彼の友人たちが作り出した音楽は、Skinnerにアルバム1枚分の新曲を書かせるほど特別なものとなった。
スキナーは、チェロ奏者、ベース奏者、サックス奏者2人とともに、全員が同じ部屋にいる、クラシックなスタイルで録音を行った。彼はその音楽を家に持ち帰り、他の多くのプロジェクトの合間に編集を行った。その後スタジオ録音の段階へ移行し、その崇高な特質を際立たせながら、徐々に新しいアルバムの形が現れ始めた。
ハサミを自由に使って、楽器間の編集を徹底的にやり始めた。そうすると、音楽に新しい命が吹き込まれたんだ。私は、セオ・パリッシュのように、曲を切り刻んだり、セクションをループさせたりする偉大なディスコのリエディットからヒントを得たんだ。私は純粋主義者ではない。過去にとらわれたくないんだ。音楽をいじくりまわして、何が起こるか見るのは本当に力になった。それが正しいことだと感じたんだ。 ──Tom Skinner
結果として、タイトでヒプノティック、そして唯一無二な音楽が完成した。『Voices of Bishara』は、時代を超越した深く感情的な音楽で構成されており、卓越したハーモニーの深みと質感を備えている。チェロとベースが織りなす深いハーモニーに支えられ、豊かな音世界の中を舞い上がる。もちろん、グレース・ジョーンズからジョニー・グリーンウッドまで様々なアーティストが賞賛を送るトム・スキナーのパーカッシブなマジックも収められている。
私たちは個々の声であり、集合的に集まっている。このアイデアは、私たちが集合することで、よりポジティブな何かをもたらすことができるというものだった。何かの始まりなんだ。 ──Tom Skinner
トム・スキナー名義での初となるアルバム『Voices of Bishara』は帯付きの日本流通仕様盤のCDと輸入盤CD、そして輸入盤LPとデジタルで11月4日に発売!


label: Brownswood Recordings
artist: Tom Skinner
title: Voices of Bishara
release: 2022.11.04
BEATINK.COM: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13009
Tracklist
1. Bishara
2. Red 2
3. The Journey
4. The Day After Tomorrow
5. Voices (of the Past)
6. Quiet as it's kept