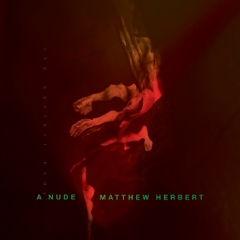 Matthew Herbert A Nude (The Perfect Body) Accidental/ホステス |
人間が生きていくうえで、不可避的に身体が立ててしまう音=ノイズを用いて音楽を創ること。マシュー・ハーバードが新作で実践したコンセプトである。起床から睡眠まで。体を洗い、何かを食べ、トイレにゆく。それらの音たちは、極めて個人的なものであり、必然的に人間の「プライベート/プライバシー」の領域問題を意識させてしまう過激なものでもある。いわば音/音楽による「裸体」?
そう、マシュー・ハーバートが新作で実践したこのコンセプトは、「音楽」における「裸体」の概念を導入する、という途轍もないものなのだ。むろん、いうまでもなく「映像」と裸体の関係はつねに密接であった。ファッションフォトであっても、ポルノグラフィであっても同様で、いわばジェンダーとプライバシーの力学関係が複雑に交錯する「政治」空間であったともいえるだろう(政治とは力学である)。同時に芸術においては「裸体」は、普遍的ともいえる主題でもあった(ヴィーナスから村上隆まで)。裸体、それはわれわれの知覚や思考に対して、ある種の混乱と、ある種の意識と、ある種の美意識と、ある種の限界を意識させてしまうものなのである。
では、映像が欠如した「音楽」のみによる「裸体」の表現は可能なのか。ハーバートは身体の発するノイズ、そのプライベートな領域にまでマイクロフォンを侵入させ、それを実現する。急いで付け加えておくが、それは単なる露悪趣味では決してない。そうではなく。そうすることで、人間の身体のたてる音=ノイズを意識させ、聴き手にある自覚を促すのである。われわれは、何らかに知的営為を行う「人間」であるのだが、同時に日々の生存をしていくために「動物」として音を発する。これは極めて当たり前の行為であるはずなのだが、われわれの社会は「人間」が「人間」であろうとするために、その動物性を綺麗に隠蔽する。
彼は、2011年に発表した『ワン・ピッグ』において、一頭の豚の、誕生から食肉として食べられるまでの音を再構築(サンプリング)し、「音楽」としてリ・コンポジションしていくことで、われわれの視界から隠蔽される食肉の問題を「意識」させたが、本作においてハーバートは「身体の発する音」を極めて美しいエクスペリメンタル・ミュージックへと再生成することで、われわれが発する「音」(動物的な?)のありようを「意識」させていくのだ。映像から切り離された音たちは、ときに自律性を発しながらも、ときに音それじたいとして主張をし、ときに元の状態がわからないサウンド・エレメントに生成変化を遂げたりもする。だが、それでも聴き手は「この音は、生活していくうえで、生物としての人間が、ごく当たり前に発する音」だと意識せざるを得ない。ハーバートが求めるものは、それである。「意識していないものを意識させてしまうこと」。それこそがサンプリング・アーティストとしての彼が「社会」に仕掛けていく「革命」なのではないか。
しかし同時に、本作に収録された「音楽」たちが、とても美しい点も重要である。彼はまずもって才能豊かな音楽家だ。とくに本作のディスク2に収録された楽曲を先入観抜きで聴いてほしい。OPNやアンディ・ストットに匹敵するインダストリアル/アンビエントが展開されている、といっても過言ではない。だが、この美しいエクスペリメンタル・ミュージックたちは、ときに人間の排便の音で組み上げられているのだ。ハーバートは「ボディ」(ある女性とある男性だという。そしてハーバート自身の音は入っていない)の発する音の群れと、「音楽」のセッションを繰り広げているというべきかもしれない。
今回、マシュー・ハーバートから本作について、社会について、興味深い言葉を頂くことができた。サンプリングが社会的な行為であり、同時に破壊でもあるとするなら、本作は、いかなる意味で「音楽」といえるのか。このインタヴューは、衝撃的な本作を聴く上での最良の補助線になるだろう。このアルバムを聴き、このインタヴューを呼んだあなたは、もはや「自分の発する音」に無自覚ではいられなくなる。
■Matthew Herbert / マシュー・ハーバート
1972年生まれ。BBCの録音技師だった父親を持ち、幼児期からピアノとヴァイオリンを学ぶ。エクセター大学で演劇を専攻したのち、1995年にウィッシュマウンテン名義で音楽活動をスタートさせる。以降、ハーバート(Herbert)、ドクター・ロキット、レディオボーイ、本名のマシュー・ハーバートなどさまざまな名義を使い分け、次々に作品を発表。その音楽性はミニマル・ハウスからミュジーク・コンクレート、社会・政治色の強いプロテスト・ポップに至るまでジャンル、内容を越え多岐にわたっている。また、プロデューサーやリミキサーとしても、ビョーク、REM、ジョン・ケール、ヨーコ・オノ、セルジュ・ゲンズブール等を手掛ける。2010年、マシュー・ハーバート名義で「ONE」シリーズ3作品(One One, One Club,One Pig)をリリース。2014年には4曲収録EPを3作品連続で発表。2015年には名作『ボディリー・ファンクション』『スケール』を彷彿とさせる全曲ヴォーカルを採用した『ザ・シェイクス』をリリースし、来日公演も行った。
世界をいまのままの状態で受け入れることに歯止めをかけるために。大切なもののために。闘い始めるために。探したのは逸脱したサウンドだ。
■どうして、このようなコンセプトでアルバムを作ろうと考えたのですか?
MH:僕が考えていたのは、まず、サウンドを使って「世界を変えたい」ということだった。いま、世の中は間違った方向に進んでいると思う。だから僕は、それを変えたい。もしくは衝撃を与えたい。ただ、人にショックを与えて終わりではなく、みんなの考え方や受け止め方をそれによって変えることができればとも思っている。そして僕らが人生を送っていく上でのありきたりのパターンを混乱させるんだ。世界はすごい勢いで、どんどんおかしなことになっているからね。ドナルド・トランプしかり、ファシズムの台頭しかり、気候の変化しかり、核兵器しかり。僕らは、いまの自分たちのあり方を急いで変える必要があると思う。というわけで僕は予定調和を壊すようなサウンドや発想を探し求めた。世界をいまのままの状態で受け入れることに歯止めをかけるために。大切なもののために。闘い始めるために。探したのは逸脱したサウンドだ。たとえば、ショッキングだったり、不快だったり、あるいは耳馴染みがなかったり、奇妙だったり、そういう感覚を促す音だ。それは何だろう? と考えたとき、思い至ったのが自分自身の音、できれば聞きたくない音だったんだ。他人がトイレに行く音とか、そういう聞きたくない音に耳を向けていく。あ、そういえば日本には、自分の「その音」を、ほかの人が聞かなくて済むように音を隠すシステムがあるよね(笑)?
■はい(笑)。
MH:他人が大便をする音なんていうのは誰も話題にはしない。誰もがやっていることなのに、それってすごく不思議だよね。誰もがすることなのにさ。何も特別なことじゃない(笑)。そんな「誰もがせざるを得ないことなのに」というのが、ひとつの出発点になったんだ。「そうか、僕がまず理解すべきなのは他人の肉体に感じる違和感なのかもしれない」と。そのためには誰か他人の肉体の音を録音してみる必要があるなと考えはじめて、それから何カ月か経ったところで僕は、それは、つまり、「ヌード」ってことだと思い当たったんだ。「裸にむき出しになるということだ、なるほど!」と。まあ、そんな感じで6カ月から8カ月ぐらいかけて発展していった発想なんだよ。ある日、目を覚ましたら急に「そうだ、これをやろう!」とひらめいたわけではない。少しずつ少しずつ、毎日そのことを考えていくうちに、そう、植物のように水をやり続けていたら、ある日、「あ、これってサボテンだったのか!」「あ、メロンがなったぞ!」となるような感覚だね。ここに至るまでのプロセスは、まさに進化の過程だった。
「ボディ」に、つまりは互いの存在に耳を傾け、受け入れる必要があるんだ。突き詰めれば人はみな同じ。女王様だってウンチはするし、カニエ・ウエストだってそう。
■日本のトイレの消音システムは「自分の音を聞かれたくない」という感覚なんですよね。
MH:ああ……、だとしたら、それはそのまんまいまの世界がはらんでいる危険性だと思うよ。この資本社会において「もっとも重要な人物は自分である」と思い込まされて人は生かされているんだ。すべて自分が中心。自分自身が、個人が、すべてである、と。でも、それは真実じゃない。人は他人との関わりの中でしか生きていけない。車だってそうだ。僕は自分では作れないから誰かに造ってもらわないと、運転して子どもたちを学校へ送ることもできない。子どもたちに勉強を教えるのも、家族の食べるものを育てるのも、誰かにやってもらわなければ僕にはできない。だったら僕にできることは何か? というと、それは音楽を作ることであり、それが僕なりの社会貢献であり、教えてあげられることというのかな。
でも、それだって聴いてくれる人がいなければできない。とにかく、人はお互いを必要としているし、力を合わせる必要があるんだ。力を合わせなければ、たとえば気候の変化に歯止めをかけることもできない。消費を抑えるとか、移動を少なくするとか、みんなでやらなければ意味がないんだから。行動を共にする必要があるんだよ。そして、そのためには隣人に目を向ける必要がある。お互いに対して、あるいはお互いのために、いったい何ができるのかを考えなければならない。僕としては、このレコードは、そのあたりのことを表すメタファーになっていると思う。「ボディ」に、つまりは互いの存在に耳を傾け、受け入れる必要があるのだ、と。突き詰めれば人はみな同じ。女王様だってウンチはするし、カニエ・ウエストだってそう。みんなやることだ。そこを認めることができたら、人間性を協調させることが可能になるかもしれない。ひいてはそれがより健全な体制を生み出すことに繋がっていくんじゃないかな。
■たしかに街中でもヘッドフォンをして周りの音をシャットアウトしている日本人もとても多いです。
MH:でも、それを責めることもできないけどね。だって世の中はどんどん騒々しくなっている。たとえば、これは最近じゃ常套句になってしまっているから僕がここでわざわざ言うのも申し訳ないようだけど(笑)、渋谷の町はその典型じゃないかな。音楽、テレビ、呼び込みの声。「こっちへ来てこれを買え!」という声が店やレストランから流れてくる。何かの統計を見たけど、人間の話す声はこの15年ぐらいで10%ぐらい大きくなっているらしいよ。まわりがうるさいから声を大きくしないと聞こえない。つまりマシーンの音に埋もれないように、人は声を荒げなければならなくなっているらしい。そういう意味じゃ、ヘッドフォンをしたくなる気持ちもわかるよ。あと、それで何を聴いているのかってのもあるよね。もしかしたら「沈黙について」なんていう番組を聴いていたりして(笑)。あるいはノーム・チョムスキーの講義だったりして。そう、何を聴いているのかわからないというのもまた、問題ではある。結局、人と人が繋がっていない、ということなんだから。
いまとなってはもう、ピアノもギターもドラムも僕は聴く必要を感じない。シンセサイザーだってそう。もちろん、それぞれ時と場所によっては素晴らしい音に聞こえるけれども、それが音楽の未来だとは僕は思わない。
■「世界を変える」いう意味では『ワン・ピッグ 』(2011)もそうでしたね。豚の誕生から食べられるまでを音にして、聴いている人に「気づかせる」……。
MH:そう。最近、僕は音楽がすごくひとりよがりで無難なものになってしまっていると感じているんだ。いまとなってはもう、ピアノもギターもドラムも僕は聴く必要を感じない。シンセサイザーだってそう。もちろん、それぞれ時と場所によっては素晴らしい音に聞こえるけれども、それが音楽の未来だとは僕は思わない。だからナイトクラブで『ワン・ピッグ 』 を演奏して、あの大音量で聴かせる、というのは僕に言わせれば興味深くもあり、衝撃的でもあり、おかしくもあり、ちょっとバカバカしくもあり、それでいて、ごく真剣なことでもあったわけで。
■さて、本作ですが、実際はどのくらいの期間で完成させていったのでしょうか。
MH:僕と「ボディ」とでやったんだけど、レコーディングは2日間かな。2日半ぐらいだったかもしれない。その音源をほかの録音機材に移して、さらに2週間ぐらいかけてあれこれ録音した。というのも彼女がその間にウンチをしなかったから(笑)。それで彼女に録音機を預けておいて、あとで催したときに録ってもらった。それでよかったと思いつつも振り返ると、違うやり方にするべきだったかなとも思ってしまう。もしかしたら最初からボディに録音機材を預けて彼女に委ねてしまったほうがよかったかもしれない。それはいわば画家が絵筆をモデルに預けるのと似た行為だよね。それってかなり斬新な解放であり、彼女にとってはそこから先の責任を自分で負えるわけで。
■いま、とても驚いたのですが、本作の「ボディ」は女性だったのですね。
すごく迷ったところなんだけど、ありがちな「白人男性が見つめる女性の肉体」という視点では終わりたくなかった。
結果的にこのレコード上のジェンダーは、レコードから聴こえてくる以上に交錯しているんだよ。
MH:うん。そこはすごく迷ったところなんだけど、ありがちな「白人男性が見つめる女性の肉体」という視点では終わりたくなかった。女性の身体を見つめる、あるいは身体に耳を傾けると特定のイメージが、あらかじめできてしまいそうだから。でもその一方で、僕ではない誰か他人であることも重要だった。男性の「ボディ」にすると皆、単純にそれが僕だと思うだろうし、それだとあまり面白くない。それに僕が自分の身体が発するノイズを自分で録音して発表するのでは、あまりにも内向き過ぎる気がして、つまらないと思った。他人の音を録音する方が、僕には遥かに興味深い。他人という意味で僕と異性である必要があるとも思ったんだ。ただし、彼女には、また別の男性も録音するよう指示を出しておいた。男性のノイズも一部、取り入れるようにと、ね。だから結果的にこのレコード上のジェンダーは、レコードから聴こえてくる以上に交錯しているんだよ。女性の音かと思えば、実は男性の音も入っている。つまり、単体の女性のボディだけではない、ということ。
■しかも、ご自身の音は入っていないのですね。私はハーバートさんの音も入っているものと思っていました。
MH:僕は何の音も立てていない。僕のノイズはこのレコードにはいっさい入っていないよ。僕じゃない。彼女は本当に大いなるコラボレーターだったよ。自分がウンチをする音を自分で録音して送ってくれる女性は、そう大勢はいないと思う。僕自身、このプロジェクトに取り掛かる以前は彼女のことを知らなかったんだ。あとオルガズムもそうだよね。あるいは洗い物をしたり、食事をしたり。正反対に眠るという、ものすごく無防備な状態も他人のために録音させてくれるなんてね。本当に彼女はこのレコードの重要な一部だよ。
ヒトの身体、とくに裸体というものに、聴覚だけで対峙するというのは、僕らがこれから検討していくべき使用価値の高いツールなんじゃないかな。
■「裸体=ヌード」は、古来から絵画や彫刻などの芸術において普遍的な題材ですよね。しかし同時に映像のない音楽においては、「裸体」の表現は困難とも思います。だからこそ、このような方法論で音楽=ヌードが実現できるとは! と驚きました。
MH:そうなんだよ。このプロジェクトには 「パーフェクト・ボディ」という副題が付いているんだけど、それがエキサイティングだと僕は感じている。目で見るものではないからこそ「美」や「姿形」は問われず、人種も関係ない。聴いている側には、彼女が日本人なのか、ロシア人なのか、アフリカの人なのかスペイン人なのかもわからない。年齢もわからない。体の様子もわからない。男女の区別もつかない。いわゆる伝統的な感覚で美しいのかどうかもわからない。これこそ本当の意味での解放だと僕は思っている。ヒトの身体、とくに裸体というものに、聴覚だけで対峙するというのは、僕らがこれから検討していくべき使用価値の高いツールなんじゃないかな。そして人間はみな、食べないわけにはいかない。トイレにも行かなければならない。そうせざるを得ないし、しなければ生存していけない。そう考えると、「非の打ちどころのないボディ=パーフェクト・ボディ」とは、「機能するボディ」、つまりは「生きているボディ」なんじゃないか。そこからすべてがはじまっているんだ。
■「命を糧として食べる」というと、ますます 『ワン・ピッグ』 の続編という感じすらしますが、その意識はありましたか?
MH:なかったよ。おかしいよね。インスピレーションというのは湧いてくるのを待つしかないんだ。自分のやっていることや決断の整合性も、あとになってようやく見えてくる場合もある。『ワン・ピッグ』 ときは、ここまでまったく考えていなかった。発想が浮かんだのは 『ザ・シェイクス』(2015) を作った後だ。実際、そう考えるとイライラするよね(笑)。自分の中にある発想に、脳みそが追いついてくるまで時間がかかって、それを待っているしかないわけだから。そして急がせることもできない。いまもまさに、その問題にぶち当たっているところだ。次のレコードをどうしようか考えているところなんだけど、まだ脳みそが追いついてこないんだ(笑)。
■ちなみにハーバートさんは他人が発する音は不快ですか?
MH:う~ん……、このレコードを作ってから少しよくなったかな。でも好きではない。たとえば劇場で隣の人の呼吸音がすごく大きかったりすると、勘弁してくれ! と思ってしまうほうだ(笑)。それが、このレコードを作ることで少しは容赦できるようになった。というか、ひとつの音として受け入れられるように少しはなった、というのかな。あんまり気にしないで、ひとつの音だというふうに脳内でイメージするようにしている。
ある意味、ジャズのレコードみたいに考えればいいのかなとも思った。彼女の出す音が主役。僕がするべきことは、とにかく彼女の音を支えて、伴奏につくことだけだった。
■録音された「音=ノイズ」の数々を、「音楽」としてコンポジションしていくにあたって何がいちばん重要でしたか?
MH:テーマの設定から入ったんだ。最初は、どう収拾をつけたらいいのかわからなくて、12時間の記録ということにした。1時間めは目覚め、2時間めは朝食、3時間めはジョギングというようにね。だけど、それがうまくいかなくて、こういう「行動別」のまとめになったんだ。ひとつのトラックが「洗う=「ボディ」のメインテナンスについて」というように、そのモデル(ボディ)が風呂に入るその時間がそのまま曲の長さになった。栓をした瞬間にはじまって、栓を抜くところで終わる。それが12分とか13分だったかな。だから難しかった。難しかったんだけど、ある意味、ジャズのレコードみたいに考えればいいのかなとも思った。モデルがマイルス・デイヴィスで、僕がバンドというふうに想像してみることにしたんだ。ソロイストをサポートする役が僕だ。彼女の出す音が主役。であれば僕は、彼女のすることをすべて受け入れて支えていけばいいんだとね。基本、彼女は全般的に物静かで行儀がよいから、僕がするべきことは、とにかく彼女の音を支えて、伴奏につくことだけだった。僕自身の構成とか音楽的な決断を押し付けるのではなくて、ね。
■“イズ・スリーピング”は睡眠中の録音ですが、ディスク1をまるごと、この睡眠にした理由を教えてください。
MH:あの録音がその長さだったからだよ。彼女が僕のために録音してくれたものが、その尺だったんだ。そうか、じゃあ、このトラックは1時間にしないとダメだな、と(笑)。だって、どこで切ればいい? というか、切る理由は何? 3分で切るか4分で切るか、あるいは20分か? で、じつはこれが今回のレコードで僕がいちばん気に入っている「音楽」なんだ。たぶん、それは独自のリズムがあるからだと思う。
■この1時間はまったく編集されていないんですね。
MH:してないよ。そのまんまだ。起きたことがそのまんま。
『ア・ヌード(ザ・パーフェクト・ボディ)』全曲試聴はここから!
僕がやろうとしたこと、あるいは僕が興味を持っていたことは、さまざまなポーズなんだ。僕は今回の作品の中で、ポーズというものの音楽における同義語は何だろう? ということに取り組んだ。
■ディスク2の方は編集やアレンジがされていますね。サンプリングによる反復と逸脱という、いかにもハーバートさんらしいトラックが展開されていました。
MH:あははは。
■「反復」というものがが、音楽、ひいては芸術において、どのような効果をもたらすとお考えですか?
MH:僕がやろうとしたこと、あるいは僕が興味を持っていたことは、さまざまなポーズなんだ。人間は、じつにさまざまなポーズをとる。モデルが何かに寄りかかっているポーズや、椅子に腰かけているときポーズまで。どれも静止したポーズだけれども、その人の一連の行動の中において、特定の一瞬でしかない。わかる? 静止しているけれども、モデルにとっては前後と繋がりのある動きの一環である、ということ。つまり動作と静止の「はざ間」の状態だね。そう考えるとすごく不思議だ。アートの世界では、その中の一瞬を切り取って静止した形で表現するけれど、音楽ではそうはいかない。発想がそもそも違うから。だから僕は今回の作品の中で、ポーズというものの音楽における同義語は何だろう? ということに取り組んだんだ。長尺で、これといった変化も起きない作品でも、目の前で、いや耳の前で、ほんのちょっとした震えや揺らぎが起きている。
■私はこのアルバムを、不思議と美しい音響作品として聴きつつも、反復的な“イズ・アウェイク”や“イズ・ムーヴィング”、リズミックな“イズ・シッテング”などには、どこかハウスミュージックのような享楽性を感じてしまいました。
MH:ふふふ……。
■で、なぜか『ボディリー・ファンクションズ』(2001)収録の“ジ・オーディンエンス”などを想起してしまったんです。
MH:マジで !? へぇぇ。
■「声の反復」の感じなどから、そう感じたのですが、いかがでしょうか?
MH:そう言われてみるとたしかにそうかも。僕の頭にはぜんぜん、なかったけどね。僕が興味を持ったのは、モデルには声があるから、ノイズもメロディも、すべて彼女の声からできている、という点なんだ。それが僕にとってはとても興味深い転換なんだ。絵に描かれたものを見ただけでは、そのモデルがどんな声をして、どんな音を立てているのかわからないけれども、音楽のポーズにおいてはモデルにも声があり、その声のトーンや質にも彼女らしさがあり、それが僕のメロディや構成を生み出す上で助けになっている。ハウス・ミュージックは今回のレコードでは僕は参照していななかったけど、反復によるリズムは有効だと思う。グルグルグルと同じところを繰り返し、めぐりめぐることによって特定の場所にハマっていられるから、そこで何かひとつの発想を固定することができる気がする。そういう意味で反復やリズムは、僕にとってはものすごく重要だ。ひとつのツールとして。
MH:じつはひとつ、ぜひとも大きく扱いたかった音があった。それが「肌」だったんだ。「肌」というか「接触」かな。
■アルバムに使われた音以外も、さまざまな音素材を録音されていたと思いますが、音を選ぶ判断基準について教えてください。
MH:まずは因習的な伝統を網羅しておきたかった。たとえば“イズ・イーティング”ではいろいろな食べ物を食べているんだけど、繰り返し登場する食べ物はリンゴなんだ。それはアダム&イヴが提示するものに繋がるからであり、リンゴが非常に象徴的な存在になったわけ。それで僕が「よし、じゃあリンゴでいこう」と決めて、7分とか、そんなものだったかな(ちょっと正確に覚えてないけど)、リンゴ1個を食べ終わるまでの時間をそのまま1曲にした。また、さっきいったように「風呂に入る」時間をそのまま録ってたり、さらに「爪を切る」音や「髪をとかす」音も、あとから乗せてある。つまり、サウンドのクラスタというかグループを作ったわけだ。彼女は風呂に入っているんだけれども、同時に「髪をとかす」音や「乾かしている」音も鳴っているという。いわば音の群像だね。かつ、ひとつひとつの音が明瞭に聴こえてほしかった。それが何の音か? とわかる程度に。いまひとつ明瞭ではないと判断した音は使わなかった。それが判断基準のひとつだね。
■録音・制作するにあたって、苦労した音というのはありますか。
MH:小さな音はすごく扱いづらかったな。じつはひとつ、ぜひとも大きく扱いたかった音があった。それが「肌」だったんだ。「肌」というか「接触」かな。手のひらで腕をこする感じとか。そういわれると、すぐに思い浮かべることはできる音だと思うけど、これが録音で拾うのは難しくて。皮肉にも僕がもっとも録音で苦労したのが「やさしさ」ということになってしまった。やわらかで、やさしくて、ごくシンプルな感覚。人間同士の「接触」の重要性は誰もが語るところだし、それが僕の訴えたかったことでもあるのに、これを捉えるのに、これを表現するのに、すごく苦戦してしまった。マイクの宿命で、どうしてもドラマチックな音の方がよく拾えるし、技術的にちゃんと録音可能なんだよね、うんと静かな事象よりも……。おもしろいことに、まだそうやって手の届かない部分が人間の身体にはある。マイクの力が及ばない部分がある。そう考えると、ある意味、なかなかに詩的だよね。
MH:誰かが小便をしている音、と言ったときに一般的に思い浮かべる音は、じつは水と水がぶつかる音であって肉体の発する音ではない。僕としては肉体の発する音と環境音との区別にこだわって、環境音は使わないよう細心の注意を払った。
■つまりサンプル音源などは、まったく使っていないわけですね。
MH:うん、それはぜんぜんしていない。「ボディ」の音だけだよ。録音は、最初はホテルの部屋ではじめたんだ。「白紙のキャンヴァスを用意する」的な考え方。ただ、たとえば誰かが小便をしている音、と言ったときに一般的に思い浮かべる音は、じつは水と水がぶつかる音であって肉体の発する音ではない。僕としては肉体の発する音と環境音との区別にこだわって、環境音は使わないよう細心の注意を払った。大便だってそうだよ。あれだってウンチが水にぶつかる音であって、聴けば、すぐに「あ、これは……」とわかるだろうけど、肉体の音ではないんだ。別物だ。そこが僕にとってはチャレンジだった。肉体の音だけを抽出するということがね。風呂に入っているときの音も、水の音に頼って音楽を作ってしまわないように心掛けた。面白みはそこにあるんじゃなくて、「洗う」という行為の方にあるんだから。大便はね、彼女がじつは下痢をしていたんだよ。驚いたことに、彼女はその状態でありのままを録音してきた。本当に勇気のある女性だよね。おかげで物体が彼女の肉体を離れる瞬間の音をとらえることができたわけ。そんな感じで、環境の音を入れ込まないように、できるだけ努力した。
■「音」であっても、個人のプライバシーの領域になればなるほど、他人には不快に感じてしまうかもしれません。そして本作は、そんなプライバシーの領域に足を踏み込んだ内容だと感じました。
MH:そう、まったくそのとおりだよ。でも、人間だって結局は動物だからね。もっと洗練された生き物だと思いたがっているけれど、要はただの獣だ。僕らはじつは農場に移り住んだところで、羊を飼っている。その羊が草をはむときに立てる音が最高に美味しそうでね。同じなんだな、と。人間も何も変わらない動物で、だからやることも同じなんだよ。ただ互いのそういう行為の音を聴くことに慣れていないだけ。
■となると、ハーバートさんにとって「音楽」と「非音楽」との境界線が、どこにあるのか気になってきます。
MH:うん、そこは僕自身、興味を持つところ。というのも、今回のこれも着手するにあたって「どうしてわざわざ音楽にするんだろう、ただのサウンドのままで十分かもしれないぞ」と考えたから。
MH:判断が難しいときがあるんだよ、何をもって「音楽」と呼ぶのか。ただ「音」を聴くのと「音楽」を聴くのとの違いは何なのか。
■なるほど。
MH:でもね、判断が難しいときがあるんだよ、何をもって「音楽」と呼ぶのか。ただ「音」を聴くのと「音楽」を聴くのとの違いは何なのか。だから、さっき話した、彼女(ボディ)がマイルス・デイヴィスで音楽はバンドとして彼女のサポート役に回る、というのがひとつの答になるかな。「洗う」が入浴である以上、そこでラウドでアグレッシヴな音楽を奏でるのは明らかに不適当だよね。彼女はただリラックスして静かにお湯に浸かったり身体を洗ったりしているだけ。その事実、そこに乗せる音楽を定義づける。自分で考えて音楽を乗せるというよりは、風呂の情景を優先して自分は身を退く。風呂というランゲージや、そこでの時間の流れに身を委ねるしかないんだ。
■ハーバートさんの方法論は物理的には制約が多いかもしれないけれど、不思議と「自由」に音楽をしているように思えます。
MH:ものすごい自由度だったよ。何しろいまは音楽を作りながら自分で下さなければならない決断があり過ぎるほどある時代だ。音ひとつ作るのにも、使えるシンセサイザーが山ほどあって、出せる音が何百万通りもある。さらにはそれを加工する方法がまた何百万通りもある。選択の自由を与えてくれているようで、音楽を作る上では、出だしからものすごい労力が必要になる。だったらむしろ「リンゴを食べる音だけで音楽を作る」という枠組みをはっきりさせておいた方が、音楽を作るという作業に専念できる。そこに僕は自由を感じる。
たとえていうなら、京都に「RAKU」(楽茶碗)って綴りの茶碗を作る工房があるんだけど、僕は、そのお茶の茶碗をすごく気に入っているんだ。その茶碗は16世紀から、おおよそ同じ作りだ。そこに僕は「作るのは茶碗。そして基本的に、こういう作り」というのがわかっている安心感の上で、思いきり制作の手腕を磨くことに専念できる、喜びみたいなものを感じるんだ。同じ枠組みの中で、どうしたら機能的で、特別で、興味深い作品を作り上げられるか。そこが勝負であって、窯を作るところからはじめなくてもいい。もちろん、そこからはじめたい人もいるだろうし、「さて、この土を練って何を作ろう」というところからはじめるのが醍醐味だと思う人もいるだろうけど、僕は「作る」という技にすべてを集中させたいから、ほかは制約しておくことがとても大事だったりする。そうしないとまったく収拾がつかなくなってしまうから。
同じ枠組みの中で、どうしたら機能的で、特別で、興味深い作品を作り上げられるか。そこが勝負であって、窯を作るところからはじめなくてもいい。僕は「作る」という技にすべてを集中させたいから、ほかは制約しておくことがとても大事だったりする。
■この作品を舞台化する計画があるそうですね。
MH:いまのところ1回だけなんだけど、ロンドンのラウンド・ハウスでやる予定だよ。希望としては振付師についてもらって、いくつかのボディを登場させ、それに動きを与えて……。まだ最終的な案ではないんだけど、観ている人のそばを通りかかるボディの気配から何か感じるとか、あるいは通りすがりに何か匂いがするとか……。でもけっこう不安もあるんだよ。というのも、そもそもこのレコードの主旨としてボディの見た目に捉われないというのがあるわけだから、舞台化してもボディを普通に露出することは避けたい。そこにはこだわりたいんだ。具体的には来月あたりから打ち合わせに入るので、それからだね。
■舞台作品は、アナウンスされているインスタレーションの展示とは違うものなのですか。
MH:うん、ナショナルギャラリーに常設するアート作品として寄贈する話もある。そっちの発想としては、ギャラリーの床とか壁とか天井とかに穴を空けて、そこに頭を突っ込むと音が聞こえてくる、というやつにする。目で見るのではなくて、聴く。音源は建物のどこかに仕込むことになると思うんだけど。そんな感じかな。
■「三次元的な体験」ですね。
MH:そうだよ。そもそも、このレコードに影響を与えたものは、さまざまなアートなんだ。音楽だけに限らない。というより音楽以外の「アート」だ。出来上がったものも「音楽作品」というよりは「芸術作品」と自分は考えている。
■「世界を変えること」が目標だとおっしゃっていたこのアルバムですが、満足するような反応は返ってきていますか。
MH:う~ん、まだちょっと早いかな。日本では7月1日のリリースだしね。まだキャンペーンもはじまったばかりで、反応らしい反応も返ってきていない状態だ。ラジオで流れるかどうかというのもポイントだね、わりとアダルトなトラックに関しては。まあ、だから、現状まだ世界を変えるには至っていない(笑)。
つまり、僕の次のレコードは、いわば目に見えないレコードってことになるかな。
■もしかすると気分を害する人もいるかもしれませんが、「警鐘」という意味では大成功でしょうね。
MH:いや、人を嫌な気持ちにさせるつもりはないんだ。ただドナルド・トランプに消えてもらいたいだけ。
■彼がこのレコードを気に入ってしまったらどうしましょう?
MH:あははは。いや、あいつがこれに興味を持つはずがない。自分にしか興味がない人間だから、他人の音になんか興味を持つわけがないよ。あるいは自分でカラオケをやるとか? 自分が風呂に入ったりウンチしたりする音を自分で録音して、このレコードのカラオケに乗せて流す。トランプによるトランプのためのトリビュート・レコード(笑)!
■(笑)。ちなみに本作の楽曲を象徴するような素晴らしいアートワークは誰が担当したのですか?
MH:写真はクリス・フリエルだ。この国では有名な風景写真家の作品で、アートワークは僕の作品を長年手掛けてくれているサラ・ホッパーがやってくれている。『ボディリー・ファンクションズ』も彼女のアートワークだったよ。中にはフォノペイパーというものを使っているんだけど、これを使うと写真を読むことができるんだ。写真の上に電話をかざすと、写真からノイズが出て、モデルが曲のタイトルを語る声が聴こえる。そして表はグラフをイメージしている。「幽霊を測ろう」としているようなイメージ。
■しかし、ここまで究極的な録音・音響作品を完成されたとなると、どうしても「次」の作品も気になってしまいます。
MH:次にやることは決まっているよ。次は本だ。『ミュージック』(MUSIC) というタイトルの本を書いたんだ。これは、僕が作ることのないレコードの解説書。つまり、僕の次のレコードは、いわば目に見えないレコードってことになるかな。
■目に見えないレコードとは! それはすごい! つねに意表をつきますね。
MH:あははは。それをめざしているよ。









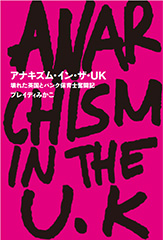 アナキズム・イン・ザ・UK
アナキズム・イン・ザ・UK







