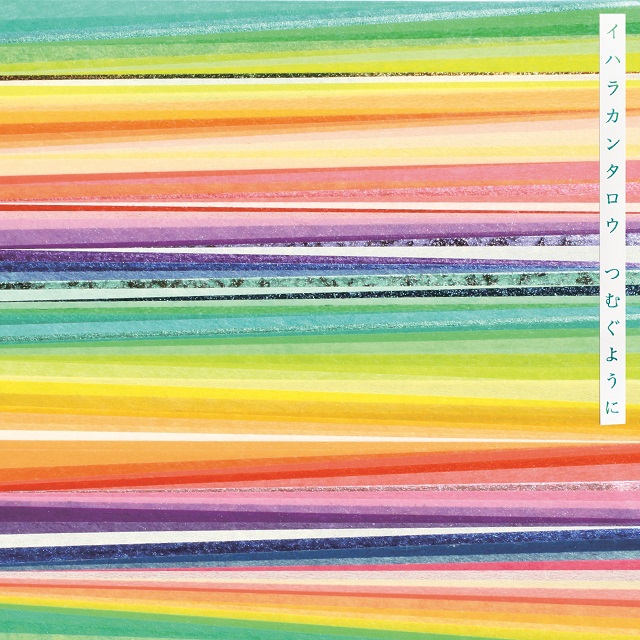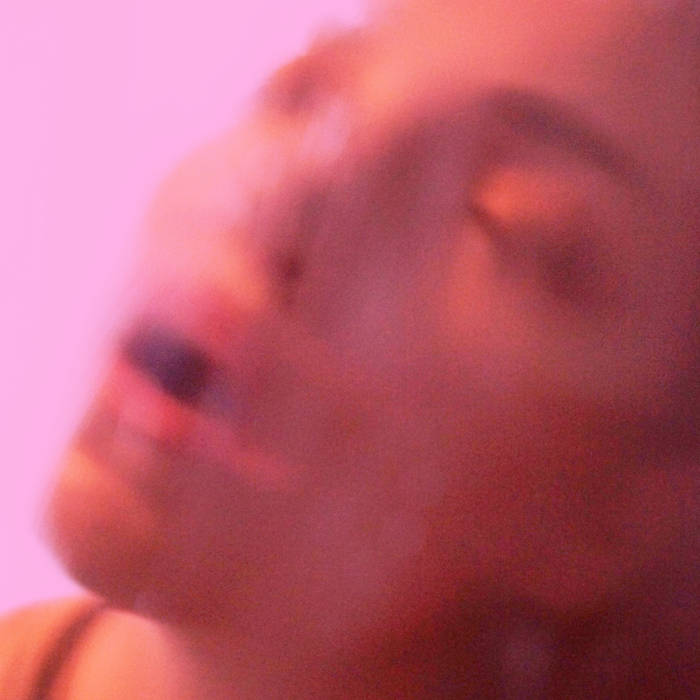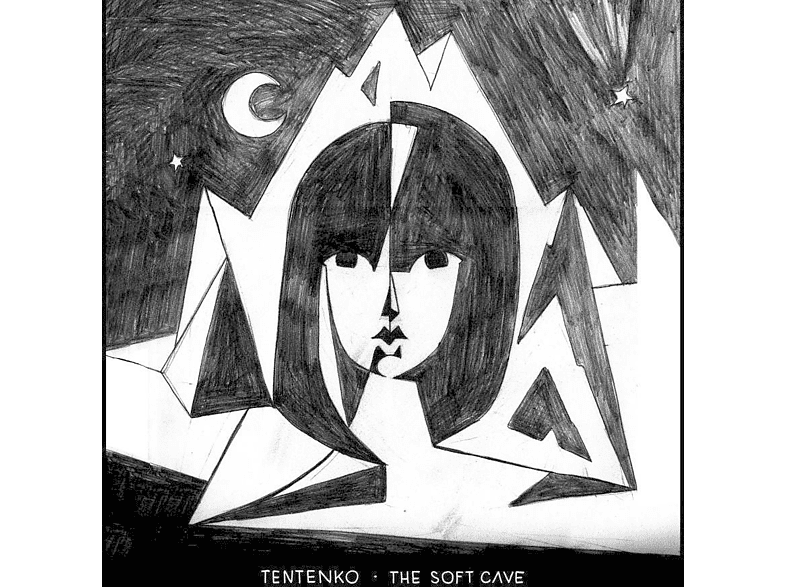シェイムやゴート・ガール、HMLTD、それらに続くブラック・ミディ、ブラック・カントリー・ニューロード、振り返ってみるとサウス・ロンドンのインディ・シーンはライヴ・バンドのシーンだったように思える。そのなかにあってソーリーは少し異彩を放っていた。このノース・ロンドン出身のバンドはシーンのなかで一目置かれ中心的な役割を果たしながらもそれと同時にベッドルームのSSWの側面も持ち合わせていた。ギターとヴォーカルを担当するアーシャ・ローレンス、ルイス・オブライエン、ふたりのソングライターの創作のルーツは SoundCloud にあってそこからソーリーははじまったのだ。
2020年にリリースされ高い評価を得た前作『925』に続きリリースされた 2nd アルバム『Anywhere But Here』はポーティスヘッドのエイドリアン・アトリーをプロデューサーに迎え、ブリストルのアリ・チャントのスタジオで録音されたそうだが、このアルバムを聞いて頭に思い浮かべるのはソーリーの持つそのもうひとつの側面だ。孤独と虚無感、陰鬱なムードが漂うこのアルバムはしかし絶妙な重さをもって心のなかにえも言えぬ余韻を残していく。このバランス感覚こそがソーリーの持つセンスで、それが深みと奥行きをもたらし、たまらないバンドの魅力を生み出しているのだ。
あるいはそれはロンドンのコミュニティのなかで育ったソーリーの内側からにじみ出てきたものなのかもしれない。ともにクリエイティヴな活動をしてきた仲間たち、アーシャは彼女の学生時代からの友人フロー・ウェブと一緒に FLASHA を名乗りソーリーのすべてのビデオを作り上げ、音楽の世界にもうひとつのレイヤーを付け加える。1st アルバム後に正式にメンバーとなったエレクトロニクス奏者のマルコ・ピニ(マルコも同じく学生時代からの友人だ)は〈Slow Dance〉のコミュニティを築き、ベース奏者のキャンベル・バウムもロックダウン中にトラディショナル・フォークのプロジェクト〈Broadside Hacks〉を立ち上げた。そこからどんどん矢印が伸びていき、いまのUKのアンダーグラウンド・シーンを盛り上げるインディペンデントなバンドや人物と重なり合う。積極的に前に出るタイプではないのだろうけれど、ソーリーは現在のインディ・シーンのなかで一目置かれ、重なり合うその円のなかで重要な役割を果たしているというのは間違いない(それが刺激になってお互いにどんどんクリエイティヴになっていく。たとえばアーシャの声は今年の夏に出ウー・ルーのアルバムでもスポーツ・チームのアルバムでも聞くことができるし、〈Broadside Hacks〉の活動のなかにキャロラインのメンバーの姿を見つけることもできる)。
そんなソーリーのルイス・オブライエンに 2nd アルバム、DIYのスタイル、敬愛するSSWアレックス・Gの影響、ロンドンのインディ・コミュニティ、SoundCloud の世界についての話を聞いた。遊び心に好奇心、飄々と皮肉とユーモアをそこに交えるソーリーのクリエイティヴなスタイルはなんと魅力的なことだろう。
「シンガーソングライター」という表現は、ここ最近本来の意味が少し失われてきているようにも感じているんだけど、僕たちはシンガーソングライターの本質を意識していたと思うよ。カーリー・サイモンやランディ・ニューマンをよく聴いていたし、エリオット・スミスは僕もアーシャも大好きだから。
■2nd アルバムのリリースおめでとうございます。前作『925』から2年半の間が空いてのリリースで、その間ライヴができない状況が続くなどありましたが、2nd アルバムを作るにあたってその影響はありましたか?
ルイス・オブライエン(Louis O’Bryen、以下LO):『925』をリリースした後、全くライヴやツアーができなかったから、(アルバムをリリースしたという)実感があまり湧かなかったんだよね。だから 2nd アルバムの制作に入るときも特に何も期待せずにはじめることができた。おかげで 1st アルバムの重みを感じずに頭でっかちにならないで制作に取り掛かることができたよ。リリースされていたけど、この世には出ていないみたいな気がしてたから 1st アルバムをもう一回作るみたいな感じだったんだ。それでストレスが軽減されたから僕たちにとって良かったと思う。
■今作はクラシックなサウンドにモダンなプロダクションを加えることを目指したそうですが、ポーティスヘッドのエイドリアン・アトリーとアリ・チャントとのレコーディングはいつ頃、どのような形ではじまったのですか?
LO:アルバムの作曲が終わった時点で、アーシャは「今回のアルバムの曲はすべて、昔ふうのソングライティングのスタイルからできたものだったね」と言っていたな。そういう意味でクラシックと言ったんだろうね。今回のアルバムは僕たちがいままでやってきたソングライティングのスタイルに忠実でありつつも、モダンでみんなが共感できるような音楽にしたかった。ポーティスヘッドは僕たちが参考にしていたアーティストのひとつで、エイドリアン・アトリーと連絡を取ったら、意気投合して、彼と一緒にアルバムを仕上げようということになり、エイドリアンがアリ・チャントを紹介してくれた。あのふたりはよく一緒に仕事をしていて、良い作品をいくつも手がけているからね。アルバムの曲には個別じゃなくて、全体でひとつのものとして一体感を持たせたかった。エイドリアンとアリはアルバムのサウンドに一貫性をもたらしてくれたんだ。それぞれの曲が同じソース(源流)からきているような感じにしてくれたよ。
■アリ・チャントは今年リリースされたヤード・アクトやケイティ・J・ピアソンのアルバムも手がけていますが、ブリストルのアリ・チャントのスタジオはどのような場所でしたか?
LO:アリ・チャントのスタジオはとてもクールだったよ。彼は父親的存在なプロデューサーで、とても感じの良い人だった。スタジオによっては、コントロール/ルームがひとつ、ドラムの部屋が別にひとつ、さらにバンドがまた別の部屋で演奏するという構造でバラバラな感じがすることもある。でもアリのスタジオはすべてがひとつの部屋に収まっているんだ。だからみんながひとつの場所に一緒にいるという状態。それが素敵だと思った。僕とアーシャは以前ベッドルームをスタジオにしていたからね。いまは僕も自分のスタジオを持っているんだけど、それでも小さな部屋がひとつだ。そういうセッティングに慣れていたからアリのスタジオでもみんなが同じ部屋にいてレコーディングできるというのが良かった。自然な感じがしたんだ。アリのスタジオはその点が素敵だと思った。
■先日、アレックス・Gの新しいアルバム『God Save the Animals』のリリースを祝うツイートをしていましたよね?
LO:ははっ(笑って頷く)
■〈Domino〉と契約したのはアレックス・ Gのいるレーベルだからとジョーク飛ばしていたこともあったりと、様々な方面から敬愛ぶりがうかがえますが、アレックス・Gのどのようなところに魅力を感じていますか?
LO:僕たちが16、17歳の頃、周りの友だちはみんなアレックス・Gの音楽を聞いていたんだ。それが僕らの共通点だった。アレックスがUKに来たとき、彼は僕たちの友人の家に泊まっていて、それでアレックスと少し仲良くなることができたんだ。彼は本当に多作な人で、〈Domino〉と契約する以前から6枚くらいアルバムをリリースしていた。それが僕たちに大きなインスピレーションを与えてくれたんだ。彼のソングライティングにはつねに一貫性があってメロディや歌詞がもの凄く面白くて、本当にうまく作られているんだ。アーティストである僕にとって彼のそういう点にインスパイアされる。あんなふうに一貫性を保っていられるのは凄いことだと思うよ。
■ちなみにアレックス・Gの新しいアルバムはどうでしたか?
LO:良かったよ。最高だった!
 Photo by Peter Eason Daniels
Photo by Peter Eason Daniels
子どもの頃MTVばかり観ていたんだけど、その当時のミュージック・ビデオはめちゃくちゃ格好良かった。あのアートは失われてしまいいまでは YouTube の動画などに変わってしまった。YouTube 動画とミュージック・ビデオは全くの別物だよ!
■アルバムのなかの1曲 “There’s So Many People That Want To Be Loved” はアレックス・Gの他にもエリオット・スミスの特に『Figure 8』の空気を感じさせるような曲で、孤独感と疎外感、それと虚無感が混ざりあったようなフィーリングがとても印象的でした。2nd アルバムはこうしたシンガーソングライターの影響を強く感じますが、意識していた部分はありますか?
LO:もちろん。「シンガーソングライター」という表現は、ここ最近本来の意味が少し失われてきているようにも感じているんだけど、僕たちはシンガーソングライターの本質を意識していたと思うよ。カーリー・サイモンやランディ・ニューマンをよく聴いていたし、エリオット・スミスは僕もアーシャも大好きだから。それにアルバムのレコーディングに入る前に、作曲が完成している状態で曲をすべて人前で披露できる状態にしておきたいと考えていたんだ。70年代のシンガーソングライターたちは、90年代もそうだったかもしれないけど、みんなそういう状態でスタジオに入っていた。彼らはスタジオに入ってから曲を完成させるという有利な状況にはいない人たちだった。つまりレコーディングに入る時点で曲をすべて完成させていなければならかったんだ。僕たちも今回、サンプルの音なんかでも、スタジオに入ってレコーディングする前に完成させて演奏できるようにした。そういう意味では作曲や構成、メロディが完成されたシンガーソングライターと呼ばれているアーティストたちのアプローチにインスパイアされていると言えるね。
■“There’s So Many People That Want To Be Loved” のビデオはロンドンの街の人びとが抱える孤独が、街の風景のなかに投影されているように感じました。このビデオも含めアーシャとフロー・ウェブの作るビデオについてお聞きしたいです。今回ルイスは宇宙飛行士役を演じていましたが、いつもどのような形でビデオの制作ははじまるのですか? アーシャは曲を聞くと色やヴィジュアルが見えるという話をしていましたが、曲作りの段階でそのイメージは共有されているのでしょうか?
LO:色やヴィジュアルが見えるというのは、何て言うんだっけ……「シナスタジア(共感覚)」って言葉があるんだよね! 僕は、嘘くさいと思うけど(笑)。適当に言ってるだけなんじゃないかな(笑)。
■(笑)。アーシャは色が見えると話してくれましたけど。
LO:はは、そうだよね。僕たちの曲はイメージがベースになっているものが多いのは確かだよ、曲にヴィジュアルがついている感じというか。ビデオはすべてアーシャが作っているから僕じゃなくて彼女の言葉を信用するべきだけど。でも僕たちが曲を書いているときにはもうすでに曲のヴィジュアルがイメージできているんだよ。アーシャはそのアイデアを展開して歌詞として浮かび上がらせるのが得意なんだと思う。“There’s So Many People That Want To Be Loved” のビデオに出てくるイメージはすべて曲の歌詞が表現されたものなんだ。僕たちにとってミュージック・ビデオはとても重要なものだから。子どもの頃MTVばかり観ていたんだけど、その当時のミュージック・ビデオはめちゃくちゃ格好良かった。くだらないと思っていた人たちもいるかもしれないけど、僕たちにとっては最高だったんだ。あのアートは失われてしまいいまでは YouTube の動画などに変わってしまった。YouTube 動画とミュージック・ビデオは全くの別物だよ! だから僕たちはミュージック・ビデオに忠実でありたいと思っている。
■“Screaming In The Rain” はルイスの物悲しげな歌声がとても魅力的で、理解することができないコミュニケーションの不全を唄っているようで印象に残っています。この曲の背景にあるものはどのようなものなのでしょうか?
LO:この曲は、愛する人と一緒にいる状況で、自分がどうすれば良いのかわからない感覚や、友人が助けを必要としているときに、自分がどう対応すれば良いかわからない感覚を歌っている曲なんだ。そういう絶望感がモチーフになっているけれど、同時に助けになりたいという思いもある。この曲は僕たちのお気に入りで、たくさんのヴァージョンを経てこの形になった。別のヴァージョンとして今後、発表していきたいと思ってるよ。僕とアーシャのヴォーカルが物悲しげなのが特徴的だよね。
[[SplitPage]]
イラストはアーシャが描いているんだけど、僕たちはそれを「曲のロゴ」と呼んでいて。曲それぞれにキャラクターというかロゴがあるようにしているんだ。
■この2ndアルバムには収録されていませんが、タイトルとして名前が残った “Anywhere But Here” という曲があって、その曲がアルバムの出発点になったとお聞きしました。その曲はどのような曲なのでしょうか? 今後リリースされることはありますか?
LO:どこから聞いたんだい!?
■アーシャが話してくれたんですよ。
LO:そうだったんだ(笑)。けどこれはまだ秘密にしておきたいから、どこまで話せるのかわからないな。でもアーシャが話していたなら、まぁいいか。うん “Anywhere But Here” という曲を書いたんだけど、それがアルバムの焦点となったんだ。それでアルバムをレコーディングしているときに、アルバム名を『Anywhere But Here』にしようと決めたんだ。最終的にこの曲はアルバムにフィットしなかったから収録しなかったんだけど。でも名前だけは残ったんだ。他のアルバム名も考えたけどしっくりこなかったからこの名前のままにした。今後この曲をリリースしたいとは思っているけど、「アルバムのリード・トラック(タイトル・トラック)がアルバムに収録されていない」というのが結構気に入っているんだ。面白いんじゃないかって思って(笑)。
■1st アルバムにしてもミックステープにしてもソーリーは作品全体に一貫した雰囲気を持たせるということにこだわっているように思います。それは今回も同様だと感じたのですが音作りに関して、あるいは曲順など 2nd アルバムの制作で意識した点を教えてください。
LO:いままでは自然にそうなっていたんだと思う。でもさっき言ったみたいに今回のアルバムに関しては、ひとつの完全なものとして作り上げたかったんだ。アルバムの曲をレコーディングするとき、僕たちはバンドとして一緒にレコーディングしたんだ。曲の大部分を2週間という期間でレコーディングしたことで、すべての曲が同じソースからきているようなサウンドにすることができたんだと思う。エイドリアンとアリも、サウンドに一貫性を持たせるようにしてくれた。アルバムのソングライティングが完成した時点で一貫した雰囲気が感じられるっていうのは僕たちにとって大切なことなんだ。今作の全体的なサウンドについては、意識した部分もあるけれど、ギターの音だったり、僕たちのソングライティングのやり方もあって自然にそうなっているところもある。あまり考え過ぎると本質が失われてしまうと思うんだ。
■前作、『925』もそうでしたがソーリーはアルバムそれぞれの曲についてモチーフ的なイラストをつけていますよね? “Key To The City” の鹿だったり、“Willow Tree” の切られた木に寄りかかる人だったり、それがとても魅力的で。これは音楽だけではなく、ビデオやアートワークを含めヴィジュアルを通した表現としてアルバムをとらえているからなのでしょうか?
LO:アートが音楽と絡んでいるというのが好きなんだと思う。イラストはアーシャが描いているんだけど、僕たちはそれを「曲のロゴ」と呼んでいて。曲それぞれにキャラクターというかロゴがあるようにしているんだ。子どもの絵本とか、いろんなキャラクターがいるアニメみたいだろ? 曲を展開させるひとつの方法というのかな。こういうものがあると曲に独自の世界観を持たせることができると思うんだ。
僕たちは何らかの忘備録的存在になるということが好きなんだと思う。それがインターネット上の YouTube にミックステープをアップすることであれ、ヴァイナルをリリースすることであれ、僕たちの作ったモノが世に出ているということだから。
■アルバムのリリースの前に7インチを2枚リリースしましたよね? サブスク全盛時代のいまはアルバムの前にこの様な形でフィジカルのシングルをリリースするバンドも少なくなってきたように思うのですが、リリースのスタイルにこだわっているところはあるのでしょうか?
LO:僕たちは何らかの忘備録的存在になるということが好きなんだと思う。それがインターネット上の YouTube にミックステープをアップすることであれ、ヴァイナルをリリースすることであれ、僕たちの作ったモノが世に出ているということだから。みんなが集めることのできるいろいろなモノのなかに僕たちが作ったモノが加わった感じ。ヴァイナルについてはスタンプを集めるスタンプ帳みたいな感じがあるしね。イギリスでは子どもの頃みんなが夢中になるサッカー選手のカードを集めるゲームがあるんだ。カードを集めてカード帳に入れていく。いちばんの困難は母親にカードを買ってもらうことだったけどね(笑)。カード帳が1ページ埋まったときはすごく嬉しかったよ。ヴァイナルもそれに似たようなものだと思っていて、ヴァイナルを全部集めることができたら見栄え的にもクールだと思うんだよね。それに僕たちはアートワークを重要視しているから、ヴァイナルやヴィジュアル・ミックステープをコレクトするということは、僕たちの芸術性とマッチしていると思うんだ。だからいろいろなモノをリリースするということに関しては今後もどんどんやっていきたいって思ってる。
■フィジカルを手に入れなければ見られないイラストに YouTube で公開されるビデオと、このような部分はクラシックなサウンドにモダンなプロダクションを目指した 2nd アルバムのコンセプトと共通しているような感じがします。
LO:そうかもしれないね。曲のロゴを YouTube のビデオや他の箇所に登場させたら、面白いと思ったんだ。聞く側にとってはある種のゲームみたいな感じで「あ、曲のロゴ見つけた!」って思ってもらえたら楽しいと思って。
■アーシャもコンピレーション・アルバムに参加していましたが、メンバーのキャンベル・バウムが立ち上げた〈Broadside Hacks〉というトラディショナル・フォークのプロジェクトがありますよね? あるいはマルコの〈Slow Dance〉があったりと、ロンドンにはこうしたインディ・コミュニティが根付いているように思いますが、その点についてどのように感じていますか? クリエイティヴな活動が分野を超えて重なりあっているという点で特に〈Slow Dance〉とソーリーは近い部分があるのではないかと感じているのですが。
LO:(ロンドンのインディ・コミュニティは)とてもクリエイティヴなところだと思うよ。一緒に育った仲間の多くがクリエイティヴな活動をする人だったり、あるいはクリエイティヴな人だったっていうのはラッキーだったと思う。それが環境によるものなのかはわからないけれど、クールで面白いことをやっている人たちが周りにいるっていうのは恵まれていることだと思うんだ。僕たちは彼らからつねに刺激を受けているから。それは僕たちのためにもなっているし、僕たちも彼らにも刺激を与えているはずだって思っているし、互いに刺激しあっているんだと思う。ロンドンのような大都市で青春時代を過ごすのはキツいこともあるから、似たような考えや価値観を持つ人たちを求めるようになるんだと思うんだ。だからいまでは周りに才能を持つ仲間がたくさんいるということはとても恵まれていることだと感じているよ。

■ルイスにしてもアーシャにしてもソーリーとは別に現在も SoundCloud に個人名義の曲をアップし続けていますよね? ふたりにとって SoundCloud というのはどのような意味を持つプラットホームなのでしょうか?
LO:SoundCloud は僕たちにとってとても重要なプラットホームだよ。SoundCloud をはじめたとき、僕はギターを弾いていたんだけど、ギターに飽きていたというか、ギターに限界を感じはじめていた。その頃から僕とアーシャは、個別にだけど、パソコンを使って音楽を作るようになった。FL Studio というプログラムを僕がダウンロードしたんだ。FL Studio は音楽制作のプログラムだったんだけどビデオゲームみたいな感覚でやっていて。14歳くらいのときだったかな。凄く楽しくてふたりでいろんな音楽を作って SoundCloud にアップして、どっちが友だちからの「いいね!」をたくさん得られるか競い合っていた(笑)。それがはじまりだったね。さっきの話と同じで、インターネット上の隅っこに僕たちのスペース(=音楽)が存在している感じで、みんながそれを見つけることができるみたいなイメージだよ。アレックス・Gもそれと同じ感じで作品を公開している人で、YouTube をチェックすれば YouTube の「アルゴリズム・ホール」(*ブラック・ホールにかけている表現)に入り込んで、アレックス・Gの音楽を無限に発見することができる。ファンである僕にとっては、アレックスの奇妙で面白い世界に足を踏み入れる楽しさがあるし、SoundCloud もそれに似たような架空の世界を拡張できるもののように捉えているんだ。
■SoundCloud にアップされているルイスの曲は悲しげなメロディの曲が多く、しみじみと感じ入るようなその感覚が好きなのですが、ルイス個人としてはどのような音楽に影響を受けてきたのでしょうか? あるいはインスピレーションを受けた映像作品やカルチャーなどがありましたら教えてください。
LO:最近はレナード・コーエンをよく聴いているよ。ニーナ・シモンも大好き。あとはエリオット・スミスやソングス・オハイアなど。好きな映画もたくさんあるよ。かなり変わってるかもしれないけど、『地獄の黙示録(Apocalypse Now)』がすごく好きなんだ。僕はどういうわけか昔の映画が好きでね、強いカタルシスを感じるんだ。特にベトナム戦争を題材にした映画はすごく強烈だし、皮肉だけどクールだと思ってしまう。
■今後も以前リリースしたミックステープのような形で曲をリリースすることはありますか?
LO:じつは秘密のミックステープというものがあるんだよ。でも詳しくは教えられない。聞きたい人はそれをどうにかして見つけないといけないんだ。面白いだろう? 今後もミックステープはリリースすると思うけど、前回のは僕たちが昔に作った曲があってそれらをリリースしたかっただけのことなんだ。ヒップホップのミックステープという感じではなくて。昔はよく自分の好きな曲を何曲も入れたCDを作って友だちや好きな人にあげたりしていたよね? 僕たちのはそういう感じのミックステープに近いんだ。好きな曲を集めて好きな人たちにあげる。そういう形のミックステープは今後ももちろん作っていきたいよ!
■1st アルバムのリリース時はパンデミックでUSツアーが途中で中止になるなど満足にライヴができなかった状況でしたが、最近のライヴ活動はどのような感じでしょうか? 2nd アルバムの曲はもうライヴで演奏していますか?
LO:今年の夏は少し休みを取っていたからあまりライヴをやっていなかったけど、3月と4月にUSとUKをツアーしたんだ。2nd アルバムからの新曲もたくさん演奏して楽しかったんだけど、まだライヴで披露していない曲がたくさんあるから、今後アルバムの曲を多くの人に演奏して世に広めていくのが楽しみだよ。
■ありがとうございます。いつか日本でライヴが見られることを願っています。
LO:こちらこそありがとう! 僕たちも日本でライヴができる日を楽しみにしてるよ!