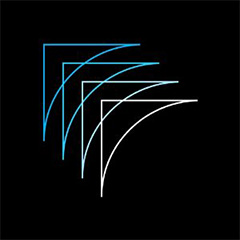先日ロンドンから帰ってきたばかりの友だちが言うには、いまは「ジャズが来ている」そうだ。流行りモノが好きな僕は、そういうひと言が気になってしまうのだが、UKは、クラブ・カルチャーにおいてジャズ/ファンク/ソウルがセットとなって周期的に流行る。ele-kingでもここ1~2年はその手のモノが紹介されているが、あるクラブ世代の固まりがある程度の年齢に達すると、ジャズ/ソウル/ファンクにアプローチする人は少なくなく、いまはダブステップ世代にとってそういう時期なのだろう。
そういえば、昨年はセオ・パリッシュによる〈ブラック・ジャズ〉(70年代のスピリチュアル・ジャズを代表するLAのレーベル)の編集盤もあったが、今年はサン・ラー生誕100周年でもある。ラー100年の記事は、海外のインディ系の多くのサイトでも載っている(彼は1914年、大正3年生まれなのだ)。
クラブ・ミュージックで言えば、フローティング・ポインツ(サム・シェファード)は、そのスジでもっとも評価の高いプロデューサーだ。彼はいまだにアルバムを出していないのだが、何枚かのシングルによって(とくに2011年の「Shadows EP」と「Faruxz / Marilyn」は必聴)、その他大勢のジャジーな連中との格の違いを見せている。ゆえに彼が運営に関わる〈エグロ〉からソロ・デビューした、スウェーデン出身ロンドン在住の女性シンガー、ファティマのフル・アルバムを楽しみにしていなかったファンなどいないだろう。
録音はロンドンとLAでおこなわれている。アルバムをサポートするメンツはかなり良い。サム・シェファードはもちろんのこと、デトロイトのセオ・パリッシュ、〈ストーンズ・スロー〉のオー・ノー、サーラーのシャフィーク・フセイン、LAのコンピュータ・ジェイ、リーヴィングからもカセットを出しているナレッジ、ケンドリック・ラマーのアルバムにも参加しているスクープ・デヴィル、ロンドンのfLako……とまあ、一流(?)どころが揃っている。
しかし、一流どころを揃えれば必ずしも試合に勝てるわけではないことは、ワールドカップをご覧の方にはおわかりだろう。チリやメキシコのようなチームは、がんばって最後まで見て良かった……と思わせる試合をした。ファティマの『イエロー・メモリーズ』がそのレヴェルに達しているかどうかは疑わしいが、確実に言えるのは、ここには過去を活かした魅力的な「現在」があることだ。
現在──ローリン・ヒルやジル・スコットで育った90年代の子供の上品な歌の背後には、モダンなビートが軽やかに鳴っている。1曲目の“Do Better”(シェファードpro)は、70年代ソウル風のドラマティックなホーンセクションではじまるが、アルバムはレトロに囚われない。マッドリブの弟によるヒップホップ・ビーツの“Technology”、コンピュータ・ジェイ(とシャフィーク・フセイン)によるネバっこファンク“Circle”、スクープ・デヴィルのうねりをもった“Ridin Round (Sky High)”……と、前半は、ヒップホップ・ファンとしての彼女の好みが展開されている。
そして、ジャズ/ソウル・スタイルの“Biggest Joke Of All”(シェファードpro)、最高にチルな“Underwater”(ナレッジpro)など、古さを活かした曲を混ぜながら、『イエロー・メモリーズ』はUKらしい折衷主義を更新する。真夜中のダウンテンポ“Talk”(シェファードpro)から最後の曲“Gave Me My Name”(シェファードpro)にかけてのメランコリーも悪くはない。

 ■佐々木敦著
■佐々木敦著