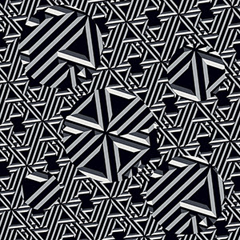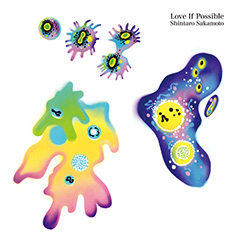かつて決して沈まないと謳われた豪華客船があった。当時の科学技術の粋を集めて造られたその船は、皮肉なことに初めての航海で氷山に接触し、多くの人びとを乗せたまま海底へと沈んでいった。その甲板では、乗客たちの不安を和らげるために、バンドが音楽を奏でていた。かれらの演奏は船が沈むその最後の瞬間まで続けられたという。
この半ば伝説と化した楽団が奏でていた音楽はラグタイムだったとも賛美歌だったとも伝えられているが、いずれにせよその音楽は非常にアンビヴァレントなものだったはずである。その音楽は、乗客たちが落ち着いて避難できるよう、かれらの耳元にまでしっかりと届けられなければならない。だが他方でその音楽は、乗客たちが能動的に聴き入ってしまうようなものであってはならない。無論、緊急事態に熱心に音楽に耳を傾ける者などいないのだろう(実際、生還した細野晴臣の祖父の耳に強く刻まれていたのは、バンドの演奏などではなく信号花火の轟音である)が、それでも、乗客たちが避難することを諦めその運命を受け入れてしまうような耽美な音楽を演奏するわけにはいかなかっただろう。
必ず聞こえなければならないが、決して聴かれてはならない音楽。それが、自らの意志で船上に残ったバンドメンバーたちが奏でなければならない音楽だった。そしてそれはエリック・サティが「家具の音楽」を作曲する8年前のことだった。
ブライアン・イーノがタイタニック号の沈没というテーマに関心を寄せるのは今回が初めてではない。イーノがプロデューサーを務め、イーノが立ち上げたレーベル〈オブスキュア〉からリリースされたギャヴィン・ブライアーズの『The Sinking Of The Titanic』(1975年)は、まさしくタイタニック号のバンドメンバーたちが演奏していたであろう音楽を、生存者の証言に基づいて再現しようとする試みだった。それは、積極的に聴かれることを目指さないという点において、後のアンビエントの先駆となる作品だった。
とはいえ、この度リリースされたイーノの新作『The Ship』は、ブライアーズのように真正面からタイタニック号の沈没と向き合うものではない。本作においてタイタニック号の沈没という出来事(1912年)は、第一次世界大戦というもうひとつの出来事(1914〜18年)とセットで扱われているのである。
日本では便宜的に第二次世界大戦までがいわゆる「近代」とされてきたけれど、ヨーロッパでは長らく第一次世界大戦までが「近代」と見做されてきた。つまり第一次世界大戦は、欧州に生きるイーノにとって、いまからひとつ前の時代の終焉を意味するものなのである。
なぜいまイーノがそのようなテーマに惹かれたのかということについては、昨年の彼の政治的な活動を振り返ると、ある程度は察しがつく。人類はすでに100年も前に科学技術や軍事力を過信することの危険性を知っているはずなのに、今日でも戦争や紛争といった問題は何も解決していないではないか、むしろ世界の状況は当時よりも悪化しているのではないか──おそらくイーノの胸中にはそういう思いが横たわっているのだろう。彼の瞳には、9•11やイラク戦争、世界金融危機を経た現在の世界の惨状が、100年前のムードと非常に似通ったものとして映っているのである。
ソロ名義としては『Lux』(2012年)以来およそ3年半ぶりとなる新作『The Ship』だが、いわゆる「歌もの」として本作を捉えた場合、『Another Day On Earth』(2005年)以来11年ぶりのアルバムということになる。とはいえこの11年の間、イーノが全く歌っていなかったというわけではない。カール・ハイドとの共作である『Someday World』(2014年)では何曲かでイーノがメイン・ヴォーカルを務めていたし、同じ時期にリリースされたデーモン・アルバーンのソロ・アルバム『Everyday Robots』でもイーノはゲストとして哀愁漂うヴォーカルを披露していた。
しかしながら、そもそも本作をいわゆる「歌もの」に分類するのにはいささか困難が伴う。たしかに、イーノは歌っている。けれど本作では最後の "I'm Set Free" を除いて、「ヴォーカル+バックトラック」という典型的な「歌もの」の構図は採用されていない。本作で聴くことのできるイーノの低い──そう、とてつもなく低い──ヴォーカルは、あくまでそれ以外のサウンドと溶け合うように、全体を構成する部分のひとつとして鳴り響いているのである。かつてイーノはU2のボノに対しヴォーカルの不毛性について説き語ったことがあるそうだが、いざ自らが歌うにあたっても、ヴォーカルを特権的に扱う趨勢に対する反抗心を忘れることはできないのだろう(そうであるがゆえにこそ、最後の "I'm Set Free" が効果的に響く)。
本作は大きく "The Ship" と "Fickle Sun" の二部から構成されている。
タイトル・トラックであ "The Ship" は、希望に満ちた新たな船出を告げるかのような、イーノらしい静謐なアンビエントで幕を開ける。6分手前からイーノの低いヴォーカルが入場し、その最も低い部分は次第に周囲の電子音と混ざり合っていく。背後ではサンプリングされた音声が小さな小さな雑音として鳴っている。それらが混ざり合う様は徐々に変化していき、13〜14分あたりで一段落すると、トラックは少しずつきな臭い様相を呈していく。15分手前からは静かなノイズと女性のものと思しきヴォイスが乱入し、不穏な空気が漂い始める。17分手前からは謎めいた声が亡霊のように語り出し、また新たなノイズが侵入してくると、それらは次第に重なり合っていく。繰り返される「Wave, after wave, after wave」という呟きが聴き手を不安へと誘い、アルバムは前半を終える。
後半の "Fickle Sun" はさらに三つのパートに分かれている。
最初のパートは "The Ship" と同じようにアンビエントで始まるものの、そこにもはや明るい未来の兆しなどはなく、出だしからベースが不吉な雰囲気を紡ぎ出していく。3分手前からイーノのヴォーカルが入り込み、5分を過ぎたあたりからシンバルが鳴り始め、6分頃にはノイジーなギターが乱入してくる。7分を過ぎた頃には全ての音が大音量で轟き始め、おそらくはここが最大の戦場なのだろう、けたたましさは頂点に達する。その後いったん静寂が訪れるものの、徐々に様々な音声が入り乱れていき、トラックの後半は声の一大実験場と化す。その様はまるで、戦場=船上で命を落とした者たちを一堂に召喚する魔術的な儀式のようである。繰り返される「When I was a young soldier」というフレーズが亡霊たちの呻き声を呼び寄せながら、"Fickle Sun" は最初のパートを終える。
二つ目のパートである "The Hour Is Thin" では、もの悲しげなピアノをバックに、タイタニック号の沈没や第一次世界大戦に関連する文書を元にマルコフ連鎖ジェネレーターによって生成されたテクストを、俳優のピーター・セラフィノウィッツが淡々と読み上げていく。その亡霊たちを鎮魂するかのような朗読に導かれ、"Fickle Sun" は三つ目のパートである "I'm Set Free" へと流れ込み、これまでの闇を一気に振り払う。長大な映画のエンディングのような余韻を与えるこのヴェルヴェット・アンダーグラウンドのカヴァーは、聴き手に新たな希望の片鱗を垣間見せるものの、それは「幻想」であると歌われ、『The Ship』は静かに幕を下ろす。
このように本作は、これまでのイーノのどのアルバムにも似ていない、極めて野心的な作品となっている。 "Fickle Sun" 中盤のノイジーな展開は、00年代以降ドローンがノイズとアンビエントとの境界を攪乱していったことに対するゴッドファーザーなりの応答である、と考えることも可能だろう。そういう意味で本作は昨今の音楽シーンへの目配りもおこなっているわけだが、それ以上に本作で重要なのは、その物語性である。
始めから通して聴けばわかるように、本作はオープニングとクライマックスとエンディングをしっかりと具えた壮大な小説のように進行していく。静穏なアンビエントやイーノ自身による歌、けたたましい騒音や様々な声の実験を経由して、最終的に本作は「私は自由になる」と歌われるポップ・ソングへと辿り着くのである。"Fickle Sun" の最初の方でイーノは「The line is long / The line is gray」と歌っているが、この「line」は「航路」であると同時に文字通り「線」でもあるのだろう。『The Ship』は一本の線のように進行していく物語なのである。
そもそも70年代にイーノが開始したアンビエントというプロジェクトには、リニアな物語として展開する音楽に異議を唱えるという側面があった。そのようなイーノ自身によって始められた試みが、この『The Ship』では、イーノ自身によって問いに付されているのである。アンビエントに歌を組み合わせるという点においてだけでなく、アルバム全体に物語性を導入するという点においても、イーノは本作で、これまでの自身のディスコグラフィから遠ざかろうと奮闘している。要するに本作は、イーノ自身によるイーノ自身への反抗なのである。
振り返れば、イーノの歩みは抵抗の連続だった。スクラッチ・オーケストラやロキシー・ミュージックへの参加は音楽のプロフェッショナルであることへの抵抗であり、〈オブスキュア〉の始動やアンビエント・ミュージックの発明はロックの昂揚感や音楽における物語性、あるいはメディテイション・ミュージックに対する抵抗であり(紙版『ele-king vol.8』および『AMBIENT definitive 1958-2013』に掲載された三田格さんによる論考およびイーノへのインタヴューはとんでもなく素晴らしい内容なので、未読の方にはご一読をお勧めする)、インスタレーションや映像作品への着手は音のみに没入するような聴取のあり方に対する抵抗であり、『Neroli』(1993年)以降の道程はレイヴ・カルチャーによって再定義されたアンビエントに対する抵抗であり(全篇アンビエントのアルバムとしては次の『Lux』まで19年ものときが空く)、U2やコールドプレイといったロック・バンドのプロデュースはアンダーグラウンドなあるいはエクスペリメンタルな音楽にしか価値を見出さない向きに対する抵抗であった。
このようにロックと現代音楽との間を、ポップとエクスペリメンタリズムとの間を行き来する彼の立ち居振る舞いは、いわゆる「ポストモダン」を体現したものであったと言うことができるだろう。『The Ship』でイーノが試みようとしているのは、そのような自身の履歴からの逃走であり、そのような自身の履歴に対する闘争なのである。
本作はひとつの大きな物語として展開していくが、そこで扱われるテーマがタイタニック号の沈没および第一次世界大戦であるのは単なる偶然ではない。先に述べたように、それら二つの出来事はイーノにとってひとつ前の時代の終焉を意味するものであった。すなわちイーノは本作において、自らの「ポストモダン」性に反抗するために、「モダン=近代」の終焉を参照するのである。
そのアイデアは、このアルバムの制作過程にも影響を与えている。
本作の制作は、イーノがストックホルムの映画館でのインスタレーションを依頼されたところから始まっている。彼はその会場内で、様々な場所に設置された様々な種類のスピーカーがそれぞれ異なる音を発していることに気がつく。それはつまり、ひとつひとつのスピーカーがそれぞれ「個性」を有しているということである。そのことにインスパイアされたイーノは、一度レコーディングされた音源を様々なスピーカーで鳴らし直すことで改めて音源に調整を加えていき、本作を練り上げていった。
ここで、第一次世界大戦の戦闘を特徴付けていたのが、機関銃と毒ガスという「新兵器」であったことを思い出そう。機関銃や毒ガスがそれ以前の武器と異なっていたのは、それらが敵の「個性」を無効化してしまうという点においてである。どのような「個性」の持ち主であれ、一度機関銃や毒ガスの前に身をさらされた者は、ただ自らの死を受け入れるほかに為す術を持たない。要するに、かつてロマン主義によって解放された「個性」は、第一次世界大戦によって粉々に打ち砕かれてしまったのである。本作でイーノが拾おうとするのは、そのようなかけがえのない「個性」の亡骸なのだ。
物語性の導入にせよ「個性」の尊重にせよ、それらが反動的な側面を有していることは否めない。つまるところ、本作は賭けなのである。それも極めて分の悪い賭けだ。イーノ自身、そのリスクは承知しているのだろう。だからこそ彼は「幻想」という言葉に導かれ、いま、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの "I'm Set Free" を歌うことを決意したのだ。「I'm set free / To find a new illusion(私は自由になる/新しい幻想を見つけるために)」。 この一節の強勢は「自由」の方にではなく「幻想」の方にある。
それはかつて科学技術や軍事力であった。それはかつて物語や「個性」であった。あるいはそれはかつて、民主主義や資本主義やキリスト教でもあっただろう。人びとがその手で生み出し、互いに合意し、信じ抜こうとするもの──それが「幻想」でなくて何だろう。音楽だってひとつの「幻想」だ。本作がデヴィッド・ボウイに捧げられていることの意味もそこにこそある。ボウイというかけがえのない「個性」が紡いだ物語も、またひとつの「幻想」であったのだから。
過去の歴史を踏まえた上で現在の世界の惨状と向き合うために、そして自身の履歴を踏まえた上で新しい音楽を生み出すために、イーノはここに『The Ship』という新たな「幻想」を作り上げた。その新たな「幻想」は、タイタニック号のバンドメンバーたちが奏でていたようなアンビヴァレントなものではない。このアルバムは、かけがえのない「個性」を持った、たったひとりのあなたに、能動的に聴かれることを欲している。かつてヴェルヴェット・アンダーグラウンドの音楽が、ブライアン・イーノというたったひとりの「個性」のもとへ届いたように。
 フューチャー・デイズ
フューチャー・デイズ