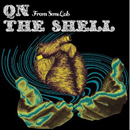年末の『エレキング』(紙版--もう書店に並んでいるので、みなさんよろしくお願いします)をホウホウの体で入稿したあとののんびりした正月の一週間で『漱石を読む』(福武書店)を読んだ。につまって個体になったブラックコーヒーのような文章の連鎖をたどるだけで、私はたいへん幸福な気分になる。以前湯浅学氏が『レコード・コレクターズ』で「溶けた鉛を飲みこむような」と評した――もしかしたらちがう人が書いたかもしれない--キャプテン・ビーフハートの代表作『トラウト・マスク・レプリカ』を文章に置き換えたら、こんな感じかもしれないと思った。いや、ほんとうは、いまから20年ほど前、学生だった私は、学生はつねにそうであるようにサヨク的であり、井上光晴をよく読んでいたが、彼が死んでひと月ほど経った『群像』だったかに彼の追悼特集が組まれ、特集とは関係のない、その号の巻頭にあった小島信夫の短編(「羽衣」だったと思う)のひとを食ったというよりも前提を無視した書き方に衝撃を受け、当時新刊だった『漱石を読む』はそのとき買ったのだが、小島信夫の批評集成が水声社からでたのを知って、再読したのだった。じつはビーフハートを聴いたのは、恥ずかしながら、その翌年の暮れにワーナーからはじめて国内盤CDがでたときであり、順番は逆だった。彼らの古典の誇張、いや、むしろ古典のディシプリンと呼びたくなる行為のなかからなにかが反転し、前衛と意図することのない道筋を、目の前に広がる道なき荒野に浮かびあがらせる感じは方法意識におもに焦点をあててきたが、私には抽象論、概念論だけではない、端正なフォーマットを否定する行為を運動に転化させる意図があった。膨大に引用する過去作品が薪や炭のように内燃機関を燃えあがらせ、吐き出した煙は粉塵をあとにのこした。エコロジカルな洗練は微塵もない。彼らは過去を他者をリスペクトしたように見せかけながら、小説や批評、あるいはブルースとブルースのあとに連なったポピュラー音楽のうえにことごとく「私ではないもの」としてあるときは傍線を引き、またあるときはその上に二重線を書きこんだが、「私」とはどういうものか?
私は大晦日の紅白歌合戦のサワリだけ見ようと、テレビをつけると浜崎あゆみが歌っていた。"ヴァージン・ロード"という歌だった。彼女は純白のウエディング・ドレスを着てNHKホールの客席の後方から現れ、ドレスの後ろ裾は何十メートルにも及んでいたようだった。その姿は歌の内容とそぐわないわけではなく、むしろそのものなのだが、彼女がウエディング・ドレスを着て熱唱したただそれだけのシンプルな演出は、NHKホールの客席はおろか、テレビの画面を眺める私たちにも向けていないようであった。歌に没頭するというより、目もくれず演じるようであり、その歌唱にはチェリッシュから平松愛理を経て木村カエラにいたる、満ち足りた結婚ソングにはない非日常性が際だっており、ひとことでいえばオペラめいており、またそれは俗流のオペラや演劇や文学がそうであるように感傷的であり悲劇的に思えた。ケータイ小説的といってもよかった。2011年になって、YouTubeで"Virgin
Road"のPVをみて、そのときかんじたことの一端はわかった。PVで彼女は花嫁姿で武装していた(形容でなくマシンガンをもった花嫁を演じていた)。浜崎あゆみは"Virgin Road"を映像化するにあたり、社会と切断した、ゼロ年代にセカイ系と呼ばれたものの雛形として、秩序を向こうにまわし戦ったボニーとクライド(『俺たちに明日はない』)を記号化したドラマがあったが、誰もが知っている通り、ボニーとクライドは悲劇である(これがシドとナンシーだったらもっと喜劇的だったろうに)。そこにはカタルシスに向かって感情を増幅させていくヴェクトルがあり、それはきわめて音楽的であるだけでなく、一面的に音楽的、つまり予定調和であり様式である。
はたして彼女はその数時間後に、シェーンベルグから〈メゴ〉に至るまで、形式と抽象主義の大国オーストリア出身の俳優と結婚したのだが、いいたいのはそんなことではない。結婚の翌日か翌々日に彼女は「私はこれからも私であり続ける」というふうなコメントを出した。ここで彼女いう「私」はどんな「私」だろうか? 彼女個人ばかりでなく、90年代後半から彼女が音楽を通して代弁してきた、無数のシチュエーションとそこに直面した無数のひとたちの心情はそこに含まないのだろうか? 結婚という人生の転機においてさえも変わらない「私」とはなんだろうか?
私には妻も子もいる(だんだん文章が妙な方向にいきそうだが......)。家庭をもつ身には家賃が高い上に狭い東京のマンションの一室では音楽さえまともに聴けない。『明暗』の津田のように親の援助を得られない境遇ではなおさらで、家人が寝静まった夜に蚊の鳴くような音でストゥージズを聴くこともしばしばである。私は強がってそこにこそ発見があるとはいわないけれども、主体はつねに状況の変容の憂き目に晒されていて、「私」は変わることは前提にある。もちろん状況とは結婚そのものを指してもいて、彼女は旧態依然とした結婚という制度に絡めとられないと宣言したとも考えられなくはない。では、ジェンダーが問題になるかといえばそうではない。ジェンダーの基底にある社会と制度、そこで拮抗する進歩主義と保守主義の両面から中心を眺めるときの視差があり、感覚的に後者に目を瞑ることで、主体である「私」は遠近感が曖昧にならざるを得ないということかもしれない。私は保守主義に与したいのではなく、制度をとりまく考えの両翼が問題にする以上に現状は屈折しており、結婚しようとしても簡単にできるものではない。との前置きを置くなかでは、戦後すぐの作家たちの初期設定だった家族観を共有できた時代--江藤淳が戦後の象徴とし、上野千鶴子が「男流」と呼んだ小島信夫に代表される家族観への両者の意見こそ視差だろう--はいまの時代、牧歌的にすら映るが、牧歌的な風景において当の「私」は家族という集団のなかで一筋縄ではいかない個別の問題を抱え翻弄される。それは古典的な制度の特異点かもしれないが、特異点としての「私」は普遍性への迂回路として機能しはじめる、そしてそういった特異点は関係性のなかにしか存在し得ないと小島信夫であれビーフハートであれいっていたように思える。浜崎あゆみにはそれがない。彼女の「私」は代名詞でこそあれ、変数ではない。90年代末、あるいはゼロ年代初頭に彼女が代弁していた最大公約数としての「私」は消え、彼女はすでにマジョリティの声ではない、というのは、産業としての音楽の斜陽化と、ポップ(アイドル)ミュージックにおける人工美がさらに加速したことが原因かもしれないし、背景にあるハイパー個人主義は多数派を作ることすら躊躇わせる何ものなのかもしれない。ハイパー個人主義というより個人主義のインフレーションが起こったこの10年は同時に、先鋭性とひきかえに金メッキのように薄く引き延ばされた(新)保守主義が社会の表層にはりついた10年だったといいかえてもいい。カルチャー全体の古典回帰はその背景と無縁ではないと思うし、私もこの数年古典に触れる機会は多かった。小島信夫しかりキャプテン・ビーフハートしかり。それらには制度/形式という組織体が存続するかぎりそこに巣くっていて蠕動する感じがある。かつてそうだっただけでなくいまでもそうなのである。そのとき「私」というものはそこでは、任意の空間における任意の点であるだけでなく、ブラウン運動をする点どうしの特殊な関係性のなかで、不確定性原理に似た対象との関わりを持たざるを得ない。となると、「社会は存在しない」という観点と、(ポスト・)フェミニズムをあわせて検証することになり、煩雑かつ長大になるので避けるが--後者については、『ゼロ年代の音楽 ビッチフォーク編』(河出書房新社)という本があるのでそちらを参照ください--ゼロ年代以降の「私」のうしろには公約数が控えているのではなく無限の匿名性が広がっており、もとが匿名的だったダンス・カルチャーの停滞はゆえなきことではなく、無数のジャンルが乱立したのは反動かもしれない。しかしそれぞれが音楽の制度であるジャンル・ミュージックとの関係を特殊に保つかぎり音楽はいくらか延命する可能をのこしている。ビーフハートのようにわかれないものとして、歴史のなかに宙づりになって。
彼はいまは絵描きとして暮らしているが、ほんとうにまた音楽をはじめるチャンスはゼロなのだろうか。そう思う間もなく、浜崎あゆみの入籍より2週間も早く、ビーフハートは鬼籍に入ってしまった。
キャプテン・ビーフハートことドン・ヴァン・ブリートは2010年12月17日に没した。その2週間前、高校の同級生で『トラウト・マスク・レプリカ』をプロデュースしたフランク・ザッパの命日にあたる12月4日に、トークショウで湯浅学氏とザッパについて話した。
「ザッパはキャプテン・ビーフハートの才能に嫉妬してはいなかったでしょうか?」
私はそう訊くと、湯浅氏は「それはあっただろう。ビーフハートみたいに形式を無視した音楽を作ったひとは、ザッパのような音楽主義者には疎んじられただろうが、憧れられもしただろう」
そう述べたのは、ビーフハートの音楽はデルタ・ブルースを土台にしたが、やり方はブルースを洗練させるものではなく、緊張させ、野生化したのだといいたかったと思われる。それがもっとも顕著にあらわれたのはいうまでも『トラウト・マスク~』だが、その前の2作『セイフ・アズ・ミルク』『ストリクトリー・パーソナル』にしてもブルースに収まりきらないものはある(後者は彼らの英国ツアー中にマネージャーが勝手にだしたものだが)。ただ遠心点をどこに置くかには迷いというか、若干の逡巡はかんじる。逆説的にいえば、ブルースはおろか、音楽さえも追い越す音楽をこの世に生み出すことの畏れを乗り越えた結果、この世に生まれたのが『トラウト~』だったといえる。それほどこのアルバムはたいへんな戦いの涯に生まれた。「作曲8時間、練習1年、録音1週間」かかったとこのアルバムは語り草になっている。しかし筆舌に尽くしがたかったのは、音楽よりヴァン・ヴリートの意を汲むところにあった、と当時マジック・バンドの一員だったズート・ホーン・ロロことビル・ハークルロートは『ルナ・ノート』(水声社)で『トラウト~』の制作過程を述懐している。
「俺はなんとなくもう『奴隷犬』みたいになりかけていた。不可能と思われるパートの練習に三時間も悪戦苦闘し続けて、豚のように汗まみれになっていたのを思い出すな。実際、それは絶対に不可能だったんだ! 最終的に俺はその八十パーセントぐらいを達成し、俺にできる限りのことはやったという結論に落ち着いたが、それは実に九ヶ月の間この曲を練習続けた後のことだ! 何より最悪なのは、どこで曲が終わるか、曲の長さがどのくらい引き延ばされるのか、いつ変更されるのかもわからない。はっきり言ってドンの気まぐれ次第だったんだ」
ヴァン・ヴリートはほとんど弾けないピアノを叩きながら『トラウト~』の曲を作曲し、マジック・バンドのメンバーに声音を使ったり色や情景で説明したりしたという。カリスマといわれるミュージシャンにありがちな過剰な自意識がそこに絡んでいるようにみえる。しかしそのエゴはただ肥大して存在を誇示するのではなく、周囲を飲みこみ、世間と衝突する運命にあった。およそ最悪な独裁者といわれてもしょうがないヴァン・ヴリートのコントロール・フリークぶりと疑心暗鬼と独善性は、彼の音楽が理解されないことへの怒りの裏返しであり、また同時に理解され得ない音楽に執着せざるを得ないみずからへの苛立ちの反動でもある。ロバート・ジョンスンが十字路で悪魔と取り交わした契約に、69年のドン・ヴァン・ヴリートは手を染めた......と書くと情緒的に過ぎるが、それほど『トラウト~』の異質さはロック史に鮮烈にのこっている。そして、つけくわえるなら、サマー・オブ・ラヴの時代の悪魔はすくなくとも戦前よりトリッピーだったはずだ。
ハークルロートはこうも述べている。
「ドンの創造力というのは、純粋に音楽的な意味では、あまり明確な形を持ってないんだな。むしろものの見方が彫刻家の目なんだよ。音も、体も、人も、全部道具として見ているのさ。結局彼のバンドの一員としての俺達の使命は、彼の持つイメージを、何度でも再生可能な『音』に変えることだった」
ハークルロートが彫刻家にどんなイメージをもっていたかはわからない。しかしヴァン・ヴリートの音楽をこれほど的確に表す評言もない。ポリフォニーともヘテロフォニーともいえる音楽の構造を空間の奥行きに置き換えたキャプテン・ビーフハートと彼のマジック・バンドは、フィル・スペクターやビートルズがスタジオに籠もって行った実験を、灼熱の砂漠にもちだしたといっても過言ではない。ビーフハートにはオーディオマニアックな人間がよろこぶ立体感やら奥行きやらはない。がしかし、どもるようにシンコペートし、強迫神経症のようにイヤな汗をかいたままループするフレーズの数々は、一音一音がそれぞれを異化し、触れられるほどの物質感をもっている。前からだけでなく、後ろからも斜めからも眺められる。賢明な読者のみなさんはもうお気づきかと思うが、それはまるでサイケデリックな体験の渦中のようだ。
追記:浜崎あゆみの入籍から3日後、元ジャパンのベーシスト、ミック・カーンが物故者になった。『トラウト~』の13曲目、"Dali's Car"と同名のバンドを元バウハウスのピーター・マーフィと再始動しようした矢先の訃報だった。ヴァン・ヴリートと同じく絵描きであり彫刻家でもあった彼のベース・ラインは音楽の規範を逸脱した、ハークルロートにならうなら、まさに彫刻的なものだった(とくに『錻力の太鼓』のアイデアは、ホルガー・シューカイとジャコ・パストリアスをつなぐものだったとも思う)。
ともにご冥福をお祈りします。
 シカゴ・ハウス第2世代Ron Trent、Chez Damier等が中心に躍り出た96年にHeaven And EarthやPurple Hazeの名義で作品をリリースし、シカゴ・ハウス・シーンに衝撃を与えたLuke Solomon。その後、Chez DamierのパーティーでDJをした際に知り合ったDerrick L. CarterとレーベルClassic Music Companyを設立。Gemini、DJ Sneak、Herber、Blaze、Metro Area等といった幅広いアーティ ストたちの良質な作品をリリースし、最重要レーベルの1つとして知られている。
シカゴ・ハウス第2世代Ron Trent、Chez Damier等が中心に躍り出た96年にHeaven And EarthやPurple Hazeの名義で作品をリリースし、シカゴ・ハウス・シーンに衝撃を与えたLuke Solomon。その後、Chez DamierのパーティーでDJをした際に知り合ったDerrick L. CarterとレーベルClassic Music Companyを設立。Gemini、DJ Sneak、Herber、Blaze、Metro Area等といった幅広いアーティ ストたちの良質な作品をリリースし、最重要レーベルの1つとして知られている。 イギリス出身のDJ/プロデューサー、アレックス・パターソンとThe KLFのジミー・コーティーによって、88年に結成。ジミー・コーティーの脱退以降、スラッシュや、キリング・ジョークのユース、システム7のスティーヴ・ヒレッジなど多数のアーティストがアルバム毎に参加。移り変わりの激しいエレクトロニック・ミュージック・シーンに於いて、常に時最先端で革新的な作品を送り出し続けている。代表作は『The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld』『U.F.Orb』『Orbus Terrarum』など数知れない。
イギリス出身のDJ/プロデューサー、アレックス・パターソンとThe KLFのジミー・コーティーによって、88年に結成。ジミー・コーティーの脱退以降、スラッシュや、キリング・ジョークのユース、システム7のスティーヴ・ヒレッジなど多数のアーティストがアルバム毎に参加。移り変わりの激しいエレクトロニック・ミュージック・シーンに於いて、常に時最先端で革新的な作品を送り出し続けている。代表作は『The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld』『U.F.Orb』『Orbus Terrarum』など数知れない。