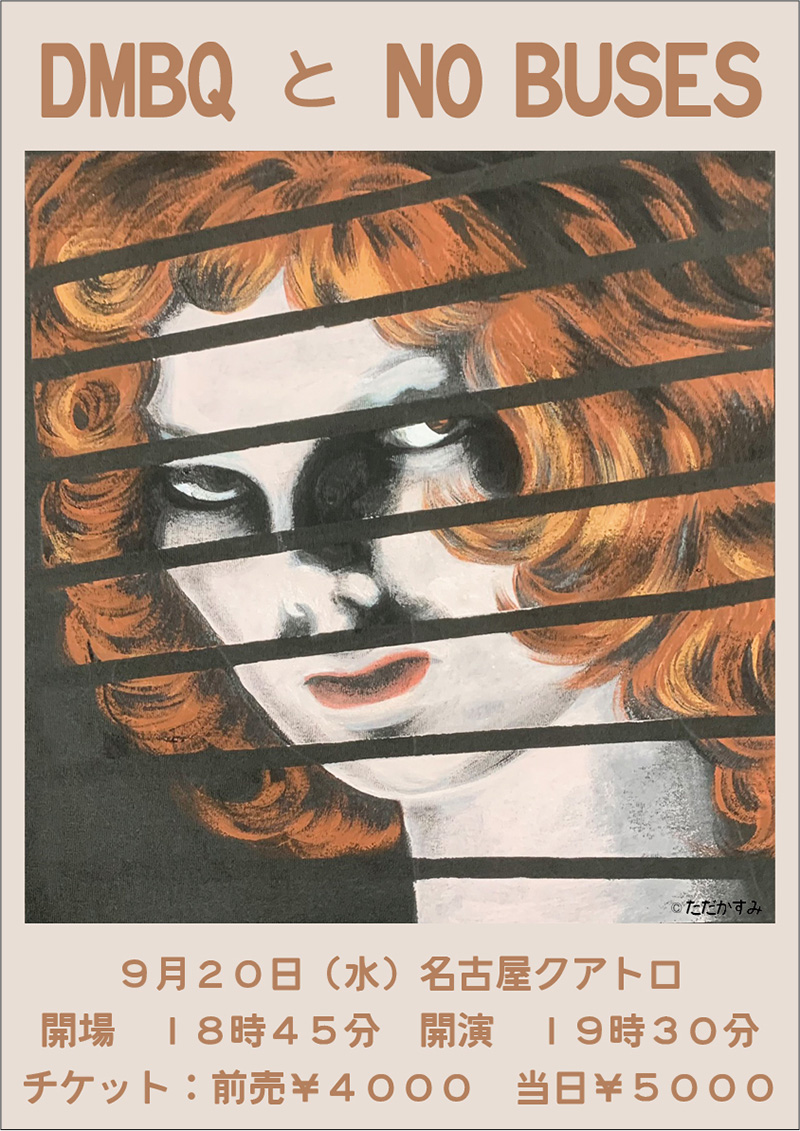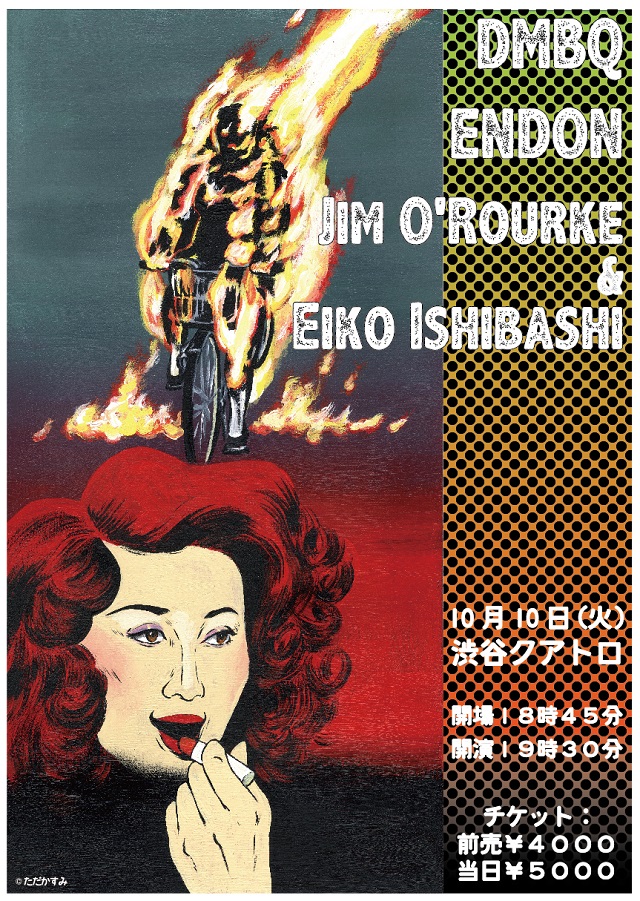ぼくの場合、マーヴィン・ゲイの『What's Going On』をちゃんと聴いたのはけっこう遅くて、80年代も後半、ぼくは20代のなかばだった。熱心に追いかけていたポスト・パンク以降がすっかりつまらなくなってしまい、だからレゲエやワールド・ミュージックを聴いてみたり、あるいは、それまでずっとリアルタイムの音楽しか聴いていなかった自分が、過去の黒人音楽を聴いてみようと自分なりに追求していた頃のことだ。
『What's Going On』の説明文には必ず「戦争」や「公害」や「貧困」といった言葉が挿入され、これはプロテスト・ミュージックとされている。ところが、買ったそのレコードは輸入盤だったので、というかまあ、正直に言えばいちいち歌詞まで分析するのは面倒なので、サウンドのみに集中し、だからぼくはただただそのサウンドの優雅さに惹かれたのである。マーヴィン・ゲイは嘆き、憤り、哀しみ、辛辣で、抵抗している。60年代の革命は失敗に終わり、抵抗勢力は片っ端から取り締まられ、ヤッピー時代の到来とともにブラック・コミュニティに暗い風が吹きはじめている。現実は極めて厳しかったろう。だが、そのサウンドは寛容で、温かく、優しい。ロマンティックな思いにさえもリンクする。これと同じような感想を、スピリチュアル・ジャズと呼ばれる音楽にも感じたことがある。あれも黒人の闘争を起点に生まれた音楽だが、出てくるサウンドには「愛」がある。あの時代の、文化のモードがそうさせたのだろう。
アメリカのテッド・ジョイアというジャーナリストの分析によれば、1950年代なかばから1960年代のなかばにかけてのアメリカにおいて興行成績が良かった映画は『サウンド・オブ・ミュージック』や『スイスファミリーロビンソン』のような作品だった。ところが近年のヒット作は、おしなべて戦闘ものが多く、間違ってもミュージカルやコメディではないそうだ。まあ、50年代のアメリカに関しては戦後の好景気ということが大きかったと思うけれど、なんにせよ、文化の根幹に楽天性があったことはたしかで、そのモードはおそらくはビートニクやヒッピー、パンクからレイヴ・カルチャーにまで通底していたと言えるのではないだろうか。たとえば、そのクライマックスにおいてベトナム戦争と反戦運動があったとしよう。しかし同時にそこにはしつこいくらいに「愛と平和」があった。陳腐な側面も多々あったと思う。だが、それはたしかにあったし、それを理解できる世代とできない世代とに分かれてもいた。そしていま、ぼくの両親の世代が「愛と平和」(ビートルズからレイヴまで)のセンスを理解できなかったのと同じように理解できない新しい世代が台頭しているのかもしれない。そんな見立ても通用するんじゃないかと思えるほどに、文化のモードは『What's Going On』の頃とは変わっている。
リベラルだろうがネトウヨだろうが好戦的で、政治家も政党もアニメも漫画もラップにおいても戦いが人気を博している。人はカラフルな服よりも白黒を好み、自分の個性を表現することよりも、なるべく目立たない(空気を壊さない)服装を好むようになった。インターネットには怒りと対立、憎しみと不寛容、攻撃と嫌みが溢れている。明治中期のロマン主義から大正ロマンに象徴されたモードが100年前の関東大震災を境に変化したのだとしたら、3.11が(ないしは安倍政権が)この変化の起点になったと言えやしないだろうか。良い悪いの話でも、好き嫌いの話でもない。ぼくだって少なからず、今日の文化のモードの影響下にいる。本当はスマイリーのTシャツを着たいけれどジョイ・ディヴィジョンで我慢している人だっているかもしれない。
とくに検証したわけではないのだが、漠然と、そんなことを考える/ことさら感じるようになったきっかけのひとつが、『Selected Ambient Works 85-92』だった。昨年は、エイフェックス・ツインのこの傑作がリリースから30周年ということで、ぼくは家でじっくり聴いたことがあった。30年前に渋谷のWAVEで買ったレコードを取り出し、聴いて、そして、あらためて驚嘆した。こんなにも、アホらしいほど楽天的でラヴリーな音楽が30年前の世界では、特別な宣伝もロック雑誌の煽りもなかったのに関わらずがちで必要とされ、多くの若い世代に享受されていたのだ。あの頃だって湾岸戦争はあったし、社会にはいろんな軋みがあったというのに。
歌詞や資料など読まずに、まずはサウンドのみに集中する。アノーニ・アンド・ザ・ジョンソンズの新作にもそのように臨んで、1曲目 “It Must Change” を聴いて微笑んでしまい、3曲目 “Sliver of Ice” を聴いてこれは素晴らしいアルバムだと確信した。なんて美しいソウル・ミュージックだろうか。ドラマティックに展開する “Scapegoat” は彼女の代表曲になるだろう。前作ほど露骨な政治性はないものの、作品の背後には、理想を諦めないアノーニの、不公正(トランス嫌悪、資本主義etc)をめぐっての嘆きがあることはつい2日前に知った。もっとも、このサウンドが醸し出すモードそれ自体が反時代的で、プロテストではあるが好戦的ではないし、さらに重要なのは、こうした過去のソウル・ミュージックを引用する際に陥りがちなたんなる反動=後ろ向きの郷愁をこのアルバムが感じさせないことだ。今日の文化のモードを引き受けながら、しかしその範疇では表現しきれないものを表現するために過去のモード、愛と寛容の時代のモードを使っている。これは言うにたやすく、説得力を持たせるにはそれなりの力量を要する。なぜなら、今日のモード外でやることは陳腐になりかねないリスクが大いにあるからだ。
アノーニは、『Age Of』制作中のダニエル・ロパティンの環境問題を諦めている態度に怒ったほどの人である。本作に、彼女のそうした現実を直視したうえでの理想主義と辛辣さ、叙情詩と個人史が散りばめられていることは先にも少し書いた。ストーンウォールの反乱から54年、彼女はクィアの人生を、たとえそれが孤独であろうと美しく描き、ギル・スコット=ヘロンではないが闘いを詩的に見せている。だからこのアルバムには、極めて今日的なトピックを持ちながらもタイムレスな魅力があり、未来の誰かの部屋のなかで再生されてもサウンドの香気が失われることはない。音楽(サウンド)でしか表現できないことがあって、それを『私の背中はあなたが渡る橋でした(My Back Was a Bridge for You to Cross)』という長ったらしいタイトルの本作はやっているという、そのことをぼくは強調したい。彼女の、みごとな表現力を携えた歌唱を支えている演奏には、電子音楽家のウィリアム・バシンスキー、イーノとの共作者で知られるレオ・アブラハムスも参加している。アートワークには「いまこそ本当に起きていることを感じるとき」という手書きの文字がある。「本当に起きていること」を人が本当に感じることは容易ではない。しかし、それでもポップ・ミュージックがその手助けになるのだとしたら、『私の背中は〜』は、愛を語ることが疎外されていることを感じさせ、そしてこの音楽が堂々と愛を語っていることを感じないわけにはいかないのだ。