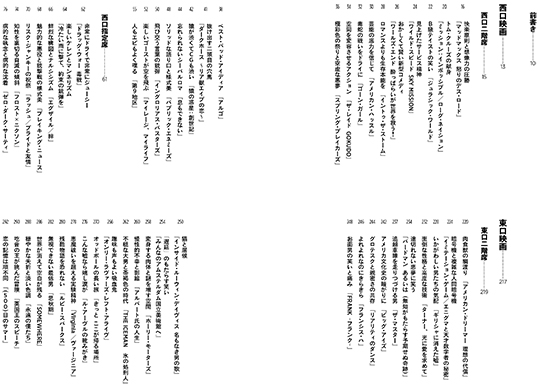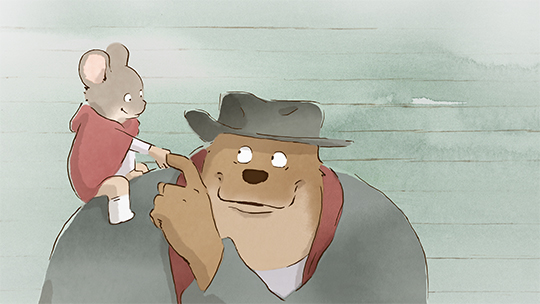大盛況のうちに終了した「マイマイ計画 × 野島健児presents マイマイセッション!」。お越しいただいたみなさま、ありがとうございました。
ご来場のみなさまには、開演までのわずかな待ち時間の中で、著者・智司さん画のマンガにセリフを入れていただきました。
子どものころは、お兄さん・健児さんと毎晩のように制作していたというこのマンガあそび。絵を描くのは智司さん、セリフを入れるのは健児さん──「いまもずっと同じことをしています」とおっしゃっていたのが印象的です。
それでは、みなさんがつくってくださった作品の中から、智司さん賞と健児さん賞をご紹介いたしましょう。智司さん賞はコメント付!
あんな短い時間で、とつぜんペンを渡されて、たくさんの方々がオリジナリティあふれるストーリーをつくってくださり、スタッフ一同驚愕とリスペクトの念に打たれました。あそびが「ひらき」ながら、クリエイティヴなエネルギーを巻き込んでいた会場でした!

ちかさん「割と適当に考えた話」

コウモリがなぜだか片言の日本語!
さかたあやこさん「うれないロールケーキやさん」

あのぐるぐるは、ロールケーキなのか?!
しのぶさん「今年の流行大賞」

トーク中に紹介した作品。ナメクジだったのか…。
よしいかずみさん「ひみつの貝」

冒頭のブタさんの非礼さがよい。

ちさかもと美さん「失恋」

森しおりさん「夕食の献立」

きょうたにかおりさん「次男のイタズラ♪」

あかさくさん「弱肉強食」

 グライム/ダブステップ・シーンの若きマエストロ、スウィンドルは幼少からピアノ等の楽器を習得、レゲエ、ジャズ、ソウルから影響を受ける。16才の頃からスタジオワークに着手し、インストゥルメンタルのMIX CDを制作。07年にグライムMCをフィーチャーした『THE 140 MIXTAPE』はトップ・ラジオDJから支持され、注目を集める。09年には自己のSwindle Productionsからインストアルバム『CURRICULUM VITAE』を発表。その後もPlanet Mu、Rwina、Butterz等からUKG、グライム、ダブステップ、エレクトロニカ等を自在に行き交う個性的なトラックを連発、12年にはMALAのDeep Mediから"Do The Jazz"、"Forest Funk"を発表、ジャジーかつディープ&ファンキーなサウンドで評価を決定づける。そして13年のアルバム『LONG LIVE THE JAZZ』(Deep Medi)は話題を独占し、フュージョン界の巨匠、LONNIE LISTON SMITHとの共演、自身のライヴ・パフォーマンスも大反響を呼ぶ。14年のシングル"Walter's Call"(Deep Medi/Brownswood)ではジャズ/ファンク/ダブ・ベースの真骨頂を発揮。そして15年9月、過去2年間にツアーした世界各地にインスパイアされた最新アルバム『PEACE,LOVE & MUSIC』(Butterz)を発表、新世代のブラック・ミュージックを提示する。
グライム/ダブステップ・シーンの若きマエストロ、スウィンドルは幼少からピアノ等の楽器を習得、レゲエ、ジャズ、ソウルから影響を受ける。16才の頃からスタジオワークに着手し、インストゥルメンタルのMIX CDを制作。07年にグライムMCをフィーチャーした『THE 140 MIXTAPE』はトップ・ラジオDJから支持され、注目を集める。09年には自己のSwindle Productionsからインストアルバム『CURRICULUM VITAE』を発表。その後もPlanet Mu、Rwina、Butterz等からUKG、グライム、ダブステップ、エレクトロニカ等を自在に行き交う個性的なトラックを連発、12年にはMALAのDeep Mediから"Do The Jazz"、"Forest Funk"を発表、ジャジーかつディープ&ファンキーなサウンドで評価を決定づける。そして13年のアルバム『LONG LIVE THE JAZZ』(Deep Medi)は話題を独占し、フュージョン界の巨匠、LONNIE LISTON SMITHとの共演、自身のライヴ・パフォーマンスも大反響を呼ぶ。14年のシングル"Walter's Call"(Deep Medi/Brownswood)ではジャズ/ファンク/ダブ・ベースの真骨頂を発揮。そして15年9月、過去2年間にツアーした世界各地にインスパイアされた最新アルバム『PEACE,LOVE & MUSIC』(Butterz)を発表、新世代のブラック・ミュージックを提示する。 名だたるフェス出演や多忙なDJブッキングでUKベースミュージック・シーンの女王とも言える活躍を見せるFlava Dは2016年、最も注目すべきアーティストの一人だ。
名だたるフェス出演や多忙なDJブッキングでUKベースミュージック・シーンの女王とも言える活躍を見せるFlava Dは2016年、最も注目すべきアーティストの一人だ。 UK発祥グライムの新時代を牽引するレーベル/アーティスト・コレクティブ、Butterzを主宰するELIJAH & SKILLIAM。イーストロンドン出身のふたりは05年、郊外のハートフォードシャーの大学で出会い、グライム好きから意気投合し、学内でのラジオやブログを始め、08年にGRIMEFORUMを立ち上げる。同年にグライムのDJを探していたRinse FMに認められ、レギュラー番組を始め、知名度を確立。10年に自分達のレーベル、Butterzを設立し、TERROR DANJAHの"Bipolar"でリリースを開始した。11年にはRinse RecordingsからELIJAH & SKILLIAM名義のmix CD『Rinse:17』を発表、グライムの新時代を提示する。その後もButterzはROYAL T、SWINDLE、CHAMPION等の新鋭を手掛け、インストゥルメンタルによるグライムのニューウェイヴを全面に打ち出し、シーンに台頭。その後、ロンドンのトップ・ヴェニュー、Fabricでのレギュラーを務め、同ヴェニューが主宰するCD『FABRICLIVE 75』に初めてのグライム・アクトとしてMIXがリリースされる。今やButterzが提示する新世代のベースミュージックは世界を席巻している!
UK発祥グライムの新時代を牽引するレーベル/アーティスト・コレクティブ、Butterzを主宰するELIJAH & SKILLIAM。イーストロンドン出身のふたりは05年、郊外のハートフォードシャーの大学で出会い、グライム好きから意気投合し、学内でのラジオやブログを始め、08年にGRIMEFORUMを立ち上げる。同年にグライムのDJを探していたRinse FMに認められ、レギュラー番組を始め、知名度を確立。10年に自分達のレーベル、Butterzを設立し、TERROR DANJAHの"Bipolar"でリリースを開始した。11年にはRinse RecordingsからELIJAH & SKILLIAM名義のmix CD『Rinse:17』を発表、グライムの新時代を提示する。その後もButterzはROYAL T、SWINDLE、CHAMPION等の新鋭を手掛け、インストゥルメンタルによるグライムのニューウェイヴを全面に打ち出し、シーンに台頭。その後、ロンドンのトップ・ヴェニュー、Fabricでのレギュラーを務め、同ヴェニューが主宰するCD『FABRICLIVE 75』に初めてのグライム・アクトとしてMIXがリリースされる。今やButterzが提示する新世代のベースミュージックは世界を席巻している!