昨年放ったサード・アルバム『Ψ』で新機軸を打ち出したパテンが、ICAロンドンでの公演にあわせて、新たなEPのリリースを発表しました。現在、収録曲の“Amulet”が先行公開されています。はたしてこのEPは『Ψ』のアウトテイク集なのか、それとも次のアルバムへの重要な布石なのか? 公開された“Amulet”は無料でダウンロードすることが可能となっていますので、それを聴きながらあれこれ想像しちゃいましょう。ダウンロードはこちらから。
patten
〈Warp〉所属の新鋭プロデューサー・デュオ、パテンが
4曲収録の最新EP「Requiem」のリリースを発表
新曲“Amulet”を無料DLで配信!
〈Warp〉の実験性と音楽性の高さを継承する新鋭プロデューサー・デュオ、パテンが、新曲4曲を収録した最新EP「Requiem」のリリースを発表! 新曲“Amulet”を公開! 公式サイトでは無料DLも可能。
patten - Amulet
https://youtu.be/zK_1y36jjCg
公式サイトで「Amulet」を無料DL配信中
https://patttten.com/
 label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS
label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS
artist: patten
title: Requiem
release date: 2017/05/12 FRI ON SALE
iTunes Store: https://itunes.apple.com/jp/album/id1231337426
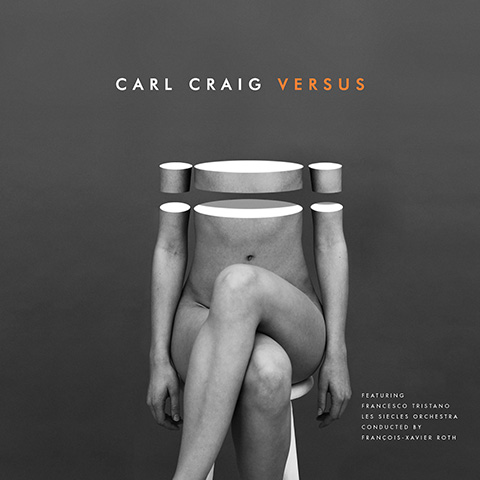

 label: BRAINFEEDER / BEAT RECORDS
label: BRAINFEEDER / BEAT RECORDS







