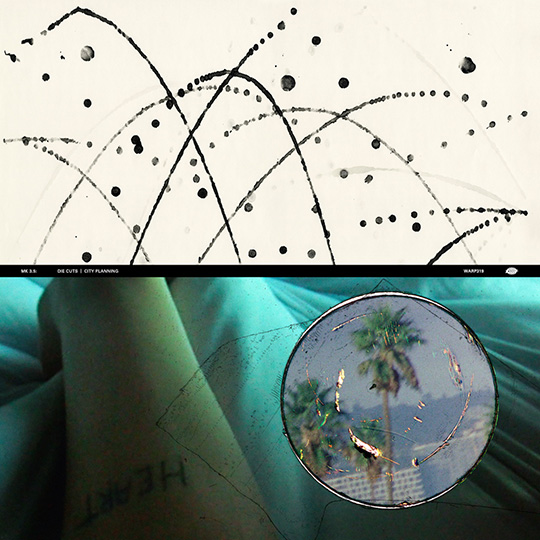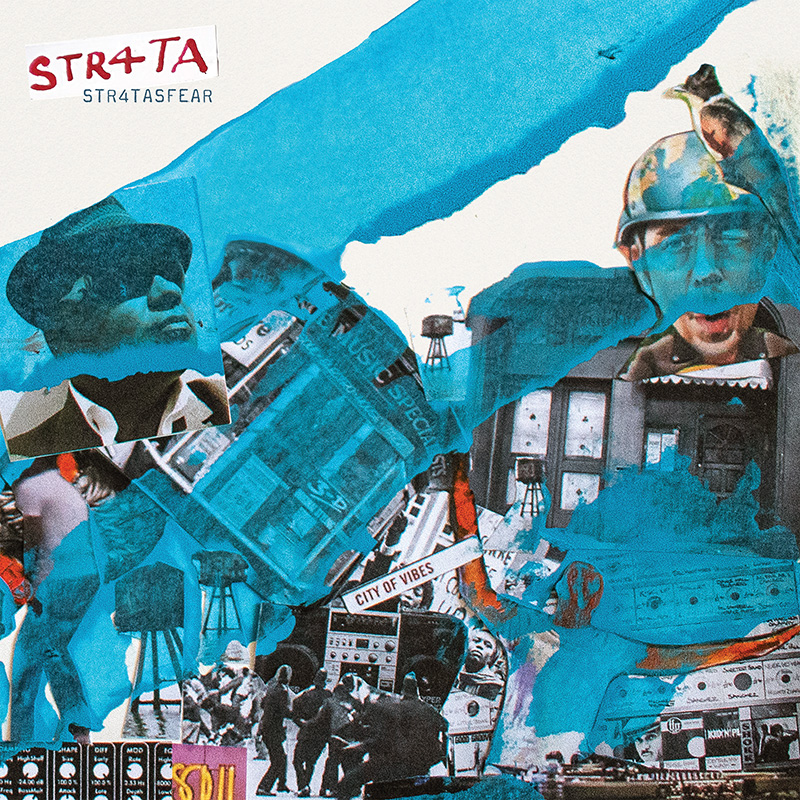エストニアのマーヤ・ヌート、なんと12月に初来日することが決定した。彼女の民俗音楽とエレクトロニカの融合が直に聴けるのは楽しみでしかない。共演にはエストニアで交流も果たしたASUNA、そして『hinged』の日本盤リリースや本公演へのきっかけを作ったShhhhhがDJで彩りを添えます。
Maarja Nuut Japan Show 2022
日程:2022年12月6日(火)
会場:代官山・晴れたら空に豆まいて
時間:OPEN 18:30 /START 19:30
料金:ADV ¥3,800 / DOOR ¥4,300 (共に1ドリンク代 600円別途)
チケット予約:https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/news/maarja-nuut-japan-show-2022/
出演:
Maarja Nuut
ASUNA
DJ: Shhhhh
Maarja Nuut:
1986年生まれ、エストニアはラクヴェレ出身のコンポーザー/プロデューサー/シンガー/ヴァイオリニスト。幼少期から合唱団の指導者でもあった母親の影響で音楽を親しむようになる、7歳からヴァイオリンのレッスンを受け始め、12歳からタリン音楽高等学校で学んだ後、エストニア音楽・演劇アカデミーに入学。エストニアやヨーロッパ各地の音楽祭に参加し、早くから民族音楽に興味を持つようになる。21歳のとき、オランダ人チェリストのサスキア・ラオ・デ・ハースとともにインドを訪れ、ヒンドゥスターン音楽を学んだ。
2008年、エストニアに戻った彼女は民族音楽の道に進むことを決め、タルトゥ大学の一部門であるヴィリヤンディ文化アカデミーで学んだ。ここで、ソビエト連邦以前のエストニアの村の音楽の78回転レコードに出会い、インスピレーション得る。2011年からストックホルム大学で学び、特にポーランドの村落民俗音楽への関心を深めた。2014年に音楽の修士号を取得して卒業した。
元々はクラシックを学んでいたが、民族〜フォーク・ミュージックへと傾倒し、伝統的なエストニアのヴィレッジ・スタイル現代的な解釈へと消化するスタイルを確立。2013年にソロ・アーティストとしてアルバム『Soolo』デビューし、タリン・ミュージック・ウィークでアーティスト賞を受賞。2016年、ソロ・セカンド作『Une Meeles』をリリースし高い評価を得た後、独自のアブストラクト・エレクトロニック・サウンドを生成するHendrikKaljujärv(別名Ruum)とのコラボレーションを開始。Maarja Nuut & Ruumのデュオ名義で2枚のアルバムをリリースし、国際的なフェスティバルへの出演も果たす。2020年にはSan Arawとのコラボ作をリリースし話題となった。そして2021年にパンデミックのタイミングで受け継がれた祖母の古い農場の開墾と修理の合間を縫って自信の海辺のスタジオでプロデュース、録音をほぼ1人で敢行した自身にとって”初めての本格的なソロ・アルバム”という『hinged』をリリースした。

Maarja Nuut
hinged
PLANCHA
・日本盤ボーナス・トラック1曲収録
・解説:松山晋也
・歌詞・対訳付き
ASUNA(アスナ):
石川県出身の日本の電子音楽家。語源から省みる事物の概念とその再考察を主題として作品を制作。同時に音の物理現象に関する美術作品の制作/パフォーマンスも行う。代表作に「organ」の語源からその原義である「機関・器官」としてオルガンを省みた『Each Organ』(2002)、本の語源としてのブナの木を元に情報の記録・運搬について扱った作品『Epidermis of Beech』(2012)などがある。近年は、干渉音の複雑な分布とモアレ共鳴に着目した作品『100 Keyboards』(2013)で、「メルボルン国際芸術祭」(2018)、「シンガポール国際芸術祭」(2019)、「ベルファスト国際芸術祭」(2019) 、など海外のアート・フェスティバルから多数の招待を受け展示/パフォーマンスを行い、昨年も米ニューヨークの名門・BAM(ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック)からの招待を受け、全公演ソールドアウトとなる単独公演を成功させた。並行した音楽制作では、10代の頃から東京の実験音楽/即興/音響シーンに関わり、様々なアコースティック楽器やPCベースによる作曲作品から即興演奏まで行いつつ、無数のオモチャ楽器と電子音楽によるパフォーマンス『100 Toys』(2007) を中心とし、録音作品では毎回多岐に渡るコンセプトながらも一貫した作品制作を行う。これまで海外25カ国以上で演奏/展示、CDやレコードなどをリリース。ドイツの電子音楽家のヤン・イェリネクや、美術家の佐藤実-m/s、トラックメーカーのshibataらと長年に渡りコラボレーションによる制作も行っている。
Shhhhh (El Folclore Paradox/ The Observatory):
DJ/東京出身。オリジナルなワールドミュージック/伝統伝承の発掘活動。フロアでは民族音楽から最新の電子音楽全般を操るフリースタイル・グルーヴを発明。
執筆活動やジャンルを跨いだ海外アーティストとの共演や招聘活動のサポート。2018年秋よりベトナムはホーチミンのクラブ、The ObservatoryのレジデントDJに就任。
ミャンマー伝統音楽のリミックス盤『Kalab Mixed Myanmar #1』(Rollers)のキュレーション。Worldwide FM、NTSへのmix提供など。Rainbow Disco Club 2022、Mindgames presents Balanceへの出演も。
https://linktr.ee/kanekoshhhhh