すごくメチャクチャをやる人っていうのが書いてあって。「なんか面白そうだな」って、それで高3のときに初めて買ったのが『リチャード・D・ジェイムス・アルバム』。それが転機になった。転機というか、道を踏み外したというか。
エイフェックス・ツインがポップ・カルチャーにぽっこりと残した巨大な玉手箱、そのひとつは"子供"、いわばピーターパンである。アニマル・コレクティヴ、コーネリアス、そしてデデマウス......。ロックンロールが思春期のものであるのなら、その思春期とやらを嘲笑するかのように掃除機で吸い取り、あるいはまるめてゴミ箱に投げる。いや、そんな悪意のあるものではない。もっと愉快なものだ、子供たちを楽しませるような。
 DE DE MOUSE 「A Journey to Freedom」 rhythm zone/Avex Trax |
話を聞くために初めてデデマウスに会った。まるで十数年来の知り合いに会ったような気分だった。彼は息つぎする間もなく喋った。僕に質問する間も与えない。これは彼の策略なのだろうか。言いたいことを言い切って、そして走って逃げていく、子供のように......いや、マンマシンのように。
2007年にインディ・レーベルから出した『Tide of Stars』がほとんど口コミを中心に驚異的なセールスを記録して、まさに日本のテクノ新世代を代表するひとりとなったデデマウスは、この度、通算3枚目になる新しいアルバム『A Journey to Freedom』をエイベックスから発表する。以下のながーい話を読んでもらえれば、彼の音楽に特有な郷愁の感覚がどこから来ているのかわかってもらえると思う。あるいはまた、彼の音楽の背後にある理想のようなもの、そしてまた彼が音楽に託す思いのようなものも......。いや、それ以上によくわかるのは、彼が心底エレクトロニック・ミュージックを愛しているってことだ。
シロー・ザ・グッドマンって......近いですよね?
デデ:すごく近いです。でも、最近会ってないです。〈ロムズ〉から「(変名で)ださない?」と言われたことがあって、シロー君と高円寺のラーメン屋さんで会いながら。
飲み屋じゃなくて。
デデ:シロー君、シャイじゃないですか。
そう? ああそうかも(笑)。
デデ:シャイなんで、すごく冗談を言うんだけど、あんま目を見てくれなかったり(笑)。
ハハハハ。いやね、シロー・ザ・グッドマンと......年末だったかなぁ。高円寺で一緒に飲んでて、「いやー、オレにとっての失敗はデデマウスを出さなかったことやわ~」とぼやいていたんだよね。
デデ:ハハハハ。ホントに〈ロムズ〉が好きで、デモを送ってたんですよ。
言ってました。なのにオレは......みたいな(笑)。
デデ:でもダメで、そしたら永田(直一)さんが出してくれるっていうんで「じゃ、出しまーす」って。で、その後、シロー君からオファーされたんだけど、「いまさら鞍替えっていうのも何なんで」って(笑)。
最初から出してくれよって(笑)。
デデ:はい(笑)。正直、そう思いました(笑)。
まあ、それはともかく、デデマウスみたいな明白なまでにテクノをやっている新しい世代が、どっから来たのか興味あるんです。僕らの時代は、ハウスがあって、で、テクノがあってという風に、クラブ・カルチャーの歩みとともにあったけど、たぶん、違うじゃない。
デデ:ああ、はい。
どっから?
デデ:小さい頃はテレビのアニメ・ソング。まさに自分が曲作りするとは思わなかった......というか、歌うのが好きで。だからそれで、光GENJIとか歌って、「自分もこーなりたいなー」と(笑)。音楽とは歌って楽しくて儲かって、っていうイメージで(笑)。群馬の片田舎で育ったんで、テレビぐらいしかなかったんですよ。オレは大きくなったらアイドルになるって(笑)。人には言わなかったけど。さすがに中学生になる頃にはアイドルになろうなんて思ってなかったけど、まわりで地味だったヤツが音楽はじめたりして、バンドやったりね、「なんで、あいつが?」って、それがすごく悔しくて。
負けず嫌い(笑)。
デデ:で、家に父親のクラシック・ギターがあったので、友人からXの楽譜をもらって、クラシック・ギターでコピーしようとしたり。
ぜんぜんテクノじゃないね(笑)。
デデ:小学生のとき『シティハンター』のアニメがあって、そのエンディングがTMネットワークだったんですよ。その影響は実は、僕ら世代では大きい。みんな言わないけどね、実は大きいんです(笑)。それと都会に対する憧れが強い。そうなったときに、ダンス・ミュージックのほうが圧倒的にアーバンなわけですよ、Xよりも(笑)。すごくサイバーな感じがして。小室さんもライヴでシンセサイザーに囲まれていたりするじゃないですか。最初はあれが格好良く見えた。で、13~14歳ぐらいの頃から、ダンス・ミュージックいいなって思っていて、それと電気グルーヴですよ。
ああ、そうなんだ。
デデ:最初はよくテレビに出てたから芸人だと思ってたんですよ。でも、電気が"NO"出した頃から聴くようになって。
3枚目の頃から。
デデ:アシッドとかやりだした頃ですね。『テクノ専門学校』を聴いたり。
それは嬉しいね。中学生?
デデ:中3か高1ぐらい。そう、それで独学でキーボードの練習をはじめるんです。あと父親がオーディオマニアで、ヴィデオテープにFM番組を録音するような。
音質が良いからね。しかしホントにマニアだね、それ。
デデ:そうなんです。それで洋楽の格好良さを僕も知ってしまって。で、父親のコレクションにアバ、シック、カイリー・ミノーグなんかがあるわけですよ。そういうのを聴いているときに、ちょうど高2の頃、テクノ・ブームに当たった。ケンイシイさんが出した『ジェリー・トーンズ』とか。ただ、群馬の田舎だったから、ソニーが出していた〈ワープ〉のCDとか、ハードフロアとか、そんなものしか入って来ないんですよ。デリック・メイの『イノヴェイター』とか、もうちょっと後にはケミカル・ブラザース、アンダーワールド......。
まさにテクノ・ブームだよね。
デデ:当時、NHKでテクノの特番があって、〈レインボー2000〉の映像を流したんですよ。そこでアンダーワールドの"ボーン・スリッピー"を初めて聴いて、「これ、聴きたい!」と思って、買ったのが『ダブノーベースウィズマイヘッドマン』で、「あれ?」って(笑)。「こんな曲だっけ?」って。しばらくしてからシングルで出ているのを知ったような(笑)。
ハハハハ。
デデ:まあ、そんな感じだったんです。エイフェックス・ツインを知ったのは『キーボード・マガジン』だったかな。すごくメチャクチャをやる人っていうのが書いてあって、「なんか面白そうだな」って、それで高3のときに初めて買ったのが『リチャード・D・ジェイムス・アルバム』。それが転機になった。転機というか、道を踏み外したというか。
[[SplitPage]]で、エレクトロニカがブームになって、エイフェックス・ツインもエレクトロニカに括られて、「なんか違うな」って。エレクトロニカって上品なイメージがあったんですよ。そんなものじゃない気がするし、ラップトップの画面を見ながらライヴをしておしまいという、なんか不健全な感じがしたんです。
そうだよね。デデマウスの音楽を聴いてまず最初に思うのは、エイフェックス・ツインからの影響だもんね。
デデ:ドラムの打ち込みとかすごいじゃないですか。連打しまくって、感覚だけで作っているっていうか。リズムのバランスも悪いし、あのアルバムのすべてにもっていかれたというか。お気に入りの玩具、ゲーム、そんなようなものというか。いっつも聴いていた。
衝撃という点ではスクエアプッシャーの『ハード・ノーマル・ダディ』でしたけどね。ジャングルの影響受けながらフュージョンみたいなことやっているし、ホントにびっくりした。96年~97年ぐらいですかね。で、ミュージック(μ-Ziq)も出てくるでしょ。もう、あのブレイクビーツを聴いてまたびっくりしちゃった。スクエアプッシャーの『ビッグ・ローダ』、ミュージック、コーンウォール一派や〈ワープ〉をずーっと聴いていましたね。貪るように聴いた。で、ソニーがしばらくして、〈リフレックス〉の日本盤も出すんですよ。田舎で日本盤しか手に入らないから、それはほとんど買い漁った。あとはもちろんオウテカ。
まあ、通ってるだろうね。
デデ:『キアスティック・スライド』。三田(格)さんがライナー書いていたんじゃないかな。で、その後に出した......。
『LP5』!
デデ:あれがもう最高で! コンピュータが自動生成されたメロディとリズムによるまったく新しい音楽に思えた。
『キアスティック・スライド』や『LP5』はミュージシャンに与えた影響が大きいよね。シロー君たちもあそこら辺からテクノに入ったって言ってたよ。
デデ:ちょうどその頃から学校で上京したんです。もうそうなったら、暇さえあればシスコに行って新譜をチェックするという。
なんか意外と真っ当な道を歩んでいるんだね。
デデ:インターネットがまだ普及していないし。
そうだよね。だけどデデマウスを聴いて、エイフェックス・ツイン、そして〈リフレックス〉からの影響というのはすごくよくわかる。
デデ:そういってもらえると嬉しいんです。僕は、そこは愛を出しているつもりです。
アンダーワールドというほうが意外だよ。
デデ:当時『ロッキングオン』にも流された世代だから(笑)。『ロッキングオン』と『エレキング』に(笑)。リチャード・D・ジェイムスに関する伝説が載ってるじゃないですか。戦車乗ってるとか、1日3曲作ってるとか。
夢のなかで作曲してるとかね(笑)。
デデ:そういうのを全部信じていた(笑)。なんて格好いいんだろうって。
遊んでいる感じがあったよね。当時のエイフェックス・ツインって、20歳そこそこの若者が、業界の大人をからかっている感じがすごくあったでしょ。
デデ:そうそう。ちょっとバカにしている(笑)。それがすごく格好良く思えたんです。暴力的で、悪意に満ちていて、それが最高だって。僕が19~20歳で作った音楽には、ものすごくその影響があったんです。突然ノイズが出てきて、「あーっっははは」って笑ってみせたりとか。
音響やポスト・ロック系も好きでしたね。モグワイも好きだった。それでもデモを送ったのは〈リフレックス〉でしたけど。で、そうしたら〈リフレックス〉から返事が返って来たんです。まだ英語も読めないし、emailもできなかったんだけど、友だちでパソコン持ってるヤツがいて、彼のところに来たんです。「なんかお前宛に英語でメールが来ているよ」って。そしたらもう怖じ気づいちゃって(笑)。
ハハハハ。
デデ:「これは出せないけど、君は良いものを持っているから、もっと送って欲しい」って。それがものすごくプレッシャーになって、しばらく〈リフレックス〉を意識したものしか作れなかった。
なるほどね。
デデ:そのまま自然体で作れれば良かったんだけど。それでいちどダメになってしまったんです。小心者だから。
まったく小心者には見えないけどね(笑)。
デデ:それくらいからCM音楽の仕事をさせてもらえるようになったんだけど、まだ若いから、カネよりも自分のやりたいことをやるんだって、バイトしてでもやろうと。だけど、90年代末になってくると、かつて自分がエレクトロニック・ミュージックに感じていたワクワク感がどうもなくなってしまって......。
うん、そうだったね。エイフェックス・ツインも「ウィンドウリッカー」(1999年)がピークだったし。
デデ:うん、あれはすごかった。あのフィルの感じとか信じられなかった。
曲もすごかったし、PVもすごかった。ところが2001年の『ドラックス』でエリック・サティとテクノの中間みたいなことになったでしょ。
デデ:でも僕はあれがいちばん好きかもしれないんです。すごくピュアだし。
ああ、たしかに、ピュアであることは間違いないよね。
デデ:みんなはピアノの曲が良いって言うけど、僕はビートが入っている曲が大好きで。ドラムマシンとブレイクビーツの絡みという点では、ものすごく影響も受けた。
なるほどね。
デデ:もちろん「ウィンドウリッカー」や「カム・トゥ・ダディ」は大好きですけど。
ポップということを意識しているよね。
デデ:うん、そうなんです。それでも僕は『ドラックス』のビートものが大好きなんです。構成的にも、ピアノの曲があって、ビートものがあって、まあ、予定調和と言えばそうなんですけど、安心して聴ける。
「ウインドーリッカー」の後にアルバムが出るって話があったじゃないですか。それをすごく楽しみにしていたんです。当時は大田区に住んでいて、毎日のように川崎のヴァージンに行って、「出てないか? 出てないか?」ってチェックしていたほど楽しみにしていた。でも、結局、あのあと出なかったじゃないですか。ものすごくがっかりしちゃって。あの頃がリチャードに対する気持ちのピークだったかもしれない。
エイフェックス・ツインの音楽のなかにはいろんな要素が入ってるしね。
デデ:そうなんです。エレクトロニック・ミュージックのピークって、やっぱ97年ぐらいがピークだったと思うんです。ジャングルがドラムンベースになって、そこからドリルンベースへと発展して......。で、しばらくしてDMXクルーみたいなエレクトロも出てきて、それはそれで面白いなと思ってたんですけど、正直、それ以外のところではそんな刺激がなくて。ボーズ・オブ・カナダみたいなのも好きでしたけど、あれがエレクトロニカって呼ばれるのが僕にはわからなくて。アブストラクトの流れなんじゃないかなと思っていた。
あるいはサイケデリック・ロックの流れというか。
デデ:そうそう。で、エレクトロニカがブームになって、エイフェックス・ツインもエレクトロニカに括られて、「なんか違うな」って。エレクトロニカって上品なイメージがあったんですよ。そんなものじゃない気がするし、ラップトップの画面を見ながらライヴをしながらおしまいという、なんか不健全な感じがしたんです。もっとフィジカルなものだったと思うし。あと......〈リフレックス〉の悪意を変な風に解釈する日本のエイフェックス・ツイン・フォロワーみたいな人たちがいて。敢えて名前を挙げると〈19頭身〉とか。
いや~、知らない。
デデ:2000年ぐらいにあったんですよ、そういうのが。〈ロムズ〉のコーマとかも初期は関係してましたよ。僕も関わっていたし。なんていうか、相手に対してただ攻撃的になればいいみたいな。「それは違うだろう」っていうのが僕にはあって。
[[SplitPage]]
僕にとって〈ロムズ〉は届かない人たちだったんですよ。みんな独自のオリジナリティというか、スキルを持っていて、自分はまだそれを確立できていないから、自分はその辺の人たちと対等にはなれないけど、近づけるようにがんばってみようって。そこからデデマウスのファーストが作られるんです。
エイジ君(コーマ)とは、じゃあ、もう知り合っていたんだ。
デデ:その頃はまだ出会ってないんです。作っていた音楽も違っていたし、僕は僕で、リチャードの幻影を追い求めるのは止めて、もっと自分のコード感を出した曲を作っていたし。コーマ君と出会ったのは2004年ぐらいです。僕の友だちの女性シンガーで、Jessicaという子がいて、それをワールズ・エンド・ガールフレンドやジョセフ・ナッシングがアレンジするっていうことで紹介されたのが最初かな。僕もそれに参加したんです。
そのときはもうデデマウスとして活動していたんだ?
デデ:いちおうしてました。でも、そんなにアクティヴではなかった。23歳の頃かな、いちど〈19頭身〉の人と喧嘩になってしまったことがあって、自分も悪かったんですけど、そういうこともあって自信をなくしている頃で、もう外に出るのが恐くなってしまって(笑)。
ハハハハ。
デデ:恐いなって。だから〈ロムズ〉の人たちもきっと恐いんだろうなと思っていました。で、ジョセフと会ったら、すごく変人だけど、すごく柔らかい人で。で、コーマ君は、〈ロムズ〉の3周年に行ったときかな、僕が「すごく良かったです」って声かけたんです。そこでデモを渡したら、後からメールをくれて「君はストリートっぽい音楽をやるよりもメロディものにいくほうがいいんじゃないかな」みたいな内容で、「あ、やっぱそうなんだ」って思って。それもターニング・ポイントだったな。
ホント、気の良い連中だからね。
デデ:〈ロムズ〉のアニーヴァーサリーは毎年行ってましたよ。
なるほど。たしかにデデマウスからは、キッド606からの影響も感じるんだよね。あのアウトサイダーな感覚というか、アナーキーな感覚というか(笑)。
デデ:それはすごく嬉しい。エイフェックス・ツインやキッド606もそうですけど、僕にとって〈ロムズ〉は届かない人たちだったんですよ。みんな独自のオリジナリティというか、スキルを持っていて、自分はまだそれを確立できていないから、自分はその辺の人たちと対等にはなれないけど、近づけるようにがんばってみようって。そこからデデマウスのファーストが作られるんです。
なるほど。
デデ:エイフェックス・ツインはとんでもなくすごいし、〈ロムズ〉の人たちもすごいし、だったら自分にできることをやるしかないって。そう思えるようになってからアクティヴになりました。
どんな場所でやってたの?
デデ:中野の〈ヘヴィーシック〉とか。自分の近くいたのが、ゲットー・ベースの人が多くて。
おお。
デデ:DJファミリーとか。
僕もミックスCD持ってますよ。
デデ:そう、あの頃ゲットー・ベースすごかったじゃないですか。あの辺の下世話で、BPMが速い感じが好きだったから。
デデマウスの音楽とはあんま繋がらないけど。
デデ:そんなことないですよ。自分のなかではあるんですよ。あの下世話さ、ストリート感、そしてメロディというのは実は自分のなかにあるんです。
なるほどなー。話聞いていてすごく面白いんだけど、デデマウスがいた場所というのは、90年代のテクノ熱がいちど終わってしまって、で、廃墟のなかでなんか子供たちが遊んでいるぞっていう、そんな感じだよね。何もないところでさ。
デデ:シーンを意識してなかったですけどね。踊らせたい、メロディを聴かせたい、それだけとも言える。それでも、〈ロムズ〉まわりの人に聴かせるのは恐かった。自信がなかったんです。それでも支持してくれて......〈ロムズ〉5周年のアニーヴァーサリーには僕も出てるんです。
あ、僕もそれ行ってるかも。アニヴァーサリーにはけっこう行ってたよ。
デデ:けっこう来てるんですよね。サワサキさんも来てたって言ってたし。そういうなかで、僕はB級だってずっと思ってたんです。
ジョセフ・ナッシングは〈プラネット・ミュー〉だし、コーマは〈ファットキャット〉だったりとか、海外からも出していたしね。
デデ:〈プラネット・ミュー〉なんか......僕のなかでは夢ですよ。僕、〈ドミノ〉から返事をもらったことがあったんです。
いいじゃない。
デデ:でもリリースまではいかなかった。ちょうどフランツ・フェルディナンドを出した頃で、良い時期だったんだけど(笑)。「がんばれ」みたいな返事だった。それはそれで自信になったんですけどね。
ただ、僕もふだんは〈ロムズ〉まわりの人たちとつるんでいたわけじゃなくて、月刊プロボーラーっているじゃないですか?
はい。
デデ:あの辺の、テクノの人たちと一緒にやってることも多かったんです。わりと根無し草的に、いろんなところでやっていた。自分のホームを欲しいなと思っていたけど、ボグダン(ラチンス)の影響があったわけじゃないけど、ライヴでめちゃくちゃやるっていうのが......。
ボグダン! あれ面白かったよね。
デデ:わけもわからず「あー」って叫んで(笑)。ラップトップでもああいうの良いなって思って。自分にカツを入れるためにマイクで「ぎゃー」って叫んでアジテートしたり。
時代のあだ花じゃないけど、ブレイクコアみたいなシーンが花咲いたよね(笑)。
デデ:すごかった。「何? ブレイクコア? 意味わかんなくねぇ?」みたいな(笑)。で、そういうなかで「ぎゃーぎゃー」言いながらライヴやってたんですけど、何かそういう、サーカスの見せ物小屋的なところで「こいつ面白い」と言われることも多くて。それがまた勘違いされる第一歩になってしまったというか。
それこそベルリンでジェフ・ミルズが初めてDJやったときは、まわしたレコードをすべて放り投げるパフォーマンスをやったという伝説があって、やっぱそういうサーカスティックな行為って「オレを見ろ!」ってことなわけでしょ?
デデ:格好いい、それ。やっぱそうなんだね。DJファミリーもね、ジャグリングがうまくて、かけたら前に放り投げるっていうことをやっていた。で、そういうことやられると、見てるほうもやっぱ上がりますよね。
重要ですよ、そういうことは。
デデ:で、あるとき〈ユニット〉でやったことがあって。シロー君も出ていて、シロー君は上でやっていて、下で永田さんがやっていて、で、僕の友だちが永田さんに僕のデモを聴かせてくれて、で、永田さんが「君、いいよ」って言ってくれて、そこからアルバムの話に発展するんです。〈ロムズ〉から出したかったんだけど、〈ロムズ〉は何も言ってくれないし(笑)。
ハハハハ。このインタヴューを真っ先にシロー君に読んでもらおう(笑)。
デデ:いやー、怒られちゃいますよ。
おおらかな人だから、笑ってくれるよ(笑)。
[[SplitPage]]僕のなかの東京のイメージなんです。自然と人工の殺伐としている風景、あんま人間くさくなくて......子供の頃に読んだ『おしいれのぼうけん 』って本があって、僕、あれが大好きで、保育園でいたずらしていた子が押し入れに閉じこめられてしまう話で、そこにはトンネルがあって、トンネルを抜けると夜の大都市に出るんです。
デデ:とにかく、それがきっかけで〈ロー・ライフ〉にも出ることになって。で、そのとき、最初はステージがあったんだけど人が押し寄せてなくなちゃって、僕のまわりに客がわーっといて、「オレの機材守れ! テーブルを持て、みんな!」って言って。で、テーブルを持たせながらライヴやって、そんなに激しい曲じゃないのに何人かの客がダイブしたりして。それを永田さんが見て、「新しい時代がはじまった」と感じたっていうんです。それでファースト・アルバムを出すことが決まるんです。
それはすっごくいい話だね。
デデ:でもね、アルバムを出すのは決まったけど、ディストリビューターも決まっていなかった。それなのにアルバムの噂が広まっていたらしくて、タワレコの人や新星堂の人たちから直接メールが来るんですよ。「アルバムを置きたいから」って。でも、「ディストリビューターがいないんです」って言っていたら、〈ロムズ〉のタカラダ君が、ウルトラ・ヴァイブを紹介してくれた。それで出したら、宣伝してなかったんだけど、みんなが応援してくれて......。
それはホントにいい話だよ。宣伝力ではなく音で売れたんだから。素晴らしいよ。
デデ:ホント、最初は信じられなくて。永田さんから「5千枚いくかもよ」って言われたときにはびっくりしちゃった。
口コミなわけでしょ。
デデ:タイミングも良かったんですよ。何故か、爆発寸前のパフュームと比べられたりして。
違うでしょ!
デデ:キラキラ・テクノみたいな(笑)。なんだかテクノ・ポップと扱われたりして。でも、中田ヤスタカさんとかもDJでかけてくれていたみたいで。ヴィレッジバンガードみたいなお店も大プッシュしてくれたりして......ホントに運が良かった。タイミングが良かっただけなんです。
それを言ったら、エイフェックス・ツインだって電気グルーヴだってURだって、みんなタイミングが良かったんだよ。
デデ:絶対にエイフェックス・ツインや〈ロムズ〉にはかなわない、そう思って違うことをやろうとはじめたのがデデマウスだったから。
デデ君のなかで〈ロムズ〉ってホントに大きかったんだね。
デデ:とても。絶対に自分よりすごいと思っていて......、アイデア、ミキシングのテクニック、すべて自分よりレヴェルが高いと思っていたし。
ファースト・アルバムが売れてもそう思っていたの?
デデ:ずっとそう思っていて、セカンド・アルバムでエイベックスに来たのも、テクノというより、自分はフュージョンにはまっていて、スーパーで流れるような音楽を作りたいって、そういう気持ちだったから。ホームセンターとかスーパーでかかるような音楽を目指したんです。郊外のニュータウンとか、僕、大好きだから。
へー、何でまた?
デデ:僕のなかの東京のイメージなんです。自然と人工の殺伐としている風景、あんま人間くさくなくて......子供の頃に読んだ『おしいれのぼうけん 』って本があって、僕、あれが大好きで、保育園でいたずらしていた子が押し入れに閉じこめられてしまう話で、そこにはトンネルがあって、トンネルを抜けると夜の大都市に出るんです。そこでねずみばあさんが出たりとか、いろいろあるんですけど、僕、その誰もいない夜の大都市というのが強い印象に残っているんですね。たとえば、誰もいない夜の高速道路とか。
群馬というのも影響しているのかね?
デデ:あるかもしれない。僕の家の近くに国道が通っていて、夜になると誰もいないんだけど、オレンジの街灯がばーっとあって。うん、だからそれとリンクしたというのもあるかもしれないけど、何故かニュータウン的なものが僕にとっての東京だったんです。
ふーん、それは興味深い話だね。決して、華やかなところではなく。
デデ:そう、閑散としたところなんです。そしてそこのホームセンターやショッピングモールでかかる安っぽいフュージョン、それをイメージしたんです。
ある種のアンビエントだね、"ミュージック・フォー・ニュータウン"とでも呼べそうな。
デデ:そうそう、ホントにそう。ああいうところでかかる音楽が好きなんです。で、スタジオ・ジブリみたいなのも好きだったから、自分の音楽のなかにどうしたら日本的なものを取り入れることができるのかって考えていて、それが、そう、ニュータウンのフュージョンであり......。
『Sunset Girls』?
デデ:そう、『Sunset Girls』です。だからあの、夏祭りのイメージとかも、その考えから来ているんです。
90年代だったら、テクノの目的意識がはっきりしているじゃない。踊らせるとか、トリップだったりとかさ、だけど、デデマウスみたいなゼロ年代のテクノはそうした拠り所みたいなものを喪失しているんだよね。クラブとかDJに90年代のようにアイデンティファイしている感覚とは違うじゃない。
デデ:自分がどこにアイデンティファイすればいいのか、わからなかったですね。
その感じは音楽に出ていると思いますよ。
デデ:上京して、深夜にクラブに出掛けても、4つ打ちのテクノしかかからないし......ハード・ミニマルは好きでしたけどね。
クラブには遊びに行っていたの?
デデ:頻繁に行くっていうほどではない。友だちが出るからとか、つき合っていた彼女から「ケンイシイの出る〈Womb〉のイヴェントに行こうよ」って誘われて行ったり、そんなものですよ。そういうところ行くと、「なんか違う」って思ってしまって。酒飲んで、4つ打ちで踊るって、音楽を聴いているっていうよりは......なんだろう? それでも昔はクラブで遊ぶのが格好いいっていうのがあったけど、いまはもうそんなのないじゃないですか。しかも自分の求めるテクノって、そういうところからはずれているものだったから。
それは90年代からそうだよ。僕がエイフェックス・ツインを好きでも、最初は肩身狭かったもん。「健吾、オウテカって面白いね」って言っても「んー、でも踊れねーじゃん!」みたいな(笑)。やっぱほら、あの頃はテクノと言っても主流はトランスだったから。〈ワープ〉なんてDJやってる連中からけっこう冷ややかだったんだから。
デデ:僕はその頃、学生で東京にいなかったから良かったのかもしれない(笑)。ただ、僕も、ブレイクコアとか、エイフェックス・ツインとか、そんなのを胸はってDJでかけて「ウォー!」ってなるなんて、考えられなかった。
だいたいね、日本で、エイフェックス・ツインの影響を自分の音楽に取り入れた最初の人って、オレが知る限り、コーネリアスだもん。
デデ:あー。
UKやヨーロッパはすぐにフォロワーが出てきたのにね。日本ではムードマンあたりが多少違っていたぐらいで、あとはおおよそトランスだった。で、ゼロ年代になって、〈ロムズ〉やデデマウスが出てきて、僕は初めてエイフェックス・ツイン・チルドレンが顕在化したと思った。USインディもそうだよね。アニマル・コレクティヴだって、バンドだけど、エイフェックス・ツインからの影響じゃない。だから、エイフェックス・ツインの影響って、意外なことにそのあとの世代から面白い人たちがけっこう出てきている。
デデ:コーネリアスの"スター・フルーツ/サーフ・ライダー"がFMから流れたときはホントにびっくりして。
あれはびっくりした。
デデ:ホントにびっくりした。自分がやりたかったことをやっている。『ファンタズマ』の"スター・フルーツ~"にいくまでの流れが最高なんですよ。
「真似しやがって!」とは思わなかった(笑)?
デデ:それよりも「やられた!」って感じでした。あれでコーネリアスはすごいと思った。
デデマウスやコーネリアスっていうのは似ているよ。音楽性はぜんぜん違うけど、「ファンタジーを見せる」っていうところは同じでしょ。
デデ:そう言ってもらえるとありがたいです。僕、アニメが好きで......古典的なアニメなんですけど。世界名作劇場とか、ルパンとか、少年が少女を救うために自分の身を犠牲にするくらいの気持ちで突っ走るっていうか。『未来少年コナン』とか、僕、大好きで。
ハハハハ。オレ、大昔だけど、ピエール瀧から「見たほうがいい」って言われて貸してもらったことがある。VHSのテープ10本ぐらい(笑)。でもさ、『未来少年コナン』なんて、うちらの世代じゃない。
デデ:だから追体験なんです。宮崎駿を掘り下げていったらそこに行ったというね。昔のアニメが好きなんですよ。野田さんがリアルタイムで見ていたような。
『巨人の星』......、いや、『マジンガーZ』とかだよ。
デデ:『マジンガーZ』はないけど、『ど根性ガエル』は好きですね。
ああ、なるほどね。あの時代の真っ直ぐな感じのアニメね。
デデ:そうそう、ラナを救うために命をかけるコナンの真っ直ぐさがたまらなくて(笑)。
実写ものにはいかなかったの? 『仮面ライダー』とか、『ウルトラセブン』とかさ。
デデ:『ウルトラセブン』は早朝、幼稚園のときに再放送で見ていた。
『ウルトラセブン』は幼稚園児には難しいでしょー。
デデ:もちろん重くて政治的なにおいをわかるようになったのは大人になってからなんだけど、ウルトラマンが格好いいと思っていたから。あとね......ロボコンとか。日曜の早朝に再放送してたんですよ。すごく影響受けましたね。
そのへんは、ジョセフ・ナッシングやエイジ君(コーマ)とも共通する体験なのかな?
デデ:どうでしょうね。実はそこまで話したことがなくて。ジョセフとはUFO話をしたことはあるけど(笑)。どうでもいい宇宙知識をいっぱい仕入れて、それで話したことはあったけど(笑)。アニメに関しては、話したことないですね。僕も最初は恥ずかしかったんです。「ジブリが好き」なんて言うと、だいたい「それって違くない?」って言われて。だからあんま言わなかった。......で、もうひとつデデマウスの影響を言うと、バグルスなんですよ。
バグルスって、あのバグルス?
デデ:そう、「ヴィディオ・キルド・レディオスター~」っていう。父親が持っていて。すごく好きになって、あの人のアルバムも聴いたんです。そしたらそのエンディングで、曲がリプライズするんですね。楽器だけの演奏で。そこがすごく好きで、で、それを僕はファースト・アルバムで最初の曲でやったんです。そう、懐かしさ......それも僕には重要な要素のひとつなんです。で、80年代のポップスって、僕のなかでそれなんです。DX-7の音を聴くとすごく懐かしくなるんです。
[[SplitPage]]
童話的な......、色あせているんだけど、煌びやかなっていうか。で、多摩ニュータウンが好きだったから、休みの日に渋谷に行くんじゃなくて、多摩ニュータウンに行くんです。散歩するんですよ。そこをユーミンやボーズ・オブ・カナダを聴きながら歩くんです(笑)。
YAMAHAのDX-7と80年代ポップスって、本当は僕の世代なんだけどね(笑)。
デデ:そこは父親が大きいですよね。だから、ジャスティスみたいなニュー・エレクトロとか、僕のなかではしっくりこないんです(笑)。「これがエレクトロ?」みたいな。いまでも解せない(笑)。
あれは文脈が違うからね。エレクトロって呼ばないでほしいよね。
デデ:僕のなかではやっぱメランコリックな要素がなければエレクトロじゃないというか、すごくそれが重要なんですよ。プローンっていたでしょ?
プローン......?
デデ:〈ワープ〉から1枚だけ出した。
はいはい(笑)。
デデ:〈ワープ〉の10周年記念盤のリミックス集のほうにも参加していて、たしかトリッキー・ディスコをリミックスしていたのかな。とにかく......プローンが好きで。プローンが僕に80年代的な記憶を呼び起こしてくれたんです。自分の記憶の奥底で暴れられているような感じというか。『アンビエント・ワークス』よりもプローンのほうが僕はすごかったんですよ。野田さんたち世代はやっぱ『アンビエント・ワークス』がすごいでしょ?
もちろん。
デデ:僕はあんまそれを感じなかった。初めて聴いた17~18歳の当時はね。それよりもプローンのほうが懐かしさを感じたんです。
あれも変な1枚だったよね。
デデ:イージー・リスニング・ブームからすると遅すぎたし(笑)。童話的な......、色あせているんだけど、煌びやかなっていうか。
なるほど。
デデ:で、多摩ニュータウンが好きだったから、休みの日に渋谷に行くんじゃなくて、多摩ニュータウンに行くんです。散歩するんですよ。そこをユーミンやボーズ・オブ・カナダを聴きながら歩くんです(笑)。
なんでユーミン(笑)?
デデ:ユーミンやキリンジみたいなニュー・ミュージックが好きだったんです。
ぜんぜんエイフェックス・ツインとは繋がらないけどね(笑)。
デデ:だから、それを繋げたかったんですよ。ミュージック(μ-Ziq)っているじゃないですか。
はいはい。マイク・パラディナスですね。
デデ:彼のキッド・スパチュラって名義の作品あるじゃないですか。
最高だったよね。あの、〈リフレクティヴ〉から出ているヤツ?
デデ:あの名義で、『Full Sunken Breaks』(2000年)というアルバムがあって。
あー、それ、聴いてないわ。『スパチュラ・フリーク』しか聴いてない。
デデ:あれが大好きだったんです。キッド・スパチュラ......初期のミュージックと言ってもいいんですけど、簡単というか稚拙というか、ものすごいわかりやすいメロディがあったじゃないですか。『アイ・ケア・ビコーズ・ユー・ドゥ』の1曲目にもそれがあるし。あのアイデアでもって、自分のグッと来るメロディ、コード感でやったらどうなるんだろう?っていうのがあって。
なるほどねー。
デデ:だから、わかりやすいメロディみたいなものを追求したくて。
ミュージックはその辺、すごかったよね。イコライジングされた変態的なブレイクビーツで、しかし上物のシンセがやけにベタなメロディを弾くんだよね(笑)。
デデ:そういう点では、僕、ミュージックからの影響すごいですよ。
あー、言われてみれば、そうだね。
デデ:〈プラネット・ミュー〉はホントに憧れです。
いまはダブステップとグライムのレーベルですよ。
デデ:あー、〈プラネット・ミュー〉から出したかったなー。
ハハハハ。ちょっと話が飛ぶけどさ、ハドソン・モホークみたいな新世代はどう?
デデ:大好き。
やっぱり。
デデ:ニュー・ジャック・スウィングでしょ、あれ。
ハハハハ。うまいこと言うね。R&Bみたいなこともやってるしね。
デデ:プリンスみたいな曲もあるでしょ。「やられたー!」って思った。プレフューズ73のときも「やられたー!」って思ったんだけど、ああいうヴォイス・サンプリングをチョップするの自分もやっていたから。だから、自分はメロディをチョップして、自分なりのものを作ってやるって思った。
そうそう、なんで使っているのが、チベットやインドネシアの少女の声なの?
デデ:ただ手元にあっただけっていう。
アジアに対する妄想があるとか(笑)。
デデ:そういうわけではないんです。ただ、手元にあって使ったら「良いね」って言われて、「じゃ、使ってみようかな」みたいな。
なかばトレードマークになってるでしょ。
デデ:ただ、エイベックスに来たときにあれはもう捨てたかったんですよ。ヴォーカリストを使って、何か他のことをやりたいと思っていたほどなんです。あの声はライヴでも使ってないし......。
しかし......そう考えると、新しいアルバムは好き放題やってるよね。
デデ:うん、そうですね。
僕は6曲目がいちばん好きです。"double moon song"、これ、ホントに良い曲だと思います。テクノが好きな人はこれは好きだと思うよ。
デデ:はっきり言うと、これ、「カム・トゥ・ダディ」の2曲目の"フリム"なんです。ああいう、妖精が飛んでいるような曲を作りたいというのがあった。実はこれ、19歳のときの曲なんです。そのときからほとんど変わってない。ビートがちょっと変わったぐらいで。テクノに対する愛をいちばんストレートに出した曲なんです。
そうだね、ホントにそう思う。
デデ:昔、NHKの深夜番組で風景の映像にアンビエント音楽だけっていうのがあったんです。ボイジャーの映像にテクノがかかるみたいな。そこで『アンビエント・ワークス』の2曲目か3曲目がかかったんです。「いいな~」って思って。そう、そのときの感覚や、"フリム"みたいな感覚、それは僕のなかですごくピュアなものなんです。それをもう1回やってもいいかなと思って。それが結局、今回のアルバムのいちばん中心になった。
3曲目の"sweet gravity"も面白かったな。
デデ:あれはねー、あからさまにやってやれって感じで(笑)。
デデマウス的なアシッド・ハウスというか(笑)。
デデ:アシッドもの好きなんですよ。
やっぱそうなんだ。
デデ:いまやっておけば、4枚目ではもっと出せるかなって(笑)。
ハハハハ。
デデ:だから、自分がやりたかったこと、やってきたことの橋渡し的なことになればいいなと思っているんです。ただ、ぶっちぎり過ぎないようにしようとは思いました。だから、やりたいことをやっているんだけど、デデマウスを客観視して作ったアルバムでもある。ようやく、〈ロムズ〉への劣等感を払拭できたというか、やっとみんなと同じところに立てたのかなというのもある。
〈ロムズ〉は、そこまで大きかったんだね。
デデ:あと去年、タイコクラブに出たとき、そこで見たスクエアプッシャーのライヴがすごく良くって。わかりにくいことをやるのかなと思ったら、初期の頃の名曲と最近のメロディアスなポップスばかり、たとえば"ア・ジャーニー・トゥ・リードハム"とか"カム・オン・マイ・セレクター"とかやるんです。それに励まされて、自分の好きなことをやろうって気持ちをさらに固めた。
ああ、そうか、"ア・ジャーニー・トゥ・リードハム"(1997年の『ビッグ・ローダ』の1曲目)から『A Journey to Freedom』が来ているんだ。
デデ:もう大好きだったから。今回は曲名もすべてパロディなんです。"マイ・フェイヴァリット・スウィング"とか"ニュータウン・ロマンサー"とか。
なるほど。
デデ:最後の曲の"same crescent song"がロキシー・ミュージックの"セイム・オールド・シーン"から来ているというのはわかりづらいかもしれないけど。
絶対にわかりません(笑)。
デデ:それで、ジャケットの方向性が決まったときに、「あ、もうこれは『A Journey to Freedom』でいこう」と。
強烈なジャケだね(笑)。
デデ:強烈ですね(笑)。
下北の駅で見たよ~。でっかいヤツ。
デデ:ハハハハ、ありがとうございます。もう......、血を見るような努力の結果なんで、これ。イラストレーターの先生(吉田明彦)がスクエアの社員の方なんで、社外仕事になってしまうじゃないですか。だから、描いてもらうのに、何度も何度もお願いして断られ、でもお願いしてって。先生自身はやる気になってくれていたんだけど。で、描いてもらえるってことになったときに、自分の入れて欲しい要素をぜんぶ入れてもらおうと思って。だから、背景に団地が描かれている。これ、多摩ニュータウンなんです。奥さんがそっちのほうの方だったので、けっこう感覚的にわかってもらえて。
なるほど。
デデ:誰もいないパレードというテーマもあった。
子供っていうのはテーマとしてずっとあるんでしょ? アルバムも子供の声からはじまっているし。
デデ:僕の場合、子供っていうのは真っ直ぐさみたいなものの象徴としてあるんです。冒険とか......思春期前の真っ直ぐさ。先の見えない真っ暗な未来へと飛び込まされる以前の、真っ直ぐさ。13歳から15歳とか、僕は、その年代のときには恐怖しかなかったけど、希望とかいうものを託して旅立たせたいという気持ちがあって。で、ひとりでは淋しいから仲間がいれば安心だろうって。そういうことなんです。
タイトルが『A Journey to Freedom』だもんね。
デデ:だけど自分が描いたストーリーはけっこうヘヴィーなんです。8曲目の"station to stars"から9曲目の"goodbye parade"って、曲名にもそれは表れている。ってことは......。
そこはいまは言わないでおこうよ。
デデ:そう、隠しているストーリーがある。パレードが葬儀にも見えるから。だけど、僕なりにメッセージがあるんです。誰も頼れる人がいなくなったときがスタート地点じゃないのかなっていう。自分がデデマウスとして活動しているとき、助けてもらえる環境がすごくあった。彼女もいたし......。だけど、彼女もいなくなって、たったひとりになったとき、「がんばらなきゃ」と思って、そこから物事が進むようになったんです。
なんだかんだ言って、デデ君の場合は、表現する場があったじゃない。それは大きいですよ。
デデ:あんま説教臭いのは好きじゃないんだけど。
そういう音楽じゃないしね。ただ......いまのオタク世代になってくると、デデマウスの思春期とは違う窮屈さがあるんだろうね。インターネットで世界に繋がっている錯覚を覚えて部屋からもでない。誰にも傷つけられないし、誰も傷つけない空間にいるっていうかね。デデ君はいろいろ傷ついたり、傷つけたりしたかもしれないけど、傷つくことを恐れて外に出ないっていうのはものすごく恐いことだと思うんだよね。だからCDが売れててもそのファンたちは、オムニバスのライヴになるとあんま来ないっていうか。自分の好きなもの以外の世界を見ようとしないというか。デデ君はだって、DJファミリーだからね(笑)。
デデ:わかりますよ。ニコニコ動画とか、ああいうなかから、ゆとり世代の子たちが出てきているじゃないですか。面白いんだけど、ああいうのを聴いていて何が足りないのかと言うと、リアルさというか、現場で感じる現場感というか。場を経験していないで作っているのがすごくよくわかるんです。フィジカルさがついてないっていうか。まあ、それは若いから当然なんだけど、でも、やっぱ自分が外に出て行って、生の人間を相手していかないと。そういう意味でも『A Journey to Freedom』なんです。
なるほど。話変わるけど、すごいですね、ロンドンの〈ビッグ・チル〉でリリース・パーティだなんて。しかもプラッドと一緒に。
デデ:いや~、プラッド、大好きなんで、ホントに嬉しい。
あの人たちはホントに才能があると思う。作っている音楽もほとんどはずれないでしょ。
デデ:うん、最高ですよ。
しかし、商業的な成功には縁がないんだよ(笑)。
デデ:地味なんですよね。LFOなんかと違って。だけど、僕はホントに尊敬している。『ダブル・フィギア』(2001年)にはとくに影響された。ああいう、微妙にポップなものが好きなんです。そういう意味ではルーク・ヴァイバートが大好きで。一時期はリチャードよりもルーク・ヴァイバートのほうが好きだったくらい。あれほど才能がある人はいない。
ハハハハ、あの人、マジですごいよね。あれこそ根無し草というか、ホントいろんなレーベルから出しているし、「いったい何枚出しているのか?」っていうか。
デデ:わけわからないアシッド・ハウスを出したかと思えばトリップホップやったり......あの人の(ワゴン・クライスト名義で〈ニンジャ・チューン〉から出した)"シャドウズ"って曲のPVが最高で。
ドラムンベースもアンビエントもIDMも、やれることは全部やってるよね。彼がすごいのは、あれだけ作品数出しながら、彼のスタイルってものがないでしょう。あれはすごい。普通はハウスとかIDMスタイルとか、普通はなにかしらあるじゃない。自分のスタイルってものが。あの人は空っぽだよなー(笑)。それで作品が良いからすごいよね(笑)。
デデ:僕、「いちばん好きなのが誰か?」って訊かれたらルーク・ヴァイバートって言うかもしれない。............(以下、延々と同じような話が続くので省略します)
 インターナショナルに活動する
インターナショナルに活動する オリジナル・ダブステッパーのひとり、ハイジャック
オリジナル・ダブステッパーのひとり、ハイジャック マイクを持って叫ぶドラムンベースの王様!
マイクを持って叫ぶドラムンベースの王様! UKアンダーグラウンドの両雄!
UKアンダーグラウンドの両雄!







 いやー、本当に、ぶっ飛びすぎ!......てか、笑えてくる。壮大な"エイリアン・ミュージック"に出会ってしまったのかもしれないな。黒光りするシンセが痛いくらいにまぶしいぜ。
いやー、本当に、ぶっ飛びすぎ!......てか、笑えてくる。壮大な"エイリアン・ミュージック"に出会ってしまったのかもしれないな。黒光りするシンセが痛いくらいにまぶしいぜ。
 DJワダの〈イグナイト〉でのアンビエント・セットを終え、天狗食堂で開かれていたDJサチホがオーガナイズする〈リリース・シット〉に駆けつけると、週末の朝に特有のとても良い空気が流れていた。DJはサチホ~スポーツ・コイデ~イナホ~リョウ・オブ・ザ・デックス・トラックスの面子でのローテーションだった。グルーヴがキープされたまま新旧のディープ・ハウスがたんたんと続く。朝の9時をしばらく過ぎると天狗食堂のイナホがロングミックスを聞かせる。足の運びが軽やかだ。スネアに引っかかりがあるが、スマートなミ二マル・ハウスがじょじょに子供の声と水の音、透明感のあるシンセとともに広がっていく。誰も声を上げず首を振りながらその音楽をきいていた。そのトラックここに挙げた。ミルコ・ロコのリカルド・ヴィラロヴォスによるリミックスである。
DJワダの〈イグナイト〉でのアンビエント・セットを終え、天狗食堂で開かれていたDJサチホがオーガナイズする〈リリース・シット〉に駆けつけると、週末の朝に特有のとても良い空気が流れていた。DJはサチホ~スポーツ・コイデ~イナホ~リョウ・オブ・ザ・デックス・トラックスの面子でのローテーションだった。グルーヴがキープされたまま新旧のディープ・ハウスがたんたんと続く。朝の9時をしばらく過ぎると天狗食堂のイナホがロングミックスを聞かせる。足の運びが軽やかだ。スネアに引っかかりがあるが、スマートなミ二マル・ハウスがじょじょに子供の声と水の音、透明感のあるシンセとともに広がっていく。誰も声を上げず首を振りながらその音楽をきいていた。そのトラックここに挙げた。ミルコ・ロコのリカルド・ヴィラロヴォスによるリミックスである。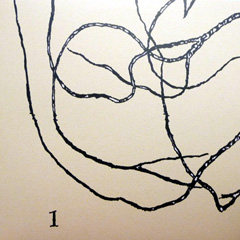 エルサレム出身でニューヨーク在住のパレスチナ人パーカッショニスト、ラズ・メシナイが率いるバダウイのニュー・シングルを紹介しよう。ラズ・メシナイとは......その名前とバダウイ、サブ・ダブ、ベドウィンといった4つの名義を使い分け、DJスプーキーのホームである〈アスフォデル〉、ビル・ラズウェルのリリースでも知られる〈リオール〉、DJワリーが率いる〈アグリカルチャー〉等から数々の傑作を放ってきた男だ。ニューヨークのアンダーグラウンドを象徴するアーティストであり、ユダヤの政治と宗教をテーマにしたサウンドと彼の芸術、そしてその超絶的なパーカッションのテクニックは多方面で高い評価を得ている。最近ではクロノス・カルッテットやジョン・ゾーンとの競演も話題になった。
エルサレム出身でニューヨーク在住のパレスチナ人パーカッショニスト、ラズ・メシナイが率いるバダウイのニュー・シングルを紹介しよう。ラズ・メシナイとは......その名前とバダウイ、サブ・ダブ、ベドウィンといった4つの名義を使い分け、DJスプーキーのホームである〈アスフォデル〉、ビル・ラズウェルのリリースでも知られる〈リオール〉、DJワリーが率いる〈アグリカルチャー〉等から数々の傑作を放ってきた男だ。ニューヨークのアンダーグラウンドを象徴するアーティストであり、ユダヤの政治と宗教をテーマにしたサウンドと彼の芸術、そしてその超絶的なパーカッションのテクニックは多方面で高い評価を得ている。最近ではクロノス・カルッテットやジョン・ゾーンとの競演も話題になった。
 「?」と言うキーワードを使うとき、決まってマーク・プリチャードの〈Ho Hum〉からリリースされた10インチ「?」を思い出す。2008年9月20日、 DBS〈DRUM & BASS x DUBSTEP WARZ〉にて筆者とユニットフロアで共演したマーラが1曲目にスピンした鮮烈な作品だ。何故ならこれは......ノンビートだからである。漆黒アンビエントが5分以上続くそのオープニングに会場は一時......静まり返った! 「なんだ、この曲は!?」、みんなそう思ったに違いない......文字通り「?」であった。そこからのマーラのプレイは言うまでもなく素晴らしいものであったが、いろんな意味を含めて話題をさらったセンセーショナルな作品が「?」だ。
「?」と言うキーワードを使うとき、決まってマーク・プリチャードの〈Ho Hum〉からリリースされた10インチ「?」を思い出す。2008年9月20日、 DBS〈DRUM & BASS x DUBSTEP WARZ〉にて筆者とユニットフロアで共演したマーラが1曲目にスピンした鮮烈な作品だ。何故ならこれは......ノンビートだからである。漆黒アンビエントが5分以上続くそのオープニングに会場は一時......静まり返った! 「なんだ、この曲は!?」、みんなそう思ったに違いない......文字通り「?」であった。そこからのマーラのプレイは言うまでもなく素晴らしいものであったが、いろんな意味を含めて話題をさらったセンセーショナルな作品が「?」だ。 UKダブ・カルチャーの拠点"ブリストル"でもダブステップは刻々と進化を続けている。90年代初期のジャングルがレイヴを席巻していたように......。その進化の過程とともに、ピンチの〈Tectonic〉と双璧の如く歩んで来たのがぺヴァーリストの〈Punch Drunk〉。90年代のジャングル/ドラムンベース・ムーヴメントを通って来たであろう彼らブリストル・ダブステッパーたちは、UKダンス・ミュージックの特性である"ハイブリッド"を巧みに取り入れた全く新しいブリストル・サウンドの提唱者となった。
UKダブ・カルチャーの拠点"ブリストル"でもダブステップは刻々と進化を続けている。90年代初期のジャングルがレイヴを席巻していたように......。その進化の過程とともに、ピンチの〈Tectonic〉と双璧の如く歩んで来たのがぺヴァーリストの〈Punch Drunk〉。90年代のジャングル/ドラムンベース・ムーヴメントを通って来たであろう彼らブリストル・ダブステッパーたちは、UKダンス・ミュージックの特性である"ハイブリッド"を巧みに取り入れた全く新しいブリストル・サウンドの提唱者となった。 筆者は、とにかくクリプティック・マインズのダブステップ・サウンドが大のお気に入りである。〈Tectonic〉からの「768」、ピンチ&ムーヴィング・ニンジャ「False Flag -Kryptic Minds RMX-」や〈Osiris〉の「Life Continuum/Wondering Why」、〈Disfigured Dubz〉から「Code 46/Weeping」など......最近のリリースすべて注目している。
筆者は、とにかくクリプティック・マインズのダブステップ・サウンドが大のお気に入りである。〈Tectonic〉からの「768」、ピンチ&ムーヴィング・ニンジャ「False Flag -Kryptic Minds RMX-」や〈Osiris〉の「Life Continuum/Wondering Why」、〈Disfigured Dubz〉から「Code 46/Weeping」など......最近のリリースすべて注目している。
 サブトラクト(Sbtrkt)。脅威のニューカマーとして昨年のデビュー以来、破竹の勢いで上り詰めた天才エレクトリック・ダブステッパー。すでにベースメントジャックス、フランツ・フェルディナンド、モードセレクター、ゴールディといった大物達のリミックスを手掛け、ミニマル~ガラージ~ファンキー~エレクトロと縦横無尽に行き来している今年その動向がもっとも期待されている大注目株である。
サブトラクト(Sbtrkt)。脅威のニューカマーとして昨年のデビュー以来、破竹の勢いで上り詰めた天才エレクトリック・ダブステッパー。すでにベースメントジャックス、フランツ・フェルディナンド、モードセレクター、ゴールディといった大物達のリミックスを手掛け、ミニマル~ガラージ~ファンキー~エレクトロと縦横無尽に行き来している今年その動向がもっとも期待されている大注目株である。 イーピーロム(Eprom)は、サンフランシスコ在住の新進気鋭ウエスト・コースト・ベース・テクニシャン。ファンキーの要素とテッキーなカッティング・ビート、ハッシュされた女性ヴォーカルにアトモスフェリックな上ものを巧みにコントロールした、これぞニュー・テック・ファンキーだ。アメリカやカナダでも大盛り上がりを見せているダブステップやベースライン・ミュージックだが、アメリカでその代表格と言えば、ファルティDL(Falty DL)、6ブロック(6Blocc)、スターキー(Starkey)、ノアD(Noah D)等々だ。今回の"Never"のリミックス・ワークを担当したのがファルティー・DLだ。
イーピーロム(Eprom)は、サンフランシスコ在住の新進気鋭ウエスト・コースト・ベース・テクニシャン。ファンキーの要素とテッキーなカッティング・ビート、ハッシュされた女性ヴォーカルにアトモスフェリックな上ものを巧みにコントロールした、これぞニュー・テック・ファンキーだ。アメリカやカナダでも大盛り上がりを見せているダブステップやベースライン・ミュージックだが、アメリカでその代表格と言えば、ファルティDL(Falty DL)、6ブロック(6Blocc)、スターキー(Starkey)、ノアD(Noah D)等々だ。今回の"Never"のリミックス・ワークを担当したのがファルティー・DLだ。
