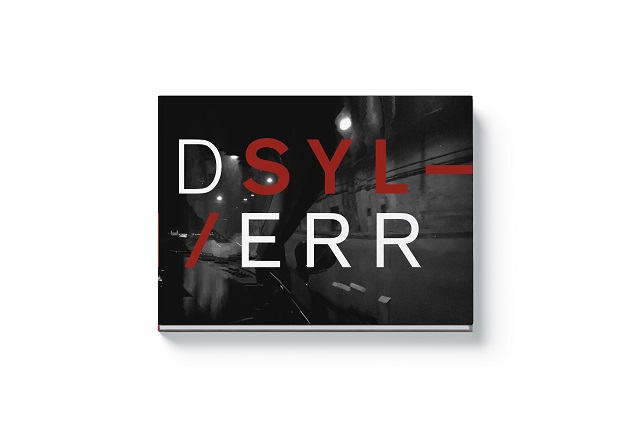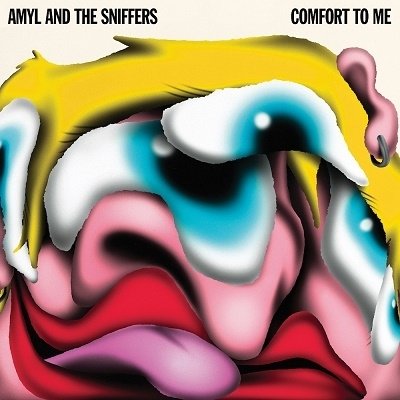すでにハッピーな人をもっとハッピーにすることができる、そう信じているんだ。セラピーは何も、鬱や、PTSDといったものの治療ばかりとは限らない。あれは実は、この世界をもっとより客観的に眺めるのを助けてくれる、アメイジングな道具なんだよ。
これまで3枚のアルバムをリリースし、新世代のシンガー・ソングライターとしてのポジションを確立させたジョーダン・ラカイ。もともとニュージーランド出身で、オーストラリアで活動基盤を築いた後にロンドンへ渡り、そこでトム・ミッシュ、ロイル・カーナー、アルファ・ミスト、リチャード・スペイヴンといった面々とコラボし、さらなる成功を収めていく。さらにはアメリカのコモンとも共演するなどワールドワイドに活躍の場を広げているジョーダンだが、そうした活動の華々しさに対して音楽そのものには非常に繊細で内省的な面がある。セカンド・アルバムの『ウォールフラワー』(2017年)がそうした一枚で、ネオ・ソウルの新星と持てはやされたファースト・アルバムの『クローク』(2016年)とは違う世界を見せてくれた。「AIシステムに立ち向かう人間の未来」を描いたサード・アルバムの『オリジン』(2019年)では、テクノロジーやネット社会が進化したゆえのディストピアへの警鐘を鳴らし、一方でディスコやAORテイストのダンサブルなサウンドも目立っていた。
3枚のアルバムでそれぞれ異なる世界や音楽性を披露してきたジョーダンだが、ニュー・アルバムの『ワット・ウィ・コール・ライフ』もまた、いままでとは違う作品となっている。録音スタイルで見ると、いままではひとりでスタジオに入ってトラック制作をすることが多かったのだが、今作はすべてバンドとリハーサルしながら曲作りをおこなっている。そして、歌詞の世界を見ると実体験に基づくパーソナルな作品が多く、より深みとリアリティを増したものとなっている。結果として『ウォールフラワー』のように内省的でアコースティックな質感の楽曲が多いのだが、そこにはセラピーによって自己の振り返りをおこなったこと、ブラック・ライヴズ・マター運動を通じて自身のルーツに思いを馳せたこと、そしてコロナ禍での生活など、さまざまな経験が『ワット・ウィ・コール・ライフ』を作っている。音楽家としてはもちろん、ひとりの人間としてのジョーダン・ラカイの成長が『ワット・ウィ・コール・ライフ』にはあるのだ。
振り返ってみると、実は非常に多くのアドヴァンテージを与えられてきたじゃないか、と。単に自分の肌の色、そして自分のジェンダーのおかげでね。自分の特権を理解することを通じて、格差をもっと縮めようとし、できるだけ誰にとっても平等なフィールドをもたらしたい。
■今日は、お時間いただきありがとうございます。
ジョーダン・ラカイ(Jordan Rakei、以下JR):いやいや、こちらこそ、取材してくれてありがとう!
■いまはどんな感じですか?
JR:うん、アルバムが出たところでハッピーだし、エネルギーの波に乗ってる感じ(笑)。エキサイトしていて、アルバム・リリースのドーパミンが出てるよ。フフフフッ!
■(笑)。近年のあなたを振り返ると、2019年にリリースしたサード・アルバムの『オリジン』のリリース後、日本公演も含むワールド・ツアーやアメリカの公共ラジオNPRがおこなうライヴ企画「タイニー・デスク・コンサート」への出演、『オリジン』を絶賛したコモンとの共演、別名義のハウス・プロジェクトであるダン・カイによるアルバム『スモール・モーメンツ』のリリース、コンピ・シリーズの『レイト・ナイト・テールズ』や〈ブルーノート〉のカヴァー・プロジェクトである『ブルーノート・リ:イマジンド 2020』への参加など、忙しい活動が続いていました。
JR:うんうん。
■そうした中でコロナ禍があり、以前とは日常生活や社会、そして音楽業界も変化してきていると思います。あなた自身や周りではいろいろ変化はありましたか?
JR:いい質問だね。うん、あれで僕は……コロナが(昨年春)ロンドンに広まったとき、あそこから確か、僕たちは4ヶ月近くロックダウン状態に入ったんだ。で、あの状況のおかげで僕は、自分に音楽があるってことをありがたく思うようになったね。音楽は僕にとってホビーであり、と同時に自分のキャリアでもある。もちろん、自分の家にこもってばかりいたから、ロックダウン期はやっぱりとても退屈ではあったんだ。ただ、僕はアルバムを作っていたし、サイド・プロジェクトとしてダン・カイ名義で『スモール・モーメンツ』を作ったり。だからあのロックダウン期間中の多くを、自己投資する時間を見出しながら過ごしていた、というのかな? これがパンデミック状況じゃなかったら、僕は大抵他の人びとの作品をプロデュースしたり、ツアーをやったり、他のアーティストのために曲を書いて過ごしているわけで、今回はほんと、自分自身にフォーカスできる滅多にない機会だった、みたいな。だからなんだ(笑)、ここしばらくとても生産的だったのは! コンピレーションをまとめることもできたし、〈ブルーノート〉のプロジェクトにも参加でき、『スモール・モーメンツ』に今回のアルバム、と。うん、ほんと創作にいそしんでいたなぁ自分、みたいな(笑)。そんなわけで音楽的な面で言えば、自分のために時間を割くことができるようになったのは本当に良かったし、一方でパーソナルな面では、些細なことにもっと感謝するようになった。たとえば友人に会う機会を以前より大事に思うようになったし、それだとかディナーで外食に出かけることとか。外食はいままで別に大したことないと思っていたんだけど、ロックダウン中はそうした機会はすべて僕たちから取り去られてしまったわけで。だからいまの自分は、人生全般に対してもっとありがたさを感じるようになった。
■ニュー・アルバムの『ワット・ウィ・コール・ライフ』は、そうしたコロナ禍によって変わってしまった世界と結びつく部分はありますか?
JR:ああ、そうなんだろうね。今回のアルバムの響きには、もうちょっとこう、静観的というのか、内省的な要素がある。自分に言わせればよりダークというか、かなり楽しくダンスフロア向けだった『オリジン』に較べて、もう少しエモーショナルかつダークなんだよ。だから、そうした面は部分的にインパクトを受けたと思う。けれども、実際に僕がこのアルバムを作っていた間は、僕のスピリットそのものはかなりポジティヴだったんだ。先ほども話したように、ロックダウン中は時間をすべて自分のために使えたわけだし、アルバムを作ることに対して相当エキサイトしてもいた。だから、やや入り混じっているというのかな、アルバムには明るくポジティヴな面もあるし、一方でかなりダークな部分もある。僕自身としてはかなり良いミックスになったと思ってるよ。
■『オリジン』のテーマには「AIシステムに立ち向かう人間の未来」があり、テクノロジーやネット社会が進化したがゆえのディストピアを描いていましたが、『ワット・ウィ・コール・ライフ』におけるテーマは何でしょうか?
JR:主たるテーマと言えば、心理セラピーを受けに行き、そこで自分が学んだ教訓すべて、だったね。自分の子供時代について、結婚したこと、オーストラリアからロンドンへの移住、自分の両親、そして兄弟との関係についてなどなど、セラピーを通じて学んだ教訓のすべて。というわけで基本的にアルバムの全体的なストーリーは僕が自分自身について学んだことだし、それらを聴き手とシェアしようとしている。だから歌詞の面での表現も、いわゆる内面で観念化したものより、もっとずっとパーソナルになっているっていう。
■具体的にどのようなセラピーだったのですか? いわゆる「セラピストのもとに通い、寝椅子に横たわって過去を語る」というもの?
JR:(笑)その通り。そもそもは実験として、面白そうだからやってみよう、ということだったんだ。というのも、セラピーを受けた当時の自分はかなりハッピーな状態だったし、とにかくセラピストがどんなことをやるのか興味があった。自分はそういったことに詳しくなかったから、実際はどんなものなんだろう? と。そんなわけで、とてもオープン・マインドかつハッピーな状態でセラピーを受けにいったところ、セラピストの女性からあれこれ質問されていくうちに、この(苦笑)、自分の心の内側にフタをしてあった邪悪な部分みたいなものをいろいろ明かしている自分に気がついた、というか。
■へえ、そうなんですか!
JR:うん、かなり驚異的な体験だった。セラピーの過程をナビゲートしていくのを手伝ってくれる、いわば第三者的な存在の人と一緒に自分自身の人生を振り返る、という行為は。そうだな、おかげで自分の子供時代にも戻ることになったし、学校で起こった様々な出来事だとか、もっと小さかった頃の兄弟との思い出なども出てきて……あれはかなりいろんなことを明かしてくれる体験だったし、僕はセラピーをみんなに勧めているんだ。そうは言っても、中には自らの過去に改めて深く潜っていくのがとても難しい、と感じる人も確実にいるだろうし、無理にではないよ。ただ、いま現在の自分を人間として理解するのに、セラピーは非常に役に立つと思う。
■でも、あなたはセラピーを受けるには若過ぎじゃないかと思うんですが(笑)?
JR:ハハハハハッ!
■実験や興味半分でやってみたとはいえ、普通セラピーと言えば、メンタル面で問題があるとか、「中年の危機」に際して受けるものではないかと?
JR:フフフッ! それは、僕がいわゆる「ポジティヴ・サイコロジー」というコンセプトを信じている、というところから来ている。どういうことかと言えば、メンタル・ヘルスの療法や心理学で用いられるツールを使い、悲しい状態からノーマルな状態に持っていくのではなく、通常の状態からハッピーな状態へ、そしてハッピーな状態からさらにハッピーな状態に人間を導いていく、というもので。だから僕はセラピーを利用することで、すでにハッピーな人をもっとハッピーにすることができる、そう信じているんだ。セラピーは何も、鬱や、PTSDといったものの治療ばかりとは限らない。あれは実は、この世界をもっとより客観的に眺めるのを助けてくれる、アメイジングな道具なんだよ。
■そうやってセラピーを通じて子供の頃のこと、両親や兄弟との関係、ロンドンに移住して自立したこと、結婚生活について、両親の夫婦関係と自身の夫婦関係との比較や理解など、いろいろなことに考えを巡らせました。また、幼い頃からの鳥恐怖症や――
JR:うん、フフフッ!(苦笑)
■その根源となる予測不可能なものに対する恐怖など、自身の内面にあった疑問がいろいろわかってきたと聞きます。恐れは克服できました?
JR:(うなずきながら)あれはおかしな話でね。僕のこれまでの人生ずっと、鳥は恐れる対象だった、みたいな。バカげた、根拠のない恐怖なんだよ。自分では説明がつくんだけど、ただ、いまだに鳥はおっかない。ほんとバカらしいよね、でも、なんとか克服しようとがんばっているところだよ。でまあ、僕が気づいたのは、鳥は……僕のいろんな恐れの中心めいた対象だったんだけど、いまやそれを、予測のつかないものに対して抱く恐れを象徴するものとして捉えている、みたいな? 僕はルーティンを守ったり、前もって計画を立てるのがかなり好きな方だし、けれどもたとえば、誰かに立ち向かうといった予測不可能な事柄、知らない人に面と向かうのは本当に怖い。それだとか社交面で感じる不安もあって、他の人びとと接して社交する状況にもビビる。そういったものはどうなるか予測できないし、何につけても、予測不可能なものには苦戦してしまうんだね。というのも……そうだなぁ、自分の中に何らかの反応が引き起こされてしまう、というか? セラピーに通って気づいたことのひとつも、僕はそういう体験には困難を感じるってことだったね。
■ライヴ・パフォーマンスの場ではどうなんでしょう? あれも見知らぬ人が多く集まる、ある意味予測不可能な状況だと思うんですが。
JR:(笑)確かに。ただ、ライヴは対処できるんだ。おもしろいことに、僕はアガることがまったくなくてね。ステージに上がるのが怖いってことは一切ない。どうしてかと言えば、自分は本当にしっかり練習してきたし、リハーサルもよくやって、観客に向けて自分がどんなことをやりたいかきちっと把握している、という感覚があるからで。それに大抵は、観客もこちらのやることに拍手を送ってくれるわけで(笑)。ある意味、観客が喝采してくれ、僕が何か語りかけるとみんなが笑いを返してくれる、というのはある程度は予想可能だし、その状況を自分も理解している、と。とは言っても、(単独公演ではなく)フェスティヴァルでプレイするのは少し勝手が違って、状況を予測するのがやや難しくなるね。お客さんも僕が何者か知らないし、だからフェス出演では普段より少しだけナーヴァスになる。うん、それは自然な成り行きだし……とは言っても、基本的に僕はステージではアガらない。
■そうしたセラピーによって音楽制作も影響されるところは大きかったのでしょうか?
JR:ああ、確実に作詞面では影響された。どの曲も、歌詞に関してはあのセラピー体験について、みたいなものだから。ただし音楽面で言えば、「たぶんそうじゃないか」ってところかな……? たぶん影響されたんだろうな、僕はあのムードにマッチするような音のパレットを作り出そうとしていたわけだし。そうしたムードの多くは生々しくエモーショナル、かつアトモスフェリックなものだったし、僕はあれらのストーリーを運び伝える詩的な媒体を与えたかった。そうだね、セラピーは僕に、歌詞そして音楽の両面で大きく影響したと思う。
[[SplitPage]]
自分の傷つきやすさを捨てて、誰かに対してやっとオープンになれた自分についての歌だし……それはほんと、メタファーを使って書けることではない。
■昨今の社会情勢が『ワット・ウィ・コール・ライフ』にも反映されていて、たとえば“クラウズ”はブラック・ライヴズ・マター運動に触発された曲です。あなたのルーツを辿ると、父親はクック諸島のマオリ族出身で、母親はニュージーランドの白人という混血ですが、肌は白かったので白人としての扱い、いわゆる「ホワイト・プリヴィレッジ」を受けてきた。で、オーストラリアという白人が大半の国で育ち、その後イギリスへ渡った。BLM運動によってそれまであまり気にしてこなかった自身の肌の色やルーツを見つめ直し、それによって受けてきた経験に思いを馳せて書いたのが“クラウズ”というわけです。改めてこの曲にこめたメッセージについて教えてください。
JR:うん、いま言われたことは基本的にあの曲をよく要約してくれている。ただ、あの曲で僕が話しているのは……まず、自分は人種が混じっていると自覚した、というのがあって。だから、これまで成長してきた間に、人種が混じっているということすら忘れてしまっていたんだよね、というのも僕の肌の色はご覧の通り白人のそれなわけで。で、ああした(BLM運動の)様々なことが起きていた中で考えていたんだ、「ああ、自分の父親の肌の色がブラウンだったことをすっかり忘れてたな!」と。父親はニュージーランド、そしてオーストラリアで暮らしてきた人生の間ずっと、ああした経験に対処してきたに違いないし、でも僕はそれについて彼と話し合ったことがなかった。彼がこうむったかもしれない人種差別に、僕はちゃんと共感したことがなかった、というか。で、先ほど言われたような自分が受けてきた特別扱い、純粋に自分の肌の色ゆえに与えられた特権について僕も考えさせられたし、白人の多い国オーストラリアで育ったことについて考え、また現在もロンドンのような場所で暮らしているし──ロンドンはもちろん多文化社会とはいえ、やはり白人が多いわけで。だから僕はとにかく、「ちょっと待てよ」と思った。というのも、僕はこれまでずっと一所懸命働いてきたし、自分が成功できたのはその努力の賜物だよ。ところがそんな自分のこれまでを振り返ってみると、実は非常に多くのアドヴァンテージを与えられてきたじゃないか、と。単に自分の肌の色、そして自分のジェンダーのおかげでね。白人の男性であるおかげで自分は成功を収めることができたというか、ハード・ワークに由来するものではなく、自分は最初の段階から得をしてきたんだな、と。で、あの曲は一種、そこから来る自分の罪悪感というか、その点を理解し、自ら認め、その上で問題に取り組みつつ前に進んでいこうとする歌なんだ。自分の特権を理解することを通じて、格差をもっと縮めようとし、できるだけ誰にとっても平等なフィールドをもたらしたい、そういうことだと思う。
■そうしたリアリティと向き合うのは難しいことですよね。あなたが非常に努力して現在の立場にいるのは我々も理解していますが、現在の社会では「白人男性」のアイデンティティはとても多くの角度から敵視されてもいて。
JR:(うなずきつつ聞いている)。
■そうしたアイデンティティの持ち主というだけで批判されてしまうのは、フェアではないんじゃないか? という気持ちも抱きます。たとえばの話、私からすれば旧型の「白人男性の特権」の象徴と言えばドナルド・トランプで。
JR:フハハッ!(苦笑)
■彼は親からビジネスを受け継いだだけで、まさに父系社会の産物ですが、あなたはそうではなく自力でここまで来た。そんなあなたが罪悪感を抱くのは、逆にこちらもモヤモヤしてしまいます。とても複雑な話なので仕方ないとはいえ……。
JR:そうだね、複雑だ。だから、さっきも話したように、自分の中でも入り混じっているんだと思う。これまでずっと、本当に努力を重ねてきたのは自分でも承知しているからね。ただ、それと同時に、たとえば……キャリア初期の頃、僕はもっとトラディショナルなソウル・ミュージックを作っていたわけだよね。ところが、UKはもちろんアメリカ、いやそれ以外の世界中にも、とんでもなく優れた黒人のソウル・シンガーで、成功していない人たちはいる。でも、僕は白人でそれをやっていたからちょっとした存在になったというか、アウトサイダーながらソウル・ミュージックをやっている風変わりな奴みたいなものになって、人びとから「おっ、彼は白人なのにこういう音楽をやってて変わってるぞ、クールだ、彼の音楽を流そう」と注目された。その点ひとつとってすら、伝統的なソウルのコミュニティの中では僕には違いがあり、それが有利に作用して初期の自分が他の人より成功することに繫がった、というか。間違いなく僕は努力したし、練習も多く重ねて歌もさんざん歌い、少ないお客相手に何年も演奏するなどの下積みはやってきた。けれども、一方で、それとは別の側面では恩恵を受けてもきたんだよ。
■“ファミリー”をはじめ家族や兄弟などについて書かれた曲もいろいろあります。家族や兄弟などプライヴェートな部分を歌詞にするのはとても勇気がいることかと思います。また歌詞も以前のように曖昧で比喩的なものではなく、“ファミリー”や“アンガーディッド”では直接的な言葉を使ってストレートに表現している場面もあります。ソングライティングをする上でいろいろ心境の変化があったのでしょうか? 以前に比べて自分をさらけ出すことを恥ずかしく思わなくなったそうですが。
JR:うん、それは確かにある。特に、君の言う通り“ファミリー”のようなトラックはそうだね。以前の僕は両義的な曖昧さ、そしてメタファーを用いて歌詞の意味合いを隠すのが好きだった。それはきっと僕自身に、ストーリーをオープンにさらけ出す自信が充分なかったからだろうね。ところが“ファミリー”では、あのストーリーを語る唯一の手段は本当に、比喩を用いずダイレクトに語ることだけだろう、そう思えた。その方が、もっと理解しやすいからね。そうは言っても、アルバム曲のいくつかにはやっぱり抽象的というか、比喩を用いたものもあるけどね、僕はああいう曲の書き方のスタイルも好きだから。ただ、数曲は、自分がこの内容を本当に語りたいのならばダイレクトに書くしかない、というものだね。たとえばさっき君の挙げた“アンガーディッド”、あれは妻との出会い、そしてそこで自分の傷つきやすさを捨てて、誰かに対してやっとオープンになれた自分についての歌だし……それはほんと、メタファーを使って書けることではないし、どんな風だったか、とにかくありのままに書く以外になかった(笑)。だから、そうしたふたつの書き方の混ざったものだし、おそらくそれは自分も成長した、人間として以前より成熟しつつあるってことなんだろうね。おかげで、場合によってはもっとオープンになった方がいいこともあると気づかされたっていう。
■そうやって歌詞の中で自分を出し、弱さも見せることには勇気が必要だと思います。
JR:うん、僕もそう思う。妙な話だけれども、僕の場合、歌を通じてそれをやる方がずっと楽に感じられるんだ。たとえばどこかで友人と会って、そこで「お前の子供時代がどうだったか教えてよ」と友人に言われたら、面と向かって話す方がずっとやりにくいだろうな、みたいな?(苦笑)
■(笑)確かに。
JR:いざ話そうとすると難しい。でも、それを歌に書くとなったら、曲作りは僕自身のスペースの中でやれるし、ある意味音楽の後ろに隠れて語ることができる、という面もあるからね。んー、まあ、音楽の中での方がほんと、自分をさらけ出すのがずっと楽なんだ。で、いまの自分としては、その方向にもっと進んでいきたいな、と。
■サウンド面を見ると、いままでのようにあなたがある程度のベース・トラックを作った上で必要に応じてゲスト・ミュージシャンを入れて録音していくのではなく、バンドとしてスタジオに入っていちからサウンドを作り上げていくレコーディングがおこなわれています。あなたのバンドはいろいろツアーをしてきて結束も強くなり、今回はそうしたバンド・サウンドを求めてレコーディングに入ったのですか?
JR:その通り、まさにそう。僕がこの作品で捉えたかったのは……以前は、音楽はすべて自分で書いて、ライヴの準備のためにそれをリハーサル場に持ち込んで皆でプレイする、というものだった。で、彼ら(=バンド)は毎回、さらに良いサウンドにしてくれるんだよ。というわけで僕も「彼らと一緒に書かなくちゃいけないな」と思ったんだ、そうすれば、レコーディングする前の段階で彼らにもっと良いサウンドにしてもらえるから(笑)。というわけでスタジオに入って──うん、これまた混ざっているんだよね。彼らバンド側の出してきたアイデアをすべて享受しつつ、でも、自分自身にも挑戦を課したかったから、僕は今回は典型的な、オールドスクールなプロデューサーの役割を自分にもっと割り当てたんだ。ある意味少し後ろに退いて、耳を傾けた。キーボード、ギター、といった具合に各パートに集中するよりも、むしろもっと音楽全体の視界を聴くというか、音楽そのものと、そこからどんなフィーリングを受け取るかに耳を傾けていった。だから実際、今回はスタジオのコントロール・ルームで過ごすことが多かったんだ、他のみんながレコーディングしている間も、自分は昔気質なプロデューサー役をやっていたっていう。あれをやるのはチャレンジだったけれども、とても楽しんだし、これまでとはまた別のやり方で音楽について多くを学んだ、という気がしている。僕はアルバムごとに音楽作りのプロセスを変えていくのが好きだし、だから次のアルバムではまた違う創作過程を踏むかもしれないよ(苦笑)、まあ、どうなるかわからないけれども。ただ、今回のようなアルバムの作り方は素晴らしかったね、うん。
■ウェールズの田舎で友人のミュージシャンたちと作ったそうですが、利便性の高いロンドンではなくウェールズを選んだのは何か理由がありますか?
JR:(笑)それは、僕たちは気を散らされるあれこれから逃れたかったからなんだ。僕としては、このレコーディング・セッションを一種の曲作りのために向かう小旅行とか休暇、それとも田舎の隠遁所で過ごす経験、みたいなものにしたかった。でも、いつもとは違う空間にいると、なんというか、自分の頭を別の働き方のモードに置くことになる、というのかな? たとえば、ロンドンにいたとしようか。僕たち全員がロンドンでこのアルバムを制作していたとして、ある日ひとつトラックを仕上げたら、みんな「さーて、どうやって家に帰ろうかな。夕飯は何を食べよう?」と考えなくちゃならない。日常生活のあれこれも考えながらやっているわけ。ところが田舎に滞在していると、日常は忘れて音楽だけに集中することになる。散歩に出かけて、木立の中を歩いて樹々を眺めているうちにインスピレーションが湧いて、スタジオに戻ってまた別のトラックに取り組んで、それで“ファミリー”ができ上がった、とか。だからあれは本当にオープンで、かつリラックスした音楽の作り方だった。と同時に、プレッシャーもあったけどね、自分たちが何をやろうとしているのか、僕たちにはまったくわかっていなかったから。でもその一方で、ああやってスタジオにいられるのはとても解放的な体験だった。だからあの2週間は本当に、くつろぎながらあの環境に入っていった、というか。
■バンドのメンバーが全員揃って強制的にスタートするのではなく、ジャム・セッション的なことをしていく中でメンバーからいろいろなアイデアが生まれ、そうした自然発生的でクリエイティヴな雰囲気の中で楽曲が磨かれていったと聞きます。ただ、前もって何も決まっていないと、「さて、どうしようか?」と途方にくれてうまくいかない場合もたまにあったんじゃないかと……。
JR:(苦笑)。
■自由だったセッションを、どんな風に舵取りしていったんでしょうか?
JR:いや、意外なことに、そういう困った場面に僕たちはあまり出くわさなかったよ(笑)。それにはクールな逸話があって……ある朝、僕たちは作業をはじめて1曲仕上げたんだ。アルバムの6曲目の“ワット・ウィ・コール・ライフ”、あれをその朝に録り終えた。よし、ということで、ランチを食べ昼休みをとって、作業再開になった。ところがみんな腹一杯ランチを食べたせいで、かなり無気力になってしまって。
■(笑)。
JR:(苦笑)おかげで、みんなやる気を起こそうと必死だった。僕はそうじゃなかったけどね、そもそも、普段からそんなに食べない方だから(笑)。で、自分はまだエネルギーが余っていたし、一方でバンドの連中は満腹で不活発になっていて、でも僕は「よし、あのシンセサイザーで何かやろう」って感じで。そこで、“アンガーディッド”のイントロになっていくベース・ラインを弾きはじめた。だからなんだ、あの曲の冒頭部がとても剥き出しな感じになったのは。そういう風に自分が淡々と弾いていたベース・ラインに過ぎなかったからだし、でも、弾いているうちにこれはいいぞ、レコーディングしよう、と思い立った。そこからはじまったようなものだったし、徐々に僕はあの曲、“アンガーディッド”へと組み立てていった。ああした素敵な、ゆったり動いていく歌が生まれたのは、僕たちがみんなパスタを腹一杯食べてダルくなっていたからだった、という(苦笑)。
■(笑)。
JR:(笑)あのときくらいだったかな、僕たちが作業を進めるのにてこずったのは。でも、ある意味あれはあれで良かったんだ、だってあそこから“アンガーディッド”が生まれたんだからね。
ビートメイカー的で、よりプロセスの細部まで突っ込んでいくタイプのプロデューサーではなくて、今回の僕はもっと俯瞰するプロデューサーをやってみたんだ。
■メンバー間の意思疎通が豊かであるからこそ生まれる雰囲気ですし、先ほどもおっしゃっていたように、今回あなたはいわばクインシー・ジョーンズ的に全体像を見るアプローチをとった、と。やはり、そこにはあなた自身のミュージシャンとしての成長もあったわけですか?
JR:その通りだ。おそらく、5年くらい前の自分にこの作品は作れていなかっただろうと思う。ロンドンで過去数年、実に多くのミュージシャンをプロデュースし一緒に仕事してきたし、いろいろな人びとのために曲もたくさん書いてきた。そうやって僕はある意味、制作プロセスへの異なるアプローチの仕方を学んできた。そこで考えたんだ、これと同じことを自分のアルバムでやってみたらどうだろう? と。プレイヤーとして演奏の多くをこなすというより、むしろもっと総合プロデューサー的にあらゆる面に目を配る、というね。で、アーティストでありつつ自分でそれをやれるのは本当にラッキーだと思っているよ、セッションそのもの、あるいはクリエイティヴなプロセスを前進させるためにプロデューサーに頼らざるを得ないアーティストをたくさん知っているからね。でも、僕には自分の音楽をどんなサウンドにしたいか、そのヴィジョンがちゃんとあるし、と同時に曲を書いてもいる。だから非常にラッキーというのかな、曲を書くことができ、かつ、それをどう仕上げるか、プロセスの最後まで見通すこともできるのは。自分の頭の中にヴィジョンが存在するからね。で、それはこれまでの経験を通じて学んだことだったし、クインシー・ジョーンズ的な全体を見るスタイルのプロデューサーという意味で、確実に自分ももっと進歩したと思う。たとえばそうだなぁ、フライング・ロータスのようなビートメイカー的で、よりプロセスの細部まで突っ込んでいくタイプのプロデューサーではなくて、今回の僕はもっと俯瞰するプロデューサーをやってみたんだ。
■『オリジン』では曲作りにおいてスティーヴィー・ワンダーやスティーリー・ダンからの影響を述べていましたが、『ワット・ウィ・コール・ライフ』を作る上で聴いていたのはローラ・マーリング、スコット・マシューズ、ジョニ・ミッチェル、ジョン・マーティンだそうですね。新旧のフォークやフォーク・ロック系のシンガー・ソングライターたちですが、彼らのどのような部分があなたの音楽に影響を与えているのでしょうか?
JR:彼らみたいな人たちは、音楽の中でもっとストーリー・テリングを基盤にしているからだと思うし、それに音楽的にもはるかにそぎ落とされて簡潔だよね。もちろん僕のアルバムはそぎ落としたものではないし、実に多く幾層も音が重なっている。とはいえ、思うに自分は、彼らの歌詞の書き方、そしてその歌詞の伝え方からインスピレーションをもらったんだろうね。それから、ハーモニーとメロディに対する彼らのアプローチの仕方にも。たとえば、スティーヴィー・ワンダーは非常にエキサイティングなハーモニーを使うんだ、非常にジャズ・ベースなハーモニー、あるいはファンクが強く基盤になったハーモニー、といった具合に。でも、今回のアルバムで僕はあまりそれはやっていなくて、それよりもっとソングライターがベースの、非常に多くレイヤーを重ねたものになっている。うん、そういったことに自分は足を踏み入れていったんだね、より歌がベースの、フォークが基盤の音楽へと。で、「このフォークがベースになっている音楽を、どうやったらもう少しモダンな、エレクトロニックな響きを持つものにできるだろう?」と自問していた。だからこのアルバムは新旧の世界の間に架かった橋、そこに存在するものだと思う。
■以前のインタヴューではボン・イヴェールとも共演したいといったことも述べていました。世間からはネオ・ソウルというイメージで捉えられがちなあなたですが、いま述べたようなアーティストたちや『ワット・ウィ・コール・ライフ』のサウンドからは、よりアコースティックでフォーキーな世界を指向しているのかなという気がしますが、いかがでしょうか?
JR:そうだね。以前の自分は……いや、誰もが僕のことをこの、「ソウル・シンガーの新星が登場」みたいに評してくれたこと、それはとても感謝しているんだよ。ただ、僕はいつだって非常に幅広く音楽を聴いてきたし、たとえば昔作った「ソウル」なレコードにしても、他に較べて少しオルタナな曲がいくつか混じっていたこともあった。要するに僕の中には常に、異なる領域を探ってみようとする側面があるっていう。ダンス・ミュージックのプロジェクトであるダン・カイをやったり、あるいはセカンドの『ウォールフラワー』ではもっとアコギ寄りだったりしたのはだからだし、僕はアルバムごとに異なるサウンドを探究している。本当にたくさんいろんなタイプの音楽を聴いているから、毎回、それらすべてを聴き手とシェアしたいと思う。だから次のアルバムではまた、もしかしたらガラッと違うサウンドをやるかもしれない(笑)。とはいっても、現時点ではどうなるかまだわからないけどね! ただ、自分はきっと違うことをやるだろう、それは確信しているし、それが楽しみでもあるんだ。というのも僕はアルバム作りを、ファンや人びとに対して自分の持つ音楽的に異なる側面を見せる場であると同時に、ある種の学びのプロセスとして考えているから。僕は決して「これ」という風に、たとえば「僕はソウル・シンガー」と狭いひとつの箱に分類されたくないし、それは自身について「ソウル・シンガー」のレッテルだけに留まらない、もっとずっと多くのことをやる人間だと感じているからであって。そうだな、それが僕のキャリアのゴールみたいなものかな、(ジャンルや名称の区分云々を越えて)もっと「アーティスト」になりたい。
■あなたの数多くの側面をパッケージした総合的な存在を目指す、と。
JR:そういうことだね。
■先ほども「次はどうなるか」という話がありましたが、今後の予定やプロジェクト、やってみたいことなどお聞かせください。まずは、可能になったところで本作向けのツアーがあるでしょうが、それを終えたら?
JR:うん、やってみたいと思っていることはいくつかある。とはいっても現時点ではまだ歌詞のコンセプトはちゃんと考えていないんだけどね、僕は前もって歌詞コンセプトを想定するのが好きだから。でも、そうだね、やりたいと思っていることがふたつあって、まずひとつはクック諸島に戻ること、なんらかの形で自分の家系的な遺産を受け入れる、ということで。だからたぶん、何ヶ月かクック諸島に滞在して、地元ミュージシャンとコラボしながら曲を書く、みたいな。それができたら本当に素晴らしいだろうと思うんだ、自分自身のカルチャーと再び触れ合うということだからね。でも、それと同時に……発表したばかりの今回のアルバムは、音の重ね方やアレンジという意味で自分としてはかなり密度の濃い作品だと思っていて。だからぜひそれとはまったく逆の、思いっきりそぎ落とした作品、ミニマル調なものをやりたいと思っているんだ(笑)。
■(笑)なるほど。
JR:(笑)僕はずっとこういう感じでやっているんだよ。ファースト・アルバムを作って、あれはかなりファンキーな作品だったから、次はもっとスローなものを作る必要があると思ったし、それでセカンドはスローなものになった。で、サードはまたファンキーな内容だったし、対して今回のアルバムはものすごく密度が濃い……という具合で、自分は作品を作りながら何もかものつり合いをとっている、そういう感覚がある。でもまあ、現時点でやりたいと考えているのはそのふたつだね。クック諸島でのなんらかのコラボレーション、そしてもっとシンプルな美しい音楽をやる。とにかくシンプルで、聴いていてリラックスできるような音楽を。というのも、いまちょうど、アンビエント・ミュージックにハマっているところでね。だからもしかしたら、2時間近い長さのアンビエントな曲をやる、とか?(笑)
■それはいいですね。たまたまですが、私もアンビエント音楽はここ最近よく聴いています。
JR:いいよね、美しい音楽だ。
■アンビエントの古典、ブライアン・イーノ作品だとか……
JR:うんうん、ブライアン・イーノね! 瞑想をやっているときや電車に乗って移動中に、僕もブライアン・イーノの『ミュージック・フォア・インスタレーションズ』なんかを聴いている。とにかく美しい経験というか、一種のムードを、心を落ち着けるムードを感じさせてくれる音楽だ。
■もう時間ですので、終了させていただきます。今日はお時間いただきありがとうございます。また、あなたとバンドの皆さんが日本にツアーに来られる日を楽しみにしています。
JR:うん、できれば来年、日本に行くつもりだよ!