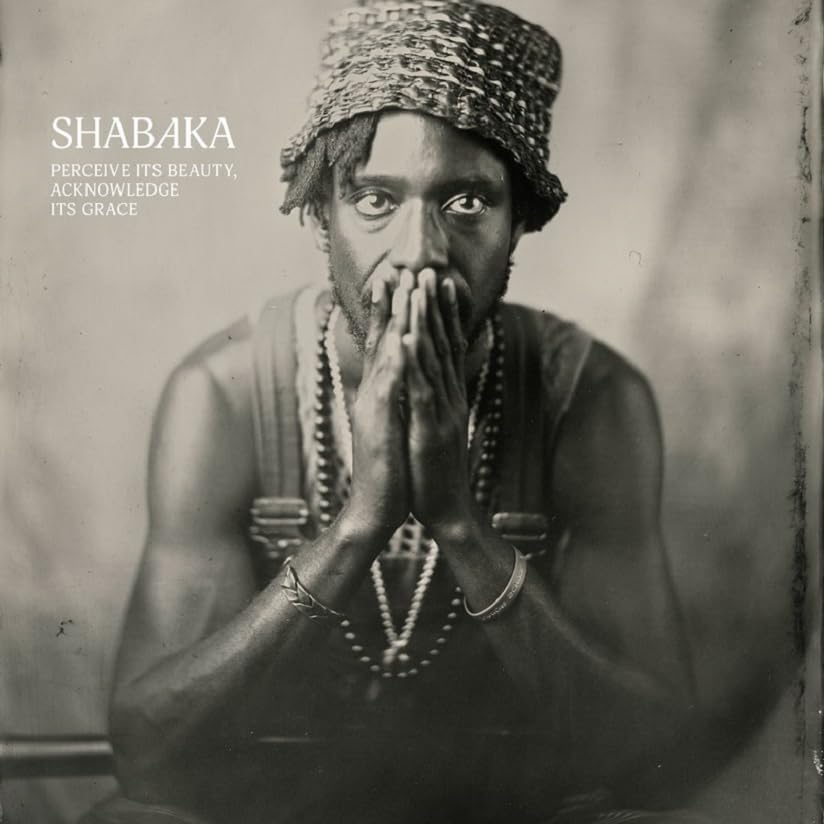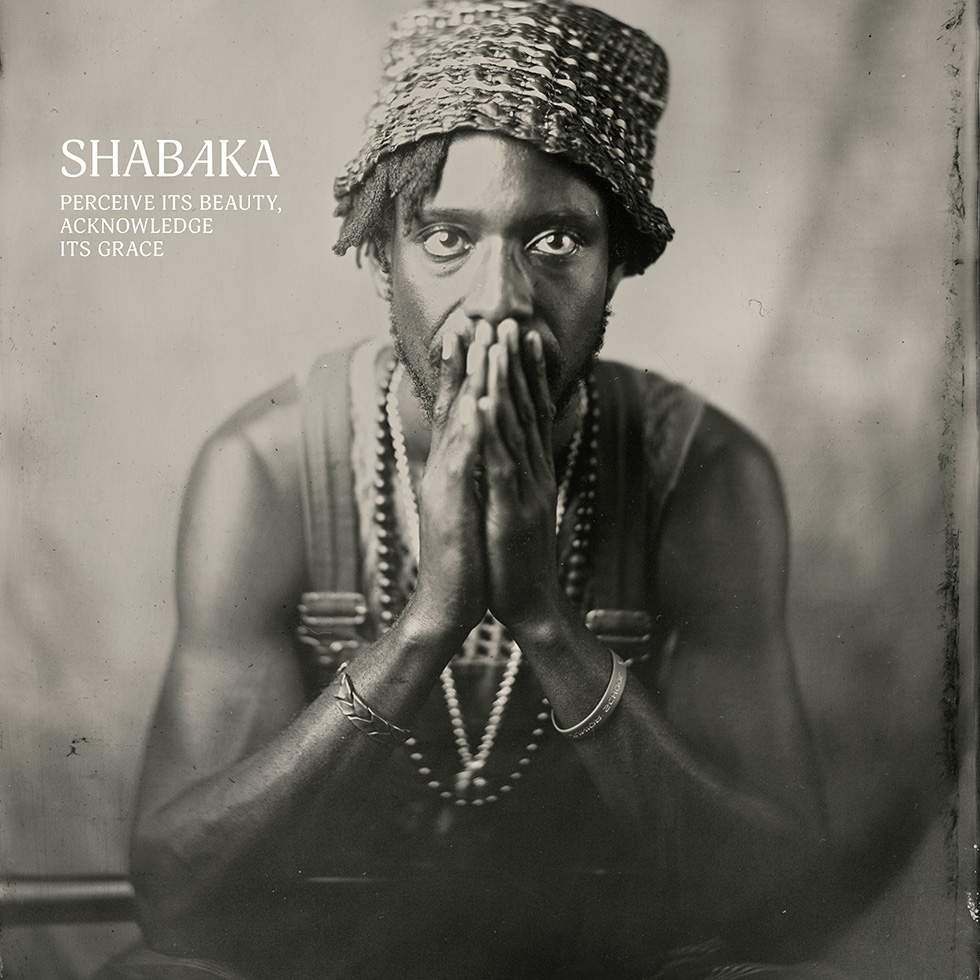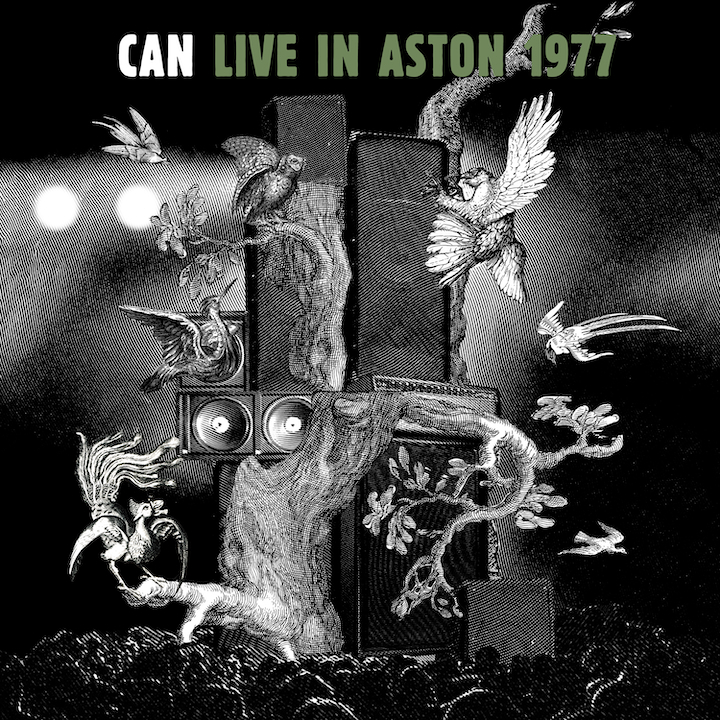近所の本屋で立ち読みをしていたらBGMがなんとも素敵なドローンに変わった。スーパーの上にある店にしては粋な選曲じゃないかとうっとり耳を傾けていたら、店員さんが押している台車が視界の端に入ってきた。ドローンどころか音楽でもなくて、台車がガラガラと立てていた音だった。ガラガラガラ……。いや、でも、坂本龍一が言っていたのは、こういうことだよなと気を取り直す。あらゆる音に音楽を聴き取るということはこういうことだろうと。ほんの数秒だったけれど、それはとても素敵なドローンだった。自分が好きな種類の音だったことに変わりはない。台車の重さだとか、店員さんが押すスピードだとか、様々な条件が重なって出た音がそれだったのである。それから数日後、同じ本屋の前を通りかかると、再び、ガラガラガラ……と同じ音が聞こえてきた。ああ、また、台車の音かと僕の脳は初めからその音を音楽としては受けつけてくれない。覚めきった脳である。もう一度ぐらい騙されてくれてもいいではないか。そして、そのまま歩き続けると、その音は台車ではなく福引きのガラガラポンを回す音だった……

坂本龍一の最後のピアノ演奏を収めた記録映画。坂本龍一が音響設計に携わった109シネマズプレミアム新宿で観ることができた。『Playing The Piano 2022』と同じく坂本龍一がひたすらピアノを弾き続けるだけで、「opus」は「作品」の意(『BTTB』の冒頭を飾る〝Opus〟はかなりゆっくりとしたアレンジに改められている)。
最初の曲は〝Lack of Love〟。坂本龍一の訃報が伝えられた直後にSpotifyで1位になった曲である。死後に何が起きるか予言していたみたいで、ちょっと驚く。真上とか横からカメラが寄っていくのではなく、穏やかでどことなくミステリアスなピアノを演奏する坂本龍一の背後からカメラが近づいていく。もしも撮影しているのが他人であれば、坂本は手を止めて振り返るような気がするけれど、息子が監督だからだろうか、無防備な背中は振り返ることなく、後ろを向いたまま。背中というより「気配」の視覚化と言いたい。こんなところから見ていいのだろうか。そんな気分に襲われる。大袈裟にいえば家族の一員になれたようなオープニングである。
宣伝資料には「コンサート映画」と謳われている。だとしたら、以下、具体的な曲名は伏せて「作品」を眺望してみよう。意外な選曲。意外な曲の構成をひた隠しにして宣伝の片棒を担ぐことにしたい。ユーチューブを検索すると坂本龍一は自分がかかわった映画についてあれこれと話す動画をたくさんアップしていることがわかる。そして、そのどれもがあまり視聴されていない。『あなたの顔』や『さよなら、ティラノ』など、いろんな映画を見てもらいたくて彼は勝手に宣伝していたのだろう。僕もいまは似たような気持ちである。

ピアノの演奏を収めた映像となると背中ばかりを映し出すわけにはいかない。坂本親子といえどもそこまでは前衛ではない。何曲か観ていると、定石通りに手元のクローズ・アップが映し出される。角度の妙なのだろうか、手元のクローズ・アップを何度か観ているうちに坂本の両手が2匹の魚に見えてきた。飛び魚が水面を跳ねて泳ぐように坂本の両手が抜いたり抜き返したりを繰り返す。曲が終わると両手がふわっと宙に持ち上げられる。坂本龍一追悼号で坂本とコラボレーションを続けたテイラー・デュプリーにどうして『Disappearance(減衰)』というタイトルにしたのか尋ね、「2人とも人生や自然の儚さに惹かれていたから」(p43)という答えを得たのだけれど、坂本がふわっと手を宙に持ち上げると、手の先にはまだ音が残っていて、それがゆっくりと空中に消えていくプロセスが目に見えるよう。曲の終わりだけではない。ひとつの音が現れては消え、次の音が現れては消える。その繰り返しに2匹の魚が自然と重なっていく。
『Opus』が捉えたのは、結果的に最後の演奏ということになったわけだけれど、どういうわけか、枯れた演奏という感じはしなかった。どの曲も次の演奏はなく、「これで終わり感」のようなものはあるのに、そのことと「枯れる」という感覚が結びつくことはなかった。似たような和音を続けざまに抑えたり、少しずつ音階がずれていく展開など、なんというか、正解を探り続けているというのか、坂本の中で完結したものを聴かされているという気がしないのである。うまく言えないけれど、この世界には感情のツボがあって、そこを一緒になって探っているような能動的な気分になっている。僕は長いあいだ『B-2 Unit』や『Esperanto』がとても好きだった。だけど『Out Of Noise』が自分の気持ちに入り込んだ瞬間から初期の作品には幼さを感じるようになり、以前と同じ気持ちで聴くことができなくなって名盤として同列に扱うことも無理になり、それだけ『Out Of Noise』が醸し出す慈しみやスケールの大きさに圧倒されて〝Merry Christmas Mr. Lawrence〟が無限大に膨れ上がったヴィジョンに包まれたような気がしていた。『Opus』を観ていて感じたこともそれに似たものがあり、枯淡の境地というような距離感のあるものには思えなかった。

そして、それらとまったく違ったのが〝Tong Poo〟。この曲だけは「次はない」という気がしなかった。やはりこの曲にはこれからYMOを始めるぞという坂本の野心が目一杯つまっていたからだろう。それまでずっと続いていた穏やかな海とは違い、〝Tong Poo〟からは人生の荒波に乗り出す期待がいまだに躍り出してくる。だからか、逆説的に「枯れた演奏」という表現がこの曲だけには当てはまると思う。少なくとも『BTTB』に収められた獰猛なヴァージョンと比較したらそれこそ老いを感じさせる演奏ではある。そして、他の曲とはあまりにトーンが違うからか、〝Tong Poo〟だけはすぐに演奏が始まらない。ほかの曲でもやり直しや単純な失敗はあったのだろうけれど、調子を整える場面を残したのはこの曲だけだったというのは映画の構成的にも正解だったと思う。
ピアノ1台だけなのにベースが聴こえてくるような気がする曲もある。演奏しながら鼻の下を伸ばす仕草も監督は逃していない。比較的好きではなかった曲もまったく違った曲に聴こえた。〝Merry Christmas Mr. Lawrence〟は様々な時期の演奏を聴いてきたつもりだけれど、極端に高音を強調した初期の演奏や最も落ち着いた2010年代の演奏、あるいはイントロの前に別なイントロがついたヴァージョンなど、そのどれとも異なる演奏で、音階が違うわけではないと思うけれど、そこはかとなく音数が多い気がして、あまりに簡素だった『Playing the Piano 2022』やモチーフによってテンポが急変する〝Merry Christmas Mr. Lawrence - Version 2020〟の演奏がまだ頭に残っているせいか、一度だけでは消化できない情報量が耳に残ったままになっている。この情報量をしばらく頭の中で転がし続けられることが、おそらくは幸せなことなのだろう。

PS
昨年始めに『12』のレビューで坂本龍一が盛んに大学生の僕たちを笑わせようとしたことを書き、これを読んでくれた小山登美夫が、イヴェントが終わってから坂本さんに「暗いよ」と言われ、だからしつこく笑わせようとしたのだということが判明いたしました。40年前も前のナゾがいまさら解き明かされるなんて。