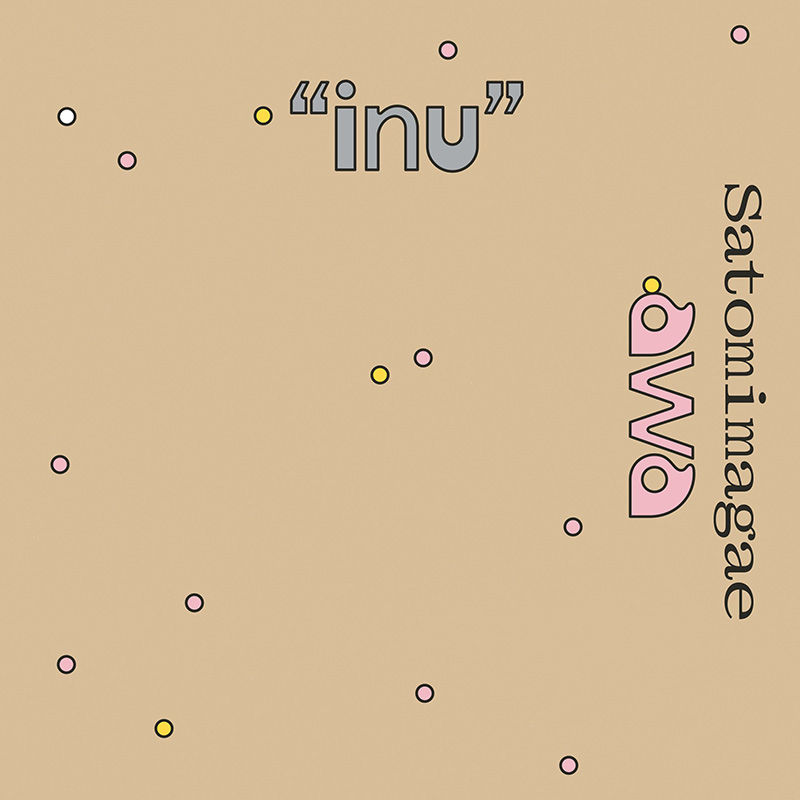■特集:エレクトロニック・ミュージックの新局面
表紙・巻頭インタヴュー:Phew
インタヴュー:ロレイン・ジェイムズ
コロナ以降激変するエレクトロニック・ミュージックの新たな動向を追跡、
今後10年の方向性を決定づけるだろう音楽の大図鑑!
シーン別に俯瞰するコラム、ディスクガイド、用語辞典、日本の電子音楽の新世代、ほか
■2022年ベスト・アルバム特集
20名以上のライター/DJなどによるジャンル別ベスト&個人チャート、編集部が選ぶ2022年の30枚+リイシュー23枚で2022年を総括!
目次
特集:エレクトロニック・ミュージックの新局面──2020年代、電子音楽の旅
インタヴュー Phew (野田努)
Phewについて──生きることを肯定する、言葉の得も言われぬ力 (細田成嗣)
インタヴュー ロレイン・ジェイムズ (ジェイムズ・ハッドフィールド/江口理恵)
ディスクガイド
2020年代エレクトロニック・ミュージックの必聴盤50
(髙橋勇人、三田格、河村祐介、yukinoise、デンシノオト、ジェイムズ・ハッドフィールド、野田努、小林拓音)
2020年代を楽しむためのジャンル用語の基礎知識 (野田努+三田格)
コラム
ジャパニーズ・エレクトロニック・ミュージックの新時代 (ジェイムズ・ハッドフィールド/江口理恵)
ベース・ミュージックは動いている (三田格)
2020年代を方向づける「ディコロナイゼーション」という運動 (浅沼優子)
音楽は古代的な「魔法」のような存在に戻りつつある (ミランダ・レミントン)
暴力と恐怖の時代 (三田格)
2022年ベスト・アルバム30
2022年ベスト・リイシュー23
ジャンル別2022年ベスト10
エレクトロニック・ダンス (髙橋勇人)
テクノ (猪股恭哉)
インディ・ロック (天野龍太郎)
ジャズ (大塚広子/小川充)
ハウス (猪股恭哉)
インディ・ラップ (Genaktion)
日本ラップ (つやちゃん)
アンビエント (三田格)
2022年わたしのお気に入りベスト10
──ライター/アーティスト/DJなど計23組による個人チャート
(青木絵美、浅沼優子、天野龍太郎、大塚広子、岡田拓郎、小川充、小山田米呂、河村祐介、木津毅、柴崎祐二、杉田元一、髙橋勇人、つやちゃん、デンシノオト、野中モモ、ジェイムズ・ハッドフィールド、二木信、細田成嗣、Mars89、イアン・F・マーティン、Takashi Makabe、三田格、yukinoise)
「長すぎる船旅」の途上で歌われた言葉──2022年、日本のポップ・ミュージックとその歌詞 (天野龍太郎)
2022年は大変な年でした (マシュー・チョジック+水越真紀+野田努)
Cover portrait: Masayuki Shioda
Collage: Satoshi Suzuki
【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】
◆amazon
◆TSUTAYAオンライン
◆Rakuten ブックス
◆7net(セブンネットショッピング)
◆ヨドバシ・ドット・コム
◆Yahoo!ショッピング
◆HMV
◆TOWER RECORDS
◆diskunion
◆紀伊國屋書店
◆honto
◆e-hon
◆Honya Club
◆mibon本の通販(未来屋書店)
◆DMM.com
【P-VINE OFFICIAL SHOP】
◆SPECIAL DELIVERY
【全国実店舗の在庫状況】
◆紀伊國屋書店
◆三省堂書店
◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア
◆旭屋書店
◆有隣堂
◆くまざわ書店
◆未来屋書店/アシーネ