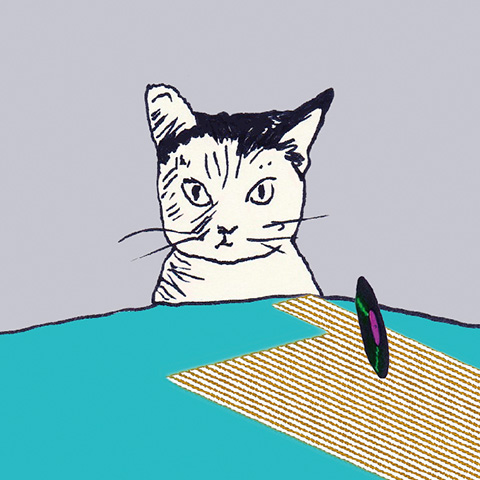Joe Armon- Jones Starting Today Brownswood/ビート |
ジョー・アーモン・ジョーンズは、UKジャズの新世代を代表する20代半ばのピアニストであり、先日リリースされた彼のデビュー・アルバム『スターティング・トゥデイ』には、いままさにはじまりの真っ直中にいるUKジャズの前向きなヴァイブレーション/喜びが詰まっている。いち音楽ファンとして、こうした新しい音楽にワクワクできるのはこのうえない幸せだとつくづく思う。
そもそも昨年リリースされた「Idiom」がいまだ12インチにしがみついている粘り強いファンのあいだで話題になった。マクスウェル・オーウェンとの共作になるこの6曲入りは、ジャズ・セッションによる(つまり即興性のある)ハウス・ミュージックで、ディープ・ハウスやデトロイト・ビートダウン系のファンからロバート・グラスパー/サンダーキャットが好きなリスナーまで虜にした。自慢じゃないが、ぼく(=野田)もそのヴァイナルを所有している。というのも、アーモン・ジョーンズの音楽には、若さや勢いだけではない、極上のメロウなフィーリングがあるからだ。嘘だと思うなら、アルバム2曲目の“Almost went Too Far”を聴いて欲しい。
無論のことUKジャズ印の雑食性はある。アルバム『スターティング・トゥデイ』を聴いていると、この2年ほどの音楽トレンド(フュージョン、ハウスなど)も見えるだろう。ただいま絶賛制作中の別冊エレキングのジャズ特集号には、アーモン・ジョーンズのインタヴューも掲載されているが、紙メディアゆえにカットせざるえない部分があった。せこい考えだがそれはもったいないし、アシッド・ジャズ以来の活況を見せているUKジャズの逆襲、その第一弾としてお届けすることにした。質問は菅澤(ブルシットのドラマー)がほとんど考えてくれた。

■チック・コリアに影響を受けたとお聞きしました。彼はオーセンティックな4ビートのジャズからエレクトリック・マイルス・バンドの脱退後に結成したサークルでのフリージャズ、そしてリターン・トゥー・フォーエヴァーでのプログレッシヴなフュージョン的アプローチまで、その音楽性は幅広いですよね。彼の音楽のどんなところに影響を受けたのでしょうか?
JAJ:難しいな。僕はもちろん、チック・コリアの大ファンで……うまく言えないけど、彼のチューンを聴けばもうすぐに、彼だってわかるんだよね。彼のスタイルはそのくらいユニークなんだ。どんなことをやっていても。ハービー・ハンコックみたいな人とプレイする時でさえ、それが伝わってくる。本当にユニークな彼独自のスタイルがあるってことなんだ。そこじゃないかな。
■UKにはジョン・テイラーやスタン・トレイシーをはじめとした素晴らしいピアニストがいますが、UKのジャズ・ピアニストで影響を受けた人はいますか?
JAJ:大勢いるよ。いまだったら、サラ・タンディ(Sarah Tandy)とか。ものすごいピアノ・プレイヤーで、イカレてるっていうか、クレイジーなんだよね。アシュリー・ヘンリー(Ashley Henry)っていう人もいる。うん、正直言ってロンドンのピアニストで僕が今好きなのは、その二人。でももちろん、他にも大勢いて……ロバート・ミッチェル(Robert Mitchell)も驚異的なピアノ・プレイヤーだし、デイヴ・コール(Dave Koor)も。彼はジ・エクスパンションズ(The Expansions)っていうバンドでやってる。最高だから、チェックする価値があるよ。うん、今は大勢才能のある人たちがプレイしてる。
■現在のロンドンのジャズ・シーンを語るうえで〈jazz re:freshed〉の存在はかなり大きいと思います。ここで演奏されているジャズはオーセンティックなジャズに対するカウンターとしての側面もあるように感じるのですが、そういった意識はあると思いますか?
JAJ:うん。僕自身はあんまりそれぞれの音楽に定義とか、名前を付けすぎたくないんだけど、〈jazz re:freshed〉にはもちろん……『独自のサウンドがある』とは言いたくないな。むしろ、もともとジャズにはなかったようなサウンドを受け入れてるんだよ。ストレートなジャズ以外のサウンドを受け入れてる。他のサウンドをプッシュしてるんだ。そこが大きな違いを作ってると思う。例えば、僕らが最初に始めた頃、〈jazz re:freshed〉ではどんなバンドでもプレイできるチャンスがあった。彼らがその音楽を気に入って、好きになれば、自分たちがやりたいことがやれたんだ。〈jazz re:freshed〉をやってるアダム(・モーゼズ、Adam Moses)とジャスティン(・マッケンジー、Justin McKenzie )にはギグに来る観客とかからもたくさんリクエストが来てるはずなんだけど、実際、彼らは自分たちが気に入った音楽をギグに出す。それだけなんだ。
■“Starting Today”で歌っているラス・アシェバーはどんな人なんでしょう? その場の即興ということは、彼があの歌詞を書いたんでしょうか。
JAJ:彼が“書いた”っていうより、フリースタイルでやったんだよね。彼がスタジオにいて。あれはかなり遅い時間、その日のセッションを終えようとする頃だった。アシェバーはその時間まで来られなかったんだけど、僕らはその日ずっと“スターティング・トゥデイ”のインストゥルメンタル部分をレコーディングしてた。で、アシェバーが夜の7時頃来たのかな? で、セッションの最後にワンテイク録ってみよう、って。彼の場合ワンテイクで十分だしね。彼にトラックを聞かせる暇もなかったし、今どうなってるかよく説明もしないまま、セッティングして始めたんだ。そしたら彼がその場であのフレーズを歌いだしたんだよ。
■英語が苦手なので教えて欲しいのですが、たとえば表題曲の“Starting Today”ではどのような詞が歌われているのでしょうか? またそれぞれの曲の詞はその曲のヴォーカリストが書かれているのですか?
JAJ:うん、そう。僕が歌詞を渡して、シンガーに歌ってもらうなんてできないからね。歌うっていうのは、すごくパーソナルなことだから。“スターティング・トゥデイ”では、アシェバーが最後の方で『アシェオ』って繰り返すんだけど、あれは『生まれ変わる』って意味なんだ。生まれ変わって、再び始める。曲自体、新たにもういちどはじめること、新しい旅をはじめることについてなんだ。歌詞っていうのはもちろん、それぞれの人に違う意味を持つものだけど、僕にとってあの曲はそれについて歌ってるんだよ。
■“Almost Went Too Far”はアルバムのなかでもAOR寄りの曲ですよね。この曲では自身が歌われていることもあって、MndsgnやサンダーキャットといったLAのミュージシャンと共振する要素を感じさせますが、彼らの音楽はあなたにとってどんな存在ですか? またAORで好きなミュージシャンはいますか?
JAJ:彼らのことは大好きだから、そう言ってもらって嬉しいね。どんな存在かっていうと難しいけど……彼らの音楽で一番好きなところ、もっともインスパイアされるところのひとつは、彼らは特に訓練を受けたシンガーとかじゃないんだけど、自分の言葉を音楽に乗せられる。そこがクールなんだ。あとホーム・スタジオで作られてて、サウンドに手作り感があるし。だから、そう、僕も自分の音楽を外に出せる、っていう自信を与えてくれたような存在かな。
■サウス・ロンドンのジャズを聴いているととくにドラマーがアフロビートの影響が強いように感じます。今回のアルバムに参加しているモーゼス・ボイドもトニーアレンからアフロビートのレクチャーを受ける動画があがっていたりもしますが、あなたにとってアフロビートの魅力は?
JAJ:もちろん、エズラ・コレクティヴを通して、アフロビートの影響は僕も受けてる。でも、僕より通じてる連中がいるから。実際、エズラ・コレクティヴのフェミ(・コレオソ、ds.)、TJ(・コレオソ、b.)、ディラン(・ジョーンズ、Tp.)、ジェームズ(・モリソン、sax.)もみんなフェラ・クティやそのあたりの音楽にすごく影響されてるんだ。だから、あのリズムは確実に僕にも大きな影響を与えてる。アルバムでプレイしたドラマーも当然そうだし……ただ僕にとっては個人的に、このアルバムではダブやサウンドシステム・カルチャーからの影響の方が大きいんだ。でもアフロビートの影響ももちろんあるし、実際、影響されない方が難しい。ただ今回は、サウンドシステム・カルチャーの方が前面に出てると思う。
■”Ragify ”に参加しているBIG SHARERについて調べたのですが、ほとんど情報を集められませんでした。彼はラッパーとして活動しているのですか?
JAJ:彼もサウス・ロンドンでやってて……ビッグ・シェアラーはルーク・ニューマン(Luke Newman)としても知られてるんだ。〈STEEZ〉っていうイベントをオーガナイズしてて、僕らも出たことがあって。あと、彼はサウスポートっていうバンドもやってた。すごく面白い男で、彼とはギグを通じて知り合ったんだ。実際、僕は彼がオーガナイズしたギグでいろんなミュージシャン、いろんな人たちについて知ったし。彼はサウス・ロンドンの音楽シーンが盛り上がってきた頃からずっとやってるんだ。しかもものすごく才能があって、歌も歌える。“Ragify”ではラップしてるけど、アウトロ・トラックで歌ってるのも彼なんだよ。
■最後の曲”OUTRO (FORNOW)”からはディアンジェロの影響を感じさせますが、いかがでしょうか?
JAJ:もちろん、そうだね(笑)。とくにサウンド・プロダクション。ヴォーカルのレイヤーがたくさんあって、いろんなことが起きてる、っていう。あのトラックで歌ってるのはビッグ・シェアラー、ルークと、あとエゴ・エラ・メイ(Ego Ella May)っていう女の子も歌ってるんだ。素晴らしいシンガーだから、彼女はチェックした方がいいよ。若いシンガー・ソングライターで、EPが6月に出るはず。きっとすごい作品になると思う。彼女は僕の家に来て、ほとんどの曲でバッキング・ヴォーカルとかをやってくれたんだけど、“アウトロ”は彼女とルークのヴォーカルを混ぜたものになった。それが気に入ってるんだ。
※UKジャズの逆襲(2)に続く……