思い出して欲しいんだよな。君がどこから来たのかを。“インディ”と呼ばれるものの意味をさ。
最初はUKだった。ラフトレードやファクトリー、チェリー・レッドといったレーベル……ジョイ・ディヴィジョン、エコー&ザ・バニーメン、ザ・スミス、それからマイ・ブラッディ・ヴァレンタイン……。
インディは、ビートルズよりもヴェルヴェット・アンダーグラウンドを支持したが、マイナー・バンドのTシャツを着ているだけの物好きな連中ではなかった。バンドは自分たちの悲観的な内面を露わにした。自分たちの経済的な貧困さも隠さなかった。ヴィヴィアン・ウェストウッドの洋服をありがたがらずに、フリーマーケットに行けば500円で売っているような服を着たってこと。自分のサイズよりも微妙に違った服。大きめのコート、ごてごてのブーツ、安っぽいチェックのシャツ。ぼさぼさの髪。基本、アンチ・エレガントかつユニセックスだった。彼らは世間並みの夢を裏切り、貧しい者が夢見る夢を見た。
その流れを汲んでいるのが、たとえばグランジやライオット・ガールだ。考えてみよう。カート・コバーンの外見はセックス・ピストルズに近かったのか、ビート/ヒッピーに近かったのか。そのどちらでもあり、そのどちらでもない。だからレイヴ・カルチャーとも正反対の文化ってわけでもなかった。あからさまなドレスダウンだった。ダボダボのセーター、ルーズフィットなズボンの男女は、90年代初頭の野外フェスにもごろごろいたしな。
彼はちゃんと気づいてる 大豆と亜麻のベジマイトのくずを そこらじゅうにまき散らしてること コンピュータを見て吐き気をもよおし スワントンの通勤の人混みを押しのけ ネクタイをはずし メトロバスの停留所の隅で寝ているホームレスの男に渡す 彼は叫ぶ 「今日は仕事に行かないぞ! どの電車が何分遅れるかチェックしながら 草むらに座ってコーラの缶でピラミッドを作るんだ」 コートニー・バーネット“Elevator Operator”
もったいぶったイントロはない。いきなり歌とギターが入る。“スウィート・ジェーン”の頃のヴェルヴェット・アンダーグラウンドのようだ。そうとう格好いい。曲も歌詞も。
声は、ときおり涙を含みながら乾いている。観察力のある言葉もクールな音もリズミックで、颯爽している。グルーヴもある。キャット・パワーの『ムーン・ピックス』を忘れよう。本当に忘れなくてもいいんだけど、この音楽はブルースも歌っているが、泣いて聴くアルバムではないのだ。ユーモアもある。声は大きくはないが、歌の存在感は大きい。躍動的で、同時に艶めかしいギター・サウンド。素晴らしいドラムとベースもある。このアルバムの隣にテレヴィジョンやオンリー・ワンズを並べてやってもいい。
いまどきこんな音楽をやるのは、いったいどんな女だろう。僕は我慢できなかった。高橋のように、インターネットで画像検索した。セックス・ピストルズのポスターが貼られた彼女のベッドルームの写真を発見した。こうして、1988年生まれのこの女性がいかにわかっているのかを確信した。言っておくが、1980年にインディ・キッズだった人間が長いあいだ冷凍保存されて、現代に解凍されたときに共感できるのは、ノスタルジーってことではない。その音楽に芯があるってことだ。
彼女の歌に描かれる若者は、陰鬱だが、おおよそ間違っていない。人生に戸惑いを覚えないほうがどうにかしている。木津毅がどうしてこの音楽にひっかからなかったのかが僕にはわからないんだよね。
「飛び降りたいのはあなたのほうでしょう 僕は自殺なんてしない ただボーッとしたいだけ ここに来るのは空想を楽しむため シムシティで遊んでるっていう想像するのが好きなんです ここから見ると みんながアリに見えて 風の音しか聞こえない」と彼は言う。 コートニー・バーネット“Elevator Operator”
インディ・キッズっていうのはね、いまでは、ときとしてシニカルな言葉なんだよと、実際にUSインディ・シーンに属していた人が僕に教えてくれた。お決まりの服装のおきまりの髪型の、ちょっとナイーヴな子たちへの皮肉も込められているんだと。けど、それを言ったらなんでもそうだからね。クラバーなんて言葉もそれなりに滑稽だろ。インディ・キッズっていうのは、ミュージシャンとお友だちであることを自慢することでも、異性関係を自慢することでも、ele-kingに数えるほどのレヴューを書くことでもない。コートニー・バーネットが歌っているように、平日ひとりで屋上に上がることだ。
ほんのわずかな期間だったとはいえ、人生でインディ・キッズだったことがある僕は、コートニー・バーネットのデビュー・アルバムをちょっと大きめのヴォリュームで聴いている。ビルの谷間の長く暗い通路を歩きながらこれを聴いたら泣いちゃうかもな。我ながら矛盾している。そもそもイヤフォンもiPodも捨てた頑固ジジイにそれはない。まあ、とにかく、屋上でひとりで過ごしたことがある人は、年齢性別問わずに、必聴。






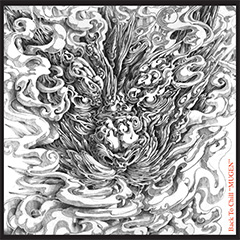

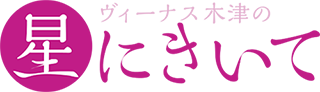



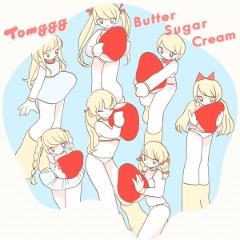
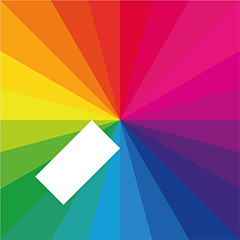 Jamie xx
Jamie xx ヤング・ファーザーズ
ヤング・ファーザーズ