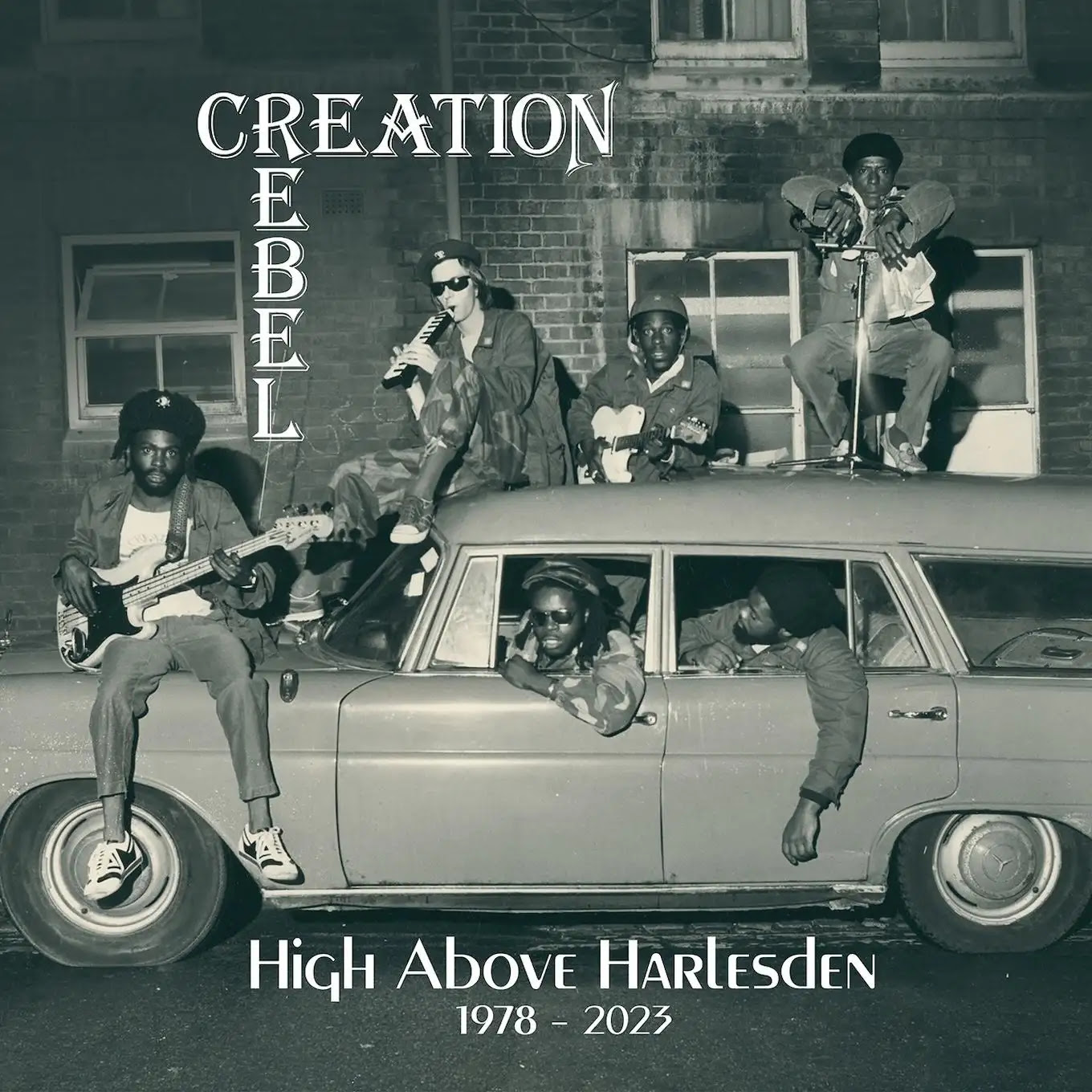「アート・ブラックメタル・テクノ・プロジェクト」、VMOことViolent Magic Orchestraが8年ぶりのアルバムを発表する。題して『DEATH RAVE』、ブラック・メタル、ハードコア、ガバ、ノイズなどがミックスされたサウンドに仕上がっているようだ(3/13リリース)。Vampilliaのメンバーはじめ、メイヘムやSunn O)))での仕事で知られるアッティラ・チハーら多くの面々が集結しており、Kentaro Hayashi、CRZKNYなども参加。新代田FEVERおよび東心斎橋CONPASSでのリリース・ライヴも決定している。詳しくは下記より。
VMOが8年ぶりのセカンドアルバム「DEATH RAVE」をベルリンのNEVER SLEEPより3月13日に発売決定。併せてリリース記念ライブの詳細も発表。
VMO a.k.a Violent Magic Orchestraが約8年ぶり、ザスターがボーカルを務める新体制後、初となるアルバム「DEATH RAVE」をベルリンのGabber Eleganza率いるレイヴ、ハードコアシーンの総本山 NEVER SLEEPよりリリースする。今作は世界中のメタル、テクノ、アートなどあらゆるジャンルのフェスに出演したVMOの経験とスタジオでの実験が爆発的な化学反応をおこしDEATH RAVEと呼ぶに相応しい作品が完成した。anoのちゅ、多様性を作詞/作曲したエンペラーaka真部脩一らVampilliaメンバーはもちろん、紅一点のボーカルザスター、ブラックメタルの伝説メイヘムのAttila Csihar、現代エクストリームハードコアの雄FULL OF HELLよりDylan Walker、アイスランドの新しい神秘Kælan Mikla、レーベルのボスGabber Eleganza、ビョークの最新作に参加したインドネシアのガムランガバユニットGabber Modus OperandiのIcan Harem、テクノの聖地TRESORからリリースするminimal violenceのinfinity devisionら海外勢に加え、アルセストことKentaro Hayashi、リヴァイアサンことCRZKNY、そしてMASF/ENDONのTaro Aikoら国内勢も参加したブラックメタル、テクノ、ハードコア、GABBER、ノイズがDEATH RAVEの名の下にネクストレベルで完成した。
そして、このアルバムを引っ提げて行われる5月末から7月頭までスペインのSONAR、北欧最大の野外フェスROSKILDEなど巨大フェスを含むリリースワールドツアーの前に、作品の世界を再現するDEATH RAVEを東京と大阪で開催。このリリースライブにはインドネシアより今作にも参加するGMOのIcan Haremも来日。ブラックメタルの暴力性とRAVEの快楽主義が奇跡的に融合する VMOのアルバムとライブを是非お楽しみください。

VMO presents
『DEATH RAVE リリース♾️メモリアル DEATH RAVE』
東京編
@新代田FEVER
2024/03/19 (火)
18:30open 19:00start
3500yen
4000yen
チケットURL
https://eplus.jp/vmo/
【ACT】
VMO
【special guest 】
Ican Harem from Gabber Modus Operandi
Jun Inagawa
大阪編
@東心斎橋CONPASS
2024/03/22 (金)
18:30open 19:00start
3500yen
4000yen
チケットURL
https://eplus.jp/sf/detail/4045710001-P0030001
【ACT】
VMO
【special guest 】
Ican Harem from Gabber Modus Operandi
KNOSIS(DJ set)

VMO a.k.a Violent Magic Orchestra「DEATH RAVE」
2024.03.13 Release | NSR014/VBR-VMO202403 |
Released by NEVERSLEEP (Japanese distribution by Virgin Babylon Records)
各種サブスクリクション同時配信
https://sq.lnk.to/NSR014_
アナログLP版発売日未定
Track List
1. PLANET HELVETECH
2. WARP
3. The Destroyer electric utilities version
4. Choking Persuasion
5. Kokka
6. Welcome to DEATH RAVE feat. Ican Harem - Gabber Modus Operandi
7. Satanic Violence Device feat. Dylan Walker - Full of Hell
8. MARTELLO MOSH PIT feat. Gabber Eleganza
9. VENOM
10. Abyss feat. Kælan Mikla
11. Ecsedi Báthory Erzsébet
12. SUPERGAZE
13. FYRE feat. Infinity Division
14. Song for the moon feat. Attila Csihar - MAYHEM
15. Flapping Dragon Wings