ヴォーカル、エレナ・トンラの話し声は、録音を再生してもういちどはっとするくらい美しかった。それは発言内容以上の雄弁であり、拾い物でさえあった。彼女たち自身が繰り返すように、テクスチャーがまず重要だという彼らの音楽にとって、まずなによりのテクスチャーはエレナの声かもしれない。暗く深い油彩の質感の中に、のびやかに溶け込み色をやわらげる白い絵具──。
 Daughter - Daughter |
コクトー・ツインズやバウハウスの上にくっきりと打ち立てられたレーベル・カラーを崩さないまま、21世紀に入ってますます鮮やかにそのキャラクターを深めている〈4AD〉。ディアハンターにアリエル・ピンクにセント・ヴィンセント、グライムス、それだけ眺めても、インディ・ロックを代表する面々が集められているというばかりでなく、はっきりとヴィジョンをもってリリースがなされているということがわかる。ドーターはとくに〈4AD〉のオリジンというか、コクトー・ツインズやディス・モータル・コイルの幽玄や耽美を直系とするようなユニットで、デビュー・アルバムも同レーベルから。2010年代の黎明、ジャングリーにトゥイー、ギター・ポップや新しく台頭したローファイ・アクトなど溌剌と明るい音が優勢なインディ・ロック・シーンの中に、ウォーペイントらとともに沈み込むような憂愁を刷いた。
音楽オタク的なところはまったくないが、彼らには、彼らのなすべきことがはっきり見えているようだ。セカンドとなる今作『ノット・トゥ・ディサピアー』は、前作より大きく変化することもなく前作よりもはっきりとドーターの音の輪郭を濃くしている。そしてエレナのヴォーカルも相俟って、「ドーターっぽい」という形容を他のバンドにも用いることを可能にするだろう。
〈ホステス・クラブ・ウィークエンダー〉に出演するため来日していたドーターを訪ねた。
ドーター / Daughter
2010年にヴォーカルのエレナ・トンラを中心にロンドンで結成された3ピース・バンド。現在までに2枚の自主EPを発表。2012年、新人アーティスト発掘音楽フェスSXSWでのライヴが話題となり、英名門レーベル〈4AD〉と契約。翌年3月にデビュー・アルバム『イフ・ユー・リーヴ』をリリース。7月にはフジロックフェスティバル出演、つづけてその翌2月には〈ホステス・クラブ・ウィークエンダー〉で来日を果たした。そして2016年1月、セカンド・アルバム『ノット・トゥ・ディサピアー』を発表する。
メロディがサウンドの中に隠れているような──それこそリヴァーブの感じも大好きなんだ。あとはディスト―ションからリズムを感じたりとかも。(イゴール・ヒーフェリ)
■以前にインタヴューさせていただいたときには、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインをお聴きになったことがないとおっしゃっていました。その後お聴きになることはありましたか?
イゴール・ヒーフェリ(以下イゴール):衝撃的だったよ。フェスで観る機会もあったんだけど、本当に素晴らしかった。
レミ・アギレラ(以下レミ):ラウドだったね。
■みなさんは、メディアなどでそうした音とよく比較されることがあると思うのですが、あらためて、なぜ自分たちが彼らと比較されるのかお考えになった部分はありますか?
イゴール:そうだな、影響されていると指摘されることは多いけど、比較という感じではないかな。自分の中ではそれほど影響を受けたり似ていたりするとは思わないんだ。ぜんぜんちがう音だよ。
■では、人々はどんなところを指して影響されていると言うのだと思います?
エレナ・トンラ(以下エレナ):質感じゃないかって思います。リヴァーブだったりヴォーカルの質感、エフェクターの効果……そういうところかなって。マイ・ブラッディ・ヴァレンタインは偉大なバンドだから、比較されるのは素直にうれしいですね。
イゴール:僕も、彼らにかぎらずシューゲイジーな音っていうのはもともと好きで、メロディがサウンドの中に隠れているような──それこそリヴァーブの感じも大好きなんだ。あとはディスト―ションからリズムを感じたりとか。そういうところはあるんじゃないかと思う。
ドリーム・ポップとか「なんとかポップ」とか、みんな、わたしたちのことをとってもいろんな言葉を使って当てはめてくれていて、そのことをエンジョイしてるんです。(エレナ・トンラ)
■みなさん若きギター・バンドでありながら、前作当時流行だったジャングリーなギター・ポップだったり、あるいは甘くて軽快な2ミニット・ポップだったりという方向にはまったく振れないですね。ポップ・シーンにあってけっして明るくならない、沈むような調子を保っているところがみなさんのかっこいいところでもあります。このあたりはどう考えていらっしゃいますか?
イゴール:僕は、自分たちがポップのシーンにいるとも思っていないし、ポップな曲を書こうと思っているわけでもないんだ。ただ好きなものをつくっているだけだから、努力してそうした状態を保っているという感じでもないしね。好きなことがやれて、それをみんなが受け入れてくれて、こうやって日本に来れたりしていることをとってもラッキーなことだと思っているよ。
エレナ:ドリーム・ポップとか「なんとかポップ」とか、みんな、わたしたちのことをとってもいろんな言葉を使って当てはめてくれていて、そのことをエンジョイしてるんです。それって、自分たちにどこにも属せない・属さない自由さがあるっていうことかなと思っていて。自分たちの好きなことをやりながら、そんな状態になっていることをうれしいと思っていますね。
■一方で、今作には“ノー・ケア”という曲がありますが、あれなんかはバンドというフォームを超えて、表現の枠がどんどん広がっているような印象を受けます。
エレナ:ええ、たしかに他の曲ととてもちがいますよね。
■そうですね、しかもバンドでできることを超えて発想されているというか。
レミ:自分たちの音楽のつくり方が自然にそうなっているということだと思うんだ。3人いることで可能性が広がっているから。たとえばエレナがギターとメロディ、それから歌詞をつくったりしている一方で、イゴールがいて僕がいていろんな組み合わせが生まれてくる。それは音楽の上でもパーソナリティの上でもそうなんだ。そこにエレクトロニックなものが組み合わさればまた広がっていく……自分たちにできることを最大限に生かして音をつくろうと思っているよ。それは僕たちにとってきわめて自然なことだね。
エレナがいてイゴールがいて僕がいて、いろんな組み合わせが生まれてくる。それは音楽の上でもパーソナリティの上でもそうなんだ。(レミ・アギレラ)
■では思考実験として、あなたがたはギターも何も持たなくても、PC一台で音楽がつくれるという可能性もありますよね。でもそうしないでバンドというかたちを選択されているのはなぜなのか教えていただけますか?
イゴール:僕はギターだけど、ギターというのはそれこそ10代のころから慣れ親しんだ楽器で、演奏していて楽しいんだ。それに、エフェクトを使うことでさらに可能性も広がっていくし、テクスチャーをコントロールできる。シンセを使ったりソフトウェアを使ったりすることもできるんだけど、自分なりのサウンドをつくることができるのはギターかな。
■その意味では〈4AD〉というレーベルはすごくあなたがたに合っていますね。ギターとその音のテクスチャーということについては歴史のあるレーベルだと思います。レーベルに対する思いを教えていただけますか?
エレナ:ギターのテクスチャーにかぎらず、いまの〈4AD〉は本当にさまざまなタイプの音が集まっていて素晴らしいレーベルです。でも昔の〈4AD〉ということで言えば、コクトー・ツインズなんかには自分たちに通じるものがあると言ってもらうこともあるし、自分たちでも影響を感じていますね。エレクトロニックなものにしろ、ギター・バンドにしろ──グライムスとかディアハンターとか──テクスチャーというものを重視しているレーベルだと思います。
〈4AD〉のサウンドを聴くと、思考というか思想というものを感じる。(イゴール)
イゴール:〈4AD〉は、ほんとによくサポートしてくれるレーベルで、プレッシャーというものがないんだ。繰り返すように、僕たちはテクスチャーやサウンドというものを重視しているけど、それについてもすべてのバンドが自分たちのスタイルというものを持っているから、〈4AD〉のサウンドを聴くと、思考というか思想というものを感じる。自分たちの主張ともいうべきものを自由に言える、表現できるということがこのレーベルの素晴らしいところだと思うよ。
■ところで、イゴールとエレナは作曲を学校で学ばれているんでしたっけ?
イゴール:学校に行ったのはすごく大きなステップだったよ。僕はティーンエイジャーの頃からスイスでギターを弾いてきたんだけど、ロンドンに来てからは1年間、学校でソング・ライティングを学んだんだ。そこで作曲を学んだことがいまの自分たちのやりかたにそのまま通じるものかといえばそうではないんだけど、自分たちの使えるツールのひとつになっていることは間違いないよ。パーソナルなスタイルを作り上げるのは自分でやらなきゃいけないことで、それへのアプローチという意味では、必ずしも学校で習ったことばかりとはいえないかな。
■なるほど。アルバムごとにいろんなテーマに取り組まれると思うんですが、一般にセカンド・アルバムはなかなか苦労や悩みの多いものだと言われます。あなたがたにとっては今回その意味でのプレッシャーや難しさはありましたか?
エレナ:その意識はあったんです。でも過剰な期待なんかはシャット・アウトして、そうしたプレッシャーを感じないようにしようと思いました。そして、すべての音の可能性に対してオープン・マインドであろう、って。それは自分たちの今回の目標でもあって、ヴォーカルにしろシンセにしろ、あらゆるアレンジを試して、いろんなことに挑戦したんです。3人の中でどんなふうに可能性に挑戦していくかということも大事な問題でしたし、「ドーター」っていうバンドの音を決めてしまっていたら、ここまでたどり着くことはできなかったと思います。
今回はスペースを借りたんです。だから何かアイディアを思いついたらすぐそこで試してみることができたし、みんなでそこに集まることもできた。(エレナ)
■いろんなチャレンジがあるということですが、みんなでスタジオに入って考えるんですか?
イゴール:みんなで集まることもあれば、それぞれがアイディアを持ちよることもあるかな。
エレナ:今回はスペースを借りたんです。そこに楽器なんかを置いてもいるんだけど、ファーストのときはそういうことができなくてリヴィング・ルームを使っていたりしたから制限がありました。今回は、何かアイディアを思いついたらすぐそこで試してみることができたし、みんなでそこに集まることもできたから、3人のコラボレーションという感じのつくり方ができたんじゃないかなと思います。
■なるほど。ではこのアルバムをつくっていた頃のことを思い浮かべていちばんに出てくる景色や様子を教えてもらえますか?
イゴール:すごく緊張感のあるプロセスだったんだ。1年かかって書きためたものを、2ヵ月半の間、同じ場所に籠って集中して仕上げたので(笑)。だから、詰め込みすぎたってことなのかな、2ヵ月半という時間が長い一日のようだったよ。
エレナ:山を登っていたようなイメージ。ひとりが転げ落ちそうになったら、誰かが「大丈夫? がんばろう」って言いながら支えて登る、という感じ(笑)。
■ははは!
今回はかなり準備ができていたんだ。だから、なにかクラシックのコンサートみたいな感じかな。自分でたくさんのリハーサルをやっておいて、本番──レコーディングを迎えるっていう。(レミ)
エレナ:お互いにテストしあったりとか、簡単なことはぜんぜんなかったと思います。でもがんばって頂上に上ると、とっても美しい景色が待っていて。そこまでに行くのはとっても大変なんですけど……。
レミ:2ヵ月半のレコーディングに入る前に、今回はかなり準備ができていたんだ。少なくとも自分にとってはそうだったから、なにか、クラシックのコンサートみたいな感じかな。自分でたくさんのリハーサルをやっておいて、本番──レコーディングを迎えるっていう。ファーストのときは、曲がコンピュータに保存されたまま、それをどう演奏するかわからないままにスタジオに入ったりしていたけど今回はその意味で準備ができていたんだ。
■では、サウンドの奥に自分が思い描いていた景色についてお訊ねしたいです。
なんだろう、ピンクと紫とブルーの、LAの空のイメージなんですけど……。(エレナ)
エレナ:“ニュー・ウェイズ”がいちばん最初に書いた作品なんですね。それで、この曲についてはロサンゼルスの夜をドライヴしているようなイメージがありました(笑)。
■へえ! それはなぜです?
エレナ:なんだろう、ピンクと紫とブルーの、LAの空のイメージなんですけど……。サンセット。エレクトロニックなサウンドとオーガニックなサウンドが混じっていて、それの延長線上にあるイメージというか。
イゴール: LAはすごく暑くて、コンクリートの熱もあれば、僕らがそこにあるスタジオに行ったときが夏だったこともあって、本当に気温が高かったんだ。プロデューサーのニコラスはそこに住んでいたんだけど、屋根に上るとハドソン川から素晴らしい景色が見えたりして、そのコントラストが印象深くて……。LAという街自体がそう。海がありながら街もある、そういうものが混じったイメージかな。ファースト・アルバムはもっとランドスケープから影響を受けた、自然に近い音だったんだ。セカンドはもうちょっと都会的なものが入ってきて、それがエレクトロニックなものと結びついていると思うんだけど、やっぱりツアーで大きな街を回った要素があるかもしれない。東京とかロンドンとかニューヨークとかね。
■なるほど、旅を音で記したようなところもあるわけですね。でも井戸水のように温度の変わらないところ、ドーターの美しいところを大事になさってください。
エレナ:ふふふ。ヒップホップにはならないと思います。
イゴール:そうだね(笑)。




















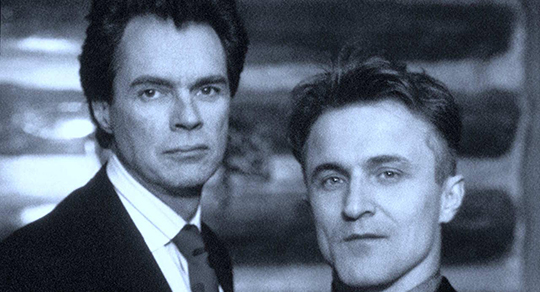



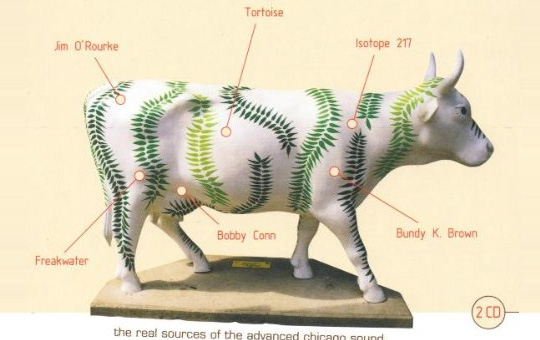

 Jesse Ruins
Jesse Ruins