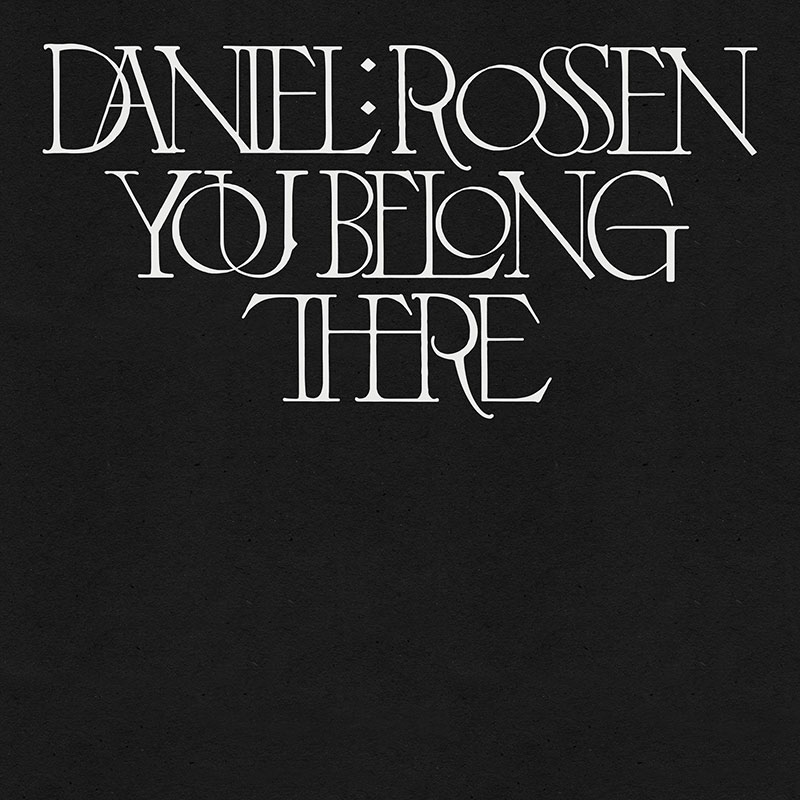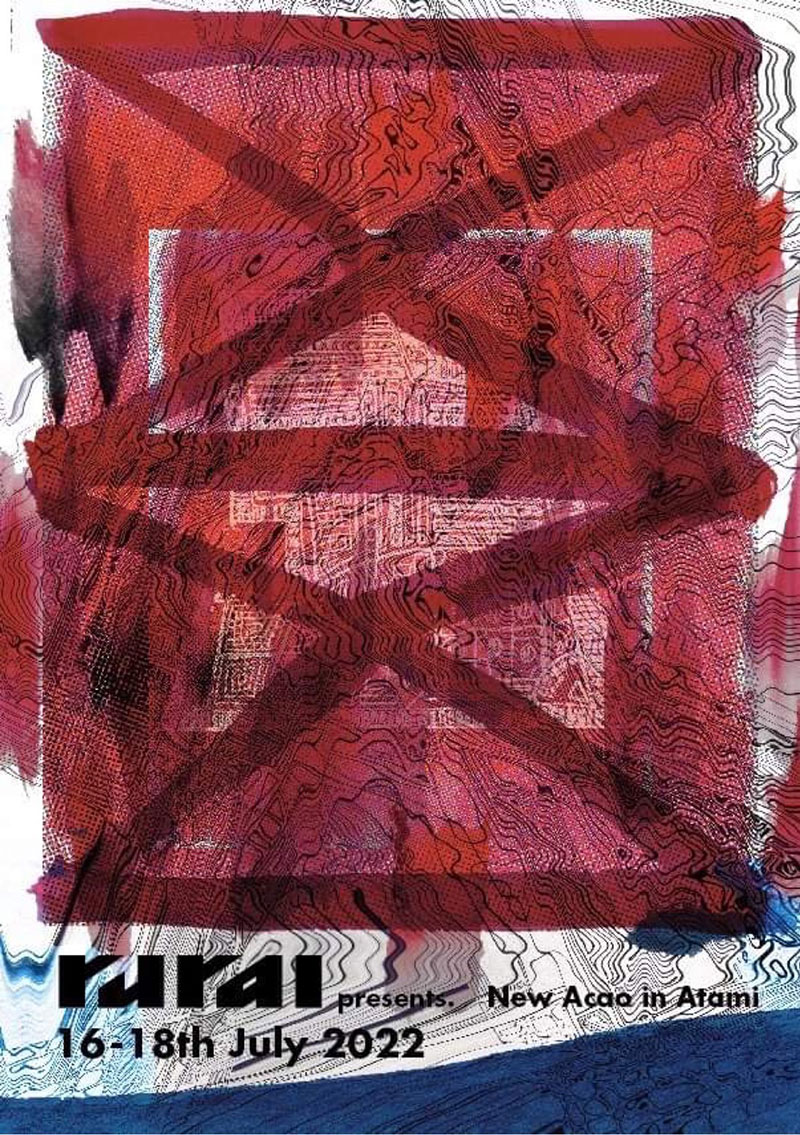本格的ドラムメディア、パワーアップして待望の第2号!
ドラマー&パーカッショニストをわくわくさせ、やる気にさせる新時代の本格派プレイヤー向け雑誌として大きな反響を呼んだ「Drum-On」の第2弾!
今回もあらゆる打楽器奏者が本当に欲しい情報満載でお届けします。
編著 小宮勝昭
ザ・ビートルズ、レッド・ツェッペリンを聴いて音楽に目覚めドラムを始める。大学卒業後つのだ☆ひろ氏に師事、独自のグルーヴ理論を学ぶ。元リズム&ドラム・マガジン編集長(2001年1月~2012年3月)という異色の経歴を持つドラマー/パーカッショニスト。ドラム・セットだけじゃなく、ジェンベなどの民族打楽器も駆使し、即興ジャズ~ロック~歌ものなど、さまざまなフィールドで活動中。並行して編集・執筆活動も行っている。
特集 ●ドラムの音色(ねいろ)
芳垣安洋、外山明、岡部洋一、アッシュ・ソーンという当代きっての名プレイヤーたちの絶品なる音色、その核心に迫るインタビュー&愛用楽器たちの実際の使用例写真満載の超大特集!!!
特別寄稿:三浦晃嗣「音のあとさき~僕の体験的音色考~」
“1つ打ち” のすべて
ドラミングの「はじまり」にして「究極」
「速く動かす」、「超スロー・テンポでも正確に叩く」など、すべての出発点である “1つ打ち” を徹底深掘り!
(染川良成[Drum Gym])
“音色” にこだわるドラマーへ
Ludwig Speed King Pedal
歴代の名器~最新 L203 の魅了を探る!
(藤掛正隆)
Nippon のドラムの匠:伊藤直樹/riddim
「ドラムと働く人」
植木寛郎さん(Drums Proshop GATEWAY)、上原貴生さん(MIKI DRUM CENTER)
【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】
◆amazon
◆TSUTAYAオンライン
◆Rakuten ブックス
◆7net(セブンネットショッピング)
◆ヨドバシ・ドット・コム
◆Yahoo!ショッピング
◆HMV
◆TOWER RECORDS
◆disk union
◆紀伊國屋書店
◆honto
◆e-hon
◆Honya Club
◆mibon本の通販(未来屋書店)
◆三木楽器ドラムセンター
◆イケベ楽器
【P-VINE OFFICIAL SHOP】
◆SPECIAL DELIVERY
【全国実店舗の在庫状況】
◆紀伊國屋書店
◆三省堂書店
◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア
◆旭屋書店
◆有隣堂
◆TSUTAYA
◆未来屋書店/アシーネ