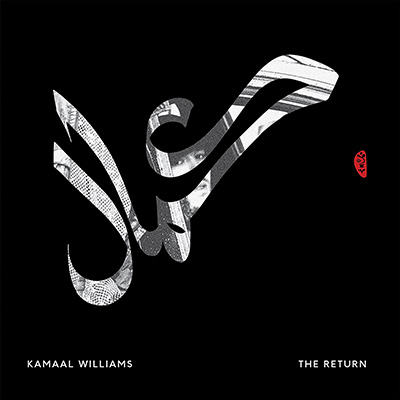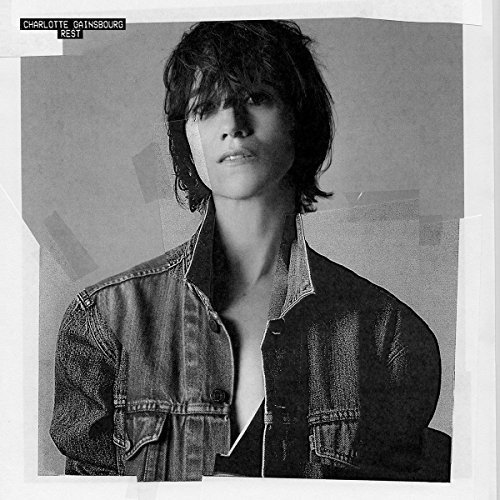静かに尖っています……4月にリリースされたフル・アルバム『Fracture』がじわじわと話題のヤン&ナオミ。その収録曲“Forest”のMVが公開されているで、それをチェックしつつ、6月からのツアーの詳細も発表されているので、ライヴにも足を運んで欲しい。彼らへのインタヴューは近々ele-kingでも掲載されます!
“Forest” music video
ウェブサイト:https://janandnaomi.localinfo.jp/
ライブ情報: https://janandnaomi.tumblr.com/

■Fracture tour 2018
全公演チケット:前売り¥2,500 (税込・1Drink別・整理番号有り)
チケット発売 5/26(土)11時~
------------------------------
■6/23(土) 札幌 PROVO
OPEN 19:00 / START 20:00 <チケット取り扱い>
PROVO電話予約:011-211-4821
メール予約:osso@provo.jp ※お名前・人数・連絡先をメールにてお送りください。
【問】PROVO 011-211-4821
■7/14(土) 福岡 UNION SODA
OPEN 18:00 / START 19:00 <チケット取り扱い>
チケットぴあ P-コード: 118-465
Live Pocket : https://t.livepocket.jp/e/4dw_4
メール予約 : info@herbay.co.jp
※お名前・人数・連絡先をメールにてお送りください。
【問】HERBAY 092-406-8466 / info@herbay.co.jp
■7/16(祝月) 京都 UrBANGUILD
OPEN 18:00 / START 19:00
guest : SOFT <チケット取り扱い>
UrBANGUILD HP予約:
https://www.urbanguild.net/ur_schedule/event/180716_fracturetour2018
【問】UrBANGUILD 075-212-1125