コロナ禍におけるUKではハウス・ミュージックがかかる違法レイヴ──いまどきの別称でいえば“隔離(quarantine)レイヴ”が頻発していることはもはやよく知られたところで、当局が30人以上のレイヴを見つけた場合は主催者に1万ポンド、参加者にも100ポンドの罰金、二回目以降は3200ポンドの罰金を科すなど政府も取り締まりに躍起になっている。まさにアナーキー・イン・ザ・UKというか、なんでも7月末には3000人規模のレイヴがあり、8月のある週末にはわかっているだけでも200件を越えるイベントがあったそうで、8月22日の電子版『ガーディアン』によれば6月以降すでに1000件の違法レイヴが発覚しているそうだ。30年ぶりのレイヴ爆発である。
それにしても……1992年~93年のクリミナル・ジャスティスのときとは違った意味で警官(ただしフェイスガードしている)に囲まれているレイヴァーたちの写真を見ていると、イギリスって本当にレイヴが好きなんだなぁと呆れるというか感心する。いまだ有効なワクチンがなく、おそらくは公衆衛生的にも欠陥だらけで、致命的な病気にかかるリスクがあるなかでの集団的な「ダンス」なので奨励するわけにはいかないけれど、しかしまあ、本当に好きなんだなぁと。そうでもしてなければやってられないと、そういうことでもあるのだろうけれど、日本でこれはまずないでしょ。
決して小さくないリスクを冒してまでいま森のなかや飛行場で踊っているのは、もちろん90年代に当事者だった中年たちではない。主役はその子どもたちの世代であって、まさか親から教え込まれたわけじゃあるまいし。文化として根付いてしまっているんだろう。
だとしても、やはりどうしてもいま集まって踊ることは昔のようなオプティミズムやロマンスとは別の意味を孕んでしまう。これはもう仕方がないことだ。そして、よりによってこんな時代──UKではクラブはいまも閉店中──に堂々と『エナジー』などという直球なタイトルのダンス・アルバムをぶちかますディスクロージャーとはナンなのかと(笑)。
いや、笑いごとではない。話はより複雑で、コロナ時代に敢えてダンスのディスクロージャーは格好いいという単純なオチでもなかったりする。コロナ前のUKにはクラブ/ハウスをめぐってのハードな議論があり、それはいまもあるので、手短に紹介したい。
まずひとつには、昨年DJ Magが掲載した秀逸な記事──いまのUKダンス・カルチャーは白人的であり中産階級的(高価な遊び)であるという問題提起に集約される。これは、クラブ・カルチャーという漠然としながらも響きの良い言葉が「ナイト・エコノミー」という新自由主義用語にすり替えられてから起きている、大きな問題だ。日本でも「ナイト・エコノミー」が言われてから、何が失われたのかを探ってみて欲しい。企業が企画するドラムンベースのイベントなんて90年代の感覚でいえば警察がギャングスタ・ラップをやるのと同じくらい考えられない話だが、しかしそれが現代なのだ。
もうひとつは、The Quetusが取り上げて批判している、ハウスキーピング問題もある。ロンドンのハウス好きな4人のDJによるハウスキーピングなるグループの何が問題かといえば、彼らの職業にある。経済的に決して裕福ではないアンダーグラウンドで生まれたこの音楽を、よりによって都市の再開発に関わる事業家や金融業者が「平等」や「隣人愛」を謳い、いかにもなトランシー・テック・ハウスをやるとはなんたることかという、ある意味ではなかなか指摘しづらいことでもある。これはよくよくディプロに叩きつけられている文化の搾取というレヴェルの話とはまた別だ。
まあつまり、このところUKではそもそもハウス・ミュージックおよびダンス・カルチャーとは何なのかという本質的なことが問い直されていると、ざっくりこんな事情があるなかで、ディスクロージャーがたとえばコロナで亡くなったデトロイトのDJ/プロデューサー、マイク・ハッカビーへのリスペクトを表明したことは、小さなことだが大きなことでもある。ハウス・ミュージックのように、ロックと違って言葉を持たない/中心を持たない音楽の文化的死(清志郎のレヴューを参照されたし)を免れるには、作品それ自体の強度のほか、ひとつは作り手やメディアが言い続けることであり、より多くのリスナーがその出自を知ることであり、音楽やリスナーがストーンウォールやロン・ハーディを忘れないことである。
ディスクロージャーは上記の議論において、ぼくが散見する限りでは、つねに賛否両論を受ける立場にいるのだけれど、だからこそ本作は注目に値するとも言える。思慮深い彼らが、では彼らのハウスをこの時代いかにディヴェロップするのかという話だ。しかもよりによって自由にダンスできない、レイヴは拡大しているが危険だし、あるいはナイト・エコノミー……いや、クラブ・カルチャーも停滞している現在にドロップされたダンス・アルバム『エナジー』、ここには彼らなりの回答がある。そのひとつはUKグライムとの共振だ。
昨年の『Nothing Great About Britain』でいっきに評価を高めたスロウタイをフィーチャーした“My High”なる曲において、活きの良いこのグライム・ラッパーは「たのむから俺のハイを邪魔すんな(please don’t fuck up my high)」と繰り返している。そのみなぎるエナジーとファンキーなリズムを前にリスナーは圧倒されるかもしれない。コロナなんて知ったこっちゃないと言わんばかりだが、しかしアルバムではこの曲の前の前の1曲目には──シカゴ・スタイルをベースが大きいUK風にアレンジしたハウスで──ケリスをフィーチャーした“Watch Your Step(気をつけて)”がある。「私は群衆を望まない/暗くなっても私はひとりで部屋にいるように踊る」とケリスは歌っているが、これはいかようにも解釈できる歌詞で、じつはアルバムは初っぱなからリスナーをアンビヴァレンツな気持ちにさせてもいるのだ。
ディスクロージャーは今年の頭に「エクスタシー」という、これまた直球すぎるタイトルの5曲入りのシングルを出している(※ちなみに本人たちの弁によれば彼らはドラッグ・ユーザーではない)。おそらくはこの夏に備えていたのだろう。コロナさえなければ彼らは2020年の夏の野外の王者になっていたかもしれない。だが事態は急変し、『エナジー』は場違いな作品になりかねなかったところだった。それが彼らの捻りと周到さによって、むしろこの夏に相応しいダンス・アルバムになっていたりもするのだ。
彼らの周到さは、『エナジー』の広がりに見受けられる。アルバムには、スロウタイやケリスのほかに、シドやコモンといった有名どころから、カメルーン出身のシンガーBlick Bassy、シカゴのラッパーMick Jenkins、マリのシンガーFatoumata Diawaraなど多彩なゲストが参加している。こうした華やかなフィーチャリングはメジャーではよくあることだが、9人のゲストの全員が非白人であり、何人かは英語以外の言語で歌っている。これもまた、ひとつのメッセージになりうるだろう。そして彼ら・彼女らは作中で浮いたりすることなく、色とりどりの趣向を配した本作の一部として機能している。
それは歯の浮いた人類愛ではない。ハウスを通して見せることができる多様性の具現化だ。もうひとつの『エナジー』の特徴は、──これは今作に限った話ではないのだが──、UK音楽がもっとも得意とするセンスの良いモダンな雑食性にある。ストリート感あり、R&Bあり、ラップあり、アフロ・テイストありと、いろんなものが詰められているがスジが通っていて、よく練られているのだ。思いきりサンバのリズムを使った表題曲“Energy”を拒否するか受け入れるかはリスナーの精神状態にかかっているかもしれないが、コロナ禍だからといって音楽まで自粛する必要はどこにもない。
2020年の夏に相応しいとはそういうことだ。『エナジー』は夏のダンスであり、UKハウスの魅力が詰まったアルバムで、と同時に、以前のようにクラブで騒げないからといって、いまダンス・ミュージックを作ることが決して無意味ではないということの問いかけにもなっている。ポップと、そしてアンダーグラウンドを行き来できることがダフト・パンクやベースメント・ジャックスの時代よりも重要になっている現在において、ディスクロージャーの『エナジー』をぼくは部屋のなかで楽しんでいる。TVからは国民不在の政治ニュースが流れているが、「たのむから俺のハイを邪魔すんな」である。

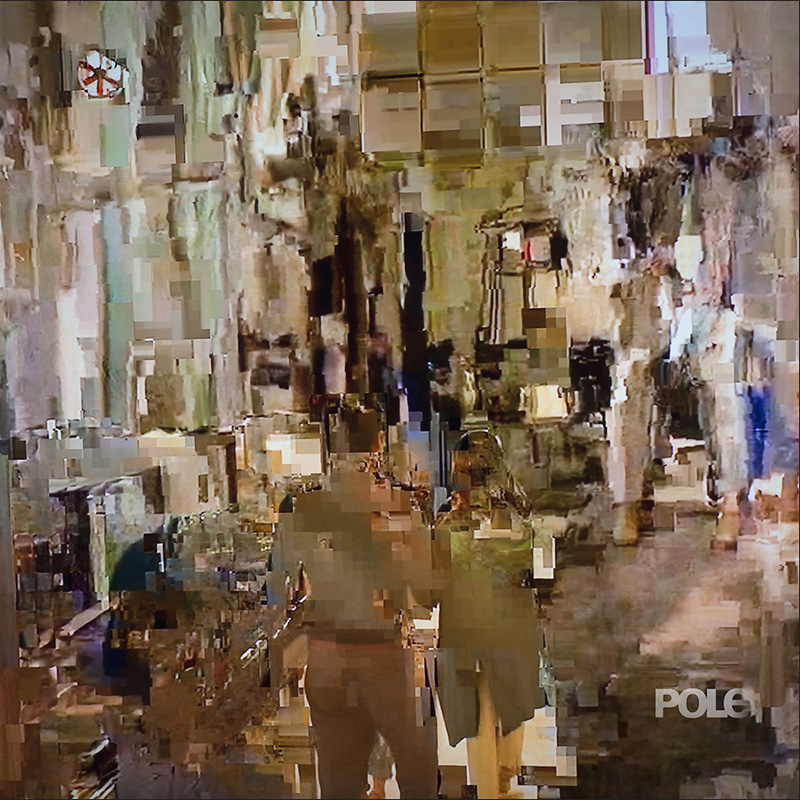 Pole
Pole






