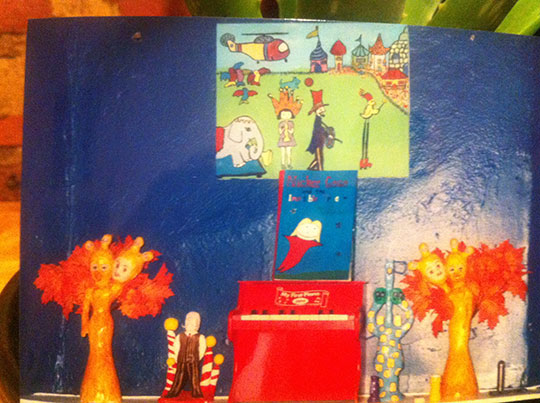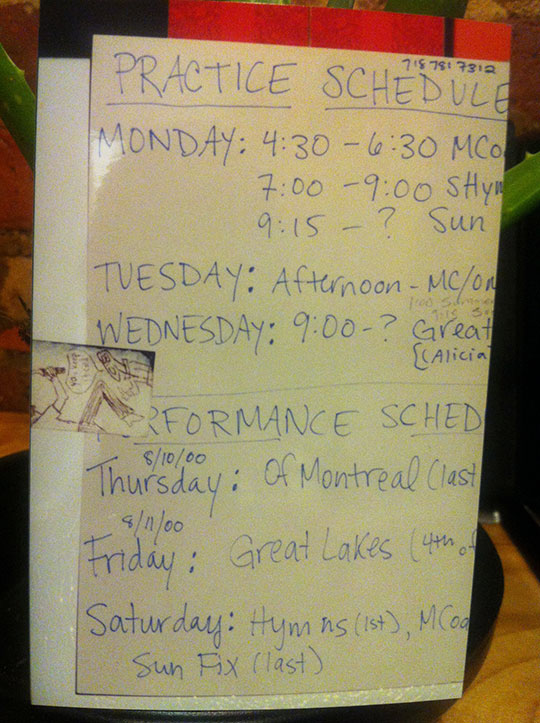新しい希望の歌文:桑田晋吾
 七尾旅人
七尾旅人リトルメロディ Felicity |
このアルバムの音源が届いてから、毎日聴いた。十数回ほど通して聴いたあとに、思った。ここでもまた、この稀有な歌い手は、音楽によるファンタジーを呼び起こしている。いままでで、もっとも親しみやすいやりかたで。そして少し、複雑な方法をとって。
はじめに聴こえるのは、砂嵐のようなノイズだ。ガイガー・カウンターを想起させる不穏な信号音。男が咳きこむ音。およそ20秒の混濁の後、輝く雨垂れのように美しいアコースティック・ギターが、そっと響きはじめる。そうして「圏内」に足を踏み入れた瞬間、この新しい音の旅は、はじまる。いま"きみのそばへ"行くために、乱れた現実のなかを、くぐりぬけていく――『リトルメロディ』は、そんな風にはじまる。
少なくない反響を呼び起こした"圏内の歌"。この曲のなかでは、雨が降っている。目に見えない物質が含まれた水で濡れた世界を、ガット・ギターとピアノが小さく乱反射しながら描き出す。歌声は、ささやくような「小さな」声だ。雨樋のある屋根。どろんこで遊ぶ子ども。水辺にうつる月。おばあちゃんの話。そのような風景の記憶を持つ人に、この曲は語りかける。「離れられない 小さな町」。それは、例えば「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏内」の小さな町であると同時に、聴く人の心のなかにある、故郷のような、その人にとって大切なものがある「町」のことかもしれない。その「町」が不条理な力で汚されたとき、人は簡単にその特別な場所を、離れることができるだろうか。どこまでも優しくて綺麗なこの音の奥にあるのは、引き裂かれるような痛みの感覚だ。
この曲をアルバムのはじめに持ってくることは、大きな決断だったはずだ。曲の美しさとは別の場所で「メッセージ性」が発生して、それによってはじかれてしまう人もいるかもしれないから。でも、この『リトルメロディ』と題された作品は、この曲を必要とした。あの日以来の現実に基づいた歌を響かせて――ある種の「重し」を聴き手の心にくくりつけてから――七尾旅人は、聴き手を飛翔させようとする。彼がずっと信じ続けてきた、「歌」という翼で。そして"my plant"で「圏内」をもういちどくぐりぬけ、歌は、湘南などの圏外の世界へ向かっていく。
『リトルメロディ』は、七尾旅人の作品のなかで、もっとも抑制されたアルバムだと思う。サイケデリアも、奇抜さも、この世界では鳴りを潜めている。そしてそれが、これまでの七尾旅人の作品とは違った種類の、曲と聴き手の親和性の高さを生みだしている。"湘南が遠くなっていく"(森俊之編曲)"サーカスナイト"(Dorian共編曲)"七夕の人""Memory Lane""リトルメロディ"。耳に残るメロディがいくつも散りばめてある。普通のJポップ・歌謡曲として流れても違和感のない曲が並んでいる。爪弾かれるアコースティック・ギター、太田朱美が奏でる風のようなフルートが、夏をメランコリックに広げる"Everything is gone"。そして"Rollin' Rollin'"に続くヒット・ソングとなるだろう、甘く苦い"サーカスナイト"。まるでサザンオールスターズのような夏の物語"湘南が遠くなってゆく"。切ない感覚を残すメロウな3曲が続き、アルバムのハイライトを作る。"七夕の人"から"Chance☆"までの煌めきが、後半をファンタジックに染めあげる。そして、コスガツヨシを迎えてエモーショナルに響く"Memory Lane"。そこで聴こえる真っ直ぐで伸びやかな歌声も、七尾旅人の新しいステージを感じさせる。
「おまじない」("アブラカダブラ")をかけること、かけようとすること。「おまじない」にかかること、かかろうとすること。それはいま、とても難しいことだろう。おそらくこの国の(戦後の)ファンタジーにおいて最大級の影響力を及ぼしてきたと言えるであろう宮崎駿も、東日本大震災の後、「いまはファンタジーを作るべきではない」と言った。
震災によって非日常的な状態が日常に入り込んでしまった新しい現実の後、なお音楽による「ファンタジー」を呼び覚ますとはどういうことなのか。この『リトルメロディ』には、七尾旅人のひとつの答えが示されている。いま、ファンタジーという言葉を使うこと自体がとても難しい。書きながらそう思っているけれど、僕がここで考えているのは、このような意味でのファンタジーの力のことだ。
「ダンスを踊ったり、音楽を聴いたりするときと同じように、物語を頭だけでなく、心と体と魂で読むならば、その物語はあなたの物語になる。そしてそれは、どんなメッセージよりもはるかに豊かなものを意味するだろう。それはあなたに美を提供するだろう。あなたに苦痛を経験させるだろう。自由を指し示すだろう」「彼ら(ファンタジーの紡ぎ手たち)が回復させようとしている感覚、取りもどそうとしている知識は、ほかの人たちがほかの種類の生活を送っているかもしれないどこかほかの場所が、どこであるにせよ、どこかにあるというものだ」(アーシュラ・K・ル=グウィン著・谷垣暁美訳『いまファンタジーにできること』河出書房新社)
『ゲド戦記』の原作者のこの言葉は、七尾旅人の歌、『リトルメロディ』にも当てはまると僕は思う。『リトルメロディ』と同じように、『911fantasia』も、大きな力が作動した後に作られた。でもふたつの作品には、対極的といっていいほどの大きな違いがある。
『911fantasia』では、「おじいちゃん」の「独り言」に、すでに死んだ子どもが相手をする。世界を覆ってきた「幻」について語る「おじいちゃん」も、じつは幻に捕えられていたという、ある意味でかなり怖い構造を持っている。幽霊や幻から目覚めようとする巨大な物語は、最後に「いつまで(幻のなかを)探してるの?/なんだかおかしいわ」と、「此処」にいる「歌」が応答することで終わる。その意味では、『911fantasia』は「ここにある歌」に立ち返ろうとする作品でもあった(そのための旅が、あまりにも大きすぎたのだが)。『911fantasia』に収められた一片の宝石"Airplane"は、「あの飛行機」に乗る女の子の視線を宿して創造された。七尾旅人の想像力が、高度何千メートルの、乗ることが不可能な飛行機のヴィジョンにまで羽ばたく。その飛行機は、この現実世界で起こった事実のなかの飛行機であり、しかし同時に「外の世界」の出来事のなかの飛行機でもあっただろう。でも"圏内の歌"、『リトルメロディ』は違う。七尾旅人は、現実の福島に赴いている。実際に七尾旅人や僕らの生きるこの国の「町」や人の歌物語だ。そこに、『リトルメロディ』の光の秘密があるように思う。
この作品の最後の歌の最初の瞬間、もういちどノイズが訪れる(歌詞の通りに耳を澄ませてこの曲を聴くと、何か巨大なものが湧き上がってくる音、風になびくような微かな歓声など、繊細なサウンド・デザインによる音の景色が聴こえる。そしてまた、水晶のようなピアノの響きが)。この"リトルメロディ"に託された想いがどんなものなのか、ここで説明するまでもないだろう。七尾旅人が創った、新しい希望の歌。最後の瞬間に子どもが口ずさむ言葉が、余韻を残していく。
大きな悲鳴のあとで、もういちど、心から「わぁ。(驚きに満ちた小さな悲鳴)」と歌うことができるように。『リトルメロディ』に、僕はそんな願いを感じる。素敵な作品だと思う。
「朝に夕に仰ぐ星と同じく現実なのです。そして、翔びたいと願うものは誰でも、歌と引きかえに翔ぶことができるのです。/歌の力によって人が肉体を離れる瞬間に、唇は語ることをやめますが、歌はなおもつづき、人が翔びつづけるかぎり歌もつづくのです。もし今夜、わたしが肉体を離れるとすれば、皆さんにも覚えておいてほしいのです。歌は終わることなしと」(トマス・M・ディッシュ著・友枝康子訳『歌の翼に』国書刊行会)
文:桑田晋吾
[[SplitPage]]小さなメロディにおける両義性 文:橋元優歩
 七尾旅人 七尾旅人リトルメロディ Felicity |
七尾旅人はこれからもフォークのスタイルをつづけていくのだろうか。『リトルメロディ』は美しいが、どこか不自由で息苦しい印象を受ける。筆者にはその理由の一端が彼のフォークにあるように思われる。かつてあれだけ多様な音楽性を乱反射させていた七尾がなぜこのスタイルへ向かったのか。
そもそもの1作目から言葉が渦を巻いていたわけだから、それが言葉とギターというシンプルな形態に結びついていったのは必然だったかもしれない。デビュー作の歌詞カードを見れば瞭然であるように、はじめそれらの言葉はまったく整理されていなかったが、ひとつひとつがつよい磁石のように、まったくおびただしい音や形式を引きよせているのがわかった。「雨に撃たえば...!」などという表記は、荒唐無稽であるようでいて、物事とその名前や意味がくっつかないでぶらぶらと宙をただよっていたようなあの時期(99年の流行語には学級崩壊やだんご三兄弟があり、改正住民基本台帳法が成立してぶらぶらしたものは数字をつけて管理されようとしていた)の感性をすばらしく圧縮している。
いま聴き直してみると、そうしたぐちゃぐちゃな表出がやがて現代詩のような体裁をそなえはじめるころに、フォークのスタイルが獲得されていったようにみえる(『ひきがたり・ものがたりVol.1 蜂雀』)。言葉の序列が整ったことがフォークを呼び寄せたのか、フォークへ行きついたことが言葉を整えさせたのかはわからないが、それは朗読や物語りを編むまでに研磨されて、やがて『911ファンタジア』へと結実していく。その意味で『911ファンタジア』はプログレッシヴなフォークというふうに言えるかもしれない。その後に発表されるのが前作『ビリオン・ヴォイシズ』である。
これらの作品にあってそのスタイルは挑戦であり先鋭性そのものであった。フォークにおいて社会的なテーマ性が往々にして硬直してしまうという難点を、ただ切り離して四畳半フォークへとスライドさせてしまうのではなく、音楽自体を研磨することで踏み抜いてしまう......つまり食えないプロテスト・ソングではなくジューシーなプロテスト・ソングを組み上げていた。「プロテスト」という言葉自体が硬直しているため、そのように言ってしまうと作品のイメージをとてもせまく限定的にしてしまうが、甘い音に固い言葉をのせるなどというレベルをはるかに超え、七尾旅人という大きな創造性のなかに彼自身の社会的な問題意識をきわめて自然に組み込んでいた。"シャッター商店街のマイルスデイビス"などは『911ファンタジア』からの方法的な成果をふまえ、ファンタジーと社会批評とが卓抜なアイディアとパフォーマンスによって縫い合わされた曲だ。そこには「フォーク・シンガーって、いかになにもしないかだと思ってるから」とうそぶく余裕やユーモア、そしてフォーク・シンガーというものの本質的ないかがわしさへの憧れをみることができた。
こうしたカーヴを描きながら、いま彼のフォークは直接性へと向かっているようにみえる。よりダイレクトに、より平易な表現で、手の届く範囲へ届けたいという思いが本作の背景にあったのではないか。フクシマに材をとった "圏内の歌"は、ここまでパッケージ化されることなく、あくまで肉声での表現にこだわって各地で歌われてきた。震災がひとつの引き金になったのかもしれないが、大胆で融通無碍な七尾のフォームは、小ささというあたらしい倫理へと変容しかけているようにみえる。それはもちろん、これまでの作風のひとつの進化として、ひとりの表現者としての誠実さや真摯さから生み出されたものであるはずだ。
七尾の近年の活動、とくにライヴ活動には、なによりもつよくコミュニケーションが前提されている。彼のフォーク・スタイルはほとんどそのために選択されているようにさえ感じられた。歌は自己表現というよりは、そこにいる人々に向かって投げられる対話の端緒であり、そのフィードバックをえて再度投げられる。客をいじるのも、ツイッターを組み込むのも同じことであり、彼はそれをとても鮮やかな手つきでみせてくれる。「百人組手」などの取り組みや、ストリーミング配信、さまざまなミュージシャンとの録音やコラボレーションも同様である。七尾はそうして対話の端口をひらこうとするような取り組みを、もうずいぶんとあの黒と麦わらのいでたちでおこなってきた。それはさながら踊り念仏の聖人のようでもあり、各地へおもむき、自分のじかの声が届く範囲の人びとに、彼の信じる歌の力を届けてまわるという"圏内の歌"=小ささの倫理のスタンスは、すでに準備されていたのだとも言えるだろう。
だが、それならばライヴ・アルバムの名盤を作ることもできたのではないか。スタジオ・アルバムというパッケージングにおいて、七尾の取り組みの価値がうまく取り出されているとは言えない。"エヴリシング・イズ・ゴーン"や"湘南が遠くなっていく""七夕の人"などは普遍的なラヴ・ソングとしての平明さをそなえ、また宛名のついた曲でもあるような直接性もにじませていて、七尾が想定する聴き手の射程がより小さく絞られたというようにもみえる。つまり、小ささの倫理にもとづき、生の声で伝えることのできるライヴやプライヴェートな演奏において引き立つ曲だというようにも思われる。"湘南が遠くなっていく"のシングル盤が湘南地区限定で販売されているのも同様の原理からであろう。だがアルバムのなかではやや一本調子である。さまざまなアーティストとの録音にはとても緊密な空気がある。だが"サーカス・ナイト"や"メモリー・レーン"は、"ローリン・ローリン"を超える一手を打てない。"アブラカダブラ"の微熱のようなサイケデリアや"ビジー・メン"のもつれるようなビートのアプローチも全面化されるわけではない。
"リトルメロディ"ではこう歌われる。「そしてみつけたよ/小さなメロディ/何千光年の遠すぎる時間を/短い歌で超えよう」......小さなメロディの本質は、その小ささで思いもかけない距離を超えていけるものとして表現されている。歌というものがものを動かす途方もない力について、七尾のような稀有な歌い手には確信があるのだ。だがその「小ささ」とはかならずしも平易さという意味ではないはずだ。「リトルメロディ」によって、自身の大きさを規制してしまってはいけない。ギターと言葉だけで人びとを愉しませ、あるいは煙にまくことの、本質的なうさんくささをもういちど引き寄せてほしい。そのことで自身のフォークのもうひとつの倫理性を立ち上げてほしい。そのように思った。
文:橋元優歩