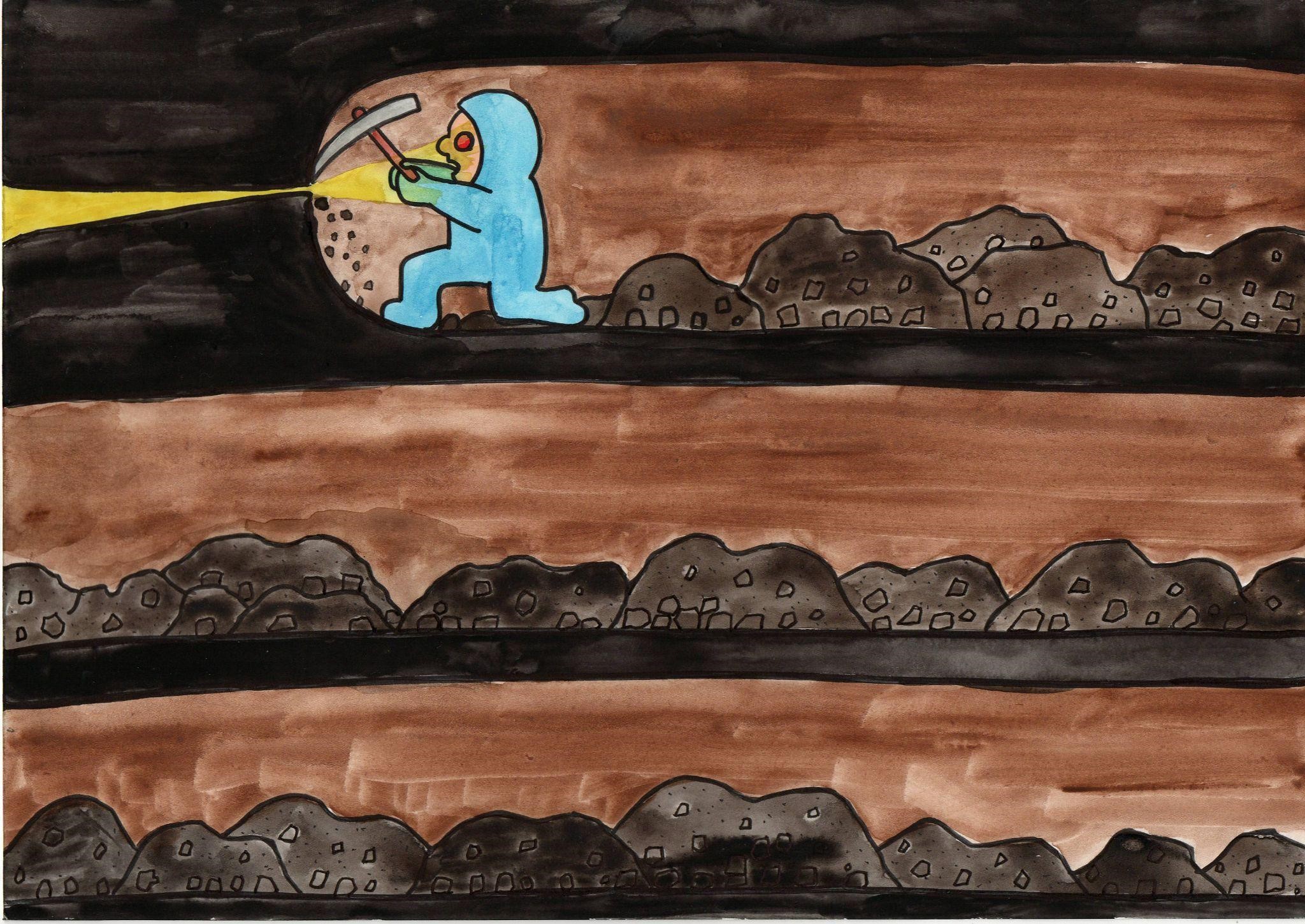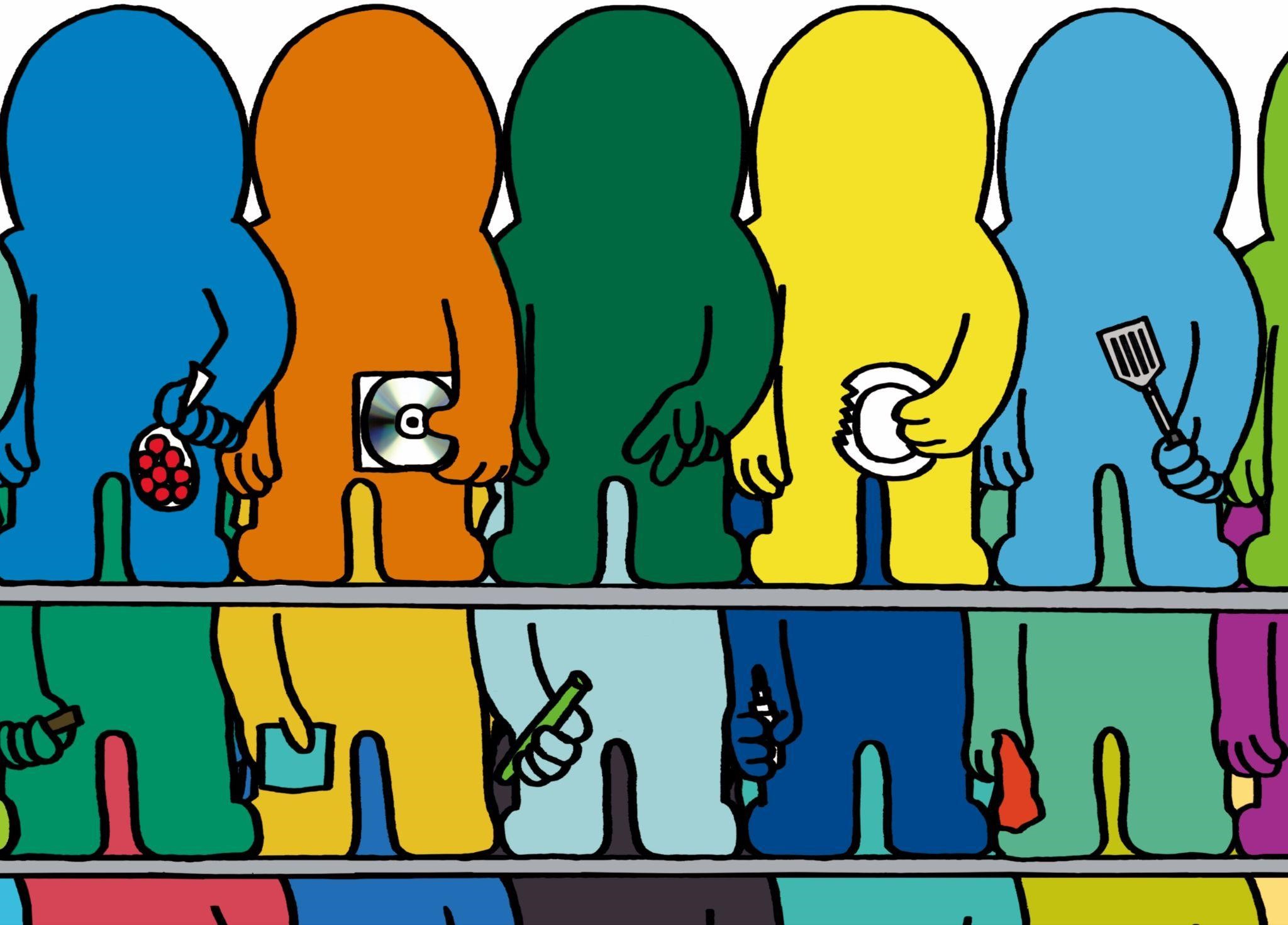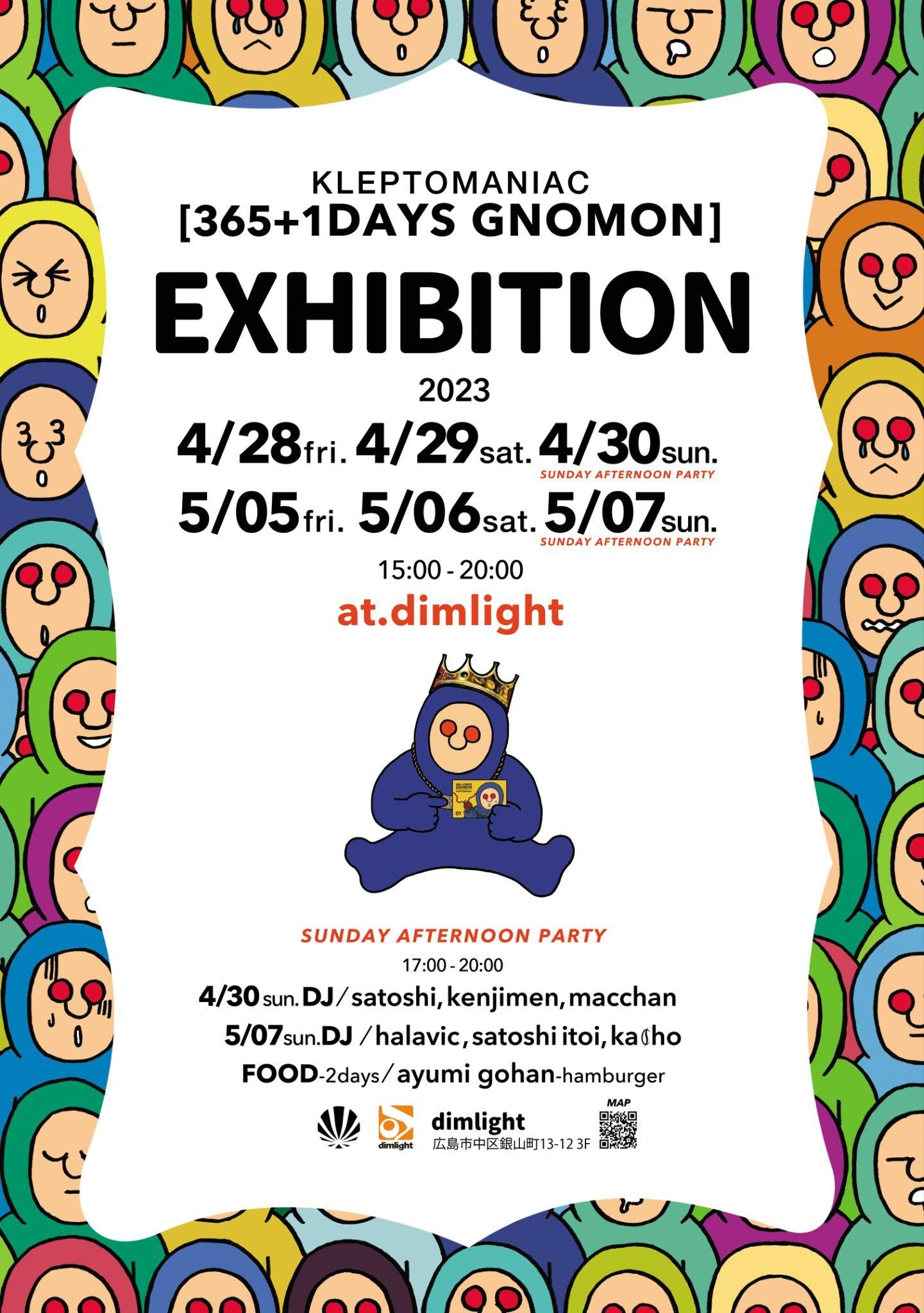シンガー・ソングライターの寺尾紗穂、ベーシストの伊賀航、ドラマーのあだち麗三郎からなる3人組、冬にわかれて。『なんにもいらない』『タンデム』と、すでに2枚のアルバムを送り出している彼らが3枚目のアルバムをリリースすることになった。アンビエント・ポップ、MPBからモンゴル民謡まで、幅広いアプローチを試みているようだ。発売は5月24日、以降全国各地でライヴも予定されている。まだときどき寒い日もあるけれど、「冬にわかれて」春を満喫したい。
もしあなたが目を凝らし、耳をすましてみれば、そこには二度と繰り返されない「生」のゆらめきがある――。寺尾紗穂、伊賀航、あだち麗三郎からなるバンド「冬にわかれて」。待望のサードアルバム『flow』が完成。

冬にわかれて 3rd album『flow』
2023.05.24 in stores
品番:KHGCD-003 CD 定価:¥3,000+税 発売元:こほろぎ舎 CD 販売元:PCI MUSIC
01. tandem ⅱ
作曲:伊賀航
02. 水面の天使
作詞:寺尾紗穂 作曲:伊賀航
03. 舟を漕ぐ人
作詞:あだち麗三郎 作曲:あだち麗三郎
04. There’s flow in flower
作曲:あだち麗三郎
05. snow snow
作詞:寺尾紗穂 作曲:伊賀航
06. もしも海
作詞:あだち麗三郎 作曲:あだち麗三郎
07. 昭和柔侠伝の唄
作詞:あがた森魚 作曲:あがた森魚
08. Girolamo
作詞:寺尾紗穂 作曲:寺尾紗穂
09.可愛い栗毛(Хөөрхөнхалиун)
モンゴル民謡
10.朝焼け A red morning
作詞:寺尾紗穂 作曲:寺尾紗穂
昨年2022年にリリースしたオリジナル・アルバム『余白のメロディ』で、唯一無二のシンガー・ソングライターとしての評価を確立しますますその活動に注目が集まる、寺尾紗穂。細野晴臣を始め、数多くのミュージシャンから絶対的な信頼を置かれる稀代のベーシスト、伊賀航。そして、自身名義での幅広い創作から、片想いなど様々なバンド/プロジェクトで活動する鬼才ドラマー/音楽家、あだち麗三郎。
そんな三者による「冬にわかれて」は、これまでに『なんにもいらない』(2018年)、とセカンドアルバム『タンデム』(2020年)を発表し、個性あふれるトリオバンドとして作を追うごとにその表現を深めてきた。
本作『flow』で、彼らの挑戦的なソングライティング/アンサンブルは過去最高のレベルに達し、一つの「バンド」としてますます紐帯を強めたといえる。各メンバーが持ち寄った個性豊かな楽曲は、三者間の熱を帯びたコミュニケーションと当意即妙のレコーディングを経て、全く例をみない形に仕上げられた。
前作アルバムの名を継ぐまろやかなインスト「tandem2」をはじめ、妖しくも軽やかな色香の漂うワルツ「水面の天使」、エレクトロニカ+アンビエントポップ的な音像に彩られた「snow snow」など、ソングライター/サウンドクリエイターとしての伊賀航は、その独自のセンスをますます深化させた。あだち麗三郎は、MPB〜ネオフィルクローレの薫りをまとった「船を漕ぐ人」、「醒」、ドライブ感溢れるプログレッシブポップ「もしも海」で、より一層自由な曲想に挑戦している。また、あがた森魚の「昭和柔侠伝の唄」、モンゴル民謡「可愛い栗毛」の斬新なカヴァーも光る。
そして、寺尾紗穂が持ち寄った2つの曲が、本作の全体に力強い生命を吹き込んでいく。時の神権政治を厳しく批判し民衆を熱狂させた15世紀フィレンツェの修道士ジロラモ・サヴォナローラにインスピレーションを得て書かれたという「Gilolamo」は、歴史と「今」をつなぎとめる彼女の鋭い社会意識が鮮烈な形で刻まれている。アルバムを締めくくる「朝焼け」は、数限りない名曲を持つ彼女のキャリアにおいても指折りの、実に感動的な曲だ。
「流れ」を意味する、タイトルの「flow」。このアルバムを聴くと、その題通り流麗でダイナミックな、流れる水に身を浸すような感覚を覚える。しかし、その「流れ」は、決してただ心地よさを誘い、去っていくものではない。静かに形を変える水面。滑るように飛びゆく鳥たち。移り去っていく季節。流れていく私達の「生」。目を凝らし、耳をすましてみれば、そこには二度とは繰り返されない彩があり、襞(ひだ)があるはずなのだ。
―柴崎祐二
[冬にわかれて プロフィール]
『楕円の夢』、『余白のメロディ』などリリース毎に作品が名盤と注目される寺尾紗穂(vo, p)と、細野晴臣や星野源、ハナレグミなどさまざまなアーティストのサポートを務めるベーシスト、伊賀航(b/lake、Old Days Tailor)、片想いやHei Tanakaの一 員でもあり、のろしレコードや東郷清丸といったアーティストのサポート、その他プロデュースやレコーディングからソロ活動までこなすマルチ・プレイヤー、あだち麗三郎(ds, sax/あだち麗三郎と美味しい水)の3人から成るバンド。2017年、7インチ・ シングル「耳をすまして」でデビュー。2018年にファースト・アルバム『なんにもいらない』をリリース。収録曲の「君の街」(伊賀航の詞曲)は、J-WAVE「TOKIO HOT 100」に3ヶ月連続でランクインした。2021年、セカンド・アルバム『タンデム』をリリース、配信において世界各地で今なお上位 にランクインが続いている。
2018年10月 1st アルバム『なんにもいらない』発表。
2021年4月 2st アルバム『タンデム』発表。
2023年5月 3rd アルバム『flow』発表。
[冬にわかれて ライブスケジュール]
5月27日 愛知 森、道、市場2023
7月4日 Billboard Live東京(寺尾紗穂/冬にわかれて)
9月3日 愛媛・今治 眞鍋造機本社ビル1F
9月24日 熊本 早川倉庫
10月8日 足柄 RingNe Festival
11月18日 栃木 OHYA BASE