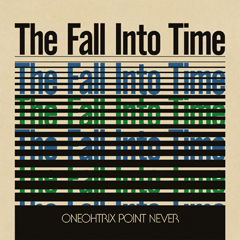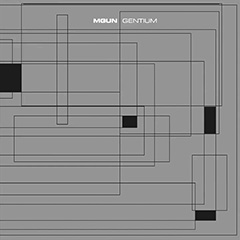新作『黄金の館』の発売を目前に控えた吉田省念。ele-kingではインタヴューも公開する予定だが、お先にMV公開の情報が届いたので、ぜひご紹介したい。ともにささやかな空間でありながら対照的な2つの場所を舞台とする映像が、このシンガーソングライターの音楽を繊細に優しく伝えている。
京都発!
奇跡のシンガーソングライター『吉田省念』完全セルフプロデュースによる6年振りとなるニューアルバム「黄金の館」が5月18日に発売。
同アルバムより2本のMVが公開中!!
■コーラスに細野晴臣を迎えた「晴れ男」ミュー-ジック・ビデオ
■ライブでもお馴染みの楽曲 「水中のレコードショップ」ミュー-ジック・ビデオ
くるりの活動を経て、暖めてきた楽曲達が遂に完成。
正統なロック・ルーツサウンドからフォーク・ブルース・アヴァンギャルド迄、彼の歩んで来た道のりを凝縮し、京都から発散するほんわりとした甘酸っぱいサウンドにミックスし、ゆったりと濃密な時が進む。多岐にわたる楽器演奏を自ら紬ぎ、素晴らしい豪華ゲスト陣が寄り添う事でその魅力を存分に伝えるメロディアスで爽快なポップ・アルバム!
ゲスト参加ミュージシャンは、細野晴臣、柳原陽一郎(exたま)、伊藤大地、四家卯大、谷健人(Turntable Films)、植田良太、めめ、さいとうともこ(Cocopeliena)。
ドイツに渡り、NEU・クラウスティンガー(ex KRAFTWORK)と共に音楽活動を行っていた尾之内和之をエンジニアに、自宅・省念スタジオで収録した執念の快心作。
■ライ・クーダーや細野晴臣氏のように過去のさまざまな音楽のエッセンスを現代に蘇らせる名工が作った作品の佇まいがあるし、その飾り気のない純朴な歌いっぷりから、京都系フォークシンガーの佳曲集とも言っていいかもしれない。
【柳原陽一郎 ex.たま】
■言葉にならないです。果てしなく胸の奥の奥の真ん中の部分に触れる。揺れる。夢中で聴いている。
【奇妙礼太郎】
■去年、舞台音楽の現場を長く共有した省念くんのソロアルバム『黄金の館』すばらしい作品でぼくもうれしい!なつっこいメロディに朴訥な歌声、かなりねじれたアレンジと底なしのギターアイデアが最高ですよ。こんな人と一緒に音楽を作れてたのが僕は誇らしいです。多くの人に聴いてもらいたい!!
【蔡忠浩 (bonobos)】

〈作品詳細〉
吉田省念 / 黄金の館
ヨシダ・ショウネン / オウゴンノヤカタ
発売日:5月18日
価格:¥2,500+税
品番:PCD-25199
Cover Art:HELLOAYACHAN
〈トラックリスト〉
1. 黄金の館
2. 一千一夜
3. 晴れ男
4. 水中のレコードショップ
5. 小さな恋の物語
6. デカダンいつでっか
7. 夏がくる
8. LUNA
9. 春の事
10. 青い空
11. 銀色の館
12. 残響のシンフォニー
13. Piano solo
[●作詞・作曲・演奏 吉田省念 ●録音 尾之内和之 ●MIX 吉田省念・尾之内和之]
<ツアー情報>
■5/14(土) 京都・拾得 「黄金の館」*バンドセット&アルバム先行発売有り
■5/17(火) 京都・磔磔 「月に吠えるワンマン」*ソロでの出演
■5/24(火) 下北沢・レテ「銀色の館 #3」*弾語りソロワンマン
■5/26(木) 三軒茶屋・Moon Factory Coffee *弾語りoono yuukiとツーマン
■6/5(日) 名古屋・KDハポーン「レコハツワンマン」*京都メンバーでのバンドセット guest:柳原陽一郎
■6/14(火) 京都・拾得 「黄金の館」
■6/30(日) 下北沢・440 「レコハツワンマン」 *バンドセット Dr.伊藤大地、Ba.千葉広樹、guest:柳原陽一郎
■7/14(木)京都・拾得 「黄金の館」
■7/18(月) 京都・磔磔 *詳細未定
■7/24(日) 大阪・ムジカジャポニカ
■8/7(日) 京都・西院ミュージックフェスティバル
吉田省念:
京都出身のミュージシャン。
13歳、エレキギターに出会い自ら音楽に興味をもち現在に至る迄、様々な形態で活動を続ける。
18歳、カセットMTRに出会い自宅録音・一人バンドに没頭 これをきに楽器を演奏する事に興味をもつこの10年間は日本語でのソングライティングに力を入れ自らも唄い活動を続ける。
2008年「soungs」をリリース。吉田省念と三日月スープを結成、2009年「Relax」をリリース。
2011年~2013年くるりに在籍 日本のロックシーンにおける第一線の現場を学ぶ。在籍中はギターとチェロを担当し「坩堝の電圧」をリリース。
2014年から地元京都の拾得にてマンスリーライブ「黄金の館」を主催し、様々なゲストミュージシャンと共演。
四家卯大(cello)、植田良太(contrabass)とのセッションを収録したライブ盤「キヌキセヌ」リリース、RISING SUN ROCK FESTIVAL 2014 in EZOに出演。
2015年ソロアルバムのレコーディングと共に、主演:森山未來 原作:荒木飛呂彦 演出:長谷川寧 舞台「死刑執行中脱獄進行中」の音楽を担当。
既成概念にとらわれない音楽活動を展開中。
website:yoshidashonen.net






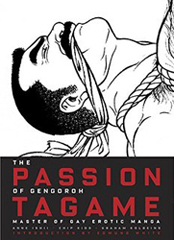



 interview with ANOHNI
interview with ANOHNI 1. アノーニと電子音楽
1. アノーニと電子音楽