なんということだ。今週土曜、ジャー・シャカが〈ユニット〉を揺るがしに東京にやってくる。しかも、ファット・フレディーズ・ドロップも同じフロアに参加。さらに、〈サルーン〉ではなんとマムダンスやブランコまでもがプレイするときている。今日のサウンド・システム・カルチャーの土台を作り上げた始祖と、その意志を継ぎ前線で戦うプレイヤーの両方を同じ場所で目の当たりにできるというだけで、足がひとりでに代官山へ向かってしまうではないか……!!!
だがここにひとつ、贅沢な問題がある。お隣は恵比寿〈リキッドルーム〉では、同じ日にUKベース・テクノの現在を語るうえで外せないペヴァラリスト、カウトン、アススの3人がついにリヴィティ・サウンドとしてのプレイを披露するのだ! 彼らに加え、早い段階から彼らの曲をプレイしてきたDJノブやムードマン、C.Eのトビー・フェルトウェルがパーティを加速させる。
ベース・カルチャーをバックグラウンドに持つリヴィティの根源に何があるかを理解するためには、ジャー・シャカを体感することは必須条件。また、ジャー・シャカを聴いてしまったら、彼が伝えた「意志」が世代から世代へどう伝わっていったのかを目撃しないではいられません。人力でルーツを探求するファット・フレディーズ・ドロップから、マシーン・ミュージックで伝統に切り込むリヴィティ・サウンドやマムダンス。「ダブ」をキーワードにシーンには素晴らしい多様性が生まれているのですから。
さぁ、あなたはどちらを選ぶ? いや、選ばなくたっていい。ハシゴするだけの価値がオオアリなサタデー・ベース・ウェイトだぜ!

■11月8日(土)
会場:代官山 UNIT
Red Bull Music Academy presents The Roots Commandment: Tokyo In Dub
UNIT :
Jah Shaka
Fat Freddy’s Drop
Cojie from Mighty Crown
SALOON :
Branko,Mumdance,Dengue Dengue Dengue!, Jah-Light
UNICE :
Fred, Felix, JUNGLE ROCK, ZUKAROHI
Open/Start 23:30
adv.3,000yen / door 3,500yen
info. 03.5459.8630 UNIT
20歳未満入場不可、要ID

■11月8日(土)
会場:LIQUIDROOM
HOUSE OF LIQUID
LIVE:
LIVITY SOUND (Peverelist, Kowton, Asusu / Bristol, UK)
DJ:
MOODMAN (HOUSE OF LIQUID / GODFATHER / SLOWMOTION)
TOBY FELTWELL (C.E Director)
DJ NOBU (FUTURE TERROR / Bitta)
Open/Start 23:00
adv. 2,500yen[limited to 100] door 3,000yen(with flyer) 3,500yen
info LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net
20歳未満入場不可、要ID
■JAH SHAKA

ジャマイカに生まれ、8才で両親とUKに移住。60年代後半、ラスタファリのスピリチュアルとマーチン・ルーサー・キング、アンジェラ・ディヴィス等、米国の公民権運動のコンシャスに影響を受け、サウンド・システムを開始、各地を巡回する。ズールー王、シャカの名を冠し独自のサウンド・システムを創造、70年代後半にはCOXSON、FATMANと共にUKの3大サウンド・システムとなる。'80年に自己のジャー・シャカ・レーベルを設立以来『COMMANDMENTS OF DUB』シリーズをはじめ、数多くのダブ/ルーツ・レゲエ作品を発表、超越的なスタジオ・ワークを継続する。
30年以上の歴史に培われた独自のサウンドシステムは、大音響で胸を直撃する重低音と聴覚を刺激する高音、更にはサイレンやシンドラムを駆使した音の洪水!! スピリチュアルな儀式とでも呼ぶべきジャー・シャカ・サウンドシステムは生きる伝説となり、あらゆる音楽ファンからワールドワイドに、熱狂的支持を集めている。heavyweight、dubwise、steppersなシャカ・サウンドのソースはエクスクルーシヴなダブ・プレート。セレクター/DJ/MC等、サウンド・システムが分業化する中、シャカはオールマイティーに、ひたすら孤高を貫いている。まさに"A WAY OF LIFE "!
■LIVITY SOUND (Peverelist, Kowton, Asusu / Bristol, UK)

UKガラージからの影響を色濃く反映したブロークン・ビーツとヘビーな低音を組み合わせることによって今までにない独自のグルーヴを提唱し続けるペヴァラリスト。グライムのエッセンスをテクノ・ハウスに落とし込んだダーティーでざらついた音楽の在り方を新たに提唱し、1つのスタイルへと昇華させたカウトン。ダブワイズな音響処理と確かな技術に裏付けられたプロセッシングを硬質なビートに施した中毒性のある高純度のミニマル・ミュージックを展開するアスス。LIVITY SOUNDは、そうした3つの突出した個性による相乗効果によって、単なる足し算ではなく、三位一体となった1つの「個」を創出してきたライブ・プロジェクト兼レーベルだ。ダブステップの潮流が大型レイヴの方向へと進行し、サウンドシステムの起源から離れていく中、ダンス・ミュージックにおける既存の枠組を取り払い拡張する、という根幹となる視点を維持し続け、新たな領域を積極的に切り開こうとする三者の意思が結実したものだと言ってもいい。その意思はハードウェアを中心としたライヴセットの中でも有機的に絡み合い、ダブ・エフェクトと即興性を活かした、まさに"セッション"と呼ぶに相応しいパフォーマンスを繰り広げることにつながっている。3人がこれまでに受けてきた音楽的な影響を抽出したものから生まれたソロ作、および共作は、それゆえにUKガラージ、テクノ、ハウス、ジャングルなど多くの方向性へとリンクしていくことが可能な音楽性を孕んでいる。この点こそ、多くのリスナーを魅了している理由であり、Resident Adviserにおける2013年レーベル・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた要因の1つだろう。今年に入り、彼らの音楽が持つ拡張性を示すかのように、Surgeon、Nick Hoppner、Kassem Mosse、A Made Up Sound、Ron Morelli、MMMの他、広範囲に渡るリミキサー陣が、LIVITY SOUNDの作品を手がけている。現在進行形のUKアンダーグラウンドを体現するLivity Soundのライヴセット、またとないこの機会をぜひとも逃さないでほしい。
■Fat Fredy’s Drop

ファット・フレディーズ・ドロップはニュージーランドの音楽史を塗り替え続けているバンドである。インディペンデント・アーティストとして過去最大の売上を記録するなど、音楽賞は総なめ、そして世界中の名立たるフェスティヴァルにも呼ばれ続けている(グラストンベリー、SONAR、ベスティヴァル、WOMAD、ローランズやロスキルドなど)。そして世界の由緒ある会場でも満員のライヴを開催し続けている(ブリクストン・アカデミー、オランダのパラディソ、ロスのヘンリー・フォンダ・シアターやパリのル・トゥリアノンなど)。レゲエ/ダブをベースに、ソウル/ファンク/ジャズ、そしてミニマルなダンスミュージックのグルーヴをクロスオーヴァーした絶妙な塩梅のバンド+打ち込み・サウンド、そして嫌いな人は絶対いないビター・スウィートな美声で万人を虜にするジョー・デューキーのボーカルなど、彼らの魅力はジャイルス・ピーターソンをはじめとする著名人を虜にしてきた。1999年にウェリングトンのアンダーグラウンド・クラブ・シーンに、ファンクやハウス、ヒップホップなどのレコードをスピンするDJ Mu(akaフィッチー)と共に演奏していたバンドが13年経った今も、同じ友情と気持ちで演奏を続けている。その進化は今日も止まる事が無い。
1st Album『Based on A True Story』
2nd Album『Blackbird』







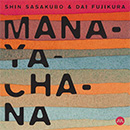




 湯浅学
湯浅学 サン・ラー
サン・ラー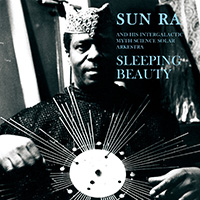 サン・ラー・アンド・ヒズ・アーケストラ
サン・ラー・アンド・ヒズ・アーケストラ 

