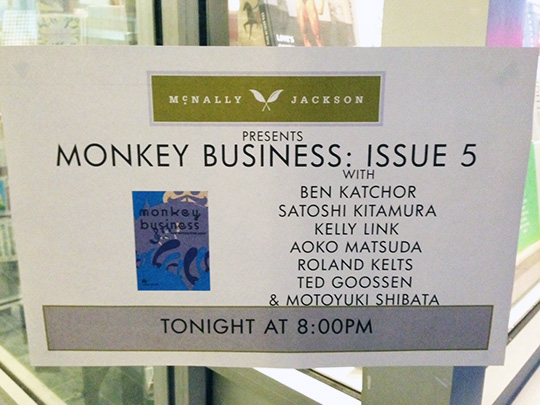洗練されたソウルとおどろくべき表現力で“歌謡曲”を更新するシンガー、入江陽。JINTANA & EMERALDS、OMSB……ジャンルも個性も異なれど、彼の傑作アルバム『仕事』のレコ発イヴェントを急角度で祝福する、すばらしい顔ぶれが報じられた。ソウルとサイケとヒップホップがしなやかに香ぐわしく交差する夜をWWWで、ともに。
6月29日(月)に渋谷WWWにて開催される入江陽『仕事』レコ発に追加ゲスト発表!
入江陽バンド編成、OMSB [DJ SET]に加えて、横浜のネオ・ドゥーワップ・バンドJINTANA & EMERALDSが出演決定です!
 仕事 入江陽 Pヴァイン |
ヒップ・ホップ以降のソウル感を感じさせる歌謡曲シンガー入江陽のセカンド・アルバム『仕事』のレコ発が6月29日(月)、WWWにて行われる。この日の入江陽のライヴは大谷能生やYasei Collectiveの別所和洋含む特別バンド編成で行われ、OMSB[DJ SET]の出演も決定している。
そしてこの日、追加で横浜発アーバン&メロウ集団PPPことPAN PACIFIC PLAYA所属のスティールギタリスト : JINTANA率いる6人組ネオ・ドゥーワップバンド、JINTANA&EMERALDSの出演が決定した!
世代もジャンルもクロスオーバーして芳醇なニオイたつこの3組が登場するのはまさに奇跡。忘れられない一夜を保証します。
チケット各プレイガイドにて発売中です!
 ■入江陽 “仕事” Album Special Release Party
■入江陽 “仕事” Album Special Release Party
2015年6月29日(月)@渋谷WWW
OPEN 19:00 / START 19:30
ADV ¥2,800 / DOOR ¥3,300(別途1ドリンク代)
出演:
入江陽バンド
・入江陽(vocal,keyboards)
・大谷能生(sax,pc,etc)
・別所和洋(keyboards) from Yasei Collective
・小杉岳(guitar) from てんやわんや
・吉良憲一(contrabass)
・藤巻鉄郎(drums)
JINTANA & EMERALDS
OMSB [DJ SET]
TICKET:
ローソンチケット[L:72333]
チケットぴあ[P:266-155]
e+
◎入江陽 プロフィール
1987年生まれ。東京都新宿区大久保出身。 シンガーソングライター、映画音楽家。
学生時代はジャズ研究会でピアノを、管弦楽団でオーボエを演奏する一方、学外ではパンクバンドやフリージャズなどの演奏にも参加、混沌とした作曲/演奏活動を展開する。
その後、試行錯誤の末、突如歌いだす。歌に関しては、ディアンジェロと井上陽水に強い影響を受けその向こうを目指す。
2013年10月シンガーソングライターとしての1stアルバム「水」をリリース。
2015年1月、音楽家/批評家の大谷能生氏プロデュースで2ndアルバム「仕事」をリリース。
映画音楽家としては、『マリアの乳房』(瀬々敬久監督)『青二才』『モーニングセット、牛乳、ハル』(サトウトシキ監督)『Sweet Sickness』(西村晋也監督)他の音楽を制作。
https://irieyo.com/
◎JINTANA & EMERALDS プロフィール
横浜発アーバン&メロウ集団PPPことPAN PACIFIC PLAYA所属のスティールギタリスト : JINTANA率いる6人組ネオ・ドゥーワップバンド、JINTANA&EMERALDS。リーダーのJINTANA、同じくPPP所属、最近ではあらゆる所で引っ張りだこのギタリスト : Kashif a.k.a. STRINGSBURN、媚薬系シンガー : 一十三十一、女優としても活躍するMAMI、黒木メイサなど幅広くダンスミュージックのプロデュースをするカミカオルという3人の歌姫達に加えミキサーにはTRAKS BOYSの半身としても知られる実力派DJ、CRYSTAL。フィル・スペクターが現代のダンスフロアに降り立ったようなネオ・アシッド・ドゥーワップ・ウォールオブサウンドで、いつしか気分は50年代の西海岸へ...そこはエメラルド色の海。エメラルド色に輝く街。エメラルドシティに暮らす若者たちの織りなす、ドリーミーでブリージンなひとときをお届けします。
https://www.jintanaandemeralds.com/
◎OMSB プロフィール
Mr. "All Bad" Jordan a.k.a. OMSB
SIMI LABでMC/Producer/無職/特攻隊長(ブッコミ)として活動。
2012年10月26日、ソロアーティストとしてのファーストアルバム「Mr. "All Bad" Jordan」を発表。
2014年3月には、自身も所属するグループSIMI LABとしてのセカンドアルバム「Page 2 : Mind Over Matter」をリリース。
兼ねてからフリーダウンロード企画でBeat Tapeを多数発表し、2014年11月にはBLACKSMOKER RECORDSよりインストビート作品集「OMBS」も発表。
その他、KOHH, ZORN, Campanella, PRIMAL等、様々なアーティストへの楽曲提供・客演参加もしている。
https://www.summit2011.net/



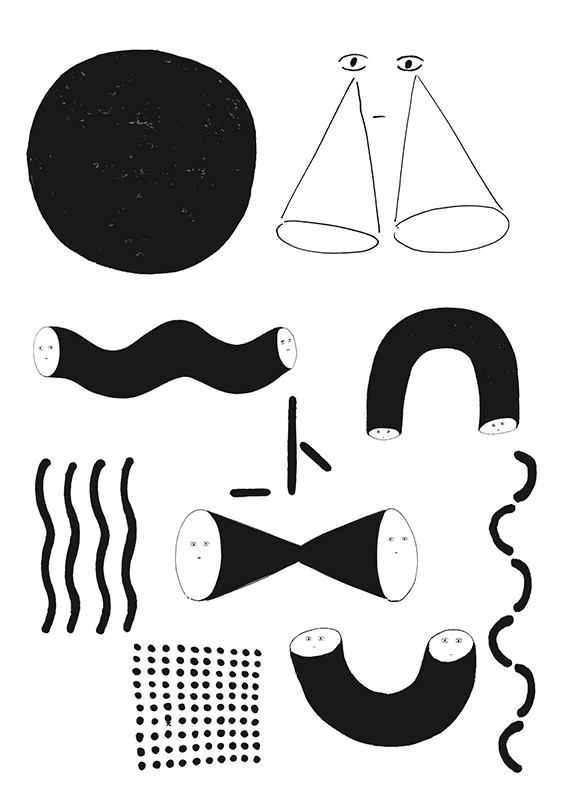
 東京ベルリンを拠点に活躍するアーティスト。写真家、芸妓、ミュージシャン、モデルなど多彩な顔を持つ。自身の日常を幻想的な色彩で切り取る写真やコラージュ、またこうした要素に音楽や立体表現を加えたインスタレーションを発表する。パレ・ド・トーキョーなどの個展、展覧会多数。ボーカルとしてdaisy chainsaw、Panacea、Kai Althoff、Mayo Thompson、Jonathan Bepler、Terre Thaemlitz、秋田昌美、中原昌也となどとコラボレーションする。tony conrad と舞台音楽で共演したり、bernhard willhelmのショウでライブパフォーマンス、そしてJürgen Paapeとカバーしたjoe le taxiはSoulwaxの2ManyDjsに使われ大ヒットした。写真作品集に『ハナヨメ』『MAGMA』『berlin』、音楽アルバム『 Gift /献上』『wooden veil』などがある。ギャラリー小柳所属。
東京ベルリンを拠点に活躍するアーティスト。写真家、芸妓、ミュージシャン、モデルなど多彩な顔を持つ。自身の日常を幻想的な色彩で切り取る写真やコラージュ、またこうした要素に音楽や立体表現を加えたインスタレーションを発表する。パレ・ド・トーキョーなどの個展、展覧会多数。ボーカルとしてdaisy chainsaw、Panacea、Kai Althoff、Mayo Thompson、Jonathan Bepler、Terre Thaemlitz、秋田昌美、中原昌也となどとコラボレーションする。tony conrad と舞台音楽で共演したり、bernhard willhelmのショウでライブパフォーマンス、そしてJürgen Paapeとカバーしたjoe le taxiはSoulwaxの2ManyDjsに使われ大ヒットした。写真作品集に『ハナヨメ』『MAGMA』『berlin』、音楽アルバム『 Gift /献上』『wooden veil』などがある。ギャラリー小柳所属。 音楽家。1990年生まれ。2010年アルバム『剃刀乙女』でデビュー。
音楽家。1990年生まれ。2010年アルバム『剃刀乙女』でデビュー。 tomoyoshi date, hiroki ono, takeshi tsubakiからなるアンビエントバンド。数多の諸概念・主義主張を融解する中庸思想を共有しながら、所作と無為を心がけ活動中。
tomoyoshi date, hiroki ono, takeshi tsubakiからなるアンビエントバンド。数多の諸概念・主義主張を融解する中庸思想を共有しながら、所作と無為を心がけ活動中。 1977年ブラジル・サンパウロ生まれ。3歳の時に日本へ移住。 ロック、ジャズ、ポスト・ロックなどを経て90年代後半より電子音楽を開始。 ソロ作品に加え、Opitope、ILLUHA、Melodiaとして活動するほか、中村としまる、KenIkeda、坂本龍一、TaylorDeupreeとも共作を重ね、世界各国のレーベルから14枚のフルアルバムをリリース。 西洋医学・東洋医学を併用する医師でもあり、2014年10月にアンビエント・クリニック「つゆくさ医院」を開院 (
1977年ブラジル・サンパウロ生まれ。3歳の時に日本へ移住。 ロック、ジャズ、ポスト・ロックなどを経て90年代後半より電子音楽を開始。 ソロ作品に加え、Opitope、ILLUHA、Melodiaとして活動するほか、中村としまる、KenIkeda、坂本龍一、TaylorDeupreeとも共作を重ね、世界各国のレーベルから14枚のフルアルバムをリリース。 西洋医学・東洋医学を併用する医師でもあり、2014年10月にアンビエント・クリニック「つゆくさ医院」を開院 ( イラストレーター。風景やモノを中心に、パターンワークやシンプルな形を使用したミニマルでリズミカルな作画で書籍や雑誌、CDジャケットを中心に活動。また音楽制作会社での勤務経験をもとに、ミュージックガイド「5X5ZINE」の制作/刊行を定期的におこなっている。
イラストレーター。風景やモノを中心に、パターンワークやシンプルな形を使用したミニマルでリズミカルな作画で書籍や雑誌、CDジャケットを中心に活動。また音楽制作会社での勤務経験をもとに、ミュージックガイド「5X5ZINE」の制作/刊行を定期的におこなっている。 餡子作りという限られた材料を元に独自の配合を研究し、日々理想の餡子を模索し続ける小豆研究家、池谷一樹によるケータリング餡子屋。一丁焼きたい焼き屋を目指し日々試行錯誤を繰り返している。今回は最中をまた同時にadzuki名義で活動する音楽家でもある。
餡子作りという限られた材料を元に独自の配合を研究し、日々理想の餡子を模索し続ける小豆研究家、池谷一樹によるケータリング餡子屋。一丁焼きたい焼き屋を目指し日々試行錯誤を繰り返している。今回は最中をまた同時にadzuki名義で活動する音楽家でもある。 手造りどぶろく屋。
手造りどぶろく屋。