
こんにちは、NaBaBaです。年の瀬迫る今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。今年もあっという間に過ぎてしまいましたが、ゲーム業界的には非常に盛り上がった1年でした。PlayStation 4とXbox Oneの二大次世代機も北米と欧州ではついに発売となり、どちらも品切れ続出の大人気のようです。
そんな僕もじつはPlayStation 4の北米発売日である11月15日に、ロサンゼルス旅行に行ってきました。あいにくゲーム機そのものは手に入らなかったのですが、発売日の深夜販売に合流してみたり、個人のゲーム・ショップで店員さんたちといっしょに遊んだりして、向こうのゲーム熱を直に感じてきたのです。

L.A.市内のゲーム・ショップ『World 8』にて。店員さんたちと開封したてのPlayStation 4で遊んだときの様子。
そしてこのロサンゼルスを舞台のモチーフにしているのが、今年最大の超大作である『Grand Theft Auto V』です。〈Rockstar Games〉の看板シリーズであり、昔『Grand Theft Auto III』が日本で発売されたときには、その暴力的内容から神奈川県で有害図書に認定されるという事件もありました。そうしたことから名前だけは知っている方も多いのではないでしょうか。
そんなシリーズの最新作である本作は発売されるや否や、数々の記録を打ち立てています。まず開発費が約2.65億ドルと歴代ゲーム1位(2位は前作『Grand Theft Auto IV』の1億ドル)で、しかも発売初日に8億ドル以上売り上げ、発売6週で約2,900万本も売り上げるなど、化物みたいな数字が目白押し。さらにVGX等の数多くのアワードでもGame of the Yearを受賞しています。
そんなあらゆる面において今年を代表し、また今世代の集大成と呼ぶにふさわしい本作のレヴューで以て、このコーナーも今年を締め括りたいと思います。
■進化・改善と新要素
先程『Grand Theft Auto V』を今世代の集大成と呼んだのは、何も比喩的な意味ばかりではありません。〈Rockstar Games〉の作品としては、今世代に発売された『Grand Theft Auto IV』のオープンワールドゲームとしての骨格の上に、『Red Dead Redemption』の自然表現やランダムミッションシステム、『Max Payne 3』のシューティングシステム等といった長所を組み合わせた、正しく字のままの集大成として仕上がっているからです。
舞台となるSan Andreas地方は、都市部と自然が織り成す、〈Rockstar Games〉の作品の中ではもっとも広大なもの。そこに詰め込まれているアクティヴィティも膨大で、現代のロサンゼルスに存在するであろう、あらゆる事物を徹底的に再現し、その上で現実では体験できないフィクションを織り交ぜています。シリーズはおろかオープンワールドゲームの中でも史上最大の物量だと密度と言っても過言ではありません。

シリーズ最大の舞台を、もっとも洗練されたゲーム・システムで楽しめる。
さて、こうした進化と改善に対して、今回からの新要素はなんといっても3人の主人公によるザッピングシステムでしょう。本作ではMichael、Franklin、Trevorというそれぞれまったく別の境遇の3人組が、お互い協力して数々の犯罪に挑んでいきます。そしてゲーム的にもプレイヤーはこの3人を使い分けながら攻略していくことになり、ゲーム全体を通して非常に重要なシステムとしてフィーチャーされています。
ではここから、前半はオープンワールドとメインミッションについて、後半は世界観の考察を交えながら、シナリオに対してこのザッピングシステムが持つ功罪について、考えていくことにしましょう。
本作の特徴についてはこの公式解説動画がもっとも纏まっている。
■3人の主人公と3種類の視点
オープンワールドゲームとしてのこの主人公のザッピングシステムは、まずはミッション中でなければ基本的にいつでも自由に操作キャラを切り替えられるという点で、遊ぶ上での利便性に寄与しています。たとえば別々の場所にいる主人公たちを切り替えることで移動の手間が多少省けるし、また、いまやっていることに飽きても他の主人公に切り替えることで、心機一転して別のことに取り組むきっかけになるのが面白い。
しかしそれ以上に個性や行えることが違う主人公たちを切り替えることで、ひとつの舞台を三者三様の角度から楽しむことができるのが効用としてはもっとも大きいと感じます。典型的なのがTrevorで、彼の破滅的な性格、言動はプレイヤーの遊び方をも自然と暴力的な方向に導いていく。MichaelやFranklinでは性格的に似合わない大量虐殺もTrevorだったら起こし得るし、実際そういう趣旨のイベントもたくさんあります。

Trevorの狂気はプレイヤーの暴力的衝動を掻き立ててくれる。
前作『Grand Theft Auto IV 』でリアリティとシリアス路線の観点からトーン・ダウンしたシリーズ元来の暴力的ハチャメチャプレイが、Trevorというキャラによってリアリティを損なうことなく実現できた意義は大変大きい。シリーズのどのタイトルのファンにとってもうれしい改善だと言えます。
[[SplitPage]]■格好良い+ 格好良い +格好良い=超格好良い!
『Grand Theft Auto V』の遊びの本軸となるメインミッションでも、先程のザッピングシステムは効果を発揮しており、ここではひとつの出来事を多角的に、かつよりスペクタクルに描き出すものとして、さらには攻略における戦術的オプションとしても機能しています。
本作のメインミッションは前述した通り、3人が協力して大仕事に挑むパターンが多い。プレイヤーは異なる役割の3人を任意に切り替えたり、または自動で切り替わったりするなかでひとつのミッションを攻略していくことになります。
これは簡単に言えば、3人の主人公の格好良い瞬間を切り貼りして、全体が構成されているという感じ。なので展開が常に引き締まっていて中弛みがなく、ひとつの出来事を多角的に見れるので物語としての厚みも増す。また役割が3人に分散するので、従来のゲームに見られた、主人公がひとりで全部やるみたいなことが起きず、リアリティにも貢献しています。
ミッション中のザッピングシステムの機能は、映像を直接見てもらうのが理解する近道だろう。
メインミッションでは大抵の場合頻繁にキャラクターを切り替えることになりますが、こうしたシステムで懸念材料になるのが、キャラクターを切り替えたときに状況が把握しきれず混乱しかねないことだと思います。しかし本作では不思議なくらいこの問題は起きませんでした。
それは良くも悪くもこのシリーズのミッションには、もともと戦略の自由度が無いからなのでしょう。とくに04年発売の『Grand Theft Auto: San Andreas 』以降のミッションは紋切型ばかりで、大局的な目線で立ち回りを考えたりといった、創意工夫を許す余地がありません。この点がいままでは欠点のひとつとして度々指摘されてきたわけですが、しかし本作に限ってはその指示された通りやればいいという単純さが、むしろ主人公を使い分ける際に混乱を抑制するプラスの効果を生んでいるのです。
また違う立場のキャラクターに切り替える機能は戦略の幅には寄与しなくとも、局所的な戦術という意味では自由度を増やしてくれています。たとえば1人が迷路のような場所を進み、もう1人が遠方からスナイパー・ライフルで援護するというシチュエーションの場合、片方の操作に専念するか、交互に使い分けるか、またその割合等もプレイヤーの裁量に委ねられるのです。

定番の狙撃で援護する場面も、する側とされる側を自由に切り替えられるとなれば俄然面白くなる。
そうした点を考えれば、紋切型という根本的な構造自体は変わっていませんが、むしろ紋切型としては、従来のゲームには無いシステムがとても新鮮で、かつそれがしっかり機能していて、とても面白いものに仕上がっていると思います。
■リーマンショック以降のアメリカ社会を切る
問題はシナリオで、ザッピングシステムがほぼ完璧に機能していると感じた先の2件に比べて、こちらは不満に感じる部分が結構ありました。しかしその点を語る前に、まずは本作の全体的な世界観から考察していきたいと思います。
このシリーズの世界観の特徴は、一貫してアメリカ社会の風刺であると思っていますが、本作ではとくにその傾向が強い。なぜなら今までのシリーズはギャングやマフィアといった裏社会の出来事を中心に描いていたのに対し、本作ではより一般人と表社会に近いところで物語が展開されるからです。
もっともわかりやすい例が主人公たちに仕事を依頼するクライアントや敵対者たちで、これまでのような裏社会の犯罪者はほんのわずかで、かわりに実業家やFIBやIAA(FBIとCIAのパロディ)の捜査官、パパラッチやエクササイズ・マニアだとかいった、ほとんどが表社会や公的機関の人々。そんな彼らが金を稼ぐため、社会で生き残るため、あるいは狂気の結果として、主人公たちに不正行為の外注をするわけです。

実業家のDevin Weston。儲け話でそそのかしながら、報酬を出し渋る嫌な奴だ。
さらに街を見回してみると、現代社会のさまざまな事物が強迫観念的に誇張されて描かれています。経済問題やセレブの堕落といった話題がニュースの紙面を賑わせ、IT会社のCEOは児童労働を高らかに宣言し、保守主義と社会主義の知事候補が日々過激な罵り合いを繰り広げ、TwitterやFacebookを模したSNSを見ると人々はヤクやセックスの話ばかりしている。
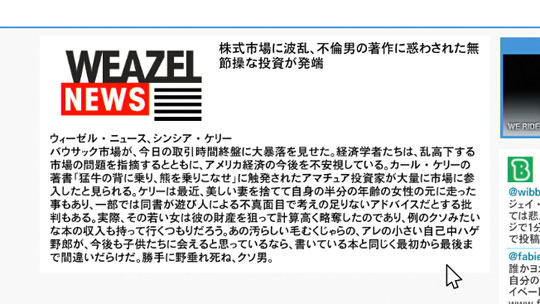
現実では建前の奥に隠している本音も、本作では皆堂々と曝け出している。
そこから浮かび上がってくるのはリーマンショック以降のアメリカの姿です。不景気や相次ぐ社会問題に喘ぎ、しかしかつての栄華を捨てきれずに体裁だけ整えようと、皆が必死になっている姿がそこにはある。劇中ではどれも表現が過激で往々にしてコミカルに見えるますが、捉えている問題は極めて現実的でシリアスなものです。
そんな世界において、主人公たちはある意味ではもっとも被害者なのかもしれません。なにしろほとんどの場合クライアントからは報酬が支払われない。これまでのシリーズでは仕事を請け負えば必ず報酬がありましたが、本作では何かと理由を付けてケチられたり、そもそも初めから無銭労働を強いられる場合も多い。
当然主人公たちはジリ貧です。物語的にはもちろん、ゲーム的にも出費だけがかさみ、そのうち何もできなくなり、最終的には自ら企画立案した仕事=強盗に挑まざるを得ない状況に追い込まれていく。

本作の自主的な強盗の動機は、基本的に生活苦なのである。
つまり本作は本質的には労働者の物語なのです。これは言うなればウォール街を占拠せよ運動で語られた、1%の富める者と99%の貧する者たちによって繰り広げられる死の舞踏なのです。問題の発露、あるいは解決に犯罪行為が選ばれているだけで、問題そのものはわれわれ一般人の生活のなかにあるものを捉えている。
そして本作の凄いところは、こうした社会風刺を言うまでもなくオープンワールドゲームとして表現している点にあります。これまでゲームに限らずあらゆるメディアに社会風刺的な作品は存在しましたが、風刺の対象となる社会そのものを仮想現実的に再現してしまうことに関しては、このシリーズに勝るものは他にありません。とりわけ本作はいままで以上に一般人の目線に立った世界観と、先述したシリーズ最高のゲーム・システムが組み合わさり、シリーズとしてもメディア作品としても風刺表現のひとつの極みに達していると言えます。
[[SplitPage]]■三兎を追う者は何とやら
問題はここから。世界観と全体的なテーマは文句なしですが、3人の主人公個々の物語として見ると話は違ってきます。結論から言えば主人公が3人になったぶん、視点が分散してしまい、両者とも十分に掘り下げきれないまま話が終わってしまう印象を受けました。
少なくとも中盤までは大変面白い。ストリート・ギャングと決別し、より現実的な方法で成功を望むもうまくいかず悶々としているFranklinは同世代として共感できるし、家庭崩壊と己の性に苦しむMichaelはいままでのゲームには無かったキャラクター像でとてもユニークです。そんなふたりに正真正銘の外道であるTrevorが合流し、毎回乱痴気騒ぎをしつつも全体的に駄目な方向に堕ちていく様子は、まさに現代版死の舞踏といった感じで、悲劇でも喜劇でもありながら独特の緊張感がある。

ついには家族に出て行かれてしまうMichael。
しかし後半以降になると途端に展開がマンネリ化してしまいます。まずFranklinは本人の目標を早々に達成してしまい、話の本筋にあまり絡まなくなってしまう。TrevorはMichaelのことをチクチク言葉責めするばかりで関係に進展がほとんどないし、3人のクライアントもほぼFIBに固定化されてしまう。

Franklinはときどき元ギャング仲間との絡みがあるだけで、後半はほとんど彼自身の物語が展開されない
こうした後半のマンネリ化に続いて、終盤で物語が収束していく段になっても、個々の出来事にいまひとつ説得力が欠けているのです。極めつけはエンディングです。3種類に分岐するのですが、どれもいままで積み重ねた伏線を回収しきれずに終わるか、もしくはまるで打ち切りマンガのように強引に風呂敷を畳む感じになってしまい、いずれにせよ不満が残ります。
以上のようなシナリオになってしまったところに、3人主人公というシステムの難しさを感じずにはいられません。エンディングについて、「もっと尺を取って個々の伏線にしっかり決着をつけるべきだった」と言うのは簡単ですが、おそらく律儀にそれをやっていたらただでさえ長大な物語がさらに気の遠くなる長さになっていたに違いありません。後半のマンネリも、3人の個々の物語を展開しつつ、本筋の大きな物語に歩調を合わせることの困難さが露呈してしまっています。
どうすればうまくいったのか簡単には思いつきませんが、つまりはそのワン・アイディアが足りなかったということでしょう。結論としては一般的なゲームのシナリオとしてはユニークさも完成度も十分と言えますが、個人的にシリーズ最高だったと思っている『Grand Theft Auto IV 』の主人公Nikoの物語と比べると、今回の3人の物語は数段落ちるのが残念でした。
■まとめ
お金をつぎ込めるだけつぎ込み、現在考えられる究極のゲームを作ったとしたら? その答えのひとつが『Grand Theft Auto V』であり、その圧倒的物量は前代未聞の領域。新しいシステムも含め全体的な完成度はとても高い。
唯一、シナリオの後半以降の粗が目立ってしまうのが玉に瑕ですが、現代アメリカの風刺としてはこれ以上無いほど極まっており、総合的に見て『Grand Theft Auto』シリーズの名に恥じない傑作と断言できます。ゲーマーは勿論、普段ゲームに興味の無い人にも手にとってほしいと感じる逸品。
最後に、『Grand Theft Auto V』はとても多義的な作品です。今回はゲーム・システムと物語という観点からレヴューしましたが、よりアメリカン・カルチャーに根ざしたところから本作を考察することもできるでしょうし、犯罪映画の数々と比較して語ることもできるでしょう。
そして『ele-king』的には何よりも音楽ではないでしょうか。本シリーズは毎回劇中のラジオという形で、時代性に即したさまざまな実在の楽曲が収録されていますが、本作もまた古くはザ・スモール・フェイセスの『オグデンズ・ナット・ゴーン・フレイク』から、近年ならジェイ・ポールの『ジャスミン』等、幅広いジャンルの曲が選ばれています。
こうした観点からのレヴューも非常に興味深いに違いありませんが、あいにく僕は音楽の専門化ではないので書くのは難しい。むしろ他の誰かが書いてくれないかな! という淡い期待を寄せつつ、本年のレヴューを締め括らせていただきたいと思います。それでは皆さん、よいお年を。










