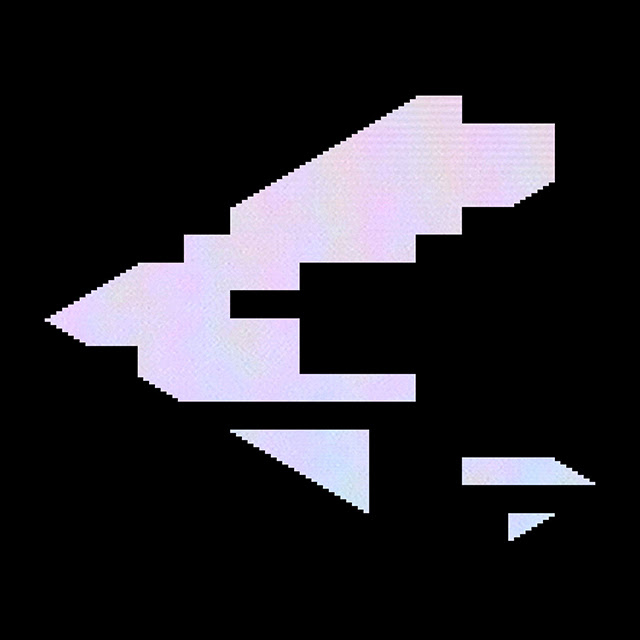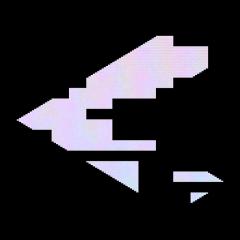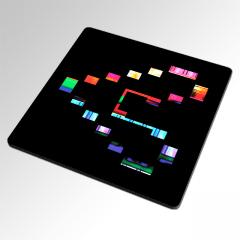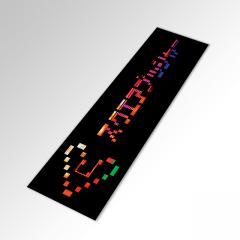日野浩志郎(goat / GEIST etc)の新作はひさびさとなる自身のレーベルからのリリースとなったカセット2作品。goat は海外ツアー、また昨年の山口 YCAM でおこなわれた GEIST もすさまじく(詳しくはこちらのレポートを)、それでもってこちらの作品も日野の現在の絶好調っぷりを感じる2作品ではないでしょうか。YPY は大雑把にいって、日野による、打ち込みの電子音を中心にしたソロ・プロジェクト。以前に著者がRAでおこなったインタヴューでは、隅々までコンポーズされた goat のようなプロジェクトとも違った、打ち込みだからこそ生まれえる予期せぬサウンドをひとつの核にしているようである。また複数のテレコを使い、カセットテープの組み合わせで構成していくワイルドなライヴも魅力のひとつ(いわゆるDJとも違う)。
これまで自身のカセット・テープ・レーベル〈birdFriend〉を中心に複数リリースし、〈EM Records〉からは初期作品『Zurhyrethm』やアルバム『Be A Little More Selfish』などがリリースされている(〈EM〉からは〈birdFriend〉の編集コンピも今後リリースされるとか)。また海外からは、ヘルムや先日すばらしいアルバムをリリースしたビアトリス・ディロンなどがリリースする〈Where To Now?〉からも作品があり、またヨーロッパを中心に同名義でツアーなどもおこなっている。そのサウンドは、日本で一時期 “ロウ・ハウス” と呼ばれていたようなインダストリアルなローファイ・テクノ、電子音のコラージュ、エスニックなパーカッション・ダブ、ときにブレイクビーツなダウンテンポなどなど多岐にわたるアプローチがなされている。そのあたりも偶然性をひとつコンセプトにすることで獲得されたサウンドではないだろうか。バラバラといえばバラバラだが、無機質に鳴らされるリズムの応酬と、サイケデリックでフリーキーなスペースを生み出すサウンド、というのがひとつ貫かれているプロジェクトの印と言えるかもしれない。
と、前置きが長くなりましたが本題を。この2連作はタイトル通り、ダブをひとつテーマにした二卵性双生児な作品といったところ。若干の制作コンセプトが異なるようだが双方とも「録って出し」がかなりの早さでおこなわれた模様である。『OVER SMILING DUB』は、強力なフィルターをかけたヴィンテージ・ドラムマシンによるトラックを下地に、さまざまな生楽器などをオーバーダブした作品。対して『NYE/D IN DUB!!!!』は、ある種ライヴ的な作り方で、同様なヴィンテージ・ドラムマシンによるトラックを下地に生ライヴ・ミックスなど4時間程度録音をおこなった音源を切り取り(ただしエデットはなし)、2曲にまとめた作品。
『OVER SMILING DUB』、まずはボブ・マーリー&リー・ペリーのドンカマ・レゲエ “ナチュラル・ミスティック” (『Exodus』収録ではないヴァージョン)のバック・トラックを1小節取り出して執拗に繰り返しながら無理矢理インダストリアル・ダブ化したかのようなA1にはじまり、フリーキーな電子音が暴れまわり、最終的にはドレクシアに接続してしまっているサイケデリックなA2。B面は間の抜けたエレクトロ・ダブと海の湿度を全く抜き取ってしまったカリビアンな感覚もありどこかインダストリアル・ダンスホール風味な2曲。特にB面後半はロウ・ジャックやダッピー・ガンのようなインダストリアル・ダンスホールにつながりそうでつながらない、メビウス&プランク『RASTAKRAUT PASTA』にむしろつながってしまった疑似インダストリアル・ダンスホール・ダブといった趣深い傑作ではないでしょうか。
『NYE/D IN DUB!!!!』A面は、どこか『OVER SMILING DUB』のA面が反転してしまったかのようなリディムで、こちらもドンカマ・レゲエの名曲、ウェイラーズ・バンド “Higher Field Marshall” (リズム&サウンド “No Partial” とカップリングでリイシューされたあれな)を彷彿とさせるグルーヴで、インダストリアルかつコズミックなダブへとじわりじわりと変化させていきます。B面は、ダンスホールとハンマービートが駆け抜けていくようなクラウトロックなグルーヴもありつつな、ジャリつくスネアとミニマルなベースラインがダブ・ミックスで加速していく楽曲です。
無機質なジャーマンなエレクトロ趣味もありつつ、いわゆるデジタル・ルーツやミニマル・ダブといったフォーミュラーな借り物のないダブ・ビート、この二品にはまいりました。『ele-king』年末号のダブ特集号の日めくり的な、その後という感じでぜひ。カセットテープは売り切れてるところ多いようですがバンドキャンプで音源そのものは変えます。カセットにはDLコードもついているようですので、末永く楽しめます。






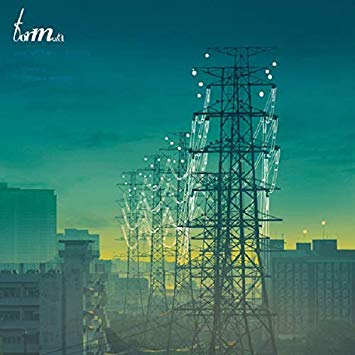

 これがSTOLENの面々。マジ格好いいし、じつはこのインタヴューが載せられるのも彼ら経由でもあります。応援しましょう!
これがSTOLENの面々。マジ格好いいし、じつはこのインタヴューが載せられるのも彼ら経由でもあります。応援しましょう!