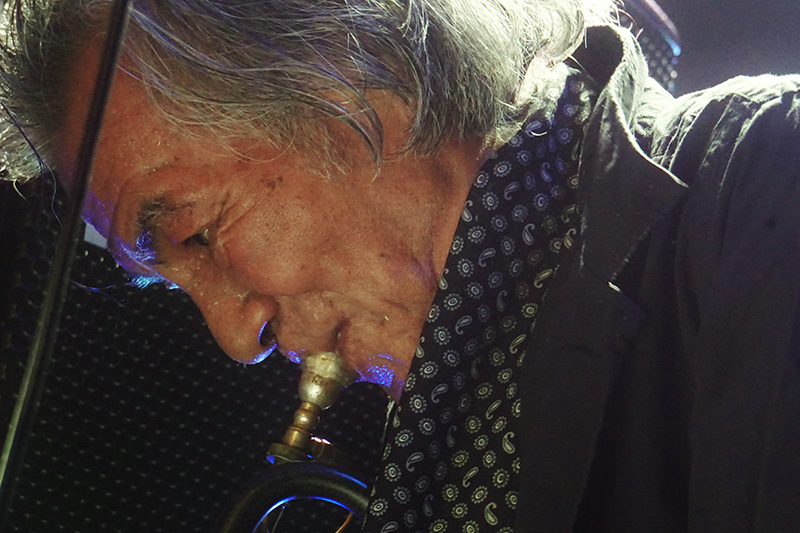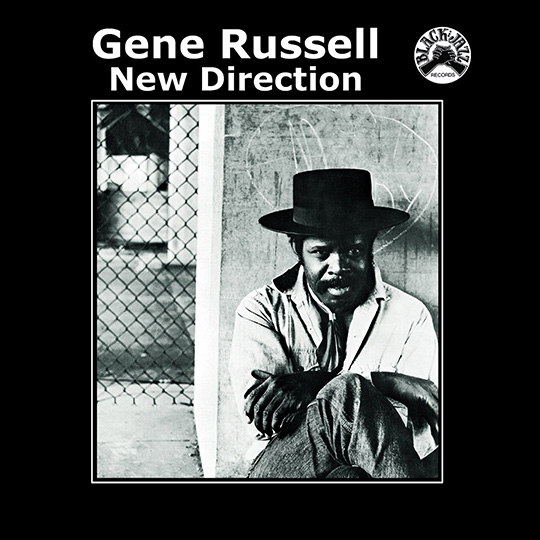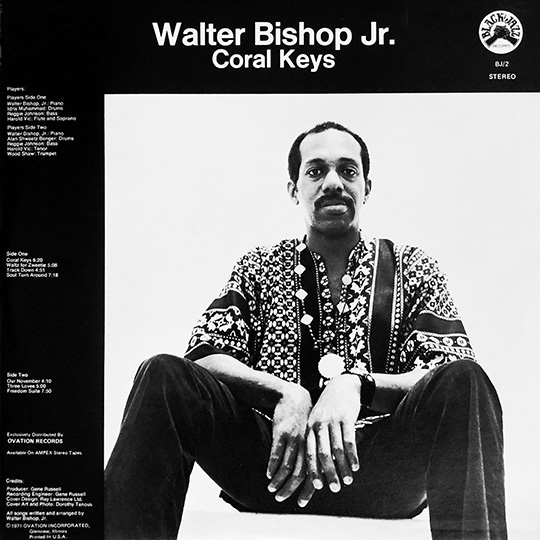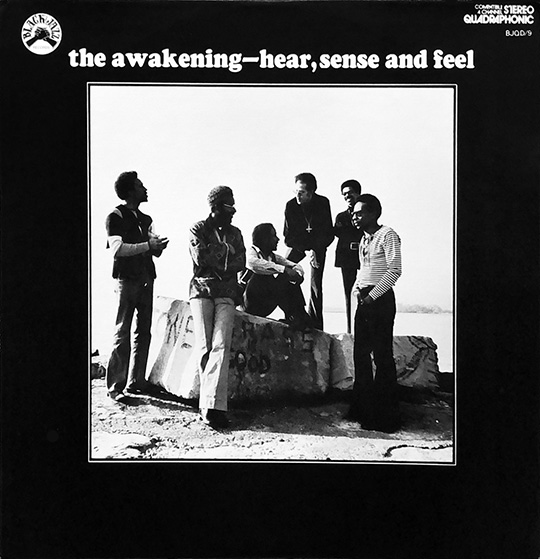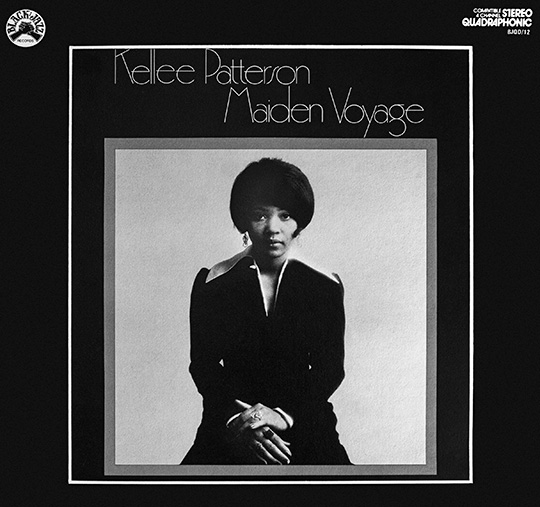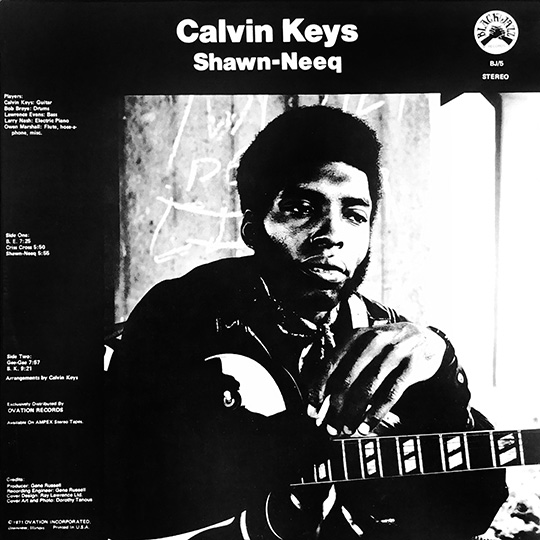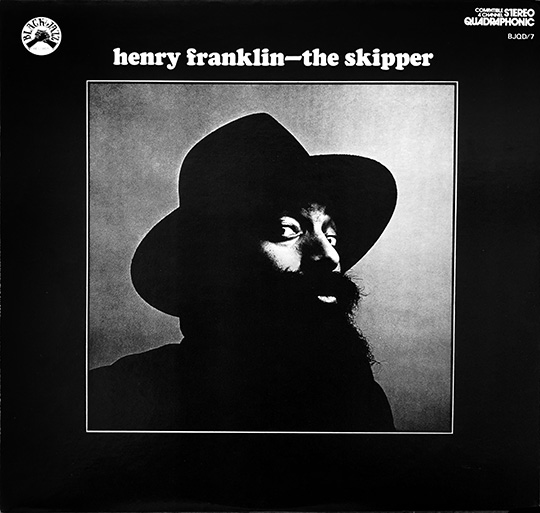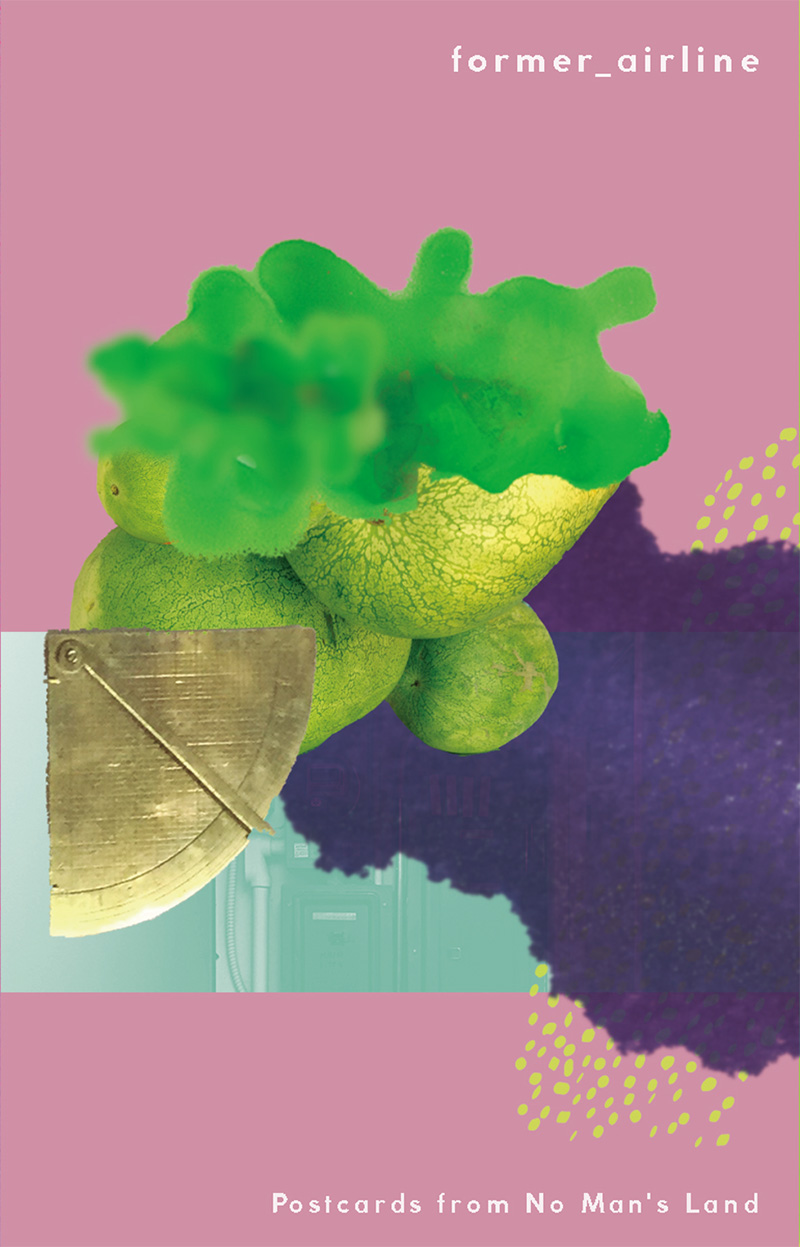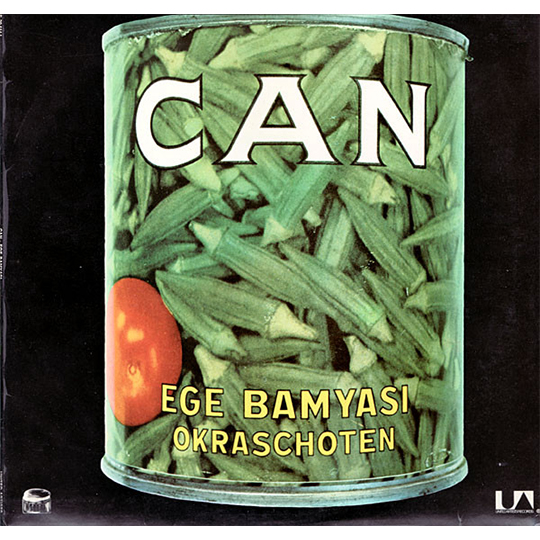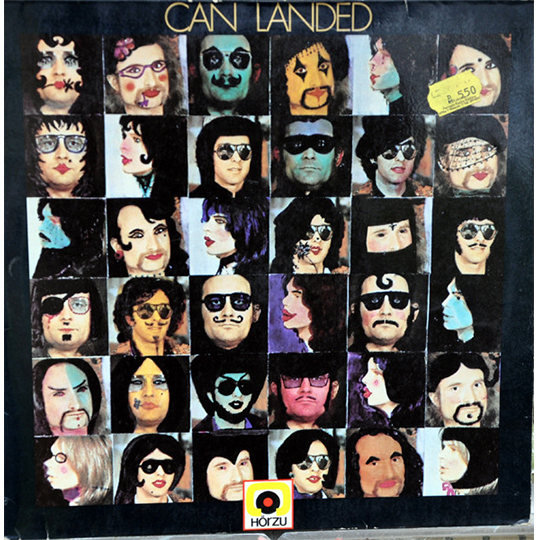ハッピーハロウィン。あなたがこのコラムを読んでいる頃にはもう、ハロウィンは終わっているだろう。思い立ってdocsに文章ファイルを作成した今日は10月30日。思い立っただけで書きたいことはまだ抽象的で、その抽象的な要素どうしが脳内で4次元構造を作りながら漂っているような状態だ。書き終わる頃にはクリスマスが見えているかもしれないし、一応メリークリスマスとも書いておこうか。

ハロウィンは明日に迫っているが、世間の浮き足立った空気は今年は感じない。ここ数年の渋谷での激しい盛り上がりが嘘のようだ。去年の今頃、初めての Protest Rave を渋谷で行なった。あの熱気が遠い過去のように感じられる。世界は変わってしまったのだ。ハロウィンといえば年に一度唯一ゴスやダークな世界観のものが表の世界でフィーチャーされる、あるいは表の世界の住人に利用される日だが、そのダークな側の世界は私が日常的に接している世界でもある。そしてそのことを思っていると、なぜ私はダークな力に惹かれ、いつから私はそのダークな力に惹かれはじめたのだろうかと、思いがけず自分の人生を振り返ってしまっていた。おそらく私のコラムを読む人の大半もまたその魅力を知っている側の人だろうと思う。昼/夜、明/暗、陽/陰、天使/悪魔、ライトサイド/ダークサイド、地上/地下などと、世界はしばしば二分される。その二分された世界で私は後者に自分の居場所を見出した。
私はクリスチャンの家庭で育った。夕食の前には神に祈り、日曜日は礼拝と教会学校に行って聖書を学んだ。自身で選択するまで洗礼は受けなくて良いという親の方針のおかげで私はクリスチャンではない。無神論者のいま、その方針には感謝している。念のために記しておくが、私は神を信じないが、宗教や他者が神を信じることを否定しない。聖書を学ぶ中で天使/悪魔という概念をまず得ることになった。その頃はビートルズが好きでよく聴いていた。
小学校3年生のときに転校をした。二つ下の弟と両親の四人で住むには木造のアパートは狭すぎたため、郊外に引っ越すことになった。転校後に仲良くなった友人の証言によると、私は転校初日から挨拶もろくにせずにノートにずっと絵を描いていたらしい。よく覚えていない。その学校では “先生のお気に入り”(嘘つき)と喧嘩をして理不尽に怒られたことが何度かあったことを覚えている。神様は全てを見ておられます。なら証言台にも立ってくれ。その頃は KISS が好きだった。血を吐いたり火を吹いたりするのに憧れていた。他のクラスメイトはモーニング娘。を聴いていた。サンタクロースはいなかった。
その後、順調に反抗期を迎えた私の反抗心は生物学上の親ではなく、宗教上の父=神に、そしてその宗教に向いた。悪魔という存在は、神に対する忠誠心の強化のために排他的で二元論的な価値観が生み出した存在だと私は主張していた。正統派の絵に描いたような中二病に正しい時期に罹患して良かったと思う。その頃よく聴いていたのは Dr Dre と Sean Paul、あと Marilyn Manson や Sum 41。不良の先輩の影響で Cyber Trance も少し。制服の下にバンドTや ALBA ROSA のTシャツを着て、ボタンを開けた制服のシャツの隙間から見えるTシャツの色や、背中に透かして見えるTシャツの柄で精一杯の自己主張をしていた。
こうしてローティーンまでの人生を過ごし、中二病的な症状が治ったあともいろいろなものと何度も衝突し、そうして自我が成長していくに従い、はじめに書いた後者の世界に自分の居場所を見出していくことになった。
良い子じゃいられなくなったとき、良い信徒になれなかったとき、お手本に忠実になれなかったとき、その決まり切った価値観から否定されたとき、そこにまた別の世界/生き方/可能性/未来が選択可能だということを示してくれたのがダークサイドのものたちだった。
「罪を告白せよ」「神はいつも正しい」と言われ、ペニー・ランボーとスティーヴ・イグノラントは「SO WHAT!」と叫んだ。「要するに良い事ー悪い事、ホンモノーニセモノっていう二律背反で物事を考えていくと、どんどん視野が狭くなっていくのさ」と江戸アケミは諭した。彼は幼いときに洗礼を受けたクリスチャンだったが、後に棄教した。坂口安吾は『堕落論』の中で「日本は負け、そして武士道は滅びたが、堕落という真実の母胎によって始めて人間が誕生したのだ。生きよ堕ちよ、その正当な手順の外に、真に人間を救い得る便利な近道がありうるだろうか。私はハラキリを好まない」と記した。二律背反で物事を考えていくと世界は非常にシンプルになる。神の側、あるいは良い事の側、正当な手順の側、ハラキリの側、文頭に書いた前者の側は二律背反で物事を考え、それに反するものを罪/悪魔/悪いこと/ニセモノ/堕落とカテゴライズしてきた。しかし、世界はより複雑であり、前者の側は無数にある選択肢のひとつに過ぎず、そしてその集合以外の場所にも無限の選択肢が存在する。選択肢は生き方であり可能性であり、無限の選択肢は無限の未来を生む。そして無限の未来は必ず希望を内包する。坂口安吾はその「正当」と「堕落」の間に存在する人間性に対する態度の差を指摘した。前者は人間らしさを恐れるあまり規律や戒律によって、あるいは力によってそれを制限しようとする。私もハラキリを好まない。彼は続けて「堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない」と記した。私はダークな力を借りて、そのハラキリを選ばない生き方の中に自身を見出した。二律背反的な思考で大きなものに寄り掛かり、そこに自身のアイデンティティを同化させて依存していては、真に人間らしい自分らしさを発見することができないどころか、その二律背反的な思考で寄り掛かった大きなものに反する人に対しては、その存在をも攻撃し、否定するようになる。規律や戒律によって、あるいは力によって人間らしさや自分らしさが否定されるとき、私たちはそれに向かって「SO WHAT!」と叫ばなければいけない。私は私のやり方で「SO WHAT!」と叫ぶ。君は君のやり方で「SO WHAT!」と叫ぶ。「SO WHAT!」と叫んだ先にこそ二律背反から解放された自由があり、そこでのみ真に自分自身を発見し、救われることができる。江戸アケミは「救われたいんだよ。けど、宗教は嫌なんだよ。だから、何に救われたいかって言ったらリズムで救われたいんだよ」と言っていた。その救いとはまさにこの、自分自身を発見した先にある救いなのではないだろうか。「SO WHAT!」と叫んだ先には無限の可能性や未来があり、その中には必ず希望があり、救いがある。もう一度言う。規律や戒律によって、あるいは力によって人間らしさや自分らしさが否定されるとき、私たちはそれに向かって「SO WHAT!」と叫ばなければいけない。
ゲイやレズビアンのカップルは子供が産めません。SO WHAT!
ピンクは女の子の色です。ブルーは男の子の色です。SO WHAT!
大麻は違法です。SO WHAT!
日本人らしくありません。SO WHAT!
言葉遣いが良くないです。SO WHAT!
そんなんじゃお嫁にいけません。SO WHAT!
タトゥーは悪の象徴です。SO WHAT!
あなたの言動は政府の方針に反します。SO WHAT!
So what, so what, so what, so what, so what, so what, so what, SO WHAT!!!