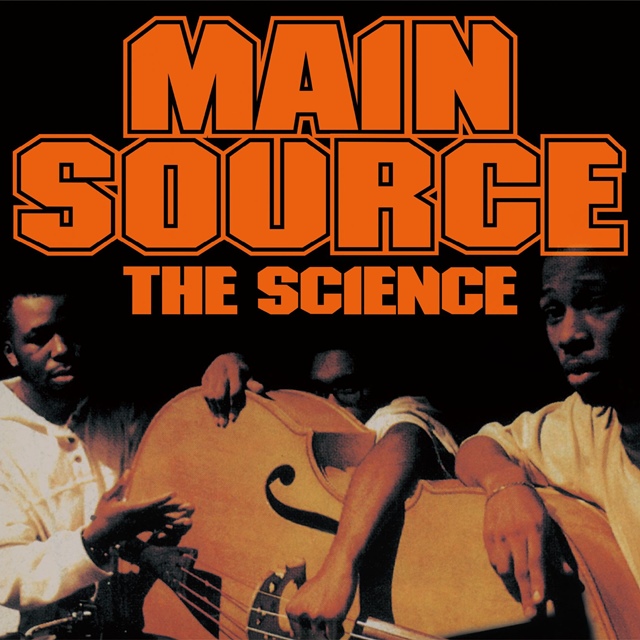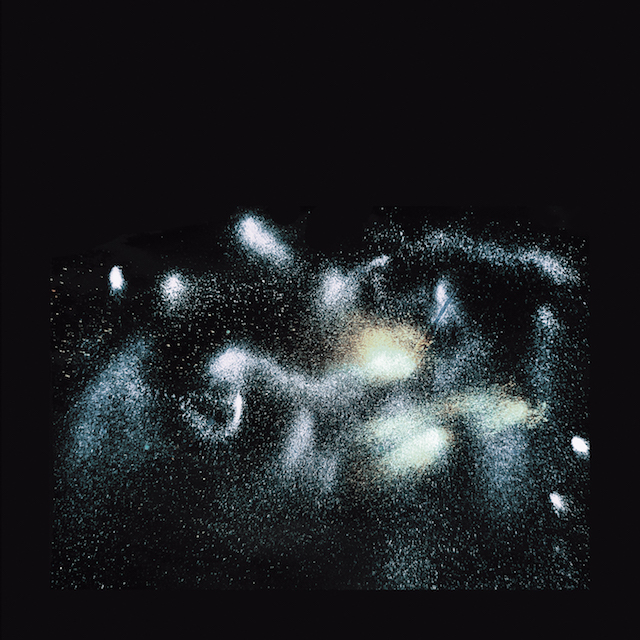〈Warp〉傘下の〈Disiples〉、いいよなぁ。このレーベルの偏ったセンス、この偏愛、まさにインディ精神、冒険心のかたまり。で、その〈Disiples〉からウルフ・アイズの新作が先日出たばかりでございます。
知ってますか? ウルフ・アイズというのは、21世紀に入ってからのUSノイズ・ロック・シーンにおいてもっとも重要なバンドなのです! このバンドが拓いた道スジに、USノイズ・シーンの後続組——Double Leopards、Yellow Swans、Burning Star Coreなどが登場し、じつはこの流れのポスト・ノイズのなかで登場したのがOPNだったりするのであります。
また、デトロイト郊外のアナーバー(ストゥージズ、MC5、そしてあのデストロイ・オール・モンスターズの故郷)で結成されたこのバンドのオリジナル・メンバーには、昨年来日を果たしたアーロン・ディロウェイ(https://www.ele-king.net/news/009048/)がいます。そのアーロンがユニヴァーサル・インディアンのジョン・オルソンと出会い、さらにまたネイト・ヤングと出会ったことで「アメリカのノイズの王様」は誕生していると。まあ、ノイズといっても、パンク、インダストリアル、ホラーを漫画のように組み合わせたイメージで、70年代、80年代のノイズとは明らかに一線を画したノイズの新感覚派、と言えるのですが……。であるから、ゼロ年代のなかばには、とにかくソニック・ユースが彼らを最大限に評価したことが後押しとなって、その人気はアンダーグラウンドからオーヴァーグラウンドへと伝染し、一時期は〈サブ・ポップ〉と契約を結ぶにもいたっているのです。また、サウンド・コラージュを駆使する彼らのシュールな世界はエレクトロニック・ミュージック・ファンに受けが良く、〈Warp〉はレーベル内に彼らのためのレーベル〈Lower Floor Music〉を設けているほど。(また、彼らはサン・ラー・アーケストラたアンソニー・ブラクストンとも共演している)
このように欧米では評価も人気もあって(『Wire』誌などは2回も表紙にしている)、残念ながら日本では過小評価されているのがウルフ・アイズで、今回の〈Disiples〉からリリースの『Dreams in Splattered Lines』は、バンド結成25周年を迎え、ふたたび上昇気流に乗っているバンドのかなり良いところが収められているので、お薦めです。2022年初頭、ニューヨーク市立図書館にて録音されたこのアルバムは、本人たちいわくシュルレアリスムの影響が反映されており、〈Disiples〉レーベルいわく「DIYエレクトロニクスとフルクサスの前衛感覚、中西部の退屈な生活の花こう岩を融合させたもの」だそうです。そんなわけでこの日本でも、もう少し、ノイズに飢えている健全な耳に、このバンドが注目されても良いんじゃないかと思う次第なのです。

Wolf Eyes
Dreams In Splattered Lines
Lower Floor Music