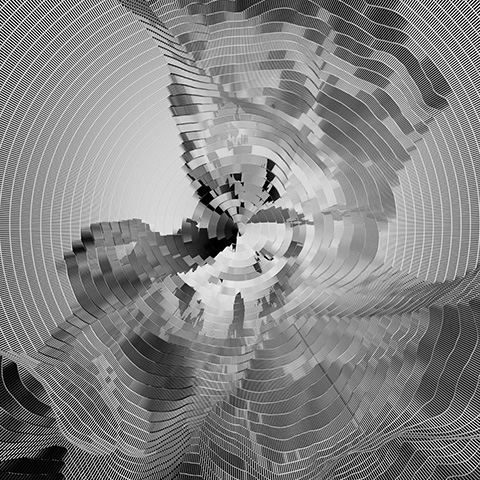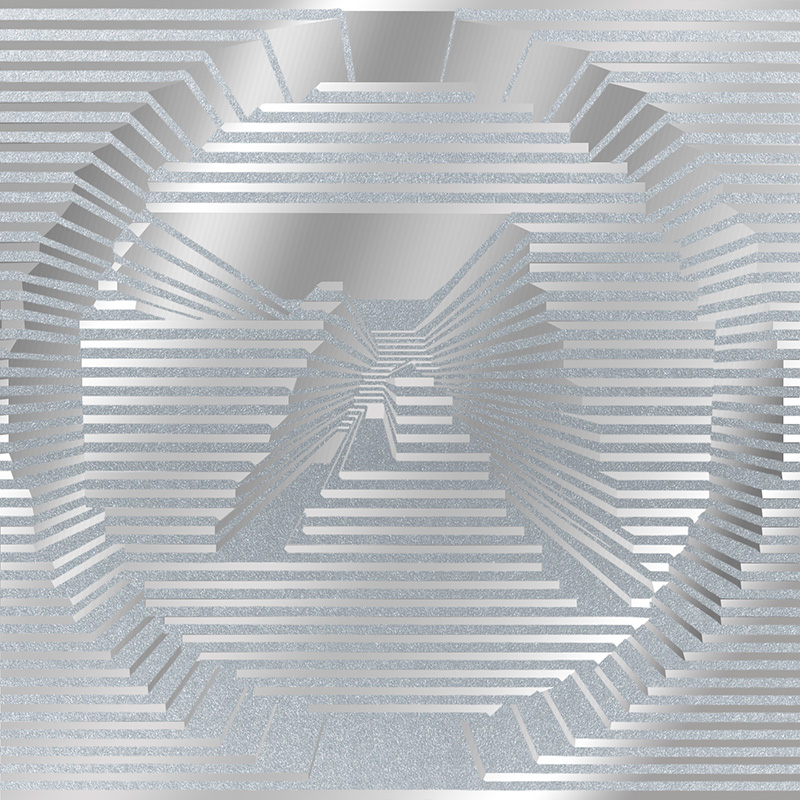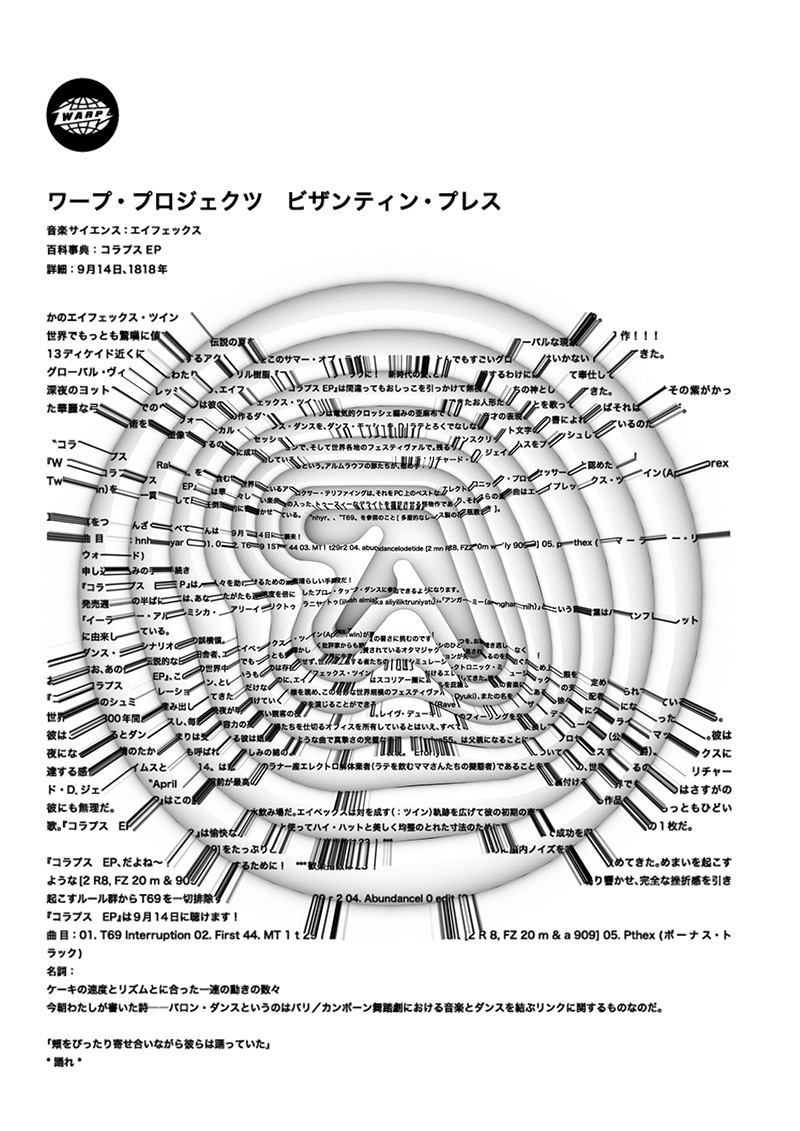時は大正デモクラシー期。理想を夢見て資本家からお金を略奪し、政府転覆を画策する若きアナキストと、女相撲という興行で全国を旅する力士が出会う瀬々敬久監督の『菊とギロチン』は、いまのところ今年いちばん心打たれた映画だ。

1917年にソビエト革命があり、1919年にワイマール憲法が制定された、世界各地で人びとは自由を求めて発言し、たたかってもいた。日本でも労働運動や女性解放運動、共産主義運動が盛んな、俗に大正デモクラシーと呼ばれる時代のことだ。政治的発言も行動も活発になった一方で、無政府主義者や共産主義者を警戒する治安維持法の前身となる法律が作られようとしていた。そんななか、1923年(大正12年)に起きた関東大震災では、混乱の中で流布した「流言飛語」によって不安に火をつけられた人びとが、隣人である朝鮮人を虐殺する事件が多発。半月後には、大杉栄と伊藤野枝も虐殺された。日本は、これから急速に不寛容、不自由な、暗い時代にむかい、長い戦争に舵を切る直前、後から見れば、さまざまな前兆が起きていたそんな時代。「ギロチン社」などというふざけた名前の政治団体を結成した実在のアナキストである中浜鐡は、貧しいものを苦しめる社会を変えるため、言論を弾圧する政治を変えようとしていた。「震災後の不景気のどん底で避難民が溢れ、食べるものもない人々は根っこを掘って口に入れる、残飯屋で1杯2銭の残飯を盗んで何人もで分ける。震災でぶっ壊れた東京の、そして震災でも覆せなかった権力の秩序に閉じ込められたまま」だと、中浜は演説をぶつ。「いたるところに自由意志を! 我々の直接行動を!」と。いや、演説というよりそれは詩だ。けれども詩を読むように夢と理想を語り、現実には資本家を襲って金を脅し取る「リャク(略奪)」を繰り返すだけ。いや、計画は立てるが、「リャク」した金は女郎屋で使い果たし、20代で梅毒持ちで……。いったいなにやってんだ?な若者だが、瀬々敬久監督は「社会を変えようと、たとえやり方は過激であり滑稽に見えさえしても、国家に死をもって処された若者の姿を描きたかった」のだという。監督は、1980年代からギロチン社の映画を撮りたかったのだという。「十代の頃、自主映画や当時登場したばかりの若い監督たちが世界を新しく変えていくのだと思い、映画を志した。僕自身が「ギロチン社」的だった」と振り返っている。身体中から湧き上がるほどに「自由」を求め、「自立」を欲し、社会を変えようと志して、それより先にまず自分が何よりも自由になろうと止むに止まれず暴走するものはアナキストとも言われ、けれどもそれは単に若者のことでもあった。「自由」の領域は時代とともに変わってきても、その本能のような心の震えはきっと今でも変わらない。

そんなギロチン青年たちが出会う菊は女相撲の力士のしこ名だ。女相撲は江戸時代から1960年くらいまでおこなわれていたという。もっともこれは明治の終わりに「国技」を名乗った男相撲とはずいぶん性格の違う、いわば見世物興行だ。女たちが肉色のシャツにふんどしを締めて、「乳見せ役」を配したり、飛び入りの客と取り組みをしたり、女と座頭が卑猥な雰囲気で取り組むような興行もあったという。大正から昭和期のエログロナンセンスの時代ともなれば、その変態的趣向はエスカレートしていき、警察は風俗紊乱の罪で監視と取り締まりを強めるようになる。その取り締まりを逃れるため、「女相撲」ではなく「手踊り」の興行だと偽って届けるなんてこともあったとか。さらに戦後にはサーカスの一部として興行した一座もあったそうだ。映画では、元姉の夫と親の言うまま結婚したが、その夫の暴力に耐えかね家出して一座を頼ってきた花菊や、元遊女で朝鮮人の十勝川、沖縄出身の与那国など、いずれも貧困(口べらし)や差別(DVなど)、あるいは何かのはずみで居場所を失った女たちが見世物になって生きていく社会的な囚われ(隔離)の場所でもあるし、同時に最後に逃げ込んだ、おだやかで優しいシェルターのようにも見える。

彼女たちがゆっくりと四股を踏む勇姿は、長い手足を持て余しているように七転八倒する中浜鐡(東出昌大)と対照的に優雅にさえ見える。長い取り組みのシーンも、相撲に全く興味がない私をも惹きつける、言葉はなくても雄弁に思いを語る。女のフリーターがボクサーを目指す武正晴監督の『百円の恋』がとても好きだ。その試合の場面も強烈に心を揺さぶられる。しかし、『百円の恋』の動機があくまでも個人の内面にあるのとはちがい、『菊とギロチン』の取り組みシーンには、職業差別や性差別といった社会的な存在の格闘が現れているように見える。そういう言葉があるわけではない。伝わるのは、ただ理不尽な貶めに対する悔しさだ。30年前から構想されていたというこの映画が今夏公開になったのはすごいタイミングではないか。なにしろ去年アメリカで始まったセクハラ告発運動#MeTooに端を発したフェミニズムの機運になかなかのれなかった日本でも、相変わらず「土俵に女は載せない」という自称国技の相撲協会やセクハラで告発された財務省事務次官に続き、東京医大の入試での明らかな女性差別採点が明らかになったことで、小さな火がついたのではないか。思えば日本では、「男女共同参画」「女性の社会参加」「女性活躍」とはいっても「男女平等」や「性差別」という言葉は長い間、少なくとも行政やマスコミなどでは使われていなかった。性差別入試への抗議行動で、「下駄を脱がせろ」というボードがあった。この件は女性を差別するな、という問題だと大方の報道では言われていたが、このボードを掲げる人は、「(男に履かせた)下駄を脱がせろ」「男性優遇はやめろ」と言ったのだ。これには私は少しばかりハッとした。それまでは女性受験生は減点された被害者だったのが、「(男の)下駄を脱がせろ」によって、なんというか、不当に優遇されている男性の足を、ちゃんと同じ地平につかせろと言うとき、女が差別された客体(被害者)とみなされるのではなく、男性こそが知らないうちに、意を無視して優遇された客体となったのだ。これって些細なことだけど、これに気付いた時、私の気分はかなり変わった。「性差別」は女の問題ではなく、男の問題だ、早く解決しておいてくれ給え、もういちいち女の手を煩わせないでくれよ、みたいな解放感といえばいいだろうか。

だいぶ話が逸れてしまったが、『菊とギロチン』の花菊と十勝川にも、似たようなことが起こる。花菊は自分を連れ戻そうとする夫との間に、十勝川は彼女を追い詰める自警団との間に。そして、そこにアナキストが関係する。そもそもアナキストと花菊たちの関係は『伊豆の踊子』(西河克己監督)のパターンのバリエーションである。すなわち頭でっかちなエリート大学生と生命力に満ち、しかし悲劇性もはらむ旅芸人一座の少女の出会いと別れだ。『はなれ瞽女おりん』(篠田正浩監督)や『ノルウェイの森』(トラン・アン・ユン監督)なんかもそうで、高等教育を受けた言葉を持つ男性が、言葉より全身で感情や生命力を表現すると女性に惹かれる。女性は過去や未来の不幸や悲劇を隠しているがそうしたものさえ自己決定で甘受したようなたくましさが期待される。けれども、これって男性(近代とでも宗主国とでもマジョリティとでも)の勝手な妄想っぽいが、『菊とギロチン』では女たち、とりわけ家族や仲間を日本人自警団による虐殺で喪った朝鮮人の十勝川には、いや、前近代的な家制度に弄ばれ暴力を受ける花菊にも、きっちりこの社会の仕組みが見えていて、それがどのように襲ってくるかもはっきりとわかっている。ただ若い生命力にまかせて甘受しているわけではない。彼女たちはたしかに「社会」に生きていて、その底辺に閉じ込められているところがちゃんと見える。もちろんそれは、花菊や十勝川の現実を救いはしない。アナキストたちの自由の後ろにも、変えられない「社会」が見えている。だからこそ、一座や青年たちが大勢で浜辺でくつろぎ、沖縄の音楽に合わせて踊り、飲み食う、いつ終わるかわからないレイヴのようなシーンが幻想的でこの世とは思えない幸福な時間となる。見えない牢獄に捕らえられていて、それでも心はいつでも自由に遊びまわる。その遠近感というのか、立体感というのか、感情の描かれ方の豊かさにつながっているように、私には感じられる。私は“激情”に弱いのだと思う。「強くなりたい」「強くなりたい」という、その切なさに、100年後の私も身がよじれる。
[8/21編集部追記:人名表記に誤りがありましたので、訂正いたしました。謹んでお詫び申し上げます]