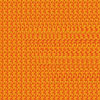1.Joy Orbison / Shrew Would Have Cushioned The Blow EP | Aus Music
 "UKガラージ"がテムズ川から南に位置するクロイドン近郊で"ダブステップ"へとトランスフォームしたのは周知の通りである。そこからしっかりと広がって、あるいはインターネットや媒体などを通してウイルスの如く目まぐるしい速度で感染していったわけだ。いまは亡きクロイドンの伝説的レコード店〈Big Apple〉から育っていったダブステップの先導者たち――スクリーム、ハイジャック、ローファーなども、"ガラージ"というフィルターを通り、インスパイヤーされている。実は筆者は2001年から2004年までのあいだのロンドン在住中、サウスロンドンのクラハムノースに住んだことがある。が、当時サウスロンドンでこのようなムーヴメントが起こっていようとは知る由もなかった。たしかにクロイドンが位置する南ロンドン周辺は、古くからジャマイカン・ミュージックやジャングル、ドラムンベース、ガラージの恩恵を受けた音楽が豊富なエリアではあるが......。
"UKガラージ"がテムズ川から南に位置するクロイドン近郊で"ダブステップ"へとトランスフォームしたのは周知の通りである。そこからしっかりと広がって、あるいはインターネットや媒体などを通してウイルスの如く目まぐるしい速度で感染していったわけだ。いまは亡きクロイドンの伝説的レコード店〈Big Apple〉から育っていったダブステップの先導者たち――スクリーム、ハイジャック、ローファーなども、"ガラージ"というフィルターを通り、インスパイヤーされている。実は筆者は2001年から2004年までのあいだのロンドン在住中、サウスロンドンのクラハムノースに住んだことがある。が、当時サウスロンドンでこのようなムーヴメントが起こっていようとは知る由もなかった。たしかにクロイドンが位置する南ロンドン周辺は、古くからジャマイカン・ミュージックやジャングル、ドラムンベース、ガラージの恩恵を受けた音楽が豊富なエリアではあるが......。
"ガラージ"の未来を担い、ポスト・ガラージの最左翼と称される20代前半の若者が昨年クロイドンからまた現れた。たった1曲により世界中を席巻してしまったジョイ・オービソン――本名はピート・オーグラディ(Pete O'Grady)という青年のことで、2009年の代表的なトラックとして取り上げられる「ハイフ・マンゴ(Hyph Mngo)」を発表したプロデューサーである。アーバン・サウンドのセンスとアイデアとクロイドンならではのサブカルチャー、そして"ガラージ"......まさにこれぞ"ミューテーション(突然変異)"というに相応しい音楽である。
ジョイ・オービソンは、12歳からDJをはじめている。ハウスやUKガラージがその中心だった。そこから、エレクトロニック・ミュージックの知識を貯え、多様な音楽性のDNAを受け継いでいる。ゆえに彼がアーバン・ベース・ミュージックのネクスト・レベルを提唱するのも必然かもしれない。 最近では、ホセ・ジェームスの「ブラック・マジック」、フォ ーテットの「ラブ・クライ」などのリミックスでも評価を高めている。
今作「The Shrew Would Have Cushioned The Blow」は、〈シンプル・レコーズ〉主宰のウィル・ソウル(Will Saul)とフィンク(Fink:〈ニンジャ・チューン〉所属)のふたりが運営しているレーベル〈Aus Music 〉からのリリースとなった。トレブルやミドルレンジがあまり広く用いられないサブ・ベース主体のダブステップに反して、上質なトレブル・サウンド・コラージュがプログラムされている彼のニュー・ガラージ感覚が注がれている。
ひょっとしたら新たなサブジャンルの誕生かもしれない......ふたたびクロイドンから世界に向けて。そしてまたしても世界中で感染するのだろう。
2. Sbtrkt / 2020 | Brainmath
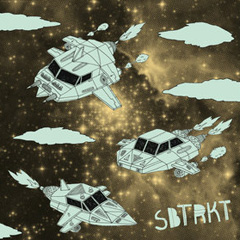 この連載の2月でも紹介したサブトラクト(Sbtrkt)だが、UKガラージ色が濃かった変則ビートの「ライカ(Laika)」に続いて、〈ブレインマス(Brainmath)〉からミニマル x ガラージを基調とした大傑作EPが届いたので紹介しよう。タイトル・トラック"2020"は、アートワークが暗示するように近未来の世界を模写したシネマティックなサウンドで、ブリアルの浮遊間溢れるダーク・エレクトロニカ感覚をさらに押し上げ、深い叙情性に富んだアンビエント・ビートなトラックになっている。4つ打ちを取り入れたハード・ミニマルなドライヴ感と音響派コズミック・ガラージとでも言えばいいのか、その素晴らしい"ジャムロック( Jamlock )"、ディープ・ミニマル・ダブと共鳴するインダストリアル・ベルリン・ステップな"ワン・ウィーク・オーヴァー"、エレクトリックなシンセ群が魅力的に交感し、パーカッシヴなビートがそれをフォローするガラージ・ステップ"パウス・フォー・ソート"......収録された4曲すべてが素晴らしい。
この連載の2月でも紹介したサブトラクト(Sbtrkt)だが、UKガラージ色が濃かった変則ビートの「ライカ(Laika)」に続いて、〈ブレインマス(Brainmath)〉からミニマル x ガラージを基調とした大傑作EPが届いたので紹介しよう。タイトル・トラック"2020"は、アートワークが暗示するように近未来の世界を模写したシネマティックなサウンドで、ブリアルの浮遊間溢れるダーク・エレクトロニカ感覚をさらに押し上げ、深い叙情性に富んだアンビエント・ビートなトラックになっている。4つ打ちを取り入れたハード・ミニマルなドライヴ感と音響派コズミック・ガラージとでも言えばいいのか、その素晴らしい"ジャムロック( Jamlock )"、ディープ・ミニマル・ダブと共鳴するインダストリアル・ベルリン・ステップな"ワン・ウィーク・オーヴァー"、エレクトリックなシンセ群が魅力的に交感し、パーカッシヴなビートがそれをフォローするガラージ・ステップ"パウス・フォー・ソート"......収録された4曲すべてが素晴らしい。
サブトラクトは最近はリミックス・ワークも好調で、オリジナルにいたっては発表するたびに新たな試みが具体化されている。彼もまた、新世代の旗手としてジャンルレスな活動をしていくだろう......と言うよりすでに各方面で話題だが......。いずれにせよ、これこそ近未来のダブステップである。と同時に、実にDJフリンドリーなサウンド・パックでもある。
3. Actress / Machine And Voice | Nonplus
 〈ノンプラス〉とは、ディープでアトモスフェリックなドラムンベースをリリースしていたインストラ:メンタル(Instra: Mental)主宰のレーベルである。インストラ:メンタルは、2009年に〈ノンプラス〉を立ち上げ盟友ディーブリッジ(dBridge)とともに「ワンダー・ウェアー/ノー・フューチャー」をリリースすると、続いてインストラ:メンタルの「ウォッチング・ユー/トラマ」を発表、シーンにディープ・ドラムンベースとでも呼ぶべき新風を巻き起こしている。ところが、2009年中頃からダブステップへとシフトしていくのである......もっともインストラ:メンタルの"音質"と"ダブステップ"との相性が抜群であったのは明らかだったのだが......。とにかく、彼らはダブステップへの転身により、アーティストとしてより輝き放ったのである。
〈ノンプラス〉とは、ディープでアトモスフェリックなドラムンベースをリリースしていたインストラ:メンタル(Instra: Mental)主宰のレーベルである。インストラ:メンタルは、2009年に〈ノンプラス〉を立ち上げ盟友ディーブリッジ(dBridge)とともに「ワンダー・ウェアー/ノー・フューチャー」をリリースすると、続いてインストラ:メンタルの「ウォッチング・ユー/トラマ」を発表、シーンにディープ・ドラムンベースとでも呼ぶべき新風を巻き起こしている。ところが、2009年中頃からダブステップへとシフトしていくのである......もっともインストラ:メンタルの"音質"と"ダブステップ"との相性が抜群であったのは明らかだったのだが......。とにかく、彼らはダブステップへの転身により、アーティストとしてより輝き放ったのである。
転身したとはいえ、その作品の大半は、トライバル・ステップやドラムンベース・トラックの作品でお馴染みの、アトモスフェリックなテッキー・ダブステップである。現在彼らはコズミック・ステッパー、エーエスシー(ASC)と一緒にアルバムを創作中とのこと......まったく楽しみな話と言うか、DJセットにどう組み込むか期待は膨らむばかりだ。
そして、レーベル5枚目となったリリースは、先述のジョイ・オービソン「The Shrew Would Have Cushioned The Blow」のリミックスも務めたアクロレス(Actress)である。アクトレス(女優)......と言っても男性プロデューサーで、彼の本名はダレン・J・カニンガム(Darren J Cunningham)というのだが。
ビート職人としても名高い彼は、独特のビート・カットやハッシュする技術により、秀逸なエクスペリメンタル・トラックを世に送り出している。2004年にレーベル〈Werk Discs〉をスタートさせ、デビュー作「ノー・トリックス」を発表している。デトロイティシュなビート・マエストロとの好評価を受け、2008年には、ファースト・アルバム『ヘイジービル(Hazyville)』、2009年にはなんとトラスミー(Trus'me)率いるハウス・レーベルの〈プライム・ナンバー〉からディープな傑作「ゴースツ・ハブ・ア・ヘブン(Ghosts have a heaven)」をリリース、その多才ぶりを如何なく発揮している。
今作「マシーン・アンド・ボイス」は、彼の新境地とも言うべきエレクトロな高音色を多用した新感覚なビートスケープだ。一見ごくありふれたビートメインのトラックのように感じたのだが......聴いていくとビートのプログラミング構成がランダムかつグルーヴィーにどんどん変化していく。予測不能に陥るエクスペリメンタルなこのトラックは、フライング・ロータスをどこか彷彿させるのだ。ハッシュされたヴォーカル・サンプルの注入具合といい、奇才の風格が漂う彼ならではのビート・コラージュである。
4. Von D & DJ Madd / U / It's Over | Boka Records
 いまもっともホットな......と言うか、流行っている......と言うか、制作者が目指しているといったほうが適切かもしれない。ダブステップのサブジャンルとして絶大な支持を得ているアトモスフェリック・ダブステップという潮流である。ロンドンの現在の事情に詳しい友人からそう聞いた。つまり、数年前のブリアルやコード9のようなアトモスフェリックな曲調は、あったことはあった......が、しかし、それを飲み込む程のダークな質感やインダストリアル・ノイズ・スケープといったものが上回っていたため、純粋の"アトモスフェリック"と言うものが流行りだしたのは、ここ最近に至っての話ではないであろうかと思う。どこか......このようなひとつのジャンルが派生していった流れは......と考えたとき、まったく同じ現象が時代を経ていま起こっていると気付いたのである。これは、90年代の中期に一世を風靡したドラムンベースのサブジャンル"アートコア"である。
いまもっともホットな......と言うか、流行っている......と言うか、制作者が目指しているといったほうが適切かもしれない。ダブステップのサブジャンルとして絶大な支持を得ているアトモスフェリック・ダブステップという潮流である。ロンドンの現在の事情に詳しい友人からそう聞いた。つまり、数年前のブリアルやコード9のようなアトモスフェリックな曲調は、あったことはあった......が、しかし、それを飲み込む程のダークな質感やインダストリアル・ノイズ・スケープといったものが上回っていたため、純粋の"アトモスフェリック"と言うものが流行りだしたのは、ここ最近に至っての話ではないであろうかと思う。どこか......このようなひとつのジャンルが派生していった流れは......と考えたとき、まったく同じ現象が時代を経ていま起こっていると気付いたのである。これは、90年代の中期に一世を風靡したドラムンベースのサブジャンル"アートコア"である。
先日、DOMMUNEで開催した「DBS・スペシャル」(これを開催するにあたり尽力して頂いた神波さん、サポートして頂いた野田さん、カーズ、宇川さん並びDOMMUNEスタッフの方々、そしてジンク&ダイナマイトMCの素晴らしいプレイに心よりお礼申し上げます)にて、野田さんが推奨した"変人"ゾンビーの2008年のアルバム『Where Were U In '92?』という作品名が語るように、彼はまさにジャングルに没頭していたわけだが、その後、同じようにクロイドンのダブステップ・リーダーたちもジャングル、とりわけアートコアはに創造性をよりかきたてられ、心躍らせていたことだろう。LTJブケムと〈グッド・ルッキング〉、オムニ・トリオ、〈ムーヴィング・シャドー〉やファビオの〈クリエイティヴ・ソース〉等々......である。そういえば、昨年、スクリームが実に面白い作品をリリースしている。シャイFX主宰の〈デジタル・サウンドボーイ〉からの「バーニング・アップ」だ。これがまた......ただのアートコアよりのレイブ・ジャングルなのだ。初期〈ムーヴィング・シャドー〉をそのままをスケッチしたようなその姿勢に、彼の少年時代の記憶を聴こえるようだ。アートコアが築いた偉大な足跡は、今日に至ってもさまざまなところで受け継がれているのである。
今回の作品「U / It's Over」は〈ボカ〉からリリースとなった。フランスのボンDとハンガリーのDJマッドによる共作だが、彼らの思考がアートコアに直結しているのは、この作品をもって証明できる。ブリージーな心地よさとファジーで温かみのあるその全体像は、コズミックな宇宙観とも違い、ファンクネス溢れるジャジー・ソール思考とも違う......やはりこれは、アートコア=アトモスフェリックなのだ。
5. Ramadanman / Ramadanman EP | Hessle Audio
 DJの視点からみて、このうえなく重宝する作品と言うのは多々ある。DJミックスによって素材の重なり具合によって作品の表情が180度変わったり、そこから予想だにしなかったグルーヴが生まれたりと......ロング・ミックス/ブレンドをこよなく愛す筆者の三台ミックス・スタイルにとって、小節単位でミックス部分を計算し、レコードをサンプルのように使うこの方法は、シンプルなサウンドほど変化させがいがあり、そこに"ハマる"貴重なものを見つける快感があるというわけだ。
DJの視点からみて、このうえなく重宝する作品と言うのは多々ある。DJミックスによって素材の重なり具合によって作品の表情が180度変わったり、そこから予想だにしなかったグルーヴが生まれたりと......ロング・ミックス/ブレンドをこよなく愛す筆者の三台ミックス・スタイルにとって、小節単位でミックス部分を計算し、レコードをサンプルのように使うこの方法は、シンプルなサウンドほど変化させがいがあり、そこに"ハマる"貴重なものを見つける快感があるというわけだ。
シンプルとはいってもごくありふれたトラックなら山ほどある。が、ここに、そうしたミックスのコンセプトに合致したトラックが、パンゲア(Pangaea)とラマダンマンのふたりが共同運営するディープ・ガラージ系のダブステップ・レーベル〈へッスル・オーディオ〉から出た。「パンゲアEP」に続いてリリースされたディープ・テッキー・リーダー、ラマダンマンのEPがそれである。ちなみにラマダンマンと言えば、〈へッスル・オーディオ〉の他、〈アップル・パイプス〉、〈セカンド・ドロップ〉、〈ソウル・ジャズ〉などからダブステップをリリースしている20歳そこそこの若手プロデューサー。今回は、高まる期待のなかのリリースである。
さて、それで1曲目に収録された"I Beg You "「I Bet You」だが、パーカッシヴなビートにシンプルなベースが呼応し、サイドエフェクト的に絡むヴォーカル・サンプルがうまいアクセントになっている。テック×ガラージに対しての回答とも言うべきリズム・プロダクションだ。"No Swing"はタイトル通り、スイングしない。ドラムの乱打にエレクトロニカ調のエフェクト・ピアノ、ピョンピョン跳ねるゲーム音を混ぜて、実に混沌とした、スイングしそうもない音である。が、しかし、これがまた実に面白いように展開しているのだ。「ノースイング=リズミカルでなく調子が悪い」とは良く言ったもので、これはコミカル感覚なノースイング・ステップだ。
続く"A Couple More Years"も、ちょっとおかしなチープでバウンシー・ベースがメインラインのトラックだ。意外とミニマルにミックスすれば、新たなテイストが現れるかもしれない。最後の"Don't Change For Me"は彼のルーツを掘り下げているようだ。レイヴ・ジャングルのアーメン・ビーツをプログラミングしているあたり、彼の好みがうかがえる。ラマダンマンはテッキーではあるが、ミニマルなトップ・アーティストたち(スキューバ、マーティン、2562等々)とはまた一線を画したセンスがあるのだ。明らかに"並"ではないその変化に富んだプロダクションは、いまだ底が見えそうにない......。ヴィラロボス、フランソア・K、ジャイルス・ピーターソンらがラマダンマンのトラックをスピンするところに、彼のユニークな存在感が証明されている。




 photo : Yuki Kuroyanagi
photo : Yuki Kuroyanagi photo : Yuki Kuroyanagi
photo : Yuki Kuroyanagi












 同期型ラップトップ・ライヴ・ユニットの次に紹介する1枚は、一転して"人力コズミック・ハウス/ディスコ"とでも言うべき作品である。
同期型ラップトップ・ライヴ・ユニットの次に紹介する1枚は、一転して"人力コズミック・ハウス/ディスコ"とでも言うべき作品である。 まず最初に断っておかなければならないのは、高校3年の夏休みにわざわざ地元の青森から上京し、宇田川町のレコード・ショップでアンダーグラウンド・レジスタンスのバックパックを購入し、現在に至るまでほぼ1日も欠かさず使用し続けているような僕が冷静で客観的な批評眼をもってURの音楽を語ることができるか、非常に怪しいということだ。もちろん、できる限りの努力は試みるが......。
まず最初に断っておかなければならないのは、高校3年の夏休みにわざわざ地元の青森から上京し、宇田川町のレコード・ショップでアンダーグラウンド・レジスタンスのバックパックを購入し、現在に至るまでほぼ1日も欠かさず使用し続けているような僕が冷静で客観的な批評眼をもってURの音楽を語ることができるか、非常に怪しいということだ。もちろん、できる限りの努力は試みるが......。

 アンダーグラウンド・レジスタンスを母体とするバンド・ユニット、ギャラクシー2ギャラクシーやロス・エルマノス(Los Hermanos)のメンバーでもあり、イーカン(Ican)名義でも活躍するS2ことサンティアゴ・サラザールがデトロイトのアーロン・カール(Aaron-Carl)の〈ウォールシェイカー〉レーベルからリリースした新作は、現在のUSアンダーグラウンド・クラブ・シーンに対するUR流儀での痛烈な問題提起である。イーカン名義のラテン・フレイヴァーなサウンドは影を潜め、感情を押し殺したようにダークなフェンダーローズの反復フレーズとフランジャーによって金属感を増したハイハットに添えられるのは「車を停めるのに20ドル、入場するのに25ドル、ドリンクを買うのに12ドルもかかる」というコマーシャリズムに傾倒したクラブ・シーンを批判するポエトリー・リーディングだ。サラザールはこう続ける「一体アンダーグラウンドに何が起こってるんだ?」
アンダーグラウンド・レジスタンスを母体とするバンド・ユニット、ギャラクシー2ギャラクシーやロス・エルマノス(Los Hermanos)のメンバーでもあり、イーカン(Ican)名義でも活躍するS2ことサンティアゴ・サラザールがデトロイトのアーロン・カール(Aaron-Carl)の〈ウォールシェイカー〉レーベルからリリースした新作は、現在のUSアンダーグラウンド・クラブ・シーンに対するUR流儀での痛烈な問題提起である。イーカン名義のラテン・フレイヴァーなサウンドは影を潜め、感情を押し殺したようにダークなフェンダーローズの反復フレーズとフランジャーによって金属感を増したハイハットに添えられるのは「車を停めるのに20ドル、入場するのに25ドル、ドリンクを買うのに12ドルもかかる」というコマーシャリズムに傾倒したクラブ・シーンを批判するポエトリー・リーディングだ。サラザールはこう続ける「一体アンダーグラウンドに何が起こってるんだ?」 DJプレイ、とりわけひとりのDJが朝までプレイするようなロングセットは、レコードによって紡がれるその世界観をしばしば旅に例えられる。今回最後に紹介するのは、そういう意味では"旅情"を高めるのに最適な1枚だ。
DJプレイ、とりわけひとりのDJが朝までプレイするようなロングセットは、レコードによって紡がれるその世界観をしばしば旅に例えられる。今回最後に紹介するのは、そういう意味では"旅情"を高めるのに最適な1枚だ。