音楽は気持ちいいほうが良いに決まっている。気持ち良さなしで生きることは不可能だと、UKはブリストルのヤング・エコーのメンバー、サム・キデルは2016年のQuietusのインタヴューで言っている。が、気持ち良さだけでは思考停止する。アドルノのそんなところに影響を受けてしまったキデルは、「快適さのために生まれた音楽」=「ミューザック」を反転させ、快適であると同時に政治的という『Disruptive Muzak(破壊的ミューザック)』なるコンセプトを練り上げた。いわく「アンチ資本主義アンビエント」。いかなるアンビエントも政治から逃れられないというのがキデルの意見だ。
「破壊的ミューザック」においてキデルは、マーク・フィッシャーが『資本主義リアリズム』のなかでこれぞ中心なき資本主義のカフカ的迷宮だと説明した「コールセンター」のやりとりをサウンドコラージュした。物事がすべて合理的に、そしてスムーズにいくように見えながら反対側の現実へとすり抜けていくような感覚、何度もかけ直しながらなにげに希望が薄れていくその反対側の現実──〈The Death of Rave〉からリリースされた「破壊的ミューザック」は、この感覚をうまく捉えている。
本国では昨年末にリリースされ、今年に入って日本のレコード店でも出回った『シリコン・イアー』なる2曲入りは、サム・キデルのコンセプチュアルなエレクトロニック・ミュージックのあらたなる成果だ。
アナログ盤のインナーでは、それぞれの曲のタネ明かしが記されている。A面の“Live @ Google Data Center”は、曲目の通り「グーグル・データ・センターにおけるライヴ」……というわけではない(笑)。さすがにそれは無理だし、これはあくまでも「そのシミュレーション」、ということである。
キデルは、グーグルのサーバ・ルームの写真および建築図面から“場”を推測し、ソフトウェアを使って“場”(スペース)の音響学的特性を推測した。彼はこれを「擬態ハッキング」(mimetic hacking)と呼んでいる。
そのサウンドをたとえるなら、オウテカの「アンチEP」の21世紀版ないしはレイヴ系IDMとでも言おうか、「破壊的ミューザック」もそうだったけれど、キデルの音楽はあらゆるエレクトロニック・ミュージックの混合である。前作がアンビエント/ヴェーパーウェイヴに焦点が当てられていたとしたら、今回の“ライヴ@グーグル・データ・センター”はダンス・ミュージックに寄っている。
グーグルやヤフーといった検索機能とニュース・サイトを併せ持つオンライン世界における問題点、おもにパーソナライズドに関する議論は、イーライ・パリサーの『フィルター・バブル インターネットが隠していること』(井口耕二訳/早川書房)という本に詳しい。利用していたつもりが、じつはインターネットに閉じ込めらているんじゃないかという感覚があるとしたらそれはどこから来ているのかということを掘り下げた本だ。キデルはそのヒンヤリとヌメっとした不気味な感覚をサウンドで表現しつつも、無機質な空間に不釣り合いなダンス・ミュージックのビートをぶつけている。かなり歪んだものではあるが。
もう片面の“Voice Recognition DoS Attack”は、音声認識ソフトの誤作動(弱点)を応用したオーディオ・パッチに基づかれている。声を使ったアンビエント系IDMで、ロバート・アシュレー(『前衛音楽入門』参照)風ではあるが、遊び心たっぷりに展開している。
それにしても……たった2曲で2400円は高いぞ! しかしまあ、それはともかく昨年ローレル・ヘイローのアルバムを出したフランスのこのレーベル〈Latency〉は要チェックだ。ほぼ同時にリリースされたMartina Lussiのアンビエント・アルバム『Diffusion Is A Force』も良かった。

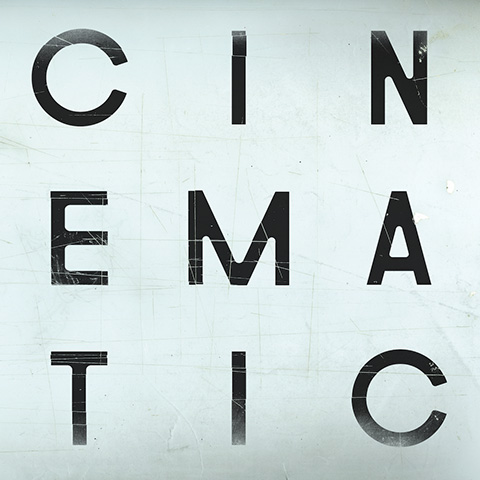


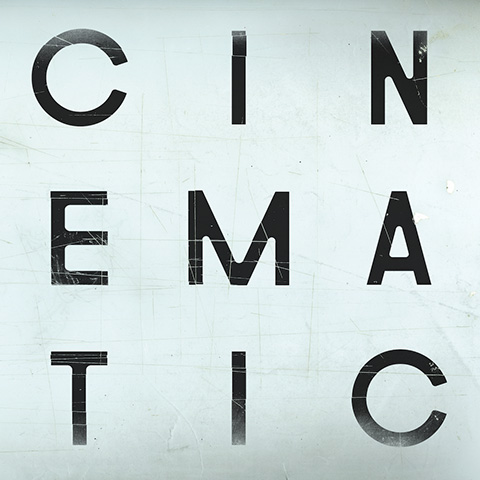 ザ・シネマティック・オーケストラの12年振りの最新アルバム『TO BELIEVE』が3月15日に発売決定。
ザ・シネマティック・オーケストラの12年振りの最新アルバム『TO BELIEVE』が3月15日に発売決定。










