 PunPunCircle Pun! SPACE SHOWER NETWORK |
「下北沢のパンダ・ベア」ことPunPunCircleが、夏の陽光をおだやかに遮るひさしをつくってくれるだろう。爪弾かれるギターから心地よく立ちあがっていく、ユーフォリックなサイケデリア──それはたとえば、アニマル・コレクティヴの『キャンプファイア・ソングス』や『サング・トングス』が、アンドリュー・ヨークのような卓越した演奏性やアレハンドロ・フラノフなどの音響的アプローチとすれ違いながら、無国籍的かつ土着的なポップ・ソングとして、いいしれぬ郷愁を誘いにくるようでもある。New Houseのギタリストとしても知られるPun Punは、バンドが表していたようなドリーミーなサイケ感覚をアシッド・フォーク的に展開しているとも言えるのかもしれない。それはとても小さく親密な空間をあたためる音であると同時に、たくさんの世界に向かって開いている音でもある。
先月はそのPunPunCircleによる待望のファースト・アルバム『Pun!』がリリースされ、今月末にはmitsumeも出演するライヴ・イヴェントが予定されている。心地よくリラックスした時間になるに違いない。理屈を書いてしまいましたが、理屈を抜きに楽しみましょう!

NO MUSIC, NO LIFE. SPECIAL PARTY vol.2
開催日時
2016年07月29日(金) 19:30
場所
渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」
出演
mitsume
PunPunCircle
参加方法
OPEN 18:30/START 19:30
TICKET ¥1,620(tax in)
※入場時に1drink代¥500頂きます。
※整理番号有り
※タワーレコード渋谷店のお支払いは現金のみとなります。ポイントカード、各種クーポン、金券、クレジットカード、電子マネーなどはご利用いただけませんのでご了承ください。
6月27日(月)10:00よりタワーレコード渋谷店1Fレジにてイベントチケット販売開始。
チケットをお持ちの方はイベント当日のOPEN15分前にタワーレコード渋谷店1F階段前に集合して頂きます。
●チケットのご購入はタワーレコード渋谷店の1Fレジでのみお受けしています。お電話やオンラインではお受けしていません
●小学生以上のお客様はチケットが必要となります
●会場周辺での徹夜等の行為は、固くお断りしております
●チケットの販売は定員に達し次第終了いたします
●チケットの有無については、画面上の表示と時差が生じることがありますので、詳しくは店頭にお問合せください
●本券はいかなる事情(紛失・破損・持ち忘れ)があっても再発行しません
●転売禁止。転売に関するトラブルについての責任を負いません
●入場前に半券を切り離すと無効となります
●係員の指示によりご整列いただき入場番号順にご入場頂きます
●当日の状況により、START時間が若干前後する場合がございますので、集合時間をお守りください
●集合時間に遅れた場合はお手持ちの入場番号に関わらず最後尾のご入場になる場合があります
●本券は一枚につき1名様指定日時に限り終演まで有効です
●都合によりイベント内容の変更・中止をさせて頂く場合もございますのでご了承下さい
●店内での飲食は禁止となっております
●許可された場合以外は、会場内に録音・録画・複写に使用する機材及び酒類・危険物の持ちこみは固くお断りします
●会場内で係員の指示及び注意事項に従わない場合、入場をお断りすることがあります
●会場内で係員の指示及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません
 ■vol.18 contents
■vol.18 contents






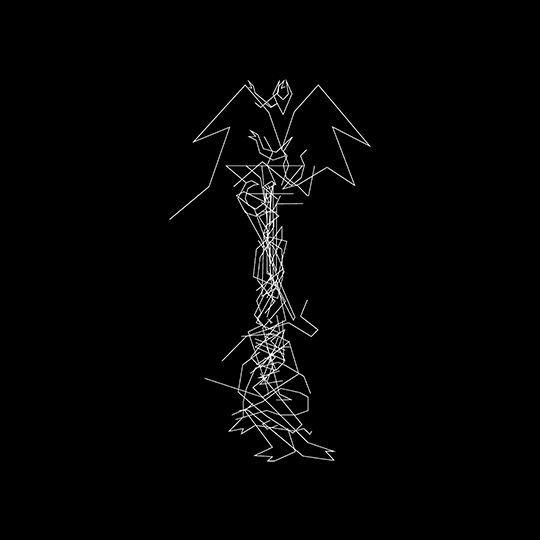
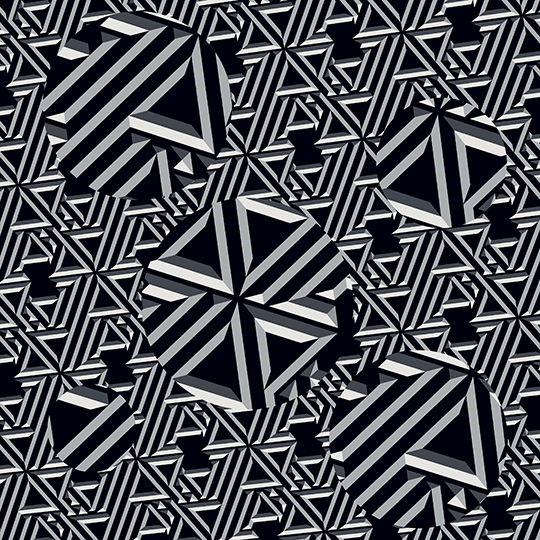



 ボトムの効いたキックとおぼろげなハイハットによるビートに神々しく降り注ぐパッドが印象的。スネアやクラップが使われていないので、浮遊感が際立っている。それに対して重厚なベースラインがコントラストとなっていて心地よい。
ボトムの効いたキックとおぼろげなハイハットによるビートに神々しく降り注ぐパッドが印象的。スネアやクラップが使われていないので、浮遊感が際立っている。それに対して重厚なベースラインがコントラストとなっていて心地よい。 深淵へゆっくりと下降していくかのようなディープな1曲。異なる周期で揺らぐパッドが重なり合うことで徐々に大きなうねりを生み出していく。擦り付けるようなハイハットが鼓膜と意識をかきむしる。
深淵へゆっくりと下降していくかのようなディープな1曲。異なる周期で揺らぐパッドが重なり合うことで徐々に大きなうねりを生み出していく。擦り付けるようなハイハットが鼓膜と意識をかきむしる。
 タイトに打ち込まれるエレクトロ・ビートの間をパッドがシンセベースと連動しながら吹き抜けていく。中盤のブレイク部ではメロディ素材と絡み合いながら程よくノスタルジックな空気をもたらしてくれる。
タイトに打ち込まれるエレクトロ・ビートの間をパッドがシンセベースと連動しながら吹き抜けていく。中盤のブレイク部ではメロディ素材と絡み合いながら程よくノスタルジックな空気をもたらしてくれる。
 いつまでも漂っていられる浮遊感がたまらない。その肝は、じわじわと解放されていくバックグラウンド・パッドの爽快なテクスチャー変化と、アシッドサウンドになりそうでならないベース・シーケンスの焦らしだ。
いつまでも漂っていられる浮遊感がたまらない。その肝は、じわじわと解放されていくバックグラウンド・パッドの爽快なテクスチャー変化と、アシッドサウンドになりそうでならないベース・シーケンスの焦らしだ。
 長く減衰する残響音がパッド代わりとなって大きく起伏するベースラインと共に鼓動する壮大なトラック。アクセントとしてホイッスルのように吹き付けられるシンセにハッとさせられる。
長く減衰する残響音がパッド代わりとなって大きく起伏するベースラインと共に鼓動する壮大なトラック。アクセントとしてホイッスルのように吹き付けられるシンセにハッとさせられる。




