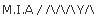オトコ的Classics
1 |
Talking Heads - This Must Be The Place (Naive Melody) - Sire |
|---|---|
 2 |
Chris Isaak - Baby Did A Bad Bad Thing (O.S.T:Eyes Wide Shut) - Reprise Records |
 3 |
Heat Wave - Mind What You Find - Epic |
 4 |
Romanthony - Hold On - Roule |
 5 |
Anne Dudley And Jaz Coleman - Minarets And Memories (12'Dance Mix) - China Records |
 6 |
Robert Hood - Who Taught You Math'Edit' - Peace Frog Records |
 7 |
CTI - Dancing Ghosts (O.S.T: Elemental 7) - Double Vision |
 8 |
Floating Points - Love Me Like This - R2 Records |
 9 |
Ash Ra Tempel - Ain't No Time For Tears (Sacred Rhythm Mix) - Raimo Symphories |
 10 |
J Dilla - So Far To Go Feat. Common & D'Angelo - BBE |