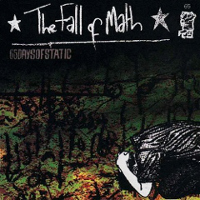V.A. アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック |
ここ1ヶ月半ほど、「ありの~ままの~すがた見せるのよぉ~」と我が家の6歳児がかしましい。もちろん彼女が歌うのは、大ヒット公開中のディズニー・プリンセス映画『アナと雪の女王』の主題歌“レット・イット・ゴー”日本語版です。アンタそれ以上ありのままになってどうするんだ……と突っ込んだところで、「何も怖くない。風よ吹け(I don't care. what they're going to say.Let the storm rage on.)」と、こちらがフローズンされそうな勢い。「友だちの話聞いてたらもう一度見に行きたくなった!」と、彼女の『アナ雪』愛は深まるばかりです。彼女の通う小学校ではサビのフレーズをどれだけ大声で歌うか、もしくはヘン声が歌うかを競うのが女の子の間で大流行。ブランコに乗りながら「アロハ~バイバ~イ」とオラフ(雪だるま)のモノマネをしたり(そんなセリフありましたっけ? 母はうろ覚え……)、オラフのギャグ「てかハンスって誰~?」を繰り返したりするのも流行っているそう。
ジブリ、ディズニー、ピクサー……これまで数々の子ども向け映画を我が子といっしょに観てきましたが、「クラス中の女子が一つの映画の話題で持ちきり」というほどに子ども界を席巻した映画はなかったように思います。日経ビジネスONLINEによれば、すでにアニメ映画として『トイ・ストーリー3』を抜く全世界歴代1位の興行収入を記録し、実写映画を含むランキングでも歴代6位なのだとか。我が子たちのフィーバーぶりに、この記録的な大ヒットをしみじみ実感しています。
大ヒットの理由については識者がすでにさまざまな論考を重ねていることでしょうが、少なくとも女児にウケた理由は識者ではない私にもわかります。まず、〈M-1グランプリ〉の決勝大会なみにギャグの手数が多いこと。オラフの体を張ったギャグの数々のおかげで、映画館では子どもたちの笑い声がひっきりなしに鳴り響いていました(女の子は小さい頃からお笑いが大好き!)。そして何より重要なのが、女の子同士の連帯を描いていることでしょう。
4~7歳のプリンセス期にある女の子は、とにかく女の子が大好き。これは女児を持つ親の多くが実感することではないでしょうか。女の子同士で「○○ちゃんだいすきだよ」「LOVE」などとカラフルなシールやハートマークをちりばめた手紙を毎日のようにやりとりし、遊ぶのももっぱら女の子。テレビを観ていても、少年アイドルやイケメン俳優より少女アイドルやヒロイン女優に夢中です。彼女たちがピンクやドレス、ティアラ、妖精といったキラキラデコデコひらひらしたものを好むのは、それが「女の子」を象徴しているからなのです。
女の子のプリンセス願望というと、王子様待ちの他力本願、受動的な生き方の象徴としてとかくやり玉に挙げられがちですが、幼い女の子は王子様など眼中にありません。21世紀以降着実に売り上げを伸ばし、現在では2万6千点以上のグッズを抱える「ディズニープリンセス」ブランドも、プリンセス映画から王子様を排除してプリンセスだけで世界観を固めたからこそ、女児のハートをつかんだのです。
日本でも現代女児の心をとらえてはなさないTVアニメは、『プリキュア』シリーズに『アイカツ!』など、女の子同士の連帯の描写に重きを置いたものばかり。白雪姫とシンデレラはグッズの中で並んでいても、手に手を取って戦ったりはしませんでしたから、プリキュアのほうが進んでいるともいえます。見方を変えれば、『アナと雪の女王』の女児人気は、「ディズニープリンセス」がプリキュア要素を取り入れた結果とも言えるのではないでしょうか。

『アナと雪の女王』
監督:ジェニファー・リー、クリス・バック
製作年 / 国:2013年 / アメリカ合衆国
配給:ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
ハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話『雪の女王』を原案とした長編アニメ映画。王家の姉妹が試練を乗り越え、凍った国を救い、自身らの愛を取り戻す顛末をスペクタクルに描くディズニー最新作。日本国内でも大ヒットを記録し、公開7週めにして累計動員970万人、興行収入121億円を突破して社会現象化しつつある。映画本体に加えてサントラ盤も好調にセールスを伸ばし、とくにMay J.が歌う主題歌“レット・イット・ゴー”は、国民的なヒット・ナンバーとして連日街頭やテレビなどを華やがせている。
なぜ女児はこれほどまでに「女の子」の世界に執着するのか。一説によれば、アイデンティティを確立する上で必要なプロセスだからだと言われています。自分が何者かであるかを意識せずに生きていくことは難しい。たいていの大人にとって性別は自明ですし、職業や周囲に認知された人格、あるいは「ボン・ジョヴィのモノマネをさせたら三国一」などの特殊技能でアイデンティティを保つこともできます。しかし通常の子どもは、そこまで確立されたアイデンティティを持ち合わせていませんし、生物学的性差への理解もあやふやです。そこで「性別を象徴するすてきな何か」に自らを同化させ、同じ性別を有する者同士で愛情を育むことで、アイデンティティ確立への第一歩を踏み出すのでしょう。男児がスーパーヒーローに自己同一化するのも同じことです(もちろん男女が逆転する場合もあるでしょう)。
ところで、女児が同性を好むのが自然な発達過程なのだとしたら、そこを当て込んだ女児向けの女の子連帯モノが昔からあってもよさそうなものです。しかし私の子ども時代の女児アニメといえば『キャンディ・キャンディ』『小公女セーラ』に代表されるように、けなげで無垢なヒロインが意地悪な同性にいじめられても耐え、お金持ちの男性に救われるというシンデレラ・ストーリーが王道でした(いじめ描写が苦手な私は女児アニメを避け、『機動戦士ガンダム』に入れ込んだものです)。富や権力が男性に握られている世界では、結婚で富を得るにしても仕事で成功するにしても、権力のある男性にすくい上げてもらうしかありません。つまりかつての女の子にとってのサクセスとは、自ら目標を立て努力し、他人と協力しながら何かを成し遂げることではなく、自分一人にスポットが当たること。そして男性に愛されるには、自意識や自我を隠し、無垢やけなげを装わなくてはいけない。女の自意識や自我は恥ずべきものであると教え込まれた女性たちは、他の同性の自意識や自我の攻撃に走ることもしばしばです。幼い頃に刷り込まれたこうした価値観は、女性たちの生きづらさの一因になっているようにも感じられます。
Be the good girl you always have to be 良い子でいなさい、いつもそうしてきたように
Conceal, don't feel, 隠しなさい、感情を抑えて
don't let them know 誰にも知られてはいけない
“レット・イット・ゴー”の歌詞の原文を読んだとき、真っ先に思い出したのは、フェイスブックの女性COOによって書かれた全米ベストセラー『リーン・イン』(シェリル・サンドバーグ)でした。同書がクローズアップしたのは、上昇志向や能力、自己主張を隠し、控えめにふるまうのが愛される「良い子」であると刷り込まれているばかりに、女性たちがチャンスを逃がしてしまうという問題です。上記の歌詞は氷を操る能力を隠すように言い聞かされて育った姉・エルサの孤独を描写するものですが、女性全般が感じがちな抑圧にも通じるのではないでしょうか。同書で紹介されている「ハイディ・ハワード実験」は、こうした抑圧の源となるバイアスを明らかにしています。実験内容は、実在する野心的な女性起業家が成功した過程を、ある学生グループに対しては男性名「ハワード」で、もう一つの学生グループには女性名「ハイディ」で、それぞれ読み上げるというもの。すると性別以外の情報はそっくり同じだったにも関わらず、ハワードは好ましい同僚と見なされ、ハイディは自己主張が激しく自分勝手で一緒に働きたくない人物と見なされたのです。単純に言ってしまえば、男性の場合は成功と好感度が正比例し、女性の場合はその逆ということなのでしょう。
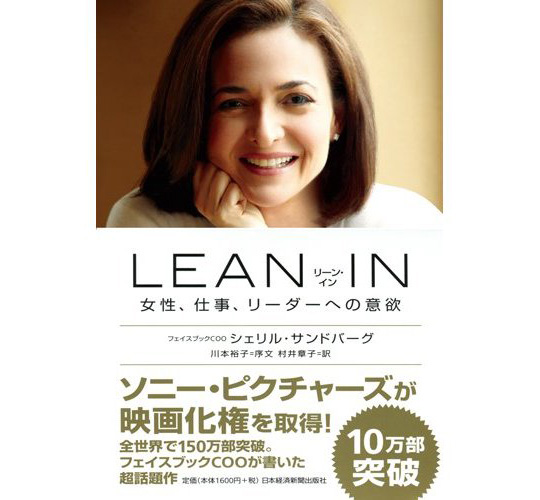
『リーン・イン 女性、仕事、リーダーへの意欲』(日本経済新聞出版)
シェリル・サンドバーグ著、村井章子訳
Amazon
著者のシェリル・サンドバーグ自身も、フェイスブックに転職した際、ライフルを構えたコラージュ写真がネットに掲載されるなど激しいバッシングにさらされたといいます(3章「できる女は嫌われる」)。「そして結局、いちばんいいのは無視することだとわかった。無視する。そして自分の仕事をするしかないのだ、と」。まさに「I don't care what they're going to say.Let the storm rage on.(もう皆に何を言われようとも気にしない。嵐よ吹き荒れるがいい)」という“レット・イット・ゴー”の歌詞のとおりです。
とはいえ、著者は「みんなに嫌われても全然オッケー!」とは言いません。「本音を言えば、チームの和を乱す女だとみなされるのではないか。文句ばかり言ういやな女だと思われるのではないか」とおびえ、意見を言うテーブルにつこうとしない女性たちに、本音でありながら怒りを招かない言い方はスキルとして習得できるとアドヴァイスしています(6章「本音のコミュニケーション」)。また、女性の能力を認めてくれる有力者が目をかけたくなるような実力を身につけ、信頼関係を築き、味方につけなさい、とも(5章「メンターになってくれませんか?」)。『アナと雪の女王』について、「エルサほどの能力があれば世界征服をすればよかったじゃないか。あの結末は日和ってる」「国民を楽しませるだけでは偉大な力の無駄遣いだ」という(主に男性の)感想をちらほら見かけます。たしかにエルサが男性であれば、「世界征服かっけー!」と力に憧れる男性たちが貢ぎ物を持ち寄り、その権力を目当てに女性たちが群がって、強者である自分に満足しながらつつがなく暮らしてゆくことができたかもしれません。しかし、エルサはあのままでは国民とともに飢え死にするほかなかったでしょう。強者ゆえの孤独は男性にもあるかもしれませんが、女性のそれは死に直結しかねません。エルサの物語は、能力を隠しきれなかったことで孤独に陥りながらも、わかってくれる者と信頼関係を築き、その能力を隠すのではなく他者の利になるようにコントロールすることで居場所を獲得したシェリルの人生に似ています。女性が健全なアイデンティティを育むには、まずは抑圧をはねのけて自我のありようを肯定し、その上で信頼できる他者に受け入れられる術を探るという2段階のプロセスをたどる必要があるのです。そう考えれば、プリンセス映画でありながら女児モノの枠を超えて大人の女性を虜にし、世界的に大ヒットした理由も想像できます。
もちろん、一般女性はエルサやシェリルのような特別な能力を有していないかもしれません。しかし「権利を主張したり賢しらにふるまったりしたら“ブス”“フェミ”として社会から排除するぞ。そうすれば生きていけないぞ」という恐怖にコントロールされ、理不尽をニコニコやり過ごしてきた女性たちも、SNSの発達で自己表現したり、同性と連帯する楽しさを知りつつあります。劇場で声を揃えて「レリゴ~」と歌う女性たちは、ひととき小さな女の子になって「女の子大好き! 自分大好き!」という自己肯定感を育み直すことで、嵐吹き荒れる社会に立ち向かう活力を得ているのかもしれません。