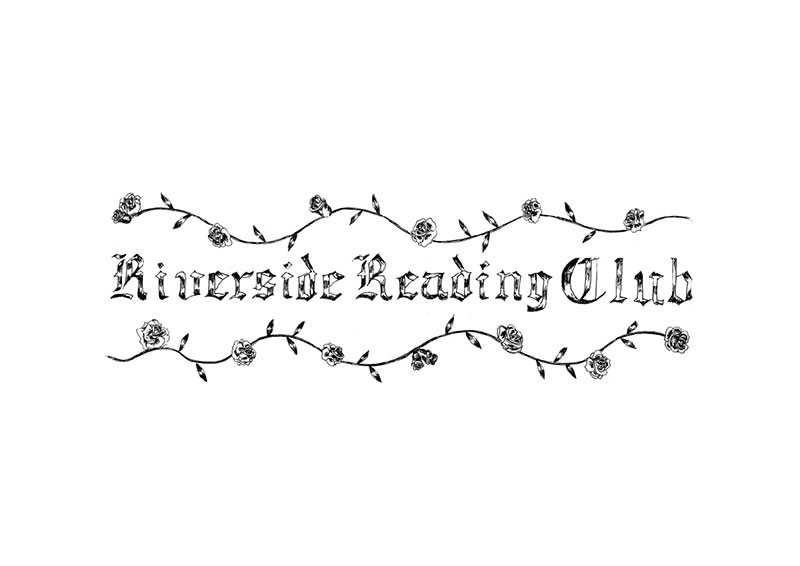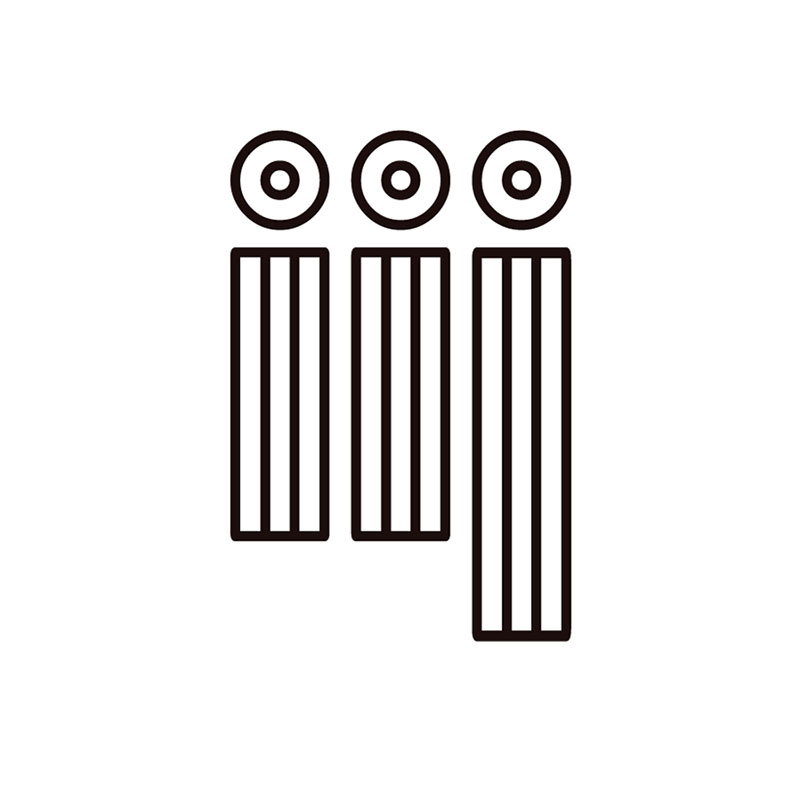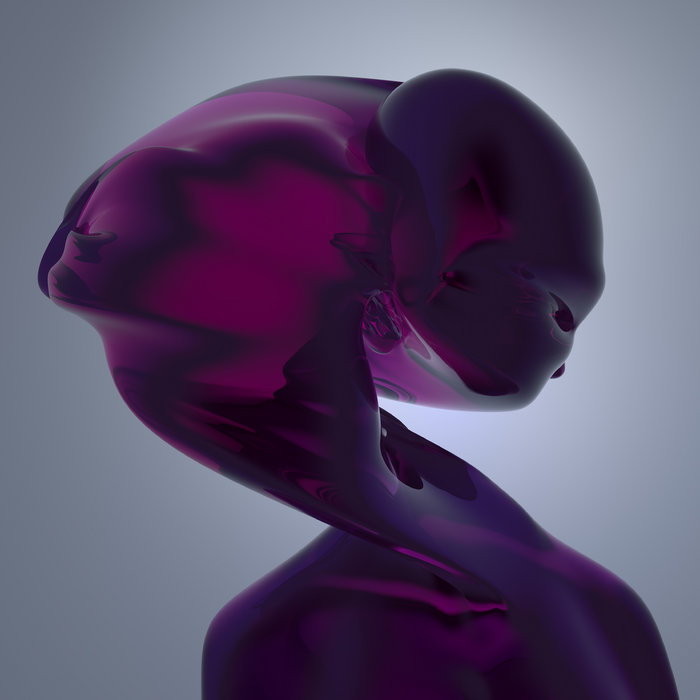現代の日本のダークサイドを風刺しているともっぱら評判の遊佐春菜のアルバム『Another Story Of Dystopia Romance』、1曲目の“everything, everything, everything”が配信を開始した。彼女の〝ディストピア・ロマン〟をぜひ聴いてみてください。
Apple Music | Spotify
アルバムはCD2枚組で、1枚はオリジナル・ミックス盤、もう1枚はリミックス盤になる。リミキサー陣は、DJ善福寺、SUGIURUMN、Yoshi Horino、Eccyといった〈kilikilivilla〉レーベルでお馴染みのベテラン勢が担当。アルバムは4月20日に発売予定。
遊佐春菜 / Another Story Of Dystopia Romance
KKV-120
4月20日発売予定
CD2枚組
税込3,300円
https://store.kilikilivilla.com/product/receivesitem/KKV-120

Disc 1 : Another Story Of Dystopia Romance
1. everything, everything, everything
2. ミッドナイトタイムライン
3. Faust
4. Night Rainbow
5. Escape
6. 巨大なパーティー
7. everything, everything, everything (beat reprise)
Disc 2 : Another Story Of Dystopia Romance Remixes
1. everything, everything, everything (beat reprise)(SUGIURUMN Remix)
2. 巨大なパーティー(DJ善福寺from井の頭レンジャーズ Remix)
3. Escape(ReminiscenceForest Remix)
4. Night Rainbow(House Violence & Yoshi Horino remix )
5. Faust(Satoshi Fumi Remix)
6. ミッドナイトタイムライン(XTAL Remix)
7. everything, everything, everything(Eccy Remix)
以下、レーベル資料から。
Remixerについて by 与田太郎
このアルバムが伝えようとする物語はクラブやパーティーが重要な舞台となっている。野外レイヴやパーティーで踊ることはこの行き詰まる日常からの解放だ、そして様々な場所からそこに集まる人々とのオープン・マインドなコミュニケーションは人生に大きな出会いをもたらしてくれる。
Have a Nice Day!のライブでフロアがモッシュピットだったことは偶然ではなく、そこに集まった人々による1時間にも満たない熱狂は彼らにとって日々を生きる糧だったはずだ。2020年以降消えてしまったパーティーやフロアの熱気がようやく今年取り戻せるかもしれない。
今作のプロデューサーである僕は90年代からパーティー・オーガナイザーとして、またDJとしてその熱気を求め続けてきた。Another Story Of Dystopia Romanceが90年代以降のダンス・カルチャーが生み出したサウンドから作られているのはそういう理由による。ならばそれぞれの楽曲のフロア向けのリミックスを作る必要があるだろう、というアイデアはすぐに実行された。
everything, everything, everything (beat reprise)(Sugiurumn Remix)
数々のパーティーを20年以上共に駆け抜けてきた盟友であり、変化の激しいシーンを生き抜いたベテランらしくないベテランSUGIURUMNは静かな熱気をきらめくようなエレクトロ・ビートの結晶に封じ込めた。
巨大なパーティー(DJ善福寺from井の頭レンジャーズ Remix)
90年代のワイルド・ライフを共に過ごした高木壮太は普段なら引き受けないリミックス、ダブの制作を2021年8月に亡くなったリー・ペリーの追悼ということで特別に引き受けてくれた。そのDJ善福寺from井の頭レンジャーズ名義のダブ・リミックスからは彼がいかに深く音楽に精通しているかを物語る。
Night Rainbow(House Violence & Yoshi Horino remix )
東京のハウス・シーンのライジング・スターHouse Violenceとワールド・ワイドなレーベルUNKNOWN SEASONをオーガナイズするYoshi Horinoがタッグを組んだリミックス、パーティーの現場に即した構成とシカゴ・テイストなビートとニューヨーク・マナーな展開は彼らが日々のパーティーで培ってきたダンス・ミュージックそのもの。
FAUST(Satoshi Fumi Remix)
90年代からプログレッシヴ・ハウスを追いかけてた僕にとってジョン・ディグウィードにフックアップされたSatoshi Fumiは特別な存在と言っていい。2022年現在、リアルタイムでワールド・クラスのプロデューサーが織りなす展開は見事としか言いようがない。彼の最新アルバムはディグウィードのBEDROCKからリリースされた。
ミッドナイトタイムライン(XTAL Remix)
Traks Boysとしても活躍するXTAL、近年の作品同様に流れで聴かせるのではなく瞬間を切り取るようなスタイルは歪み成分がまるで音の粒子のように広がるって聞こえてくる。バレアリックかつシューゲイズなタッチは彼ならではの作品となった。
everything, everything, everything(Eccy Remix)
かつてSLYE RECORDSを共に率いたトラック・メイカーは今またコンスタントに作品を発表している。オリジナル・アルバムのオープニング・ナンバーは現代の日本を見つめるインターネットの視点から歌われているがEccyのビートはそのディストピアのダークサイドを見つめている。