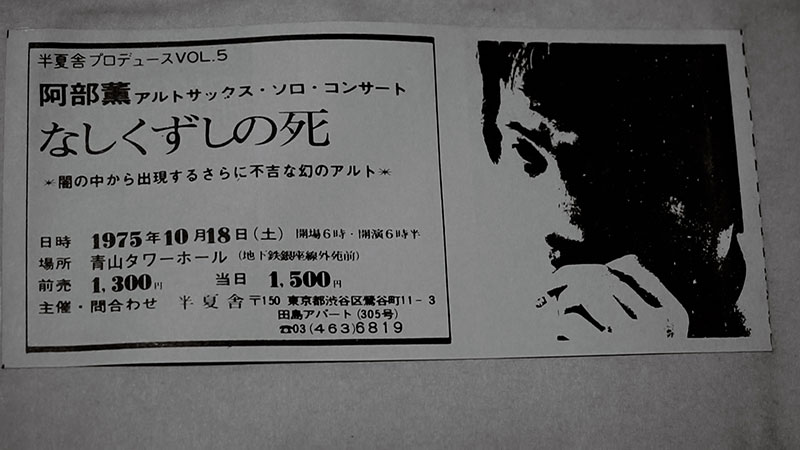ゴート・ガールのセカンド・アルバムは、2021年初頭のクライマックスのひとつだろう。本作がリリースされた1月から2月にかけてのおよそ1ヶ月ものあいだ、ぼくは三田格とともに『テクノ・ディフィニティヴ』改造版のため、ほぼ毎日、1日8時間以上、エレクトロニック・ミュージックを片っ端から耳に流し込んでは文章を書きまくっていたので(それはそれで充実した日々だったけれど)、ほかの音楽を聴く時間などなかったし、ましてや新譜などエレクトロニックでなければ後回しである。で、『テクノ・ディフィニティヴ』が終わったと思ったらここ1ヶ月は、またしても三田格とともに別冊のフィッシュマンズ号のために取材をしたり調べたり、ほぼ毎日、1日8時間以上はフィッシュマンズを聴いている……わけではないので、いまようやくゴート・ガールまで追いついたという。ふぅ、いまようやく、彼女たちの新作『On All Fours』が素晴らしい出来であることを知ったのであった。
にしても……バンドというものは、こうして成長するのか。本作3曲目に“Jazz (In The Supermarket)”という曲がある。喩えるなら、この曲はザ・クラッシュの『サンディニスタ!』やザ・レインコーツのセカンドのなかに入っていたとしても不自然ではない、そう言えるほどの舌打ちしたくなるような格好いい雑食性がある。レゲエ風のリズムも個人的にかなりツボで、本文を書いているたったいま現在かなり空腹であることから、ロンドン郊外のあまり高級ではないエスニック・レストラン街が夜霧の向こうに見えてくるようだ。
ふざけている場合ではない。『On All Fours』はメランコリックで、雑多で、不機嫌で暗い顔をしている人たちをひそかに讃えながら、不安の波が打ち寄せる空しい夜の甘い甘いサウンドトラックとなる。“P.T.S. Tea”のトランペットといい、“Once Again”のベースラインといい、“A-Men”のドラムマシンといい、そしてアルバム全体を浮遊し漂泊するシンセサイザーやギターの音色といい、ゴート・ガールはポストパンク流の格好の付け方をよくわかっている。ちなみに1曲目の曲名は“ペスト”、歌詞は読んでいない、ぼくはまだ音だけに集中している段階なんだけれど、本作がパンデミックの状況にリンクしていることは確実だろうし、メンバーの深刻な病も無関係でないだろう。
しかし『On All Fours』には、そうした不吉なムードを払いのける強さもある。ザ・フォールの前座を務めたという経歴は伊達ではなかったし、憂鬱で冷たくて、しかし13曲すべてにそれぞれ固有のアイデアがあって、それらすべての曲がキャッチーでもあるこのアルバムは、ものごとがどうにもうまくいかない愛すべき人たちのなかで何度も反復されるだろう。フィッシュマンズのことを考えている最中に聴いても、あまり違和感がない。