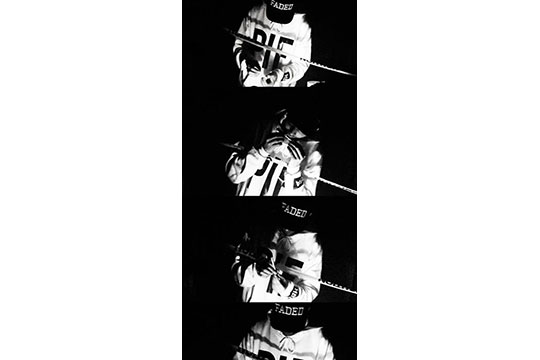SEIHOU Abstraktsex DAY TRIPPER |
勢いが止まらない! そして夏休みは終らない! 先月インタヴューにてele-kingにも登場してもらったSeihoのセカンド・アルバム、『ABSTRAKTSEX』リリース・パーティーがすごいぞ。ゲストにはUltrademonが参加! Seapunkがモニターを飛び出す! 迎えうつゲスト勢も、tomadからAvec Avecら盟友がズラリと一同に会した豪華な布陣。いま彼らのまわりに何が起こっているのか、目撃するチャンスは今日&明日。今年最高の「陸の海」へと、さあ、繰り出そう!
いよいよ今週! トロピカルなモチーフでファッションのトレンドにもなった10年代のネット/ユース・カルチャーを象徴する #Seapunk のオリジネーター Ultrademonが遂に日本へ初上陸!東京公演では新世代ビートメーカーの旗手Seihoのセカンド・アルバム『ABSTRAKTSEX』のリリパにゲスト出演!!
【Ultrademon Japan Tour 2013】
■8.16 (FRI) @ Circus Osaka with idlemoments
 OPEN/START 18:00
OPEN/START 18:00
ADV 1,500 yen / Door 2,000 yen (+1drink)
LINE UP:
Ultrademon
gigandect
Avec Avec
Terror Fingers (okadada+keita kawakami)
SEKITOVA
eadonmm
doopiio
kibayasi
Alice
?
VJ:
Tatsuya Fujimoto
FOOD:
カレー屋台村山ねこ
more info: https://idlemoments-jp.com
■8.17 (SAT) @ UNIT with Seiho ABSTRAKTSEX Release Party
 OPEN/START 23:00 | ADV 3,000yen / DOOR 3,500yen
OPEN/START 23:00 | ADV 3,000yen / DOOR 3,500yen
LINE UP:
[UNIT]
Seiho
Ultrademon
LUVRAW & BTB + Mr.MELODY
RLP
Taquwami
terror fingers (okadada & Keita Kawakami)
tomad
eadonmm
VJ:
ネオカンサイ
Kazuya Ito as toi whakairo
[SALOON]
Licaxxx
Redcompass
Mismi
Hercelot
FRUITY
andrew/Eiji Ando
more info: https://www.unit-tokyo.com