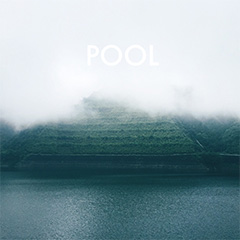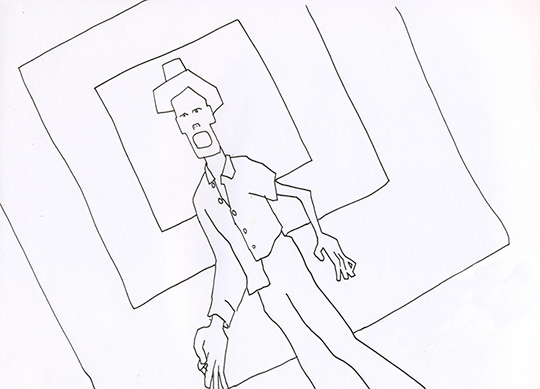福岡で地道にして実験的なリリース活動を続けるカセット(だけでもないけれども)・レーベル、〈Duenn(ダエン)〉。そのカタログにはMerzbowからNyantoraまで、chihei hatakeyamaやHakobuneといったエレクトロニカの前線や、食品まつりにMadeggやあらべぇ、shotahiramaなど、2010年代のエレクトロニック・ミュージックの俊英も細やかに名を連ねる。
さてその〈Duenn〉によるレーベル・ショーケースとも言うべきイヴェントが、11月、東京にて開催されるようだ。新譜が本当に心待ちにされるPhewにIkue Moriという見逃せない掛け算を筆頭に、なんとも豪華な面々が「×」で登場する。
このイヴェント〈extokyo〉では前売予約者に貴重な音源特典もある。〈Duenn〉へのフレンドシップの下、テイラー・デュプリー(〈12K〉)が撮り下ろした写真に1分の音を付けるというルールで、Markusu popp a.k.a Oval、Taylor Deupree、Merzbow、Nyantora、勝井祐二(ROVO)など計31組のアーティストが楽曲を提供、「V.A one plus pne」と題されたコンピレーション・アルバムである。先着順で一定数に達したら終了とのこと、ご予約を急がれたい。
そして、前日にはこれまたスペシャルな6組による前夜祭ライヴが〈vacant〉で開催。先日Open Reel Ensembleを“卒業”したてのMother Terecoの名も見える。日にまたがりアーティストを交差し、楕円の音楽体験を。
■2015.11.24(Tue.)
Duenn presents
ex tokyo at WWW
福岡のカセットテープレーベル「Duenn」が「ちょっと実験的な音楽会」というコンセプトで不定期開催しているレーベル自主イヴェント。
これまでに浅野忠信、中原昌也、イクエモリ、Ovalら国内外のアーティストを招聘し2015年5月にはくるり岸田繁のドローンライブセットの企画が話題になった。
今回レーベルショーケースとして初の東京公演を11月24日に渋谷WWWで開催する。
イベントテーマは「trial and error 」。
OPEN / START:
18:30 / 19:00
ADV./DOOR:
¥4,500 / ¥5,500 (税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)
LINE UP:
【area01】
Ikue Mori+Phew
Taylor Deupree+FourColor+MARCUS FISCHER
mito+agraph
NYANTORA+Duenn
Hair Stylistics+空間現代
Photodisco+中山晃子
【area02】
akiko kiyama
shotahirama
chihei hatakeyama
YPY
SHE TALKS SILENCE
TICKET:
プレイガイド発売:8/2(日) チケットぴあ[272-776] / ローソンチケット[70762] / e+
詳細 https://www-shibuya.jp/schedule/1511/006322.html
■2015.11.23(Mon)

Duenn presents
echo(エコー) at vacant
福岡のカセットレーベルduennが「少し実験的な音楽会」というコンセプトで、毎回国内外の先鋭的なアーティストを招聘し開催しているレーベル自主イベントexperimental program ex。今回はレーベルショーケースとして初の東京公演が決定し、前夜祭をVACANTにて開催。
OPEN / START:
14:00 / 14:00
ADV. / DOOR:
¥2,500 / ¥3,000(+ 1drink)
LINE UP:
Ikue Mori
フルカワミキ
Akiko Kiyama
ハチスノイト
Mother Tereco
Duenn
TICKET:
https://duenn.thebase.in/
■レーベル公式サイト
https://duenn.thebase.in/



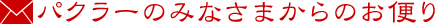

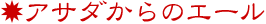


 Valentino Canzani aka French Fries のストーリーは、1975年に彼の両親が当時の独裁的な政治から逃れるためウルグアイよりアルゼンチンに亡命し、パリへ行き着いた場面から始まる。彼の父親である Pajaro Canzani はウルグアイのマルチ演奏者として、そして自身のグループ “Los Jaivas” のプロデューサーとしてスーパースター的な地位を築いていた。パリに辿り着くと、ドラムや様々な種類のパーカッションを備えたスタジオを再建したが、これがのちに Valentino や彼の妹のリズムセンス、レコーディング技術を幼い頃から習熟させるきっかけとなった。
Valentino Canzani aka French Fries のストーリーは、1975年に彼の両親が当時の独裁的な政治から逃れるためウルグアイよりアルゼンチンに亡命し、パリへ行き着いた場面から始まる。彼の父親である Pajaro Canzani はウルグアイのマルチ演奏者として、そして自身のグループ “Los Jaivas” のプロデューサーとしてスーパースター的な地位を築いていた。パリに辿り着くと、ドラムや様々な種類のパーカッションを備えたスタジオを再建したが、これがのちに Valentino や彼の妹のリズムセンス、レコーディング技術を幼い頃から習熟させるきっかけとなった。