最近よく聴く曲
 1 |
Unknown – Yardman - TheMostHigh |
|---|---|
 2 |
Radikal Guru vs Scientist – No Good - Dubby |
 3 |
CESSMAN - MILITANT DUB - WhoDemSound |
 4 |
DJ Madd – 1 Spliff - 1Drop |
 5 |
EshOne - Hot Sauce - Artikal Music UK |
 6 |
Skeptical – Echo Dub - Tempa |
 7 |
Henry & Louis Featuring Steve Harper – Rise Up (Rsd Remix) - 2Kings Records |
 8 |
The Illuminated – Peace Man Time (The Illuminated Version) - Grand Ancestor |
 9 |
Pinch – Chamber Dub - Soul Jazz Records |
 10 |
Johnny Osbourne – Fally Ranking (V.I.V.E.K Remix) - Greensleeves Records |
家でよく聴くレコードを選びました。
Dubstep好きですが、その中でもReggae色の強いものを好んで聴いています。
(情報)
<<プロフィール>>
毎月第1月曜日、新宿ドゥースラーにてDJ Yewと共に”YR LAB.”開催中
<<スケジュール>>
03/30(水) 20:00-24:00 AMJ meets RSD "SKY BLUE LOVE" release party @新宿ドーゥースラー
https://www.facebook.com/events/223686141314522/
https://www.bs0.club/
04/04(月) 20:00-24:00 YR LAB. Vol.15 @新宿ドーゥースラー
https://duusraa.com/
04/07(木) 22:30-LATE Back To Chill @clubasia
https://www.facebook.com/events/816648375105947/





 ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。
ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。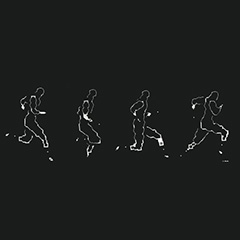 ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。
ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。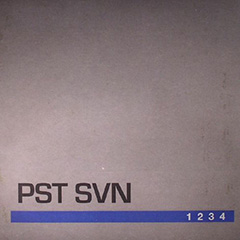 何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。
何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。 00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。
00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。 ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。
ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。
 デイヴィッド・シルヴィアン
デイヴィッド・シルヴィアン









