さて、紙ele-kingの季節です。
特集はもちろん、QNやtomadなど日本の才能、フライング・ロータスなど海外の巨才、小杉武久という伝説まで、インタヴューも濃縮クオリティ。
発売は9月28日(金)です!
●アニマル・コレクティヴ表紙&巻頭インタヴュー!!
●特集 ノイズ/ドローンのニューエイジ!
――コンプリート・ガイド・トゥ・ノイズ/ドローン2001-2012
インディ・ミュージックの世界において、いまふたたびノイズ/ドローンが熱い注目を浴びていることにはお気づきだろうか? あのジム・ジャームッシュまでもが、最近は自身でドローンを演奏しているのだ! とはいえ、「ノイズ」という概念は更新されつつある。そこではいろいろな音がつながり、変化し、日々あたらしい力が生み出されている。今回特集するのはそんな「これからの歴史に残る」ノイズ・ミュージック! ノット・ノット・ファンやエメラルズなど、現在を彩るインディ・ロックやアンビエント、またニューエイジ的なルーツを持った異才たちの、その背景にある音たちを探っていきます。2001年から2012年までの重要作品をきっちり網羅したディスク・ガイドも収録。コラムも加えて大充実の必携本に!! いつものele-king執筆陣も筆をふるっております!
*インタヴュー
ピート・スワンソン、小杉武久(タージ・マハル旅行団)、ジム・オルーク、シンリシュープリーム、アース、メデリン・マーキー他
*ディスクガイド60
クロニクル2001~2012! まだ書かれていない歴史をここに。選りすぐり60枚!
倉本諒、デンシノオト、橋元優歩、三田格、松村正人、湯浅学
*コラム
佐々木敦、美川俊治ほか
* USノイズ・マップ!by倉本諒
●TALK
フライング・ロータスが新作を語るロング・インタヴュー
シミラボ脱退後はじめて心境を語るQNインタヴュー
〈マルチネ・レコーズ〉主宰tomadの新展開インタヴュー「音楽とお金とレーベルの新しい関係」
森美術館での個展や伝記映画公開でこの秋注目! 日本を代表する画家、会田誠インタヴュー
数奇なるフォークシンガー、倉内太インタヴュー
●前号からの新連載も絶好調!!
山本精一「ナポレオン通信」、西村ツチカのマンガ「本日の鳩みくじ」がスタート!
●好評連載中!
粉川哲夫、戸川純、shing02、tomad、二木信、T・美川、こだま和文×水越真紀 各氏
●カルチャー・レヴュー
五所純子(映画)、プルサーマル・フジコ(演劇)、小原真史(写真)
●巻頭フォト
阿部健
●表紙撮影
塩田正幸
編集 野田努、松村正人、橋元優歩
撮影 小原泰広ほか
















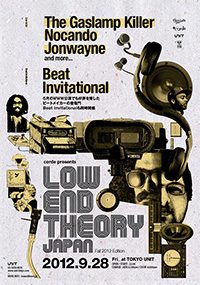



 [CD]
[CD] 【関連商品情報】
【関連商品情報】


