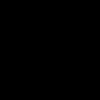春のはじまりは楽しいライヴを観るのがいいに決まっている。野田編集長はノルウェーからキュートな女子がやって来たのにウキウキしていたようだが、僕はと言えば、アメリカの田舎からヒゲもじゃのおっさんたちが来たことにニヤニヤしていた。会場は埋まりきっていないものの、真面目なUSインディ好き......だけでなく、何だか妙にテンションの高い大人が集まってきていた。僕の周りにいた3、40代の酒が入った男女のグループが、フジロックにスティーブ・キモックが出演する話で盛り上がっている......と、別のグループの40代が話に参加しはじめる。僕は会話に加わりはしないが、そのわかりやすさに笑みを浮かべる。ここにいる誰もが、いまからステージで、情熱的で、豪快な演奏が繰り広げられることを知っている......。

暗転して現れたメンバーはジェケット姿で洒落た楽団風でありながら、長髪とヒゲのむさ苦しさは隠せていない。"ヴィクトリー・ダンス"の不穏なイントロからじわじわと熱を上げていく。「勝利の舞を見たいんだ/毎日の仕事の後で」、その通り! エレキがソロを歌い、バンドか狂おしくそれに答えれば、フロアからは叫び声が上がる。続く"サーキタル"の時点で、僕はもう笑いが止まらなくなっていた。巨体のドラマー、パトリックが力いっぱいドカドカとスネアを叩きまくる。日本の街を歩いていたら、獣と間違われても仕方ないだろう......。ギターのリフが繰り返され、やはり長髪でヒゲ面のジム・ジェームズがハイトーンでメランコリックなメロディを歌う......と、ドラムが加わり、視界が開ける。軽快にキーボードが加わり、フィルを繰り返すドラムは決して走らない。そしてメンバーが目配せすると、完璧なタイミングでアタックが叩きつけられる。その快感に身体を預けるだけでいい、すべてがそこでは開放されていく。僕はヒートテックのタイツを履いてきたことを後悔していた。
それから2時間強のあいだで起きた、細かいことを書いても仕方ないだろう。万単位の会場を端っこまで熱狂させるアメリカのジャム・バンドが、手加減することなく日本のステージで力いっぱい演奏したのだ。カントリー、ブルーズ、ハード・ロックにメタル、フォーク、ファンク、あるいはエレクトロニカや室内楽までを貪欲に取り込み、ダラダラしたジャムに持ち込むことなくそれらをエモーションの昂ぶりへと変換させていく。ジムの高い声はよく伸びて、耳から入って脳のなかに響く。抜きん出た演奏力で非常によくコントロールされているものの、音源で垣間見せる繊細さはライヴでは野性に獰猛に食い散らかされ、ラウドなギターが吼える。かと思えば、"スロウ・スロウ・チューン"、"ムーヴィン・アウェイ"といった穏やかなバラードではゆっくりとした時間が広がっていく。しかしそのスケールの大きさはどの曲も同じ。アメリカの田舎の大地が、そのまま宇宙まで繋がっているかのようだ。どこからこんなエネルギーがやってくるのかまったくわからないが、米国のジャム・バンド特有のワイルドさと大らかさが、そこではありったけ祝福されていた。オーディエンスを叫び声を上げ、あるいは思わずガッツポーズを取り、両の手を掲げてそれに応えた。
20分近くはやっていただろう燃えたぎるサイケデリック・ジャム"ドンダンテ"の狂乱は、バンドのあちこちのライヴを何十回と聴いてきたという超コア・ファンの友人をして「これまででいちばん凄かった」と言わしめるほどの極みを見せ、そして本編ラストはキラーの"ワン・ビッグ・ホリデイ"だ。エレキギターを髪の毛を振り乱して演奏する姿はやっぱり獣にしか見えない......が、バンドはそんなことお構いなしに爆発する。僕の隣の40代は「ぎゃー!」と叫んでいる。「俺たちは大いなる休暇を生きるんだ」......その溢れんばかりの生命力を、ロック・ミュージックへと変換させることへの迷いのなさ。

そう、マイ・モーニング・ジャケットのライヴは生きるためのエネルギーの爆発そのものだ。ライヴが終わってしまうと僕は次の日の仕事のことを忘れ、ビールを飲んでお好み焼きをたらふく食って、にやけた顔のまま帰った。(ただ、ジムの体調不良とはいえ、名古屋の公演中止はあまりにも残念だ。次はぜひ名古屋も宇宙に連れて行ってほしいと思う)









 King of UK Bass Music。最先端、革新的なエレクトロニック・ミュージックのパイオニアとして知られる彼は、1995年に〈ピースフロッグ〉から「Brown By August」をリリースしてその華々しいキャリアをスタートさせる。これまで、〈ピースフロッグ〉を含む〈トレゾア〉、〈Sativae〉、〈ソニック・グルーヴ〉、〈モスキート〉、〈プラネット・ミュー〉など、世界的に影響力のあるテクノ/エレクトロニックレーベルから数々のレコードを実験的、斬新な音と共にリリースし、その新しい表現は世界中からの注目を浴びその独特のスタイルや世界観は彼のコピーアーティストを生むほどの影響力を持つ。
King of UK Bass Music。最先端、革新的なエレクトロニック・ミュージックのパイオニアとして知られる彼は、1995年に〈ピースフロッグ〉から「Brown By August」をリリースしてその華々しいキャリアをスタートさせる。これまで、〈ピースフロッグ〉を含む〈トレゾア〉、〈Sativae〉、〈ソニック・グルーヴ〉、〈モスキート〉、〈プラネット・ミュー〉など、世界的に影響力のあるテクノ/エレクトロニックレーベルから数々のレコードを実験的、斬新な音と共にリリースし、その新しい表現は世界中からの注目を浴びその独特のスタイルや世界観は彼のコピーアーティストを生むほどの影響力を持つ。