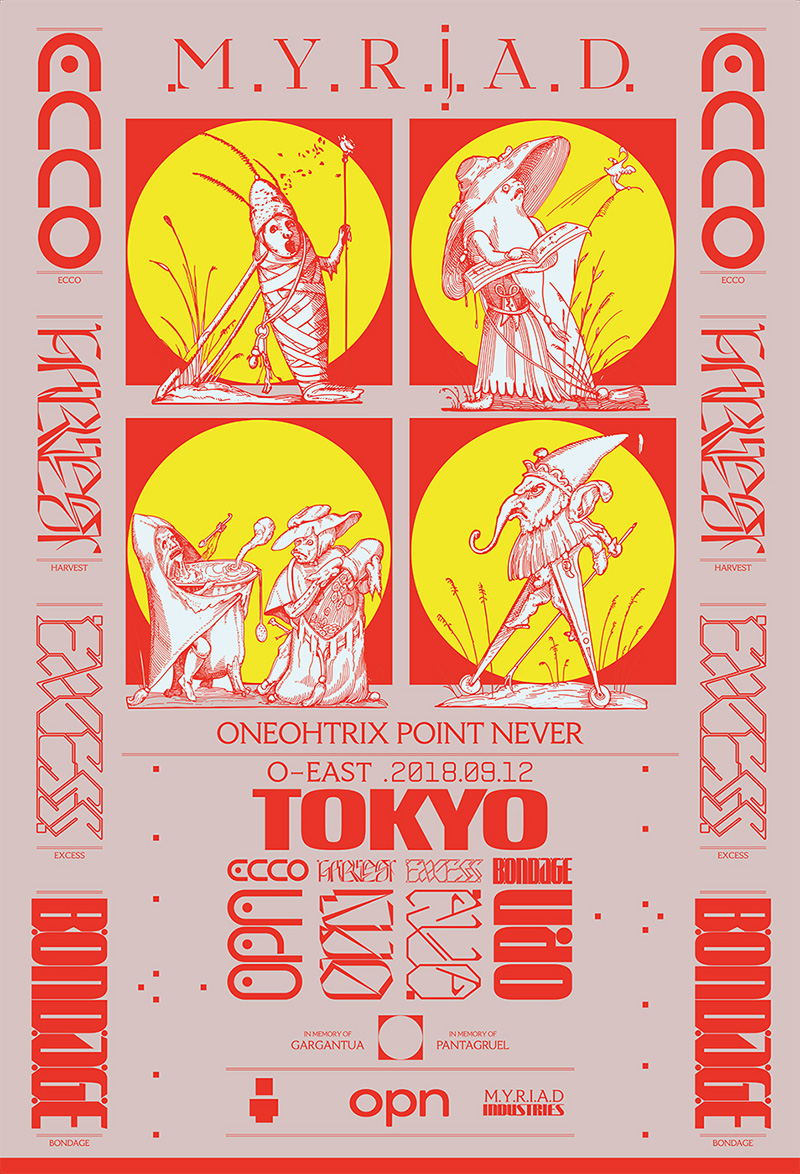ele-king booksからプロレスの本!? そう思われている方も多いでしょうが、現在のプロレスの盛り上がりを見逃すことはできなかったのです。
古くは力道山、馬場&猪木、初代タイガーマスク、UWFにはじまる格闘技路線と大仁田厚以降のインディー団体乱立、新日本の三銃士と全日本の四天王――時代時代でさまざまな話題をふりまいては盛り上がってきた日本のプロレスですが、90年代後半の格闘技ブームに押され、今世紀に入ってからはやや沈滞ムードが続いていました。
しかしながらここ数年、新日本を中心とした華やかで楽しいプロレス、そしてデスマッチをはじめ工夫を凝らして特色を出した数々のインディー団体など、プロレス界は再度活況を呈してきています。特に今回のブームの特徴は女性ファンが増えたことで、イケメンレスラーの華麗なファイトにうっとりするに留まらず、蛍光灯で殴り合い血まみれになるような過激な試合を展開している会場に黄色い声援が飛び交う様にはなかなか驚かされるものがあります。
ライブ・エンターテインメントとしての文句なしの楽しさ。そして多くの試合会場では大きな物販スペースが設けられ、選手自ら売り子をしたりサインに応じたりする姿は昨今のアイドルのサービス精神にも通じるものがあります。こりゃたしかに人気出るわ。
今や書店にも大きなプロレスコーナーが設けられ、ベストセラーとなる本も数多く出ていますが、不思議なことにビギナー向けの入門書というのが見当たりません。「なんか盛り上がってるらしいけど、どこで見れるの?」「友達が最近ハマってるらしいんで興味あるけど、どこから見たらいいのかわからない」といったこれからのファンたちのために、簡単に今のプロレスを楽しむためのガイドとなるような本があるといいんじゃないのかな、ていうか自分がそんな本を読みたいぞ。
――そんなモチベーションから本当に作ってしまったという次第。自分の好きなプロレスを探す第一歩を踏み出すための一冊になっているはずです。
 現代プロレス入門 注目の選手から初めての観戦まで
現代プロレス入門 注目の選手から初めての観戦まで
大坪ケムタ(著)
目次
はじめに
巻頭インタビュー1 飯伏幸太
巻頭インタビュー2 葛西純
団体紹介
ローカル団体
アメリカン・プロレス(WWE)
アマチュア(学生・社会人プロレス)
今、注目の選手を一挙紹介! レスラー名鑑
タイプ別レスラー紹介
レジェンドレスラー
チーム・ユニットで構図が見えてくる
Column プロレスとアパレル レスラーとSNS
Column レスラーになるには
Column プロレス好きの有名人
観戦の手引き
観戦のおともに~便利グッズあれこれ
プロレス会場の数々
グッズショップから飲食店まで――お店ガイド
Column リング外のイベント
奇想天外! 変わり種興行
在宅観戦
Column レスラーと音楽
プロレスの歴史
プロレスのルール
Column アイドルファンとプロレスファン
技がわかればプロレスがわかる! プロレス技ガイド
プロレスが10倍おもしろくなるブックガイド
熱いドラマから奇想天外なドキュメンタリーまで プロレス映画ガイド
FAQ
あとがき