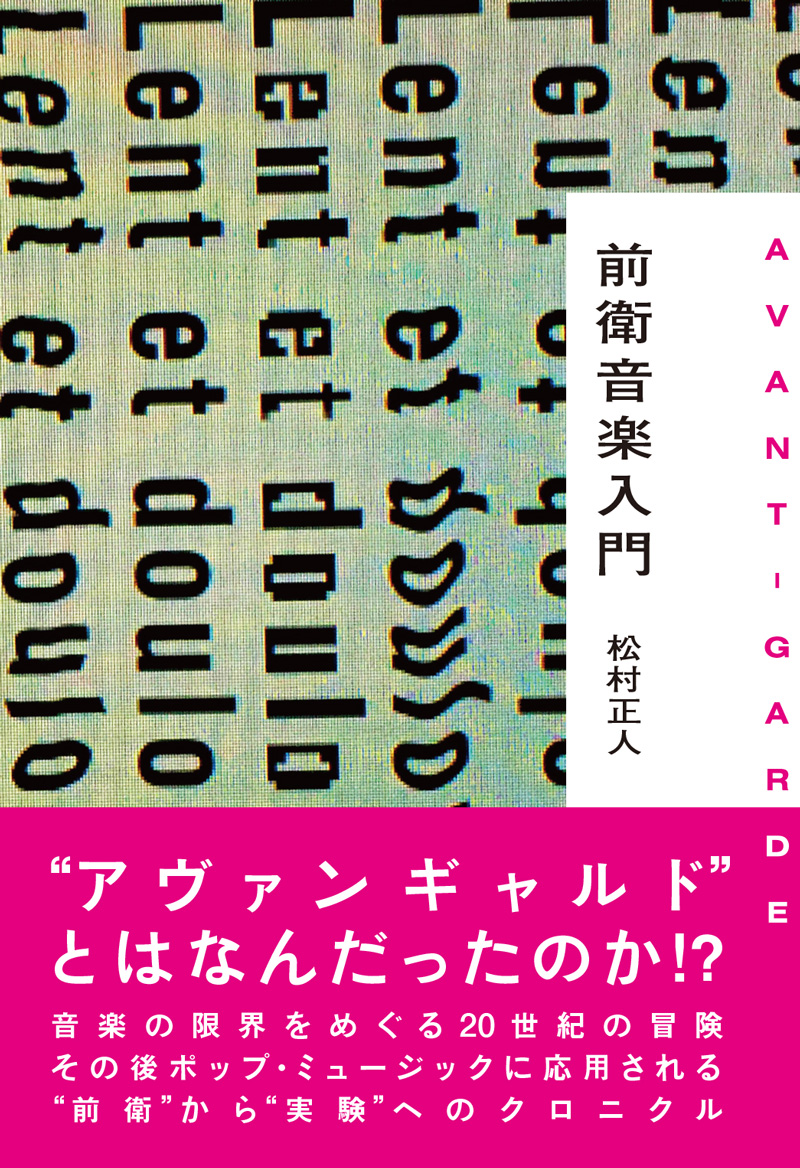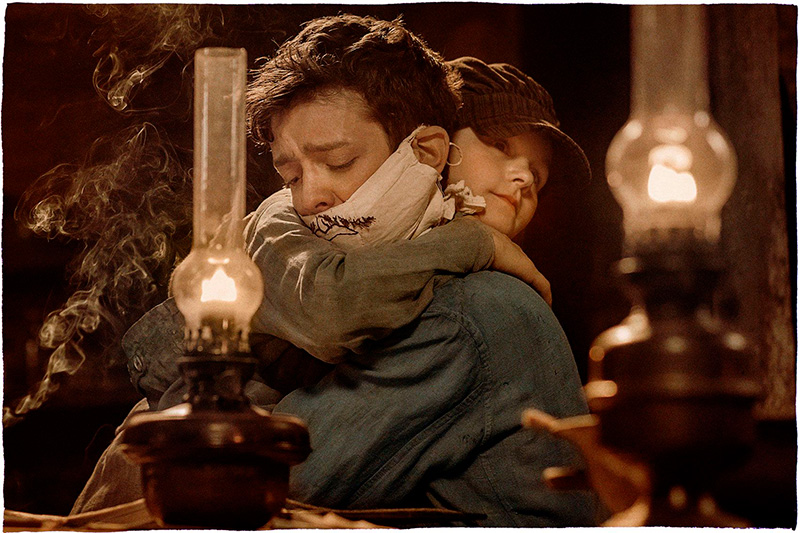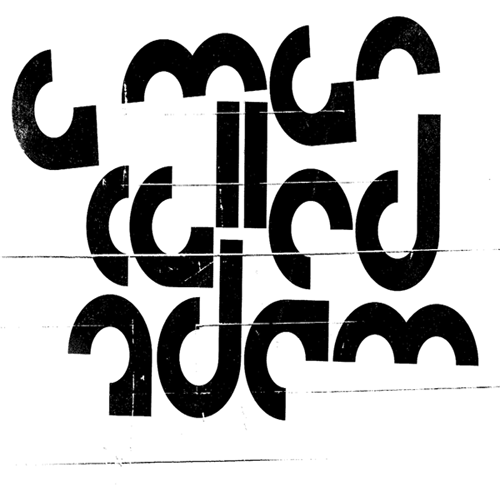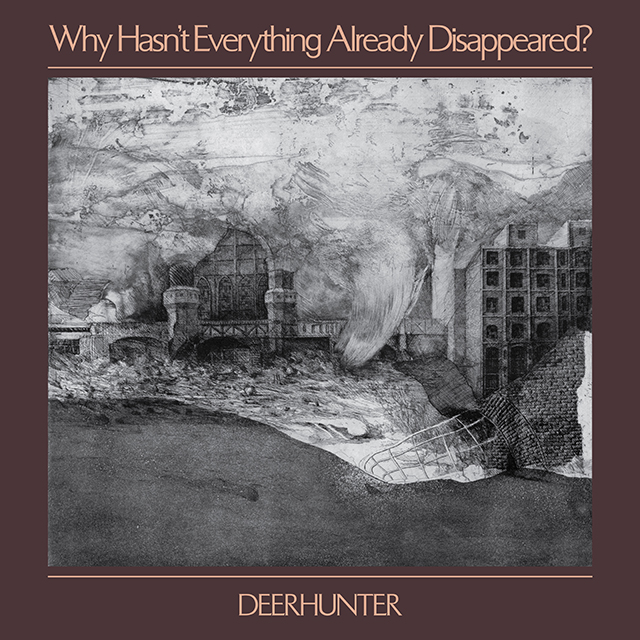ドラム・セットを眺めていると、本当にこれを扱えるのかわからなくなるときがある。恐る恐る椅子に座ると、意志のスイッチが切れて不思議と叩いている。これまでの出鱈目なドラムの道筋が思い返されて、しかしそれも、あんな練習もしたなぁとかそんなこともあったなぁといった具合に他人事のようだ。意志の断絶。確かに道筋はあるのだが、まるで初めて叩いているような気分。これはひとつの成就で、その瞬間の自己脱却なのだろうか。

成就といえば、人生で二度だけ経験したことがある。一度は、仕事もなく修行僧のように、2年ほどドラムを離れてパーカッションばかり練習しながら、南米の音楽やアフリカの音楽ばかり聴いていた頃、久しぶりにはっぴいえんどとザ・バンドとミレニウムの『ビギン』を思い出してドラム・セットに座ってみたら、いつの日か夢想していたアフロを内包した8ビートを叩けた気分になったとき。ドラムは整った、日本語ロックをしたい、と一念発起。ギターの練習を始めたが、ままならないうちに岡田と出会った。一度は、『森は生きている』で見えかけていた「夢」のような空言の種を、『グッド・ナイト』で形としては作詞で孵化させたとき。どちらも、どこからやってきたものかは不明なものの、意志の主張がそれなりの時間と労力かけて形をなしたものだ。だから、少しわがままなところがある。しかも、ネジはゆるめられなければならないことになっていて、『グッド・ナイト』リリース後はしばらく何も手につかなくなってしまった。その後のモードの回復、成り行きと強引が同居するプロジェクトの顛末はそのままこのコラムに書いていることになる。

年末から年始にかけて個人的カタスロフィが連続して、上野、宇都宮、白岡、大分を訳がわからないくらい行き来している。旅行は一切含まれない。そうこうしているとドラムに限らずこだわりのようなものが抜けてきて、そのときを生きるしかなくなってくる。その合間数多くないドラムを叩く機会すべてで、冒頭に書いたような現象が起こる。秒針が刻むように、毎度取り巻くものが更新していくような気分。まるで憑きものが落ちたような気分。意志の主張がそのまま意志の断絶に繋がるような気分。
もちろんそんな暢気なことばかりではなくて、やらなければならないこと新しい仕事は始まっている。GONNO×MASUMURAは次作のリズムアイデアがいくつか形になった。ただ、このような例外的時間をもって、仕事に臨みたいと願う。そうざらには与えられないことだし、楽しいからだ。そして、飽きずに続けられる意欲を与えてくれる。客観的にどこまでの変化があるかわからないが、毎度死んで生き返る、生き返ってまた死ぬなんて楽しいに決まっている。ニール・ヤングが何かで「変わり続けることが変わらないってことだ」と言っていたが、あなたずっと一緒じゃんというツッコミを入れたくなるのを抑えて心動く。

機材の変化も今は特に面白くて、2月いっぱいで上野の家が使えなくなったあとは、白岡の後輩の家を関東の拠点にさせてもらう予定で引っ越しもすでに始まっているのだが、彼も打楽器奏者にしていままで散々一緒に叩いてきた仲で、二人の楽器が合わさるとなかなかの壮観。本来減らさなければいけないところのものが、二人でテンションがあがって、買ったり貸し借りし合ったりしている。シンバル1枚変わるだけで全体のテンションに影響があるなんて、当たり前のことなのだが、ここまで自由にセットを変えられることはなかったから楽しくて仕方がない。これも「例外的時間」を助長してくれているのだろう。楽器もまたレコードと同じで行くべきところへいったほうがよいし、使わないと意味がない。そんな言い訳を元に、オークションやリサイクルショップのパトロールは続く。
どうせネジは緩むときがくる。回避し難いみな等しく負っている「責」はつきまとう。しかし、僕たちの仕事のひとつに「責」の隙間をついて空虚な可能性を追っていくことがあるのではないだろうか。何もしないでいいならそれがいいのだけれど、そうもいかない。ああ、そう書いて気がついたけど、まだ本当の意志の断絶までには随分距離がありそうだ。