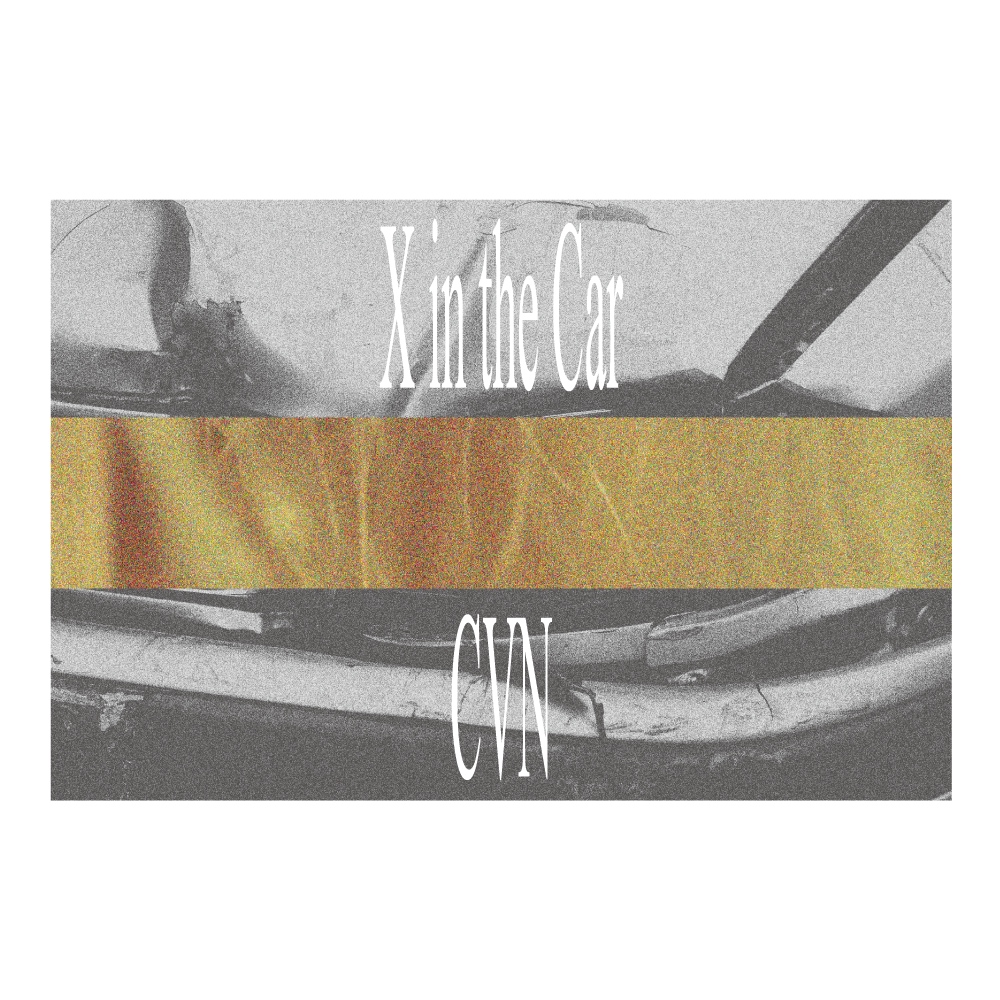ジェシー・ルインズあらためCVNのアルバム『X in the Car』が3月14日にリリースされる。
覚えているでしょう。10年前に発生した、ものうげで、ヒプナゴジックで、ドリーミーで、やわらかい液体のようなインディ運動に連なっていたジェシー・ルインズは、あらたなる音楽コンセプトのもと名義をCVNとして、ここ数年欧米のインディ・レーベルに作品を供給し続けている。それらアナログやカセットテープ音源+新曲がこのたび1枚のCDとなる。
もしあなたがCVNの新局面のいちぶを知りたかったら、彼が主宰する仮想広場のGrey Matter Archivesをチェックすべきだ。そしてアップルのデヴァイスに膨らんだあなたの部屋から、不吉で官能的なミステリーを満喫して欲しい。
「KINGã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
 Various Artists Diggin In The Carts Hyperdub / ビート |
2004年に設立された〈ハイパーダブ〉はそれ以降、現代のエレクトロニック・ミュージックにおける最重要レーベルとしての地位を堅守し続けてきた。昨年に限定して振り返ってみても、アイコニカやローレル・ヘイローの意欲的なアルバム、クラインおよびリー・ギャンブルという尖鋭的な音楽家との契約、さらには日本のゲーム・ミュージックに特化したコンピレイション『Diggin In The Carts』のリリースと、興味深い動きが続いている。
その〈ハイパーダブ〉の設立者がコード9ことスティーヴ・グッドマンである。去る11月、LIQUIDROOMにて催された『DITC』のイベントのために来日していた彼は、そのコンピレイションが持つコンセプトについて、昨年の〈ハイパーダブ〉の動きや最近注目している音楽について、そして自身が序文を執筆しているとある重要な本について、われわれの質問に対し真摯に応答してくれた。レーベル・オウナーであると同時にアーティストでもあり、さらには思索する者でもある彼の言葉を以下にお届けする。

僕がいいなと思った音楽のゲームは、じつはものすごくつまらなかったりもしたんだ(笑)。でも音自体は良かったので、それはぜんぶ選んだね。
■今回日本のゲーム・ミュージックに特化したコンピレイションがリリースされましたが、〈ハイパーダブ〉はこれまでもクアルタ330のようなチップ・チューンのアーティストを送り出しています。以前から日本の音楽には関心が高かったのでしょうか?
スティーヴ・グッドマン(Steve Goodman、以下SG):〈ハイパーダブ〉はもともと、2005~06年くらいまではダブステップのレーベルだった。でもそういったサウンドにちょっと飽きを感じてしまって、もっと自分の音楽をカラフルなものにしたいと思っていたんだ。そんなときに友人がクアルタ330のリミックスを送ってくれて、それが気に入ったんだよね。それと、自分の音楽としてもう少しキラキラしたサウンドを作るために、ヴィデオ・ゲームの要素を取り入れるようになった。アイコニカやゾンビー、ジョーカー、ダークスター、テラー・デンジャーたちもゲームの音楽から影響を受けているアーティストだった。テクスチャーを変えるためにゲーム音楽に興味を持ち始めたのが2005、06年で、その時代にレーベルに入ってきたものを今回また取り戻してリリースした、という感じだね。
■日本のゲーム・ミュージックには幼い頃から触れてきたのですか?
SG:少しは遊んでいたね。でもそれが日本のものという意識はあまりなかった。自分がプレイしていたものが日本のゲームかどうかもわからなかった。ゲームはやっていたとはいえゲーマーではなかったし、今回のコンピレイションもけっして自分がゲームをしていた頃を懐かしむようなノスタルジックな作品ではないんだ。
〈ハイパーダブ〉というレーベルの目線で言うと、2010年に日本の80年代のエレクトロニック・ミュージックに注目するようになった。YMOや、YMOのメンバーそれぞれのソロ作品などから影響を受けていたから、(ゲーム音楽を)ゲームというよりもエレクトロニック・ミュージックとして見ているんだよね。伝統音楽とエレクトロニックのブレンドのようなところに魅力を感じている。5、6年前にスペンサーD(Spencer Doran)の『Fairlights, Mallets and Bamboo: Fourth-World Japan, Years 1980-1986』というDJミックスを聴いたんだけど、それでより興味を持つようになって、今回のコンピもそういう内容になっている。そのミックスにはマライア、坂本龍一や細野晴臣、高田みどり、ロジック・システム、清水靖晃、あとは越美晴なんかが入っていて、そこから日本の80年代の音楽をいろいろと学んだ。もちろんそういう音楽とゲーム・ミュージックは違うものではあるけれど、チップというものを使っている点は共通しているし、おもしろい時代の音楽だと思う。
■先日監修者のニック・ドワイヤーさんに取材したのですが、『DITC』はゲーム・ミュージックのなかでもサウンドとしておもしろいものを選んでいると言っていました。つまり今回のコンピは、ゲーム音楽のファンよりもふだんから〈ハイパーダブ〉の音楽を聴いているような層に向けて、「ゲーム・ミュージックにもおもしろいものがあるんだよ」ということを伝える、というような意図で制作されたのでしょうか?
SG:その両方と言えるね。僕もゲームは好きだけれど、そこまでゲーマーではない。そういう両方の人たちが楽しめる作品になっていると思う。ニックがすごく深いリサーチをして、フィルターをかけた上で何百もの曲を送ってくれたんだけど、それまで自分が聴いたことのない音楽ばかりだった。それらのゲームに関して僕はいっさい思い入れがないんだ。ただたんに曲が良かったから選んだ。ゲームのプレイヤーがどうのというよりも、音としてベストだと思ったものを使った。やっぱり人気のあったゲームって、先にゲームがあってそれに合わせて音楽が作られているわけで、(音楽は)優先順位としては二番目のものだったと思うんだよ。それもあってか、人気のゲームのBGMにはあまりいいと思えるものがなかった。コマーシャルっぽいものもあるだろうし。だから、僕がいいなと思った音楽のゲームは、じつはものすごくつまらなかったりもしたんだ(笑)。でも音自体は良かったので、それはぜんぶ選んだね。
ヒップホップやクラシック音楽にはなりえない、ゲーム・ミュージックとしてだけ存在していたものを捉えるのが今回の目的だった。
■先ほど「ノスタルジックな作品ではない」と仰っていましたが、送り手と受け手とのあいだである程度ギャップは生じると思うんですね。このコンピに先駆けて公開されたドキュメンタリーにはフライング・ロータスやファティマ・アル・ケイディリらが出演していて、どちらかというといわゆる音楽ファンに向けて作られているように感じました。ですが、日本で今回のコンピを手にとってくれる人の多くは、懐かしさを求めているのではないかという気もします。そういう方たちがこのコンピをきっかけに、たとえば他の〈ハイパーダブ〉の作品を聴くようになってほしいと思いますか?
SG:それはすごく難しいところで、もちろんゲーム好きの人たちにも聴いてほしいとは思うし、他方でエレクトロニックな世界ともオーヴァーラップしているんだけれども、やっぱり同時に違う世界でもあるんだよね。ただ、いまはテクノロジーの進化でよりオーヴァーラップしているかもしれない。ニックが言っていたように、僕が捉えたかったのはメモリーやチップという制限のある時代のゲーム・ミュージックなんだ。質問への答えにはなっていないかもしれないけど、ゲームがそれ自身だけのゾーンのなかに存在していた時代のゲーム・ミュージックというものを捉えたかった。ヒップホップやクラシック音楽にはなりえない、ゲーム・ミュージックとしてだけ存在していたものを捉えるのが今回の目的だった。
■今回のコンピには80年代後期から90年代中期までの音源が収められていますが、それはデトロイト・テクノやアシッド・ハウス、レイヴ・カルチャーやジャングルが出てきた時期と重なります。その時代に日本でこのような音楽が作られていたこと、その同時代性についてはどう思いますか?
SG:僕にとってデトロイト・テクノはデトロイトから来ているものだし、同時期に流行っていたアシッド・ハウスはシカゴから、ジャングルはロンドンから出てきたものだよね。日本ではそれがチップ・ミュージックだったということだね。そうやってそれぞれの場所から違うエレクトロニック・ミュージックが流行っていったんだと思う。それがお互いに影響し合っていた、いい時代だったと思う。
■ゲーム・ミュージックには「音がメインではない、音が主張しすぎてはいけない」という側面があると思うのですが、それもある意味では8ビットや16ビットといったテクノロジーの問題と同じように制約と捉えることもできます。そういう側面についてはどう思いますか?
SG:音楽が第二に来るというのは映画音楽と同じだと思う。やっぱりまず映像があっての音楽だし、そのぶん予算も削られるし、音楽はいつも最後のギリギリのところで付けられるから、そこは共通していると思う。テクノロジーに限界があることと、音楽が第二に来ることは繋がっていると思うんだよね。音楽が第二だったからこそ、予算があるにもかかわらずそれが使われない、だから制限が生まれたんだと思う。お金をかければ音楽のためにすごくいい機材を使うことだってできたはずなんだ。でもヴィジュアルが最初にあるからこそ、音楽が第二のものになってしまった。だからこそ制作に使われるものに制限ができた。そのことによって逆にユニークなものが偶然生まれたという点がおもしろいと思うし、僕たちはそのユニークさに惹かれたんだ。
[[SplitPage]]僕はブリアルっぽいサウンドはいっさい聴かないんだ。だからぜんぜん知らない。10年くらい前から彼の影響を受けたアーティストがたくさん出てきていると思うんだけど、その頃からいっさい聴いていない
 Various Artists Diggin In The Carts Hyperdub / ビート |
■2017年、〈ハイパーダブ〉はクラインと契約してEPをリリースしました。彼女のEPを出すことになった経緯や、彼女の音楽の魅力について教えてください。
SG:彼女はすごくユニークなアーティストなんだけど……この質問は難しいね。
通訳:難しいのはなぜですか?
SG:なぜ難しいかって、彼女が特別でユニークだからなんだけど、それがどこにもフィットしないので、言葉で表現するのが難しいということ。あと彼女は歌声がとても美しいんだけど、音楽はちょっと奇妙で本当に予想がつかないから、これから彼女がどう進化していくかがすごく楽しみだね。彼女の音楽からはすごく即興性が感じられて、何か計画して作ったものではなく、自分がいま思ったことを外に表現している、そういう音楽だと思う。
■同じく2017年、〈ハイパーダブ〉はリー・ギャンブルとも契約しました。彼の作品を出そうと思ったのはなぜですか?
SG:僕も彼もジャングルが大好きで、その意味ではふたりとも同じバックグラウンドを持っているんだ。音楽性は少し違うけど、ジャングルの要素は彼の曲のなかに活かされているし、彼は哲学が本当に好きでそれを表現しようともしている。それについても僕と似ているから、シェアできるものがたくさんあるんだよね。彼のことはリスペクトしている。それはなぜかというと、サウンドの扱い方やエレクトロニック・ミュージックに対する姿勢などにすごく共感できたからなんだ。
■そういったクラインやリー・ギャンブルとの契約のあとにこの『DITC』のリリースの話が入ってきたので、とても驚きました。サウンドの種類はまったく異なると思うのですが、今回のコンピもクラインやリー・ギャンブルと同じ地平に連なるものと考えているのでしょうか?
SG:共通点はないね(笑)。
■なるほど(笑)。共通点はないがそれぞれ個別におもしろい、と。
SG:そのとおり。互いに違うからこそユニークなんだよ。
■2017年はブリアルの『Untrue』がリリースされてからちょうど10年ということもあってか、ヴェイカントや〈フェント・プレイツ〉の諸作など、ブリアルから影響を受けた音楽が盛り上がりましたが――
SG:ヴェイカントは知らないね。僕はブリアルっぽいサウンドはいっさい聴かないんだ。だからぜんぜん知らない。10年くらい前から彼の影響を受けたアーティストがたくさん出てきていると思うんだけど、その頃からいっさい聴いていないので、知らないんだ。
■そうなんですね。近年はフェイク・ニュースが横行したり「ポスト・トゥルース」という言葉が取り沙汰されたりしていますが、いま振り返ると『Untrue』というアルバム・タイトルは意味深長で、そういった昨今の情況を先取りしていたようにも思えます。
SG:いいセオリーだと思う。そうだと思うよ。
■『Untrue』はいまでも聴き返しますか?
SG:やっぱりリリース10周年ということで、みんなが盛り上がっているのを見たり聞いたりして聴き返すことはあるんだけど、僕もブリアル当人も10周年というのは気にしていないんだ。僕たちが気にしているのは「彼が次に何をやるか」ということ。だからリリース10周年ということに関してはあまり意識していない。ファンだけが盛り上がっているような感じだね。
■南アフリカで生まれたゴム(gqom)という音楽は、あなたがDJセットに取り入れたことで世界中に広がりましたが――
SG:(「ごむ」という日本語の発音を受けて)コッ(と口のなかで舌を鳴らす)。コッ、コッ(と「gqo」の部分の音を実演してくれる)。本当はこう発音するんだ。
■へえ! そのゴムの魅力はどこにあると思いますか?
SG:リズムがすごく好きなんだ。3連符のリズムやダークなところが好きだし、あとはミニマルなんだけどダンサブルなところもすごく魅力的だと思う。
彼は左翼だったんだけど、いまは右翼になってしまった。当時彼の考え方に賛同していた人たちはいまはもう彼とは正反対で、嫌ってしまっているというか。僕も彼の90年代の考え方のほうに興味がある。
■ゴム以降、非欧米の音楽で何かおもしろいものを発見しましたか?
SG:僕はここ最近ずっと中国でDJをしていて、中国の音楽にすごく興味を持っている。上海には〈Genome 6.66 Mbp〉というおもしろいレーベルもあるし、クラブ・イベントもどんどん増えてきていて、キッズたちが外の音楽を吸収するのはもちろん、それだけではなく、いま彼らは自分たちのエレクトロニック・ミュージックを作ろうとしている時期なんだと思う。これから中国のエレクトロニック・シーンはすごくおもしろくなっていくと思う。
もうひとつ、最近気になっているのはロンドンで「UKドリル」と呼ばれている音楽だね。これはグライムから進化したジャンルなんだけど、いまサウス・ロンドンのラッパーがすごく人気なんだ。ギグスというラッパーはすごく人気だし、あと67やハーレム・スパルタンズ(Harlem Spartans)といったクルーもとてもいい。やっぱりロンドンは自分が育った場所だから、僕にとってはローカル・ミュージックなんだよね。ブリクストンやペックハム、キャンバーウェルあたりの音楽はいまアンダーグラウンド・シーンが盛況で、メインにはスケプタやストームジーがいるんだけど、そうじゃないもっとアンダーグラウンドなところも盛り上がってきている。
■スケプタやストームジーはマーキュリー・プライズを受賞したりチャートの上位に食いこんだりと、オーヴァーグラウンドで彼らの人気が高いことは情報としては伝わってくるんですが、ここ日本にいると実感としてはわかりづらいんですよね。UKの若者たちはやはり日常的に彼らの音楽を聴いているのでしょうか?
SG:ロンドンではポップ・スターだね。ロンドンに限らず、イギリス全土でもアメリカでもポップ・スターだよ。まさにオーヴァーグラウンドなんだよね。それが影響して、これからヨーロッパでもポップ・スターになると思う。
■日本でスケプタやストームジーを聴いていたら、おそらく「アンダーグラウンドな音楽好き」ということになります。
SG:はははは。やっぱりヴォーカルが何を言っているかということが重要な音楽だから、言語が理解できないと人気にはならないよね。難しいと思う。
■ベルリンでもグライムはぜんぜん人気がないという話を聞いたことがあるのですが、それも変わっていくと思いますか?
SG:たしかにアンダーグラウンドだね。やっぱりそれも言語の壁があって、行けたとしても「ビッグなアンダーグラウンド」までだろうね。オーヴァーグラウンドまでは行けないと思う。たとえばフェスティヴァルで何千人もを前にしてプレイする、ということにはなるだろうけど、オーヴァーグラウンドのチャートに入れるかというと、入れないと思う。英語圏ではない国ではね。
■2年前に『Nothing』がリリースされたときのインタヴューで、「加速主義に関心がある」と仰っていましたが(紙版『ele-king vol.17』掲載)、それ(accelerationism)に影響を与えたとされる哲学者ニック・ランド(Nick Land)は、UKではどのようなポジションにいるのでしょう? オルト=ライト(オルタナ右翼)にも影響を与えているそうですが。
SG:彼はいま上海に住んでいるよ。
通訳:ロンドンでは知られていないのでしょうか?
SG:そうだね。僕が90年代に勉強をしていたとき、彼は僕のスーパーヴァイザーだったんだよ。彼は左翼だったんだけど、いまは右翼になってしまった。当時彼の考え方に賛同していた人たちはいまはもう彼とは正反対で、嫌ってしまっているというか。僕も彼の90年代の考え方のほうに興味がある。いまはもう変わってしまったけれど、その政治論のオリジナルが90年代の彼の考え方だったんだよね。
■私たちは2018年の秋頃に、コドウォ・エシュン(Kodwo Eshun)の『More Brilliant than the Sun』の翻訳を出版する予定です。
SG:ああ、その本の翻訳者がいまロンドンに住んでいてね、彼を知っているよ。マンスリー・イベントにいつも来てくれるんだ。
■髙橋勇人くんですよね?
SG:そう。彼はいつも僕のインスタグラムを見てくれているしね(笑)。
■彼はイギリスへ渡る前、ele-king編集部にいたんですよ。
SG:彼を知っているよ。ゴールドスミス大学で勉強していたね。その本を書いたコドウォ・エシュンがそこで教えていて、彼はエシュンのもとで研究しているんだ。
■『More Brilliant than the Sun』は新版が発売される予定で、あなたがその序文を書いているんですよね。
SG:そのイントロダクションを書くために彼(コドウォ・エシュン)にインタヴューする予定なんだけど、まだできていないんだよね。
■『More Brilliant than the Sun』の重要性について教えてください。
SG:僕にとってすごく影響力のある本で、本当にいろいろなアイデアが詰まっている。1000冊もの本がひとつになったような濃い内容の本なんだ。ソニック・フィクションからアフロフューチャリズムまで、エレクトロニック・ミュージックの歴史が詰まっていて、サン・ラやジョージ・クリントン、リー・スクラッチ・ペリーから始まって、ブラック・エレクトロのことも書いてあるんだけど、90年代の本だからジャングルで止まっているんだよね。〈ハイパーダブ〉はそのあとにできたレーベルだから、僕たちがその本のあとを辿っているような感じだね。
刊行されてからだいぶ経つが、昨年読んだ小説で面白かったのは村上春樹の『騎士団長殺し』だった。物語の設定が、ここ数年個人的によく考えていることとリンクしたからだ。主人公の「私」は妻と別れ、谷間の入口の山の上の家に住むことになった。家にはパソコンもテレビもないが、ラジオと暖炉があり、レコードコレクションとその再生装置があった。屋根裏にはみみずくが住んでいる。「私」は肖像画を専門とする絵描きで、気が向けば家のレコードを聴く。外部との連絡はメールではなく、家電話を使っている(携帯も持っていない)。
谷間を挟んではす向かいの山の上には、ひときわ人目を引くモダンな家がある。白いコンクリートと青いフィルターガラスに囲われたその3階建ての家の外側には自動制御された照明があり、家のなかにはエクササイズ・マシンを備えたジムやオーディオルームもある。住人は、「免色」という(色のないという意味の)不思議な名字を持った男。若くして金融関係の事業で財を成した彼は、脱税かマネーロンダリングかで東京地検に逮捕されたことがあるが無罪となって釈放され、会社を売ったお金でその家を買った。なかば隠居的に、ひとりで暮らしている。たまに書斎に籠もってインターネットを使って株式と為替を動かしているらしい。
いうなれば「免色」は情報の世界に住んでいる。綺麗で明るく、そして脱魔術化された暗闇を持たない世界に住んでいると言える。対して「私」はいわばモノの世界に住んでいる。「私」の家にはみみずくが生息する屋根裏部屋がある。そこには知られるざる過去の記録が隠されている。こうした、谷間を挟んだ山のきわめて暗喩的なふたつの世界が出会うことで(あるいは暗闇をめぐって)物語は展開していく。この設定が、ぼくが音楽文化について切れ切れながらも考えをめぐらせていることと繫がる……というかぼくが勝手に繋げている。
音楽のストリーミング・サービスは、定額制でどれだけの数量の音楽が聴けるのかというコンテンツ量が重要なポイントになる。どこも似たり寄ったりの量だから、サービスによってJポップが多いか、洋楽が多いかという“傾向”も決め手にはなるだろうが、基本は、自分が聴くであろう数量=情報量に対するコストパフォーマンスが優先される。
いま音楽は“情報”だ。レコードという“モノ”を買って聴くという行為から得られる体験とは同じであり、違ってもいる。ぼくも定額制のサービスを利用している。自分のプレイリストを作ったりして、それなりに楽しんでいる。聴いていなかった曲をこんなにも簡単に聴けるなんて便利な世のなかだと感心する。ファンカデリックのアルバムだってぜんぶ聴ける。買うことはないであろうが聴きたいとは思うセックス・ピストルズの1976年のライヴとか、ジョイ・ディヴィジョンのライヴとか、そういう微妙な録音物を聴けるのは少し嬉しい。しかし失ったものもある。なんども言われ続けていることだが、それはアナログ固有の音質であり、アートワークのインパクトだ。
やっぱりモノの強さというのはある。1979年、高校生だったぼくが通っていた輸入盤店の壁の新譜コーナーにザ・ポップ・グループの『Y』とザ・スリッツの『カット』が並んだときの衝撃はそうとうなものだった。恐怖の感覚さえ覚えたものだ。レジデンツやイエロのアートワークもショックだった。輸入盤を買う文化がまだ定着する前の話だ。得体の知れないこれらのレコードを欲することは、自分に悪魔が憑依したのではないかと思うほどぞっとする感覚だった。初めてジョイ・ディヴィジョンの『クローサー』のジャケットを手にしたときもものおそろしさを感じた。写真とデザインもさることながら、あのざらざらの紙はレコード・ジャケットではまず使われない材質だ。1枚のアルバムは、フェティッシュな魅力も携えていた(PiLの『メタル・ボックス』やCRASSのポスタージャケットも)。
そんなフェティシズムはCDの登場によって後退したのだから、老いたる者の思い出話もいいかげんにしろだろう。もともとの12インチの文化だってヴィジュアルを捨てている。が、アナログ盤はもちろんのこと、CDにしたってリスナーは明瞭に1枚の作品と向き合うことになる。読み応えのあるライナーノートが封入されていれば、さらにその作品の深いところまで聴こうとするだろう。ストリーミングには、そうした音以外に踏みとどまらせる要素がない。すぐ飛ばせるし、どんどんどん他の曲を聴けてしまう(ヘタすればスマホの画面を切り替えて、『サッカーキング』と『BuzzFeed』を見てしまっている)。深い聴き方ができないとは思わないが、どうにもぼくの場合は質よりも量に向かってしまう。
Spotifyの“人気曲”という機能も良し悪しだ。ラモーンズの人気曲には“ニードルズ&ピンズ”が入ってないし、ウルトラヴォックスの人気曲には“ヒロシマ・モナムール”も入ってないし、カンの人気曲には“ピンチ”も“マザー・スカイ”も入っていないじゃないか(カンの場合はほとんどのアルバムがSpotifyにない。レインコーツもないし)。まあ、こういう突っ込みがタチの悪いことぐらいはわかっている。すべてが網羅されていたら、それこそおそろしい事態だ。まだまだレコードやCDでしか聴けない曲はある。そして、買うほどではないが聴きたい曲を聴ける、しかも移動中に聴けるという便利さがストリーミングにはある。あの音質にさえ慣れてしまえば。
ぼくが洋楽にのめりこんだ理由のひとつには、アートワークが日本のレコードよりも圧倒的に洗練されていたし、実験的だったということがあった。ストリーミング・サービスの画面に出てくる無数のアートワークはどれもが絵文字のように見えてしまう。それらは、情報としての音楽と同じようにフラットに並んでいる。高度情報化社会では情報がモノと同価である。モノはいらないけれど情報だけが欲しいというひとは多いし、この先もっと増えるだろう。実際のところ、文化は更新されている。何を言っても後の祭りかもしれない。そして音楽は時代の変化を敏感に感じとり、作品に反映させる。
こうした情報としての音楽と対峙しながら批評的に創作しているのがハイプ・ウィリアムスであり、ジェイムス・フェラーロのような人たちだ。ベリアルの『アントゥルー』がフェイク時代を予見した作品だという議論が昨年の英米では盛り上がったという話だが(紙エレキングの髙橋勇人の原稿を参照)、忘れてならないのは、高度情報化社会に対するシニカルな反応として、謎かけのようなカオスを展開したのはハイプ・ウィリアムスだったということ。何度も書いているけれど、2018年のいまになっても、心底衝撃的だったと言えるライヴは2012年のハイプ・ウィリアムスだ。あれはエレクトロニック・ミュージックの歴史において、ぼくがそれまで経験したことのない、旧来とはまったく違うアプローチだった。匿名性ではなく、偽名性において表現する彼らは、本来であれば暗い照明が好まれるライヴ会場を最終的には目が明けられないほど明るく照らした。あの暗闇のない世界、異様なまぶしさは、インターネット社会の明るさのメタファーだろう。これは幻覚ではない、現実だ。そう言わんばかりの明るさ……。
チルウェイヴ~ヴェイパーウェイヴないしはヒプナゴジック・ポップなどと言われたいっときの現象は、いま思えば、ひとから睡眠を奪う24時間フル稼働のネット型消費社会への抵抗/渇きのような反応であり、ミステリアスさ/いかがわしさを奪取せんとする動きだったと言える。個人的に苦手ではあるけれど、現在のニューエイジ・ブームがその延長にあるのはたしかだ。ちなみに日本では、元Jesse Ruins/現CVCが主宰するGrey Matter Archivesなるサイトが、サイバースペースにおける妖しい輝きを発している。ぼくがかつて感じたアートワークへの衝撃は、ひとつはいまはこういうところ、デジタル・アンダーグラウンドな世界で起きている。
その明るさに懐疑的で、高度情報化社会にどこかで抗おうとしている自分がいる。『騎士団長殺し』をぼくのように読む人は多くはないだろうけれど、あの小説はアナログ盤にかじりついている音楽ファン目線で読んでいくとそれはそれで面白いのだ。「私」の親友がカセットテープで音楽を聴きたいがために車を古いのに買い換えたというエピソードはちとやり過ぎじゃないかと思ったけれど、カセットテープを買ってダウンロードで聴くという行為よりはスジが通っている。
小説のなかでもっとも好きなフレーズは、その親友から「今はもう二十一世紀なんだよ。それは知ってたか?」と問われるところだ。「話だけは」と私は言った。──と小説では続く。ぼくはなんとか21世紀を生きている。シーンにおけるキーパーソンや注視すべきポイントもより見えてきている。年末年始の休みのあいだはコンピュータを持たず、本とスマホだけを持って帰省した。この1〜2年は移動中はストリーミングでひたすら音楽を聴いている。近年は12インチ・シングルが少量しかプレスされないので、すぐに売り切れる。アナログ盤にこだわっていると良い曲を逃してしまうことになる。自分はいまのリリース量/リリース速度についていけてないので、こういうときにインターネットやストリーミングはありがたい。リー・ギャンブルが見いだした、グラスゴーを拠点とするLanark Artefaxは、〈Wisdom Teeth〉のLoftなどとともに、近々間違いなくテクノ新世代としてより広く注目されると見た。Spotifyに入っている人は、「Whities 011」というシングルを聴いて欲しい。21世紀を生きるドレクシアがここにいる!
(※リリース元は、抜け目のない〈ヤング・タークス〉傘下の〈ホワイティーズ〉です)
その特異な音楽性とDIYな活動で80年代に大きな足跡を残した伝説のユニット、EP-4。その中心人物・佐藤薫が新たにレーベルを始動する。その名も〈φonon(フォノン)〉。まずは2月18日に EP-4 [fn.ψ] と Radio ensembles Aiida のCD作品2タイトルがリリースされる。EP-4 [fn.ψ] は EP-4 の別働ユニットで、佐藤薫と家口成樹のふたりから成る。Radio ensembles Aiida は A.Mizuki のソロ・ユニットで、今回発売されるのは昨秋リリースされた初作品集の続編にあたるもの。かつて EP-4 はサウンドだけでなくその発信の方法に関しても独自の実践をおこなっていただけに、今後この新レーベルがどのような動きを見せていくのか目が離せない。
φonon (フォノン) について
新レーベル〈φonon (フォノン)〉は、EP-4の佐藤薫が80年代に立ち上げたインディー・レーベル〈SKATING PEARS〉のサブレーベルとして始動する。〈SKATING PEARS〉は当初カセットテープ・メディアを中心に多彩な作品をリリースしてきたが、φononは佐藤薫のディレクションによって主にエレクトリック/ノイズ系の作品を中心にリリースする尖鋭的なレーベルだ。

EP-4 [fn.ψ]
OBLIQUES
作品概要
EP-4 の別動ユニット EP-4 [fn.ψ] の初CDとなる『OBLIQUES』。EP-4 の佐藤薫と PARA や EP-4 のサポートなどマルチに活動する家口成樹の2人によって2015年に組まれたユニット EP-4 [fn.ψ]。ラップトップ・ガジェット、シンセサイザー、エフェクターなどが織りなす即興的音の立体空間は、ノイズでありアンビエントでもあるという対語的多面的要素を見事に融合した音のアマルガムを構成する。
本作は2017年6月大阪で行われたライヴの演奏を収録した作品だ。フィールド録音の変調や現実音を切り取って即興編集される佐藤のソニックスコープと純正律チューニングを自在に操る家口の重畳的シンセサイザーが、ときにストリームのように、ときにはフィルミーに立体的な音空間を織りなす。安易なリズムやビートを徹底して排除したかのような音の洪水が空間を切り裂く、約60分間のシームレスなライヴ録音となっている。※ [fn.ψ] = [ファンクション サイ]
 アーティスト:EP-4 [fn.ψ]
アーティスト:EP-4 [fn.ψ]
アルバム・タイトル:OBLIQUES
発売日:2018年2月18日(日)
定価:¥2,000+税
品番:SPF-001
JAN:4562293382516
発売元:φonon (フォノン) div. of SKATING PEARS
流通:p*dis / 株式会社インパートメント
Tel: 03-5467-7277・Fax: 03-5467-3207
〈トラックリスト〉
01. Panmagic
02. Enantiomorphs
03. Sonic Agglomeration
04. Pluralism
05. Pogo Beans
06. Hyperbola
07. Diagonal
08. Flyby Observations
09. Plural (outro)

Radio ensembles Aiida (ラヂオ Ensembles アイーダ)
From ASIA (Radio of the Day #2)
作品概要
A.Mizuki のソロ・ユニットであるラヂオ Ensembles アイーダ『From ASIA (Radio of the Day #2)』。2017年11月に発表された初作品集『IN A ROOM (Radio of the Day #1)』の続編であり、Radio of the Day シリーズの第2作となる。複数のBCLラジオが偶然織り成す一期一会の受信音と、リレースイッチの電流制御などによって生まれるビート/グルーヴをコンダクトし、類のないサウンドスケープ的な音世界を紡ぐ。前作では自室の音風景を切りとり繊細かつ大胆な不思議空間を表現していたが、本作ではタイトルどおり、BCLチューナーを抱えて訪れたアジアの街角でのフィールド・レコーディングで構成された不思議空間を創出している。つまりその不思議が、待ち受け開放から本来の開放を求める不品行な能動へとシフトしたのがこの作品集だ。彼女とラヂオの出会う世界をひとはラヂオデリアと喚ぶ!
 アーティスト:Radio ensembles Aiida(ラヂオ Ensembles アイーダ)
アーティスト:Radio ensembles Aiida(ラヂオ Ensembles アイーダ)
アルバム・タイトル:From ASIA (Radio of the Day #2)
発売日:2018年2月18日(日)
定価:¥2,000+税
品番:SPF-002
JAN:4562293382523
発売元:φonon (フォノン) div. of SKATINGPEARS
流通:p*dis / 株式会社インパートメント
Tel: 03-5467-7277・Fax: 03-5467-3207
〈トラックリスト〉
01. Secret SW - Singapore
02. Market - Singapore
03. Restaurant - Singapore
04. Square - Singapore
05. Changi Airport - Singapore
06. Secret MW - Japan
07. Revolve! - Japan
08. Specter × Festival - Japan
09. Radio TUK-TUK - Thailand
10. Squall - Thailand
11. T-Rap announcer - Thailand
12. Radio Free Bangkok - Thailand
いまエレクトロニック/クラブ・ミュージックはどんどんワールド・ミュージックと交錯していっている。とはいえ、一言で「ワールド・ミュージック」といってもそのあり方はじつに多岐にわたる。その多様性や複雑さを損なうことなく新たな形で示してくれるアクトのひとつが、世界各地の音楽を実験精神をもって表現しているデュオ、フィラスティン&ノヴァだ。バルセロナを拠点としているフィラスティンとインドネシア出身のノヴァから成るこのユニット、詳しくは下記のバイオを読んでいただきたいが、なかなかに尖っている(ちなみにフィラスティンは先日亡くなったECDとこんな曲を共作してもいる)。そんな彼らの久しぶりの日本ツアーが開催されるとのことで、これは足を運ばずにはいられない。東京公演には KILLER-BONG や ZVIZMO(伊東篤宏×テンテンコ)らも出演。要チェック。
越境するマルチメディア・デュオ、FILASTINE & NOVAのジャパン・ツアー決定!
東京公演は2/11(sun)に代官山のSALOONにて開催!
2月にバルセロナを拠点とする作曲家/映像作家フィラスティンと、インドネシア出身のネオ・ソウル・ヴォーカリスト、ノヴァ・ルスによるデュオが来日、ジャパン・ツアーを敢行する。「都市の未来を崩壊させるようなベース・ミュージック(Spin)」、「ワールド・ミュージックというよりも、もう一つの世界から来た音楽(Pitchfork)」と評される、映像、音楽、デザイン、ダンスを駆使したダイナミックなライヴ・パフォーマンスは必見だ。
FILASTINE & NOVA
Drapetomania Japan Tour 2018
2/6 福岡 art space tetra
2/7 尾道 浄泉寺
2/8 名古屋 K.D Japon
2/9 京都 octave
2/11 東京 SALOON
2/12 札幌 第2三谷ビル6F 特設会場
2/11(sun)に代官山のSALOONにて開催される東京公演では、“最も黒い男” KILLER-BONG、アヴァン・エレポップ/ストレンジ・テクノイズを響かせる ZVIZMO(伊東篤宏×テンテンコ)がライヴを披露、また、オリジナルなワールド・ミュージック/伝統伝承の発掘活動も展開する Shhhhh、空族の映画『バンコクナイツ』への参加でも知られる Soi48、ヒップホップやアンビエントを行き来しながら活動を展開する YAMAAN といった独創的なDJたちがスペシャルなプレイをくり広げる。VJとして rokapenis の参加も決定している。世界各地域の音楽、文化を実験精神をもって独自に表現する面々によるクレイジーでダンサンブルな一夜になるだろう。
FILASTINE & NOVA
Drapetomania Japan Tour 2018 in Tokyo
2018.02.11 (sun)
@代官山 SALOON
Open/Start 18:00
Adv 2500yen(1D付き)/ Door 3000yen(1D付き)
| Live |
FILASTINE & NOVA
KILLER-BONG
ZVIZMO
| DJ |
Shhhhh
Soi48
YAMAAN
| VJ |
rokapenis
| Ticket |
前売りチケット取扱い店
・IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
・disk union
└ 渋谷クラブミュージックショップ
└ 下北沢クラブミュージックショップ
└ 新宿クラブミュージックショップ
└ 新宿ラテン・ブラジル館
└ 吉祥寺店
└ 池袋店
・予約 filastine.tokyo2018@gmail.com
| Info |
IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
https://ira.tokyo/filastine-nova-tokyo/ | 03-3352-6916
【PROFILE】
●FILASTINE & NOVA

バルセロナを拠点とする作曲家/映像作家フィラスティンと、インドネシア出身のネオ・ソウル・ヴォーカリスト、ノヴァ・ルスによるデュオ。ブラジルのカーニバルのバトゥカーダやモロッコの神秘主義者たちとの関わりから打楽器を学び、ラディカル・マーチングバンド The Infernal Noise Brigade を率いたフィラスティンと、幼い頃からペンテコステ派の霊歌やコーランを歌い、ガムラン・パーカッションを演奏し、インドネシアのヒップホップ・シーン草創期にラッパーとしても活躍したノヴァが生み出す音楽は、まさに「ワールド・ミュージックというよりも、もう一つの世界から来た音楽(Pitchfork)」である。世界各地の音楽フェスティバルに出演する以外にも、ドキュメンタリー映画『アクト・オブ・キリング』の公式ミックステープ制作や、フランス・カレーの巨大難民キャンプ「ジャングル」でのライヴ、掃除婦や鉱夫などの底辺の労働者がダンスによって解放される映像シリーズの制作など、音楽を通して「もう一つの世界」の実現を目指すラディカルな表現活動を続けている。2017年に最新アルバム『Drapetomania』を発表した。
https://soundcloud.com/filastine
●KILLER-BONG

〈BLACK SMOKER RECORDS〉主宰、最も黒い男。
●ZVIZMO

蛍光灯音具 OPTRON (オプトロン) プレイヤーの伊東篤宏と、アンダーグラウンド⇔メジャーを縦横無尽に行き来する テンテンコ によるデュオ・ユニット。テンテンコの聴き易いが意外に重たいエレクトロ・ビートと伊東のフリーキーだが意外とキャッチーな OPTRON が作り出すその音世界は「奇天烈だが何故かフレンドリー」な響きに満ちている。2017年11月に〈BLACK SMOKER RECORDS〉より1st アルバムをリリースした。
●Shhhhh(El Folclore Paradox)

DJ/東京出身。オリジナルなワールド・ミュージック/伝統伝承の発掘活動。フロアでは民族音楽から最新の電子音楽全般を操るフリースタイル・グルーヴを発明。13年に発表したオフィシャルミックスCD、『EL FOLCLORE PARADOX』のコンセプトを発展させた同名レーベルを2017年から始動し、南米から Nicola Cruz、DJ Spaniol らを招聘。アート/パーティ・コレクティヴ、Voodoohop のコンピレーションLPのリリースなど。dublab.jp のレギュラーや、オトナとコドモのニュー・サマー・キャンプ“NU VILLAGE”のオーガナイズ・チーム。ライナーノーツ、ディスク・レヴューなど執筆活動やジャンルを跨いだ海外アーティストとの共演や招聘活動のサポート。全国各地のカルト野外パーティー/奇祭からフェス。はたまた町の酒場で幅広く活動中。
https://soundcloud.com/shhhhhsunhouse
https://twitter.com/shhhhhsunhouse
https://www.facebook.com/kanekosunhouse
●Soi48(KEIICHI UTSUKI & SHINSUKE TAKAGI)

旅行先で出会ったレコード、カセット、CD、VCD、USBなどフォーマットを問わないスタイルで音楽発掘し、再発する2人組DJユニット。空族の新作映画『バンコクナイツ』にDJとして参加、〈EM Records〉タイ作品の監修、『爆音映画祭タイ・イサーン特集』主催。フジロックや海外でのDJツアー、トークショーやラジオなどでタイ音楽や旅の魅力を伝えている。その活動の様子はNHKのTV番組にも取り上げられ大きな話題となった。CDジャーナル、boidマガジンにて連載中。英Wire Magazineにも紹介された、『Soi48』というパーティーを新宿歌舞伎町にて不定期開催中。Brian Shimkovitz (AWESOME TAPES FROM AFRICA)、Zack Bar (FORTUNA RECORDS) からモーラム歌手アンカナーン・クンチャイ、弓神楽ただ一人の後継者、田中律子宮司など個性的なゲストを招いてのパーティーは大きな反響を呼んでいる。タイ音楽と旅についての書籍『TRIP TO ISAN: 旅するタイ・イサーン音楽ディスクガイド』好評発売中。
https://soi48.blogspot.jp/
https://www.instagram.com/soi48/
●YAMAAN

HIPHOPやAMBIENTを行き来しながら活動中。2017年2月に“NN EP”をリリースした。
@Mirage______


「ある雨上がりの夜。霧さえ出ていないものの、道路のミラーや駐まっている車のフロントガラスは、白く水蒸気の寄り場となり、映るすべてのものを抽象化して、妖気を与えている。街灯の光は月のように、自分の姿は知らない他人のように。幻覚のようなそこに映るものは、いつか見たことがあるような気がするというよりは、これから出会うかもしれないという妙な不安を誘うものである。そこで、はっと気づいた。いつか見たことがあるようなものと、これから出会う予感のするものに些かの違いがあるのだろうか」
これは 2014 年くらいのメモにあったもので、僕は以前そんなムードの切れ端をメモしておこうという気を起こして『グッド・ナイト』の歌詞を書いた。さて、ドラムにもこのような郷愁を持ち込んでいいものかどうか。
今は、このようなムードは一旦去った。ただ、モードが帰ってきている。モードは「~モード」とかよく一般的に言われているものと同義で差し支えない。ムードはある時期にしか属してくれず、すぐどこかへ行ってしまうけど、モードこそ気持ちでどうにかできるものでもないと気がついた。ただ、モードさえ帰ってくればムードは思い返すことならできるかもしれない。そういった点、僕は今図らずも「森は生きている」のよきリスナーになっているのかもしれない。当時ムードをドラムにまで持ち込みたかったどうかは覚えていないが、所謂きちんとしたドラマーの仕事をするというよりは、パーカッションからの影響を8ビートに還元することに執念を燃やしたり、ライヴではロイ・ブルックスやスティーブ・リードのように少し喋り過ぎていたようだ。
そんな「森は生きている」のいつかのライヴのあとにgonnoさんと口約束したプロジェクトが約3年越しに実行する。(https://diskunion.net/latin/ct/detail/1007589182)僕は、周りをぐっと昇華させるようなレヴォン・ヘルムやナナ・ヴァスコンセロスに憧れる反面、喋り過ぎる(喋ることができる)ドラムを叩くロイ・ブルックスやスティーヴ・リードにずっと憧れていた。gonnoさんの音楽はどこか懐かしく柔らかい。それなのに強度もある。僕が喋り過ぎたくらい包み込んでくれる懐の深さがきっとある。というか、今回はあまり作戦立てをし過ぎず、お互いの処女の会話を作品にしたいと思っている。作戦立ては今後いくらでもできるし。だから、ムードをドラムに持ち込むモード全開だ。

もう一つ新しいバンドのプロジェクトは歌を生かさなければならない。シンガーソングライター特有の曲の間にできる真空のようなものを共有しなければならない。これが絶妙で、一からドラムをやり直さなければならない練習モードにさせられている。最近、作詞の依頼から資料集めの一環で尾崎亜美などを聴いていたのだが、言葉のことより林立夫氏のドラムに驚いた。『大滝詠一』『HOSONO HOUSE』のドラミングはすごく聴いてきて、やはり一種のなつかしさがあって(駒沢氏のペダル・スティールが助長している節も大きい)、それなりにコピーにも取り組んできたのだが、それ以降のドラミングはなつかしさが多少去って、それでもかっこよさは残りながら、上手さと凄みを湛えている。はっきり言って勝手に凹んだ。でも、ちょうどいい。大分に一人でいるのも申し訳ない気持ちになることがいつも山に叩きに行かせるので、練習モードは歓迎だ。そして、最近話題の大貫妙子『SUNSHOWER』におけるクリス・パーカーや、ジェイムス・テイラーにおけるリーランド・スカラーと組んだ時のラス・カンケルのドラミングに改めて驚嘆した。”Nobody But You”の間奏明け1:52~1:56までスネアを抜いたプレイは圧巻。そしてスネア一発帰って来たときのなつかしさは言葉にできない。スティービー・ワンダー”bird of beauty”におけるボビー・ホールのドラミングも思い出した。なんだか急に色々思い出してきた。
2月になったらすぐ東京へ行って2週間ほど滞在しながら、このどちらもを一気に進めます。岡田とのプロジェクトも並行して行います。あと一週間はスウェディッシュ・トーチの力を借りて、寒さに負けず山へ。

サバール練習会
ECDさんといつまでも(Together forever)
矢野利裕
ECDさんが亡くなってしまったことが、とても悲しく、つらいです。
ele-kingのかたより「ECDさんの追悼文を書きませんか」と連絡をいただきました。わざわざ人前で追悼文を発表することに抵抗感があるし、「オレなんかが」という気持ちもあります。しかし、そういう局面において、いつでも覚悟を持って言葉を発することを選び続けることが、ECDさんをはじめとする日本語ラップの格闘だったはずで、僕自身、この20年、日本語ラップのそういうアティテュードにおおいに勇気づけられてきたので、自分なりにECDさんについて書かせてもらいます。
紋切の言いかたですが、20年まえ、14歳のときに『BIG YOUTH』という作品でECDを知ったことからこそ現在の僕がいます。本気でそう思っています。具体的に言うと、地に足をつけた労働者であるとともに、表現者であるということ。僕はいま、自分なりのヒップホップ観の延長で、中高一貫校の教員という仕事をしています(ようするに、KRS ONE的「TEACHA」による「Edu-tainment」を目指している、ということです)。幸いなことに、それなりにまともな給料をもらっています。ただ、よく言われるように、教員というのはなかなか休みに恵まれません。運動部の顧問ということもあり、土日の休みもままならず、肉体労働の側面も強いと感じます。疲労とストレスがたまって、肉体的・精神的に弱ってくるたびに「いっそ文章を書くことに専念したい」と思います。でも、辞めない。なぜか。でも、お金の問題は関係ない。仕事を続けるのは、労働をしながら表現をすることが誠実でかっこいいことだ、と思っているからです。労働者であることと表現者であることが深く結びついていること。生活が表現を生むこと。その表現が生活に戻ってくること。そういう生きかたを強烈に体現した人が、ECDさんでした。「21世紀のECD」以降を生きる僕にとって、「好きなことをして食べる」という一途な生きかたは、それほど魅力的には映っていないのです。
『BIG YOUTH』を初めて聴いたとき、ヒップホップというものに触れること自体がほとんど初めてだったから、めくるめくサウンドとラップに本当に衝撃を受けました。ああ、こんなにもスリルと喜びに満ちた音楽があるのか! すぐに心を奪われました。『BIG YOUTH』は、自分が音楽にのめり込むきっかけの大きなひとつで、例えば、マーヴィン・ゲイを聴くようになったのは、「ECDのロンリー・ガール feat. K DUB SHINE」で下敷きにされていたからでした。その他、ミュート・ビートにしてもデ・スーナーズにしても、「ECDが使ったから」が根拠になって、自分の音楽の世界は広がりました。『BIG YOUTH』の冒頭、クール・ハーク、グランドマスター・フラッシュ、ラキム、KRS ONEの名前が出てくるのですが、無知な自分としては、それらがなにを意味しているのかまったくわからない。人の名前だったと知るまで、まるで呪文のように頭にこびりついていました。あるいは、「復活祭」においてシャウトアウトされるポール・Cや江戸アケミの名前。こちらは、人名だとは分かったけど、いくらヒップホップの棚を見ても、ポール・CのCDなどないし(エンジニアだから当然だ)、江戸アケミという人も見つからない。だから、さらに調べて探す(遅いぞ、追いついて来い)。僕にとって1998年とは、ECDさんに導かれるように、次々と新しい音楽に出会う幸福な時期でした(この点においては、実はもうひとり、同時期のDEV LEARGEという存在もすごく大きかったです。ECDさんもDEV LEARGEさんも亡くなってしまい、僕の音楽的原風景が無くなってしまった気持ちです)。
ECDさんはその後、ヒップホップ自体から距離を取るようになりました。「ヒップホップでなければ何でもいい」という態度で制作された『MELTING POT』をはじめ、この時期の作品(ka『MELTING POT』『THRILL OF IT ALL』『SEASON OFF』)は、アルコール中毒に悩んでいた時期ということもあるのか、いびつな印象もありますが、そのぶん、ECDさんが切り拓く新しい領域に食らいついて行こうと、熱心に聴き込んだことを覚えています。だから、いずれも大好きな作品です。avexを辞め、ECDさんが本格的に働き始めるのもこの時期で、個人的には、このあたりからECDさんがまた違うフェーズに入ったと思っています。自主盤として『失点 in the park』『ECDVD』『Private Control』シリーズなどが、安価で発売されました。『失点 in the park』のジャケットは、「反戦」「スペクタクル社会」と書かれた公衆トイレの写真です。この公衆トイレがあるわかば公園は、まさにECDさんを聴き始めた中学生時代、友人たちとのたまり場になっていたところだったので、驚きました。この頃から、音楽以上にECDさんの生きかたや態度について、深く受け止めるようになった記憶があります。正確に言えば、ECDさんの音楽に向き合うことがそのままECDさんの生活や考えに向き合うことを意味した、という感じでしょうか。例えば、アルバム『失点 in the park』はたしか、定価が1500円でした。レコード会社を通して高くするより自主盤で安く届けたほうがいい、というECDさんの信念の反映です。あるいは、サウンドデモの不当逮捕に対して作られた「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」という曲は、著作権とは関係のないところで朱里エイコの曲をそのまま使い、即日ウェブにアップされました。政治的なリリックだから政治的なのだということではなく、音楽にともなうECDさんの振る舞いすべてが、政治的なアティテュードとしてありました。僕自身、社会問題や政治思想を自分の問題として考えるようになったのは、明確にこの時期、ECDさんがきっかけでした。僕が刺激を受け、惹かれていたのは、労働も生活も表現もすべて飲み込んで、全身で社会と対峙しているECDさんのありかたでした。意欲的であり続けるECDさんの新作を聴くたび、生活人としての自分の中途半端さに恥じ入るような気持ちとともに、またエネルギーが湧いてくるのでした(遅いぞ、追いついてない)。
日々、仕事して給料をもらう。充実してもいるが、ときには疲弊もする。そんなときは、愛すべき音楽を聴いて、明日へのエネルギーとする。日々の労働のなかで感じたことや考えたことを、言葉にして文章を書く。生活のなかから言葉を練り上げる。その言葉をまた生活のほうに戻す。僕の暮らしは、だいたいこんなものです。でも、このなかに、話したこともないECDさんから受け取ったものがどれほどあることか。もちろん僕は、教員になるような退屈な男で、ECDさんのようなラディカルさやアナーキーさはありません。個別には、意見の違いもあるでしょう。とは言え、個人的な思いとしては、いま、この文章を書いている、明日、また仕事に行く、その行動ひとつひとつのなかに、ECDさんの存在が入り込んでいるように感じます。もしECDさんがいなかったら、いまの僕はばらばらにほどけてしまいそうです。その意味で、多くのファンと同じように、自分にとっていちばん大事なミュージシャンでした。とても悲しく、つらいです。
昨年、ECDさんの自伝的エッセイ『他人の始まり 因果の終わり』が出ました。家族をめぐるこの作品は、パンクスとして「個」になったECDさんが、その地点から、ヒップホップによって新しい「つながり」(POSSE)を築く物語だと思いました。大学院生のとき、アルバイトさきの中古レコード店が素人の乱の近くでした。夕方になると、近所のバンドマンから冷えた味噌汁の差し入れがあるなど、オルタナティヴな「つながり」を肌で感じていました。素人の乱店主のひとり、松本哉さんがおこなった「高円寺一揆」にECDさんが来るかもしれない、ということを、僕がECDファンであることを知っている、インテリパンクさんという年上の友人に教えてもらいました。当日、フィラスティンのDJ中にふらりと現れたECDさんは、アカペラで「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」を披露しました。高円寺駅前に出現した一時的自律ゾーンで大好きな「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」がラップされる、というスリリングな状況に、僕はずいぶん興奮し、いちばんまえで、ECDさんに合わせて、ずっと大声でラップをしていました。このときのことについては、ECDさんの『いるべき場所』という音楽的自伝の最後に書かれています。
しばらくして、司会らしきひとのリクエストで僕はアカペラで「言うこと~」をやることになった。最近のライヴではレパートリーから外れていた「言うこと~」は歌詞がうろ覚えで誤魔化し誤魔化しのラップだったが、ひとびとのレスポンスがそれを補って余りあるものだった。コール&レスポンスがあんなに自然発生的に盛り上ったのは自分のライブでは初めてのことだった。
いまでも思い出すのは、このとき、ECDさんが「わかっちゃいるけど路上解放区」という一節が出てこなくて、大声で歌っていた僕の声だけが一瞬、鳴り響いてしまったこと。僕のなかでは気恥ずかしい思い出として残っていたのですが、のちの『いるべき場所』によれば、ECDさんはその場面を「ひとびとのレスポンス」として捉えていました。ECDさんが書いている場面と僕が思い出している場面が同じという保証もないのですが、『いるべき場所』を読んだとき、自分がECDさんの「音楽的自伝」のなかに参加したようで勝手に嬉しくなりました。なかば妄想として自分に言い聞かせるように書きますが、単にテンションが上がっているだけの僕の声が、目のまえのECDさんにとって、ほんの少しだけでも力になったのなら、それはなんと喜ばしいことでしょう。涙が出そうです。もっとも、僕がECDさんから受け取ったエネルギーに比べたら、ほんの微々たるものですが。まったくの「他人」である僕は、「他人」であるからこその仕方でECDさんとともに歩ませてもらった、という気持ちがあります。ここには書ききれませんが、アルバムから12インチから、本当に全作品がそれぞれに素晴らしいです。そのようなECDさんの表現に触れることは、僕にとって生きることの一部でした。これは、ECDさんの言う「つながり」(POSSE)と言えるでしょうか。言いたい気持ちはあるけど、わかりません。ECDさんの死後も、そのような「つながり」(POSSE)の感覚は維持されるでしょうか。ECDさんといつまでも。
労働と生活と表現のすべてを飲み込んで、最後まで全身でこの社会を生ききったECDさんが亡くなってしまいました。ECDさんのファンである僕も、ECDさんのように、働き、生活をし、表現をし、全身で生ききりたいという気持ちがあります。でも。でも、ECDさんが亡くなった以降にそれを実践するのは、とても厳しいよ! ああ、悲しいよ! 体がばらばらになって、ふとしたとき、自分が自分でなくなってしまうようだ! だって、いまの仕事をしていることも、それを続けていることも、その合間にこうやって文章を書いていることも、その出発点にはECDがいるじゃないか! あの、まっすぐに社会と対峙し、そこから唯一無二の表現を練り上げるECDの姿が! ECDがいたから! 本当にありがとうございました! 本当に本当にありがとうございました! これからがんばってみます! どうか、安らかに。
追悼ECD
野田努
ぼくが石田さんの曲でいまでも強く印象に残っているのは、“言うこと聴くよな奴らじゃないぞ”だ。2003年の対イラク戦争への反戦集会で、石田さんは1枚100円でこの曲のCDRを手売りしていた。その曲はデモ隊への励ましの曲だった。2年前のSEALDs主宰の国会議事堂前の抗議集会のときに、酸欠か何かでひとりの女性が倒れたことがあった。数人の男性がその女性を救護していたのだが、そのひとりが石田さんだった。あ、ECDがいる、と遠目に見ながら思った。石田さんはずっと変わらずに、仕事をしながら音楽活動を続け、ある時期からご家族を支えようと奮闘し、現場での献身的な(反戦、反原発、反差別などの)抗議活動も続けていた。そんなアーティストがこの世から消えたのだ。覚悟していたこととはいえ、あらためてその喪失感を感じている。とても悲しい。24日朝方の悲報に日本中のファンが大きな悲しを覚えたことと思う。
ぼくが初めてお会いしたのは『Big Youth』(1997年)のときだった。「最近は働きながらバンドやっている連中に共感する」みたいなことを、当時はメジャーレーベルに所属して、ヒップホップのスポークスマン的な立場をこなしていた彼は言った(まだミュージシャンがそれなりに潤っていた時代にである)。『シック・オブ・オール・イット』のときは自分はヒップホップと同じようにパンクも好きなんだと、この元ロック少年はなんども「パンク」を強調した。それ以降も断続的にお会いする機会があった。2000年代前半の『ファイナル・ジャンキー』の頃はライヴハウスでなんどかライヴを観ている(共演者はハードコア・バンドのSFPであったり、ヒップホップ・グループのMSC であったり……まさにパンクとヒップホップのECDだった)。個人的に好きな曲がMute Beatをサンプリングした“ECDのAfter The Rain”だったので、こだま和文さんと対談してもらったこともあったな。
ぼくが最後に編集長を務めた009年の『remix』で(『天国よりマシなパンの耳』の頃)、「ボヘミアン」をテーマに原稿を依頼したことがあった。そうしたら文中に当時の自分の所得額をしっかり書いて、月40万もらっていたメジャー時代の収入の半分にも満たない「いま」のほうが、もちろん不安を抱えてはいるが、生きていて楽しいというようなことを書いてきた(家族がある身でそれだけじゃダメなんだけど、とも加えて)。そういうことを本心からさらっと言えてしまうのが、ECDだった。ピュア、あるいはピュアリストという言葉は、ときにシニカルな使われ方をするけれど、石田さんはぼくから見て、デヴィッド・ボウイの歌詞の世界を本気で実践しているかのような、あまりにもピュアで、ある意味ピュアリストだった。その真面目さに息苦しさを感じたこともあったけれど、ぼくが知る限りで言っても、ECDは見えないところで人を助ける人だった。くだんの原稿のときは、ジョージ・オーウェルの『葉蘭を窓辺に飾れ』の翻訳本の表紙を自分のページのヴィジュアルに指定してきたが、この世知辛いご時世のなか、ある種プロレタリアートめいた自分を誇りにさえ思っていたのではないだろうか。それはいわゆる清貧主義ではないと思う。それはいまになってもぼくには説明がつかない、ひとつの信念のようなものが彼にはあるんだとずっと感じていた。そうえいば、ECDとは稲垣足穂の『弥勒』に出てくる江美留について話したこともあった。
昨年の春頃、紙エレキングのヒップホップ特集の際に取材でお会いしたのが結局は最後となってしまった。貧困問題をテーマに喋ってもらったそのときにも「お金がなくても自由だぜ」ってことを伝えたい、と彼は言った。気の利いた未来像などラッパーは言わない、ただ「生きてるぜ」ってことを見せるのがラッパーだ、と彼は言った。なんて力強い言葉だろう。いつだってECDは弱き者、不器用な者、ドロップアウター、スマートには生きられない者たちの味方であり、基本的にそこから外れたことはなかった。石田さん、本当に本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。心からご冥福を祈ります。
(※写真は、カメラマンの小原泰広が2007年に『失点 in the Park』で描かれた下北沢の公園で撮影したものです)
『いるべき場所』のこと
大久保潤
ECDによる私的音楽史を書いてほしいと思ったのは、『RECORDer』というミニコミと『クイック・ジャパン』誌に載った「ECDの音楽史」という記事がきっかけだ。前者は日本のパンク/ニューウェイヴ、後者は日本のヒップホップ・シーンについての貴重な目撃証言だった。
とはいえ、当時の自分はECDとは面識もなく、紹介してもらえるような知人もいない。どうやって連絡を取ったらいいか考えた末、『SEASON OFF』収録の“GO!”という曲で、自分の住所をラップしていたので(!)、それを頼りに手紙を書くことにした。
「もう引っ越してるかも……ていうかそもそも本当の住所なのかな?」とか思いつつ投函するとほどなくメールが届き、下北沢駅前の、駅舎に隣接したドトールで会うことになる。寡黙だが発言に無駄のない人なので、話は早かった。音楽的自伝という趣旨で、基本的に1章につき10年分とすること(1960年生まれなので、産まれてからのことを10年ごとに書いていくとちょうど60年代、70年代……となるのだ)にして、毎月1章ずつ書いてもらうことにした。途中から内容の濃くなる時期は5年で1章になったりもするが、それでも半年くらいで書き上がる計算だ。
それから月に1度、同じドトールで会うことになる。原稿用紙に鉛筆書きで推敲の跡も生々しく残った原稿を受け取り、その場で目を通す。書いた本人が目の前にいて、無言でじっと見ている中で原稿を読むというのはこちらも緊張する時間だったが、さいわい毎回面白かった。そのドトールはもうずいぶん前になくなってしまったけれど、下北の南口に出ると今でも当時の店内の様子とECDの顔が目に浮かぶ。
締め切りはきっちり守ってくれて(時にはちょっと前倒しでくれることすらあり)、そこから本が出るまではスムーズだった。こちらは『ECDの音楽史』というタイトルを考えていたのだが、本人が『いるべき場所』にしたいという。ちょっとわかりにくいでは?という気もしたのだが、居場所を求めて様々なシーンを転々とする軌跡を描いた本なので、すぐに納得した。一冊の本のタイトルであることを超えて、ECDの人生を表すキーワードのとなったと思う。
最後に新しく彼女ができたことを明かしてこの本は終わっている。その「彼女」と結婚して間もなく子供も生まれ、ECDの人生はまた新たな局面を迎えた。それ以外にもいろんなことがあったその後10年のことを加えた『増補版 いるべき場所』を作りたかったのだけれど、それもかなわなくなってしまった。「直したい箇所がある」とは聞いていたので、せめてそこだけでもちゃんと教えてもらっておけばよかった。今はそのことばかり考えている。
ダンス・ミュージックがもたらしたリズムの発明は、フィジカルな肉体の運動を促すものだけではない。ある種の、甘美なる怠惰のためのBGMというか、リラックスのためのビートも生み出している。ある種のヒップホップの手法だったブレイクビーツから派生したダウンテンポと呼ばれる音楽は、リラックスのための最良のグルーヴを生み出した(もちろん、そのリズムであなたがゆったりと体を動かすことは自由だ)。ジョージ・エヴリン(DJ E.A.S.E.)を中心としたプロジェクト、ナイトメアズ・オン・ワックスとは、その名前とは裏腹に、心地よいその手のサウンドのイノヴェイターとしてUKの音楽史に30年近く君臨してきたアーティストだ(そういえば、LFOのマーク・ベルが2014年に死去したことを考えれば〈WARP〉の最古参アーティストでもある)。
1995年にリリースしたセカンド・アルバム『スモーカーズ・デライト』が、そのアーティスト史的には転機と呼べる作品であり、音楽史に残るある種の発明でもある。ソウルやファンク、R&B、そしてレゲエ/ダブなどを吸い込んだ、ヒップホップ的なサンプリング・センスと、ザ・KLFの『チルアウト』のコセンプトを掛け合わせたというそのサウンドは、まさにヒップホップのある種の“チルアウト性能”を極限まで音楽的に増大させた。それはダウンテンポ(もしくは当時の流行り名でいえばトリップホップ)と呼ばれる音楽の雛形のような作品となった。そのタイトルが象徴するようなある種の実用性(むろん、そこから離れた単なるリラックスした空間での実用性も含めた)のなかでのサウンドトラックとして増殖し続け、フォロワーも星の数ほどいるジャンルとなっている。
 Nightmares On Wax Shape The Future Warp / ビート |
前置きが長くなったが、ここにナイトメアズ・オン・ワックスの実に5年ぶりとなる8作目の新作『シェイプ・ザ・フューチャー』が届いた。野太いベースとソウルフルなサウンドに支配されたダウンテンポ──基本サウンドはもちろん『スモーカーズ・デライト』から変化がないと言えるかもしれない。しかし、もはやそれは彼の作品を貫く美学でもある。もちろん、これまで以上に熟成したサウンドが展開されてもいるし、そして新たな変化もある。ひとつ新作の特徴を挙げるとすれば、それは歌にフォーカスしたアルバムと言えることだ。これまでの作品にも参加してきた、モーゼズ、LSK、クリス・ドーキンス、JD73、シャベルといったシンガーに加えて、サディー・ウォーカー、ジョーダン・ラカイ、アンドリュー・アショングなど新世代のシンガーも参加しており、アルバム全体としてはR&Bへとそのサウンドの舵をきっているとも言えるだろう。彼のサウンドの長年のファンに説明するとすれば、どちらかといえば近作2作のファンキーなビート・サウンドの作品よりも、『マインド・エレヴェイション』や『イン・ア・スペース・アウタ・サウンド』といった、歌モノが心地よい、よりチルな雰囲気のシルキーでソウルフルなサウンドを思い浮かべてもらえればいいかもしれない。甘美な怠惰のためのビートはソウルフルに鳴り続けるのだ。
メディアの言うこと、政治、他人が言ったことではなく、自分のフィーリングや自分と誰かの会話から生まれるものに従って世界を見て、未来を作っていくという意味さ。
■現在もリーズに住まわれているんでしょうか? それともイビサですか?
ジョージ・エヴリン(George Evelyn、以下GE):イビザだよ。もう11年になる。
■制作はどのくらいの期間で行われたのですか?
GE:3~4年くらいかな。はっきりとは言えないんだけどね。というのも、俺はアルバムを作ろうと決めて作品を作り出すわけではないから。常に曲を作っていて、ある程度の数ができあがったときに、それにアルバムとしてのまとまりを感じれば、そこで「お、これはアルバムになるな」と思うんだ(笑)。
■〈WARP〉の他のアーティストもそうだと思いますが、リリース・サイクルは自由なんですね(笑)。
GE:そうだよ。あまり「なにかを作らなければいけない」という考えに縛られるのが好きじゃないんでね。自分のなかから自然に出てくるものを活かしたいんだ。締め切りとかに制限されず、自分の音楽には自由なスピリットを取り入れたい。そっちの方が、誠実な作品を作ることができるからね。
■資料には本アルバムの制作をして「肉体的にも精神的にも新しい旅をした」と書かれていますが具体的にはどんなところでしょうか?
GE:肉体的というのは、もちろんツアーで旅をしていたこと。そして、その旅を通じて様々な文化を体験したし、国を訪れる度に、現地の人たちに聞いて、その土地の社会や経済、政治、音楽シーンについて学んだんだ。それによって、世界をまた違った角度から見ることができた。様々な問題や崩壊したシステムが存在することがわかったし、俺は、それに興味を持ったんだ。精神的というか、内面的にも様々なものを見て、感じたんだよ。その経験を通して、世界の見方について考えるようになった。多くの人々は、自分の目で世界を見ていないと思う。外部からの情報に影響されていて、その情報は正しいものでなかったり、ポジティヴでないものが多いんだ。そこで、もし自分たちがそういうものに左右されず、情報、政治、宗教がなく、自分たち自身の見解で未来を考えたらどうなるだろうと考え始めた。世界をどう見るか自分たちにはどんな未来にするかを選ぶ選択肢があるということ。それに気づき、それを表現したいと思ったんだ。
■それでアルバムのタイトルが「Shape The Future」なんですね?
GE:その通り。メディアの言うこと、政治、他人が言ったことではなく、自分のフィーリングや自分と誰かの会話から生まれるものに従って世界を見て、未来を作っていくという意味さ。
■本作はこれまでのあなたのキャリアで最も“歌”に注力したアルバムではないかと思うんですがいかがでしょうか? もしそうであれば理由も教えてください。
GE:結果的にはそうだね。でもさっきも話したように、俺は計画して作品を作るわけではないから、たまたまそうなったんだ。ただそれくらい、今回は伝えたいメッセージがあったんだろうね。俺の音楽は作っている時の自分の状態が映し出されたものだから。
■Little Ann “Deep Shadows”をカヴァーしたのはなぜですか?
GE:アルバムに女性のミュージシャンをフィーチャーしたらいいんじゃないかという話をマネージャーとしていて、マネージャーが送ってきた曲の候補の中にあの曲があって、いいなと思ったんだ。誰かと親しくしていても、その関係の中でなにかが満たされないというか。ひとつの方向にとらわれず、複数のアングルから人間関係を見ているのが面白いと思った。そういう曖昧な部分に惹かれたんだ。
■これまでの作品にも参加してきたシンガーに加えて、ジョーダン・ラカイ、アンドリュー・アショングといったシンガーも名を連ねています。彼らはどのように起用したのでしょうか?
GE:ふたりとも、俺のイベント《Wax Da Jam》に参加してくれたアーティストなんだ。アンドリューとは、曲を作って、去年EPとしてリリースしたんだけど(註:2016年のEP「Ground Floor」のこと)、その作品の出来が良かったからまた彼を招くことにしたんだ。さっき話したイベントのクロージング・パーティーでジョーダンはプレイしたんだけど、その次の日に俺の家でバーベキューをやって、それに彼が来て、その流れで一緒にスタジオに入ってレコーディングした。その曲をアルバムに入れることにしたんだよ。
ベースは、暖かい毛布のようなもの。そう考えればいいのさ(笑)。寒かったら、俺のレコードを聴けばいい(笑)。
■また今回はウォルフガング・ハフナーなど、ジャズ・ミュージシャンの演奏も多く取り入れている模様ですが、このあたりはどういったコンセプトがあったんでしょうか?
GE:いや、ないね。さっきも話したように、あまり何かを決めて作品を作ることはないから。これまでもジャズ・ミュージシャンたちとはたくさん共演してきているから、俺は特に多いとは感じていない。アルバムに参加してくれているミュージシャンたちは、皆友だちなんだ。彼らのような素晴らしいミュージシャンに参加してもらえたのはすごく嬉しいね。
■全体の何割ぐらいをミュージシャンの生演奏を使っているのですか?
GE:50%くらいだと思う。このアルバムに限らず、俺は常にアナログとデジタルの融合を意識している。
■やはりいまでもサンプリングという作曲方法にマジックを感じていますか? それはどんな部分ですか?
GE:もちろん。サンプリングは俺にとって主要な表現方法だからね。サンプリングに自分のアイディアを混ぜ、新しいものを作る。俺のバックグラウンドはヒップホップだから、サンプリングは俺をここまで連れてきてくれた基本。曲作りにおいてだけでなく、曲選びのスキルもサンプリングで鍛えられたと言ってもいい。サンプリングの魅力は、ある曲のわずかな数ミリの瞬間をもとに、そこにアイディアを加えて混ぜることで、全く新しい作品が生まれるところだね。
■あなたやJ・ディラといったアーティストが切り開いたブレイクビーツ・ミュージックが逆に新世代のジャズ・アーティストに影響を与えるという状況もでているようです。こうした事態に関してあなたはどう思いますか?
GE:興味深いと思うよ。インスピレーションの循環のひとつだと思うし、それがナチュラルに起こっているならより良い。意識してやってしまうと、それはコピーになってしまうからね。インスパイアされることによって自分の作品がより深いものになるなら、それは素晴らしいことだと思う。
■最近のジャズやR&Bのアーティストでおもしろいと思うアーティストはいますか? たとえばハイエイタス・カイヨーテやロバート・グラスパーなどはどう思いますか?
GE:Electrio っていうイギリスのグループで、彼らはすごく面白いよ。それからニック・ハキム。ハイエイタス・カイヨーテもロバート・グラスパーも素晴らしいと思うよ。ハイエイタスはアルバムも良かったし、去年フェスで一緒になったからパフォーマンスを見たけど、あれは素晴らしかった。あと、カマシ・ワシントンも最高だね。
■アラン・キングダムはなぜ起用したのでしょうか?
GE:すでに作っていた曲があって、そこにもっと若いエナジーを加えたいと思いつつそのままになっていたんだ。でも、あるときアランがスタジオに来る機会があって、彼がピッタリだと思った。彼はコンテンポラリーなヒップホップ・アーティストだし、アルバムにダイナミックさをもたらしてくれると思ったんだ。
■この作品に限らず、いくつかの例外はあるにせよ、あなたの作品は基本的にある種のベース・ミュージックだと理解しています。とても心地よいヘヴィーなベースがずっとなっていて、それが楽曲全体を印象づけていると思っています。
GE:どうだろう(笑)。心地よい音楽を作っているつもりではあるし、暖かいベースを作りたいとは思っているけど(笑)。暖かくもありながら、セクシーな気分になったりダンスをしたくなるベースでもあり、かつハッピーにもなれるベースが最高だね(笑)。
■ベース・ミュージックをうまく作る秘訣を教えてください!
GE:ハートで音楽を作ることさ。頭ではなく、ハートで作ること。ベースは、暖かい毛布のようなもの。そう考えればいいのさ(笑)。寒かったら、俺のレコードを聴けばいい(笑)。
■あなたの音楽は『Smokers Delight』という作品の名前が象徴的ですが、スモーカーたちを喜ばせ続けるようなサウンドをリリースし続けています。歳をとるとやめてしまう人もいますが、あなたはいまでも優秀な“スモーカー”ですか?
GE:今は若い時ほどは吸わないね。例えば、今も3日間吸ってない。自分にとって前ほど必要なものではないよ。
君はダブクラを知っているか? もしまだ知らないのなら早めにチェックしておいたほうがいい。グライムから影響を受け、いま東京でもっとも尖った音楽をやっているアクトのひとつだ(インタヴューはこちら)。そんなダブクラこと Double Clapperz が新たに10インチEPをリリースする。今回は東京の若手トラックメイカー、EGL とのコラボEPで(EGL はファティマ・アル・ケイディリのリミックスも発表している)、発売は2月中旬を予定。リリース元は彼ら自身のレーベル〈Ice Wave Records〉。また、フィーチャーされている Ralph は20歳の若きラッパーで、彼にとっては本作が初のフィジカル・リリース作品となるそう。そろそろ君も馴れ合いをやめて、斜に構えてみてはいかがだろう?


Double Clapperz & EGL -
斜に構える feat. Ralph / Obscure VIP
A. EGL - 斜に構える feat. Ralph (Double Clapperz VIP)
B. Double Clapperz - Obscure (EGL VIP)
発売 - 2月中旬
※アナログ・リリース・オンリー
MP3ダウンロード付き
購入リンク:https://doubleclapperz.bandcamp.com/
■Ralph
Instagram - https://www.instagram.com/ralphlamed/
■EGL
SoundCloud - https://soundcloud.com/itsegl
Twitter - https://twitter.com/ItsEGL
Instagram - https://www.instagram.com/itsegl/
■Double Clapperz
SoundCloud - https://soundcloud.com/doubleclapperz
Twitter - https://twitter.com/doubleclapperz
「午前中、ある村から帰るとき、大きな狒狒が、車のわずか十メートルくらい前の道路を横切った。リュタンはよだれを流す、文字通り。しかし僕は、いかなる狩猟本能の爆発も感じないので、ただ、猿の青い尻に目をとめただだけだ。思ったより鋼鉄色を帯びた青だ」(ミシェル・レリス/岡谷公二・田中淳一・高橋達明訳/平凡社)
ミシェル・レリスは1931年5月19日から33年2月16日までの1年9ヶ月にわたったダカール=ジブチ、アフリカ横断調査団の公的な日誌の体裁をかりた日記文学『幻のアフリカ』の31年7月31日づけの記録に上記の文章を書きつけている。彼らはこのとき仏領スーダン、いまのマリ共和国西部のキタに滞在していた、午前いっぱいをあたりの調査についやした帰り道、同じ車に乗り合わせた調査団の同僚リュタンは車上から猿をみてよだれをながさんばかり。というより文字通りよだれをながしたのだった。興奮したのだろうね。それは狩猟本能の爆発だとレリスは書く。しかし彼の指摘は日本人の読者にぴんとこないかもしれない。食料をえるためにではなく、動物を狩る、仕留める、殺すことはこの社会一般に広く浸透しているようにはみえない。すくなくとも私にはそう思われた。むろん封建時代の王侯貴族や、日本では大名や将軍にとって狩りは彼らの特権を確認する余暇であり、近代以降はブルジョワがとってかわり、たとえば、この映画の資料も言及するヘミングウェイがアフリカへの狩猟の旅をもとにしたためた『アフリカの緑の丘』などにも脈々とうけつがれている。ヘミングウェイのアフリカにいったのは1933年なので時期的にはちょうどレリスがフィールドワークしてまわったころとかさなる。広大なアフリカ大陸でふたりは交錯する、私はそこに偶然ときってすてられない符牒めいたものをおぼえもする。大戦間の欧米には非西欧への憧憬がまだ生きていた。近代におこったそのような機運は20世紀にはいってから、音楽でいえばサティやドビュッシーを刺激し、ブルトンの通底器となり――かつてシュルレアリストだったレリスはブルトンと袂を分かってアフリカに出てきた――フロイトの無意識にも働きかけたかもしれないが、産業革命以後、狭くなった人間の世界認識が求める他者と外部は同時に帝国の海外侵出の契機ともなった。国家にとってのエキゾチシズムとは侵略である。日本が東アジアに乗り出したように欧州はアフリカや東南アジアに植民地をもうけた。とはいえポスト・コロニアルの論点整理は本稿の任ではないのでこのあたりできりあげたいが、レリスのアフリカ行もほとんどがフランスの植民地をめぐるものであり、それらの地名のいちぶはたとえばパリ=ダカール・ラリーなどの名称にのこっているのはおぼえておいてソンはない。
ウルリヒ・ザイドルのドキュメンタリー『サファリ』の舞台はナミビア、テーマはトロフィーハンティングである。またしても聞きなれないことばだが、獲物の毛皮や頭めあてに金を払い狩猟する、おもにヨーロッパの観光客をあてこんだ、現在のアフリカ諸国の一大観光資源ともいわれるレジャー産業であり、耳ざとい読者におかれては、数年前獲物となったライオンの前で誇らしげな写真をSNSに載せたアメリカ人歯科医師の投稿が炎上したのをご記憶かもしれない。ことほどさようにトロフィーハンターたちは写真を撮る。せっせとそうする。『サファリ』に登場するハンターたちも例外ではない。殺しのあとに彼らがとりかかるのは写真を撮ることだ。
中年のハンターは死んだヌーの鼻面をぽんぽんと叩きこういう。頑張ったな、友よ、と。ヌーの肩口の致命傷となった銃創に血がにじんでいる。猟犬のルビーがそれを舐める。簡単ではなかった。銃弾を放つまで、ハンターたちは息をつめる。十分な距離まで接近するまで動物にけどられてはならない。ガイドはハンターに耳打ちする。ゆっくり時間をかけて自分のタイミングで。かすれた囁き声は性交のときの睦言に似ている。それとも悪魔の囁きだろうか。さあしっかり狙いをさだめて、いつものように――ガイドはそんなことはひとこともいっていないがそんなふうに聞こえそうになる。息をつめる。間。世界が真空になった。ハンターはひきがねをひく、発射する。だいたいが数百メートルの距離なので命中したかはすぐにはわからない。獲物にちかづいていく彼らの背中にことを終え一息ついたあとに戻ってくる社会性がおいすがる。息絶えた動物を前に安堵するハンターはパートナーやガイドとかたく抱き合う。よくやった、と。一家4人でトロフィーハンティングにやってきた母親は娘にこういう。あなたに自信をつけさせたいの。そこで訪れる解放感と達成感と癒やしと、そのために生命を奪う愚劣さとを私はどう天秤にかけていいのかわからなくなる。すぐれて倫理的だが一般道徳ではたやすく片づけられない。

ウルリヒ・ザイドルはそのようなものをつねに追い求めてきた。ドキュメンタリストとしてキャリアをスタートし、5作目の『予測された喪失』(1992年)は翌年の山形国際ドキュメンタリー映画祭のコンペティション部門で優秀賞を獲得した。2001年の初の長編フィクション『ドッグ・デイズ』でもヴェネチアで賞をもらっている。「愛」「神」「希望」と題した『パラダイス三部作』(2012年)の記憶はいまだあたらしい読者もすくなくないだろう。私もそうです。リゾート地の黒人男性の買う欧州の中年女性、宗教と世俗をめぐる聖と性、欲望における自我と愛――そのような人間の芯の部分にある、たぶんに生きることにかかわるなにものかをザイドルはみつめつづけてきた。したがって私は編集を担当した『別冊ele-king』のジム・オルークの特集号のインタヴューでジムさんが三部作の「希望」を激賞し「私はザイドルのスーパーファン」というのを聞いてミミズ腫れするほど膝を叩いたのは、透徹ということばではなまやさしい対象の物自体にむかう視線に彼らの共通項をみた気がしたからだ。
映画はもちろんあらゆる表現形式をみわたしてもそういうひとはそう多くはない。
ザイドルはパゾリーニ、ヘルツォーク、ブニュエル、ユスターシュやタルコフスキーやカサヴェテスらが映画の道に足を踏み入れたときのアイドルだったという。ヘルツォークが「私はザイドルほどには地獄の部分を直視していない」とコメントしたのは『ドッグ・デイズ』のときだっただろうか。そのザイドルもいまやハネケとならぶオーストリアを代表する巨匠である。だからといってザイドルの筆致が鈍るわけではない。『サファリ』にも下腹に響くシーンが頻出する。ことに後半銃弾に斃れたキリンがこときれるまえ、長い首をもたげ、傾げて絶命する場面。死んだキリンは現地の男たちが解体する、その場面もザイドルはきっちりフィルムにおさめている。キリンの皮があれほど厚いとは上野動物園にいっても志村動物園をみても絶対にわからない。あふれでる内蔵のいろとりどりのグラデーション、皮を剥がれた動物たちの真皮の白さ、目をそむけたくなる作業を、しかし現地の男たちは生活の糧をえるためおこなっている。たんたんとした、滑稽なほど即物的な作業風景には映画史における狂気にとりつかれた殺人者たちの姿がオーバーラップするがこれが彼らの日常の場面なのだ。そしてそこにはドキュメンタリーならではの出来事、現実の死が表現の形式にとりこまれるさいの虚構とのせめぎあいがおこる。逆のパターンは、ネオレアリズモからもヌーヴェルヴァーグからも何十年も経ったいま、なかなかにむずかしい。たとえば河瀬直美監督の『2つ目の窓』(2014年)のじっさいにヤギをしめる場面が虚構に嵌入した現実そのものではなく、たんにロマン主義的なメッセージを代弁してしまっていたこと。すくなくとも、シマでヤギをしめるときはあんなふうではなかった。私は十六で本土の学校にあがるときのお祝いはヤギ汁だったが、ヤギをしめたひとたちはむしろ『サファリ』の解体するひとたちにちかった。

とはいえ『サファリ』でも、ことに後半にいたって、富裕な白人と貧しい現地のひとたちという図式的な描き方になっていたのはいぶかしかった。ザイドルの本領は告発にとどまらないはずだからである。ザイドルは作中でハンターにインタヴューを試みる一方、作業に従事する黒人たちはことばを発さない。資料によれば、その必要性を認めなかったとのことだが、ザイドル特有のファインダーに正対した人物たちの記念撮影を思わせる不動のショットは白人と黒人とを問わず、人間たちをひとしなみに無時間性のなかに置き去りにする。あたかも装飾品として流通する動物たちの頭部のように。
やがて『サファリ』はレヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』の最後の一文と同工異曲の発言で幕をおろした。私はつまるところザイドルも古典に答えを求めたのか、と明るくなった試写室でしばし思案したが、よくよく考えると、そのことばの主こそ動物を殺す当事者なのだと気づいたとき、思考があざやかにひっくりかえるような感じをおぼえた。これがあるからザイドルは見逃せない。(了)