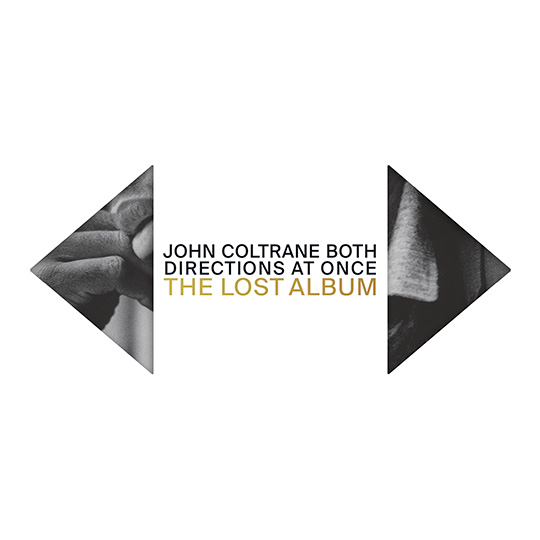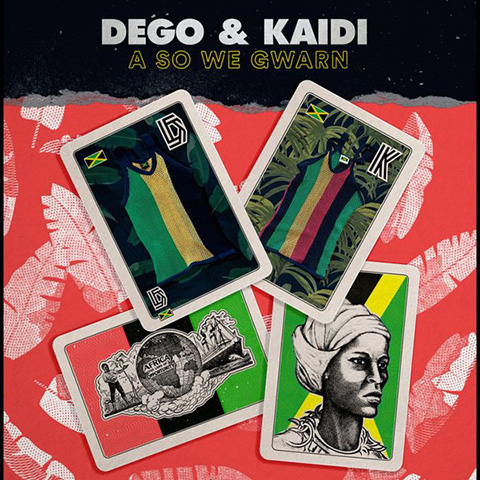Moodoid シテ・シャンパーニュ Because Music/ホステス |
フランスはなんだかんだといかなる時代においても強力なポップスを生んでいる。とくにこの20年あまりは、エディット・ピアフやセルジュ・ゲンズブールの時代のような言葉への強いこだわりよりも、エレクトロニック・ミュージックとダンス・サウンドへの注力によって、国際舞台で活躍するアーティストを多数輩出していることはみなさんもよく知っての通りである。ダフト・パンク、エール、カシアス、ジャスティス、あるいはシャルロット・ゲンズブール……。それらは別次元からやって来た別次元のポップスのようにぼくたちの耳を楽しませる。ムードイドはひょっとしたらこの輝かしい流れに乗れるかもしれない。
で、ムードイドという謎めいた名前の正体だが、パブロ・パドヴァーニなる青年が率いるプロジェクトのことである。ムードイドはすでに3年ほど前の2014年に最初のアルバムを出している。それはエールの美学を受け継ぐファンタジーで、しかめっ面をして聴くようなタイプの音楽ではない。そして新作『シテ・シャンパーニュ』においてムードイドは、まさに21世紀のフレンチ・ポップと呼びうる音楽を完成させている。その2枚目となるアルバムでパブロは、ゲンズブール流のポップスとエール流の音響をところどころつまみあげ、それぞれの良さを結合させると、アメリカや日本の音楽からの影響もうまい具合にミックスする。日本? 水曜日のカンパネラの新しいEP「ガラパゴス」には1曲ムードイドが共作というかたちで参加している。じっさいパブロ・パドヴァーニはかなりの量のJ-Popを聴いているようだし、『シテ・シャンパーニュ』はJ-Popに影響されたフレンチ・ポップというなんとも奇妙なハイドブリッド感を有している。
取材がはじまる前に、ムードイドは日仏会館の中庭でたこ焼きを食していた。うん、とてもおいしかったという満足した顔で、彼は初夏の日差しが差し込む取材の部屋にやって来た。椅子に座って、そして以下のような興味深い話をしてくれた。
例えば、日本ってけっこうポルノっぽいものとか、ゲームだったりとかが日常のなかに溢れていて、そういう騒々しいもの、猥雑なものと、それから伝統的なものとか、禅の考えとか、風水的な考えとかが、本当に自然に共存していると思います。フランスでは考えられないです。
■ムードイドのフランスっぽさは、ご自身、意識して出しているんですか?
パブロ・パドヴァーニ(Pablo Padovani以下、PP):じつはフランスでは、ムードイドの音楽はアングロサクソン、英語圏の音楽に近いと言われています。というのも、フランスの音楽、フレンチのシャンソンと言われるものに関しては、非常に歌詞が重要なんです。けれど僕にとって歌詞というか、声はインストゥルメンタルのひとつ、楽器のひとつとしか思っていないので、そういった意味では、もしかしたらフランス的というのが少ないかもしれないです。
でも、たしかに新しいアルバム『シテ・シャンパーニュ』ではもう少しヴォーカルを意識したりとか、ちょっとセルジュ・ゲンズブールぽく歌ってみるとか、ちょっと官能的な感じでウィスパーヴォイスを使ったりとか試みています。フランスにはジェーン・バーキンをはじめ、ウィスパーヴォイスを上手く使う歌手が多くいるので、そこはちょっと意識しました。
■なるほど。あなたの初期の曲 “Je suis la Montagne(ジュ・セ・ラ・モンターネ)”がとても好きなんですが、これを聴いたときにはエールとゲンズブールを合体させてアップデートしたようなふうに感じました。
PP:たしかにエールはすごくインスピレーションのもとになっています。彼らが醸し出す雰囲気が大好きですね。その曲ではリヴァーブのなかにヴォーカルが埋もれているようなところがあると思いますが、これはケヴィン・パーカーの仕事です。彼はテーム・インパラとかMGMTとかの仕事をしていますが、そういったところが感じられるのではないかなと自分でも思っています。
■さっきあなたがおっしゃったように、たしかにファースト・アルバムはUK、USのロックの影響を感じましたし、ムードイドをやる以前のメロディーズ・エコー・チャンバーの音楽なんかはすごいUKっぽいですよね。そういうあなたのこれまでのキャリアを考えると、今作『シテ・シャンパーニュ』はすごくフレンチ・ポップというものを感じました。
PP:いま「フレンチ・ポップ」と言ってくれたことは、すごく正しいと思います。というのも、ヴォーカルをもう少し意識したということもありますし、ポップというのは自分のなかですごく大きいからです。ただ、影響としてはフランスの音楽ではなく、じつは日本だったりアメリカだったりの80'sのものにすごく影響を受けて作ったアルバムなんです。
たとえば、アメリカのプリンスの影響を色濃く反映させた曲を作るのではなく……、そういう意味では、坂本龍一、YMO、『パシフィック』……松下誠、坂本慎太郎、コーネリアスとか、そういった日本の音楽が、今回のアルバムに関しては自分のインスピレーション音源でした。なので、そういった意味ではハイブリッドという言い方もできるのではないかと思います。
■すごく高名なジャズのサックス奏者であるお父さんがいる音楽家庭で育ったと思いますが、ジャズではなくロックやポップスみたいな方へいったのは、お父さんに対する反発心みたいなものがあったからですか?
PP:反発と言えるかどうかはわからないです。とにかく、ポップ・カルチャーに自分は非常に影響を受けていると思います。もともとは映画の勉強をしていたので、ムードイドという名前が知られるようになったのは、自分が作ったMVからだと思っています。“ジュ・セ・ラ・モンターネ” もそうですし “De Folie Pure(ホーリー・ピュア)”という曲も自分でクリップを加工しています。そこが自分のもともとのルーツというか、音楽に関してもポップ・カルチャーの方から来たのではないかなと思っています。ただ、今回のアルバムに関しては、フランスの若いジャズ・アーティストを呼んで、「80年代的な感じで、ジャム・バンドみたいにして自由にやって下さい」と言って録音したので、ジャズの要素もこのアルバムには含まれているのではないかと思います。

国境を無くすということがこの時代のポップ・カルチャーのいちばん大きな部分だと思います。というのも新しいアーティストが受けている影響というのは、インターネットのおかげで、国境が非常に無くなってきている。例えば、J-POPがすごく好きなのですが、YouTubeが無ければ、こんなにたくさんのJ-POPを知ることができなかったと思います。
■ポップ・カルチャーというものの可能性についてどう思いますか?
PP:ポップ・カルチャーには非常に可能性を感じています。自分たちの世代はインターネットもありますし、新しいメディアの形も変わりつつある時代なのではないかと思います。そういったなかで、クリエイティヴィティというものにも新しいものが求められていて、新しいものが出てきている時代だと思うんです。音楽ひとつとっても、クリップも非常に大事ですし、ヴィジュアルも大事ですし。そういった意味で、音楽に対する新しいアプローチというものが求められる時代に生きていて、新しい音楽の歴史がはじまっているような気がします。ポップ・カルチャーはまだまだ新しい扉が開かれるのではないかと思っています。昨日、水曜日のカンパネラと一緒にクリップを録ったのですが、日本人の仕事を見ていると僕たちの20年は先を行っているように思いました。フランスではありえないような、新しいやり方、斬新なやり方がとられていて、まだまだこれから可能性があるんじゃないかなと思えたところでもあります。
■ポップ・カルチャーが成しうる最良のことは何だと思いますか?
PP:国境を無くすということがこの時代のポップ・カルチャーのいちばん大きな部分だと思います。というのも新しいアーティストが受けている影響というのは、インターネットのおかげで、国境が非常に無くなってきている。例えば、J-POPがすごく好きなのですが、YouTubeが無ければ、こんなにたくさんのJ-POPを知ることができなかったと思います。そういう意味で、新しいものが生まれ、そしてそれがどんどん混ざっていき、ハイブリッドになっていくということが、ポップ・カルチャーが成しえるもっとも素晴らしいことのひとつだと思います。フランスのシーンをひとつとってもいろいろなスタイルを持ったアーティストそれぞれが自分のスタイルをすごく確立していて、それを前に出していくアーティストが増えているので、やはりポップ・カルチャーのハイブリッドさの成せる業だと思います。
■ちなみに、あなたをポップ・カルチャーの世界に引き入れた張本人は誰ですか?
PP:圧倒的にプリンスですね。
■フェイヴァリット・アルバムは?
PP:フェイヴァリット・アルバムというよりも、まず『パープル・レイン』という映画を自分のなかのいちばんのお気に入りで挙げたいです。映画からサントラとしての『パープル・レイン』というのがあって、映画とサントラというひとつの世界観が作られたという意味で、自分がそんなものを作ることができたら良いなと思える憧れの見本みたいな存在です。
■さっきからJ-POPの話が出ていて、実際に今回の “プラネット・トウキョウ”と7曲目の “チェンバー・ホテル” にすごくJ-POPを感じました。この2曲はJ-POPですよね(笑)?
PP:本当におっしゃる通りです(笑)。日本の80年代のポップ・ミュージックの作られ方というものにすごく憧れを抱いています。日本のアーティストはすごく技術が高いというのがいちばんに言えることです。日本の80年代の音楽は、スタジオ・ミュージシャン、スタジオでの作業というものが、非常に高みにあがった時代なのではないかと思います。例えば、シンセにしても、ローランドやヤマハ、コルグ、そのあたりが日本で非常に発展した時代だと思っていて、日本はラボそのものなのではないかと思えます。もっとも新しいマシンがあって、もっとも新しい音があって、それになおかつテクニックと音楽的要素がちゃんと重なっている。そういう意味で、このアルバムのコンセプトになっているのが、80年代の日本の音楽であると思います。
■あなたは80年代のJ-POP、日本の音楽を聴いて何を想像しますか?
PP:80年代の日本の音楽から連想させるものは、大きな喜びとポジティヴさだと思っています。それは自分にとって音楽をやる上ですごく大切なエモーションでもあります。要するに、ナイーヴとも言えるような善良さというものが、音楽から滲み出てくるというのが非常に自分の心を打つんですね。あとはジャズの影響というものもベースやギターのプレイに感じられます。例えば、アメリカのスティーリー・ダンみたいな感じで、英語で歌を歌ってみたり。そういう日本のアーティストのアプローチがすごく自分にも通じるところがあると思っていて、同じようなことを自分もフランス語でやっていると思うんです。例えば、YMOはクラフトワークのオリエンタル版だと思っているのですが、クラフトワークと違ってそこにすごく温かいもの、何かもっと人間的なものを感じます。『増殖』はラジオ仕様になっていたりとか、ジョークをつねに言っていたりとか。あのアルバムでのアプローチというのはすごい大好きです。
■『増殖』はのギャグは、日本語だからなかなか意味はわからないと思うのですけど?
PP:しかしあのアルバムのなかで、英語で会話をしているのに日本語で答えたりしている部分があると思うんですが、すごく自虐的でアイロニカルで面白いと思っています。足が短いとか、性器が小さいとか、そういう話をしていると思うんですけど、そういうところがじつはすごく好きで、自分のクリップでもアメリカ的なものをコピーしたというか、自分なりに解釈してやったというのがあるんですけど、そのなかでも、フランスパンを使ったり、チーズを使ったりして、他の文化に対するちょっとした勘違いというものってよくあると思うんですけど、そういった異文化へのファンタジー、ファンタジーというか、勘違いのなかで生まれてくる新しさみたいなものがすごく大好きです。
■80年代の日本の音楽に関していうと、バブル経済真っ直なかの音楽だから日本人はものすごくそれに対するアンビヴァレンスというか、憧れを持っている世代もいるいっぽうで、ぼくなんかはモノによっては素直に向き合えないところがあるんですけどね。
PP:まずひとつ思うのが、国が悪いときにアーティストは良いものを生み出すのではないかと思うんですよね。クリエイティヴィティが刺激されているんじゃないかと思うんです。だからきっと日本の人にとってはYMOの見づらい部分というものが、僕たちの心を打つところでも実はあるんじゃないかなと思っています。これは自分の場合なのですが、東京に初めて来たときに、自分がまったく知らない本当に新しい世界に来たというふうに思いました。暮らし方からしてもそうですし、言語もそうですし、なにもかもが新しくて。そういった意味で、新世界を発見したみたいなところがすごく引き付けられる大きな部分だと思います。そのなかに少し入ってみて感じるのは、生活のなかにある相反する要素。例えば、日本ってけっこうポルノっぽいものとか、ゲームだったりとかが日常のなかに溢れていて、そういう騒々しいもの、猥雑なものと、それから伝統的なものとか、禅の考えとか、風水的な考えとかが、本当に自然に共存していると思います。フランスでは考えられないです。
■たしかに。
PP:例えば、アルバムのなかで "レプティル(Reptil)” という曲があるんですけど、これはフランスで起きたテロを経て作った曲なんです。やっぱりフランスのアーティストでテロの影響が直接的でも間接的でもアルバムに現れているアーティストというのはすごく多くて、そういった意味で、国の状況というのが自分たちのクリエイティヴィティに与える影響はすごく大きいと思うし、テロに関して今後も自分たちの音楽のなかに何かしらの影響を及ぼすんじゃないかな。
■なぜレプティル=爬虫類だったのですか?
PP:これはこのアルバムで最初に書いた曲で、テロがあったその夜に書きました。1時間くらいで書きあがったんですけど、そのときはすごく悲しい気持ちで書きました。爬虫類というのは、相手を食べてしまったり、自分の仲間すらも食べてしまうような種族なので自分にとってすごくアグレッシヴなものの象徴です。でも自分はそこからどうやって自由でいるかということを歌っています。
ただ、アルバムを作っていくにあたってムードイドの音楽というのは、もっと喜びに満ちていて、そして、いろいろなヴァラエティに富んだものであるべきだ、そして、希望が感じられるようなものであるべきだと思ってきたんです。結局そのあと、曲やアルバム自体が仕上がったときに、このアルバム全体を聴いてみると、もっとお祭り騒ぎ的なものとかも入っていると思っていて。そのお祭り騒ぎというのは結局あの夜テロリストによって、壊されたものだと思うんですけど、その壊されたもののなかから、どうやって生き延びて、自分たちの自由をキープしながら、どうやってお祭り騒ぎを続けていくのか、どうやって愛を重ねていくのか、というようなことを自分は最終的に歌っているんじゃないかなと思います。
■ありがとうございました。
取材の翌日、ぼくは代官山のクラブでの水曜日のカンパネラのライヴを見にいった。途中コムアイに呼ばれると、ギターを抱えたムードイドはステージに上がり、コラボレーション曲を披露した。それはなんとも微笑ましい一幕で、それはどう考えても、未来という方角に向かっているようだった。