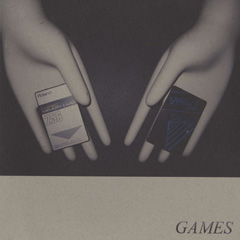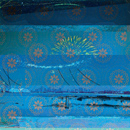1. Toddla T ft. Wayne Marshall / Sky Surfing | Ninja Tune
トドラ・Tとは、ダンスホール・スタイルのマイク・スキナーと評価されているシェフィールドのDJで(まだ25歳ぐらい)、2009年に最初のアルバム『スカンキー・スカンキー』を〈1965〉から発表している(僕はかなり好みだった)。暗い感覚が多くを占めるUKのアンダーグラウンドにおいて、異例と言える陽気さを持っている人で、彼の音楽の売りのひとつである"笑えるリリック"がわからなくても、グライムとダンスホールのハイブリッドなポップ・ヴァージョンとして楽しめる。で、その明るさ、その音楽性を考えれば〈ニンジャ・チューン〉ほど彼に納まりの良いレーベルもなくて、これは移籍第一弾のシングルとなる。
"スカイ・サーフィン"はジャマイカのMC、ウェイン・マーシャルをフィーチャーしたご機嫌なダンスホール・ナンバーで、リミキサーはベンガ、新人のドウスター(Douster)、グラスゴーのベテラン、DJ Q、で、もうひとりもベテランで、ロス・オートン。オリジナルでは今年流行の絶頂を迎えているオートチューンを使い......、だからもうその声はいい加減聴き飽きたぜよと思うのだが、ウェイン・マーシャルのガッツ溢れるラップがこのエレクトロ・ダンスホールに生気を与えている。そして、これでもかと言わんばかりのアッパー・チューンをベンガはダークなサイバー・テイストに、新人のドウスターはポスト・ダブステップへと変換する。『スカンキー・スカンキー』の共同プロデューサーであるロス・オートンはさらにそれをレゲエ色を強め、ファンキーなシンセベースを注入し、DJフレンドリーに仕上げている。セカンド・アルバムのリリースは来年だそうだ。
2. Subatomic Sound System Meets Ari Up & Lee Scratch Perry / Hello, Hello, Hell Is Very Low / Bed Athletes | Subatomic Sound

アリ・アップにとって遺作なってしまったのがこの7インチで、彼女が急逝する2ヶ月前にリリースされている。両面とも『スーパー・エイプ』に収録された有名な"アンダーグラウンド"を使い、アリ・アップは彼女のラバダブを披露している。ラバダブ(Rub A Dub)とは、既存のレコードに上に新たに歌をのせたり、トースティングしたりするジャマイカのDJスタイルで、アリ・アップはリー・ペリーとともに、このクラシカルなリディムの上に素晴らしい声を乗せている。A面ではダブステップのテイストを取り入れ、そして後半にはオーガスタス・パブロのピアニカのような音色を響かせる。B面は、同じく"アンダーグラウンド"をネタにアリ・アップがセクシーで陽気なダンスホール・スタイルで歌いまくる。スピリチュアルでユーモラスな1枚。そして聴いて元気になる1枚だ。ファンなら絶対に買い。
3. Games / Everything Is Working / Heartlands | Hippos In Tanks
OPNのダニエル・ロペイティンが(ジョエル・フォードなる人といっしょに)チルウェイヴをやってる! と言われれば三田格でなくとも興奮するでしょう。この7インチ、A面の"エヴリシング・イズ・ウォーキング"が素晴らしい。ウォッシュト・アウトが永遠の夏なら、こちらは恍惚としたぬかるみとでも言いましょうか。まるでブリアルがダウンテンポ・ディスコをやったようなビートと儚く消えていく声という声、途中で入るギターのアルペジオが少々臭いが許そう......せめて10分ぐらいのロング・ヴァージョンで聴きたい。B面の"ハートランズ"はジェームス・ブレイクとウィッチ・ハウスの溝を埋めるかのような亡霊の歌の入ったダンス・ナンバーで、まあ、悪くはない。このプロジェクトのアルバムが出たら本当にすごいことになりそうだ。
4. James Blake / Klavierwerke EP | R & S Records
 今年のナンバー・ワン・シングルはこれで決まり......いやいや、ちょっと待った、ネットで出回っているこれもまたすごいのよ。とにかくいま、12インチを買って家で聴いて驚きを感じるひとり、ジェームス・ブレイクのこの夏の大ヒット曲"CMJK"に続くシングルは、早速その手法(R&Bサンプルのグロテスクな応用)をいろんなところでコピーされたと思いきや、今度は違う角度から攻めてきた。アグラフのセカンド・アルバムと同じようにこれもピアノをテーマにしているが、しかしアグラフとはまったく違う方角を向いている。これは......ダークサイド・ミュージックで、ロンドンの汚れた街がよく似合うポスト・ダブステップである。
今年のナンバー・ワン・シングルはこれで決まり......いやいや、ちょっと待った、ネットで出回っているこれもまたすごいのよ。とにかくいま、12インチを買って家で聴いて驚きを感じるひとり、ジェームス・ブレイクのこの夏の大ヒット曲"CMJK"に続くシングルは、早速その手法(R&Bサンプルのグロテスクな応用)をいろんなところでコピーされたと思いきや、今度は違う角度から攻めてきた。アグラフのセカンド・アルバムと同じようにこれもピアノをテーマにしているが、しかしアグラフとはまったく違う方角を向いている。これは......ダークサイド・ミュージックで、ロンドンの汚れた街がよく似合うポスト・ダブステップである。
前作同様に今回も4曲。歪んだベースが心臓の鼓動のように鳴り続ける上を蜃気楼のようなサンプリングが流れ、ブリープ音と合流する"クラヴィアヴェルク"。これもテクノやハウスともクロスオーヴァーできるトラックで、まあ、UKでクラブ・ヒットするのもうなずける。続く"ドント・ユー・シンク・アイ・ドゥ"もメロウで良い曲だ。ちまたにあるその他大勢の曲とくらべればずいぶんとぶっ飛んだ曲だが、ここには人を惹きつける美しいメロディがある......が、実を言うとB面の1曲目に収録された"アイ・オンリー・ノー"こそこのシングルにおける最高の瞬間だ。ピアノからはじまり、幽霊声がメロウに流れていく。ピッチは遅めで、シンプルなドラムとメランコリックなピアノの断片が空間を彷徨い続けている。
かつてワイルド・バンチがアメリカのヒップホップとジャマイカのレゲエをブレンドして独自のハイブリッド・ミュージック(ブリストル・サウンド)を作ったように、ジェームス・ブレイクはアメリカのR&Bとダブステップをブレンドしてこの時代のストリート・ミュージックを創造している。ブリアルの次は彼だ。
5. Model 500 / OFI / Huesca | R & S Records
ゴッドファーザーの復帰作である。それだけで充分だろう。デトロイト・エレクトロここにありだ。しかも歌っている。36歳の伊東輝悦は清水エスパルスを解雇されてしまったが、来月48歳になるホアン・アトキンスはまだ現役なのだ。そして、多くのファンはこのシングルにモデル500の永遠のクラシック"ノー・UFOズ"を聴くだろう。マイク・バンクスによるリミックスは実際に"ノー・UFOズ"のシンセ・ベースラインが加えられ、デトロイトの伝説の復活を解説する。アトキンスはその心意気に応えるように、「アイム・フライング」と"ノー・UFOズ"のサビを歌う。俺はいまもぶっ飛んでいる。そう、ホアン・アトキンスこそデトロイト・テクノにおいてもっともぶっ飛んだ男である。そしてB面の"ヒュースカ"、これ、半分以上はマイク・バンクスの曲だと読んだ。