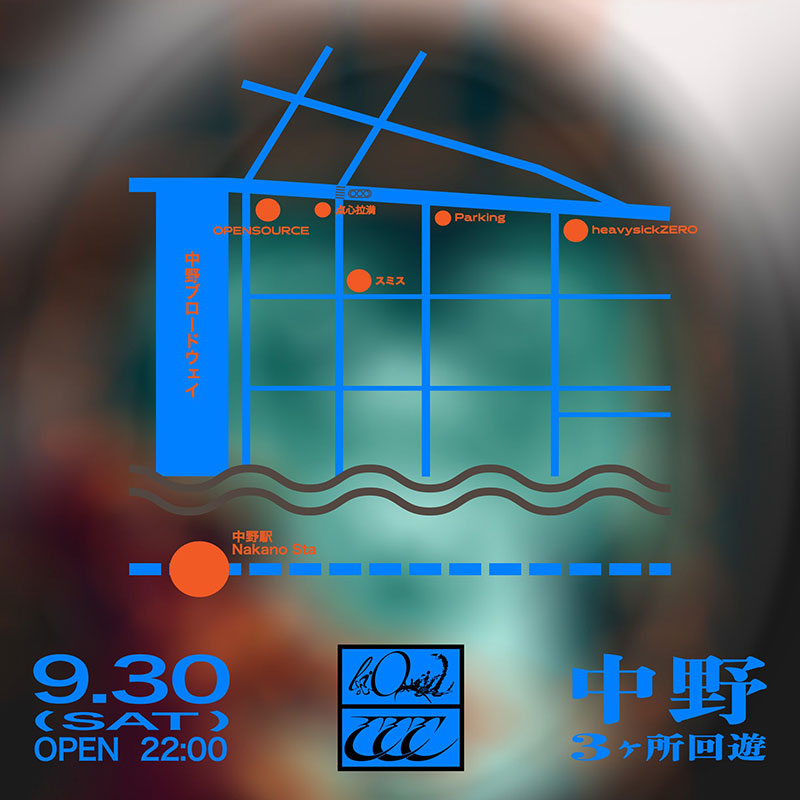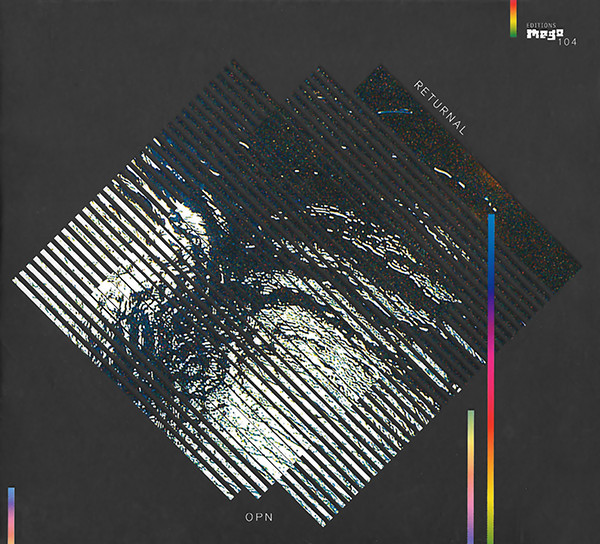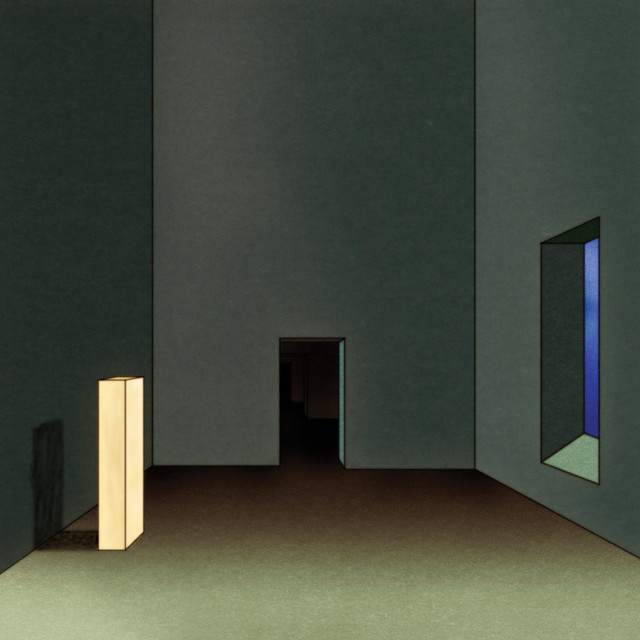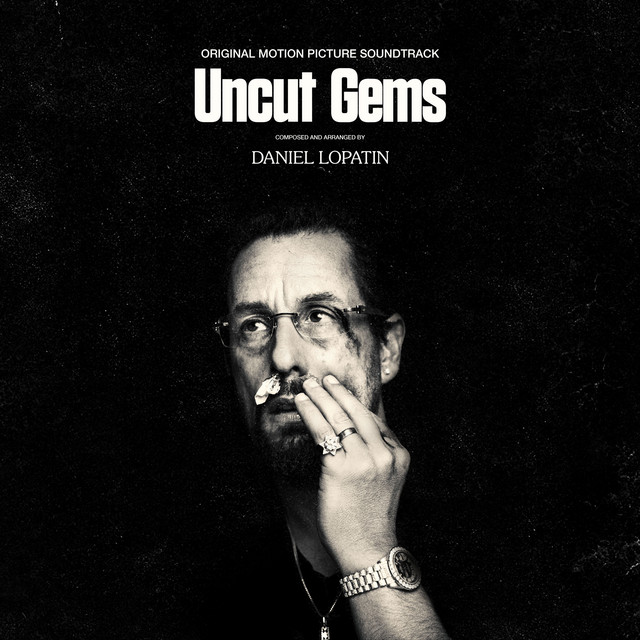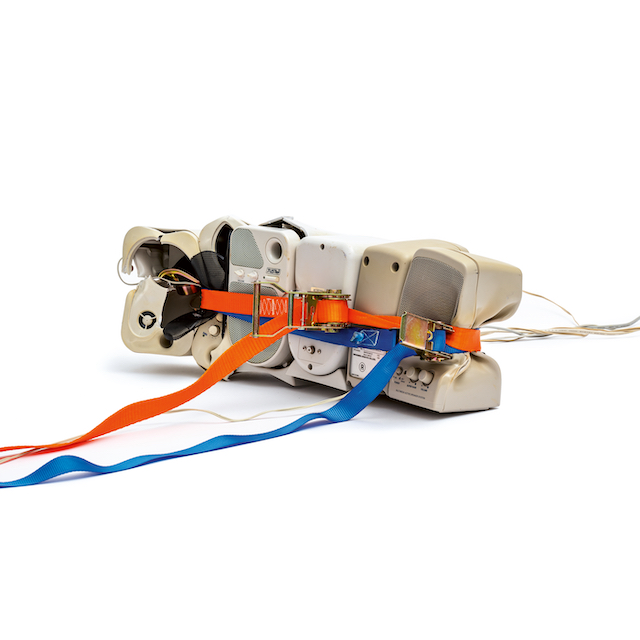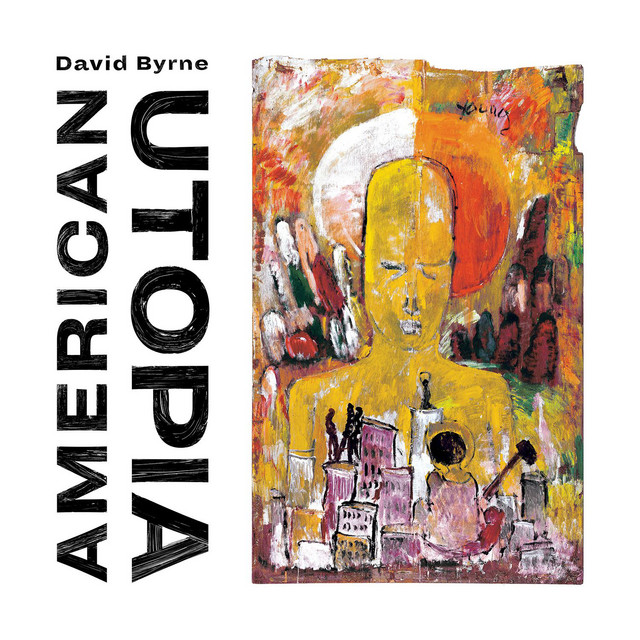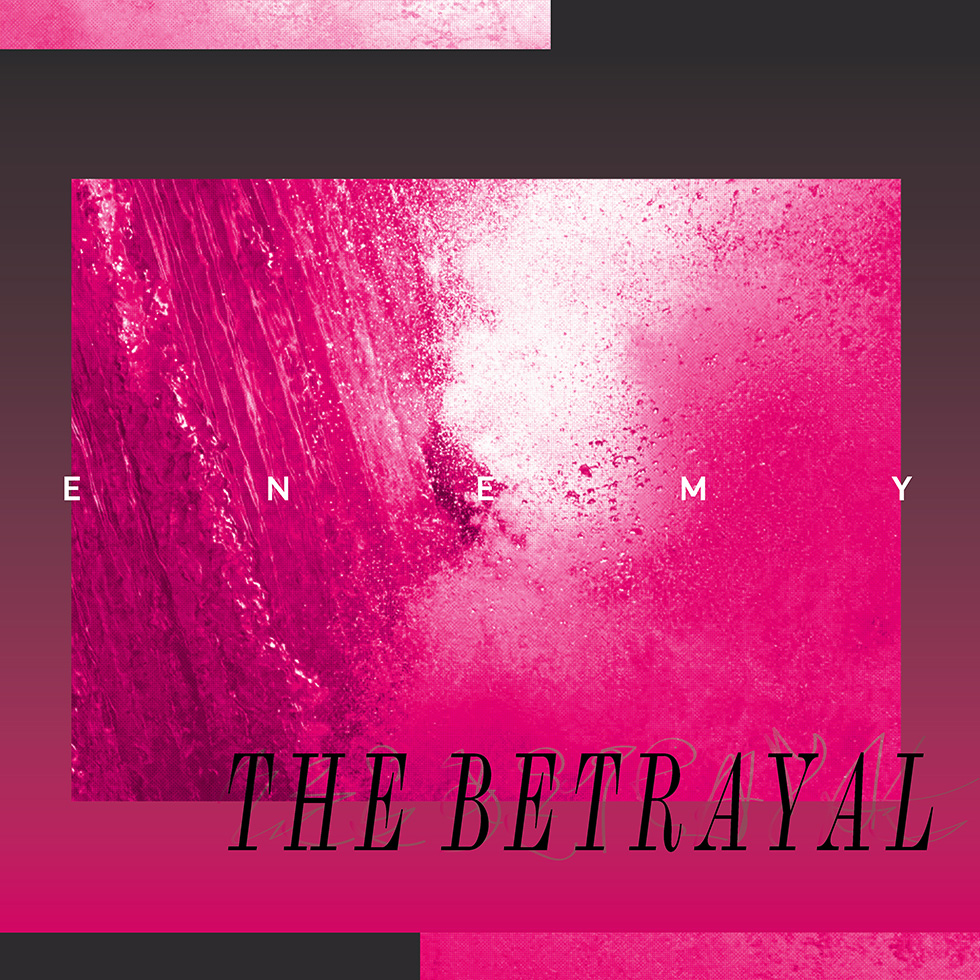ゲーム音楽を追ってきた耳にとって、最初に大きなインパクトがあったのはLFOをはじめとするブリープ・ハウスでした。ものすごく音がそぎ落とされているところに、大昔のゲーム音楽や後のチップチューンに繋がるものを感じましたし、当時テクノ・ハウスと呼ばれていたものとも違う新しい波も感じていました。ただそのときはまだ〈Warp〉というレーベルを意識していたわけではなかったんです。
90年代初頭はクラブ系のテクノの知名度が日本でも高まってきた時期ですが、その頃いわゆるハードコアが中心だったところに、正反対ともいえるアンビエント志向のものが出てきた。正直なところ最初はピンと来なかったんですが、それでも新しさに惹かれて追いかけていくなかで、最初に愛聴したのは〈Apollo〉から出ていたエイフェックス・ツインの『Selected Ambient Works 85-92』(92)だったかな。それを経て『Artificial Intelligence』(92)に辿り着きます。ここでやっと〈Warp〉というレーベルを意識するに至り、そのあとにLFOも同じレーベルだったのかと気づく。「なるほど、まだジャンルとして固まっていないものをいちはやく形にしていくレーベルなんだ」ということがわかってきて、〈Warp〉の先見性が見えてくる感じでしたね。
93年~94年にかけて有名どころは一通り聴いていたと思います。ザ・ブラック・ドッグやエイフェックス・ツインといった『AI』の軸線上のものはもちろん、ケニー・ラーキンとかリッチー・ホウティンあたりのデトロイト系アーティストのものも好んで聴いていましたね。
いい意味で想定外というか、予想を遥かに上回るものが出てきたなと感じたのは、特にオウテカ、セイバーズ・オブ・パラダイス、スクエアプッシャー。僕にとってはまさに先見性の塊という感じで、どれも「こういう音楽があっていいんだ」という衝撃がありましたね。オウテカで初めて聴いたのは『Amber』(94)でしたが、より衝撃だったのは大化けした『Tri Repetae』(95)以降。セイバーズ・オブ・パラダイス『Haunted Dancehall』(94)は、僕にトリップホップの醍醐味を教えてくれた大事な1枚です。
スクエアプッシャーは、やはり『Hard Normal Daddy』のインパクトが大きかった。エレクトロニック・ミュージックとそうじゃないものの境界をこれまでにない感覚で攻めている印象があって、まさに僕にとっての〈Warp〉らしさ、つまり「ジャンルとして固まっていないもの」への貪欲さを感じました。
〈Warp〉が繰り出してくるような音楽は、おなじエレクトロニック・ミュージックでもゲーム音楽とは相容れないというか、ゲーム音楽でやるには先進的すぎるシロモノという認識で、「こういうものがゲーム音楽にも入ってきたらいいなあ」と思う一方で、「まず入ってこないよね」みたいな感覚でした(笑)。でもゲームの外側でなら、そのふたつを接合できるのではないかというところで、チップチューンに意識が向いていったところもあります。当時はエレクトロニック・ミュージックとチップチューンを接合しうる領域としてエレクトロがあったのですが、そういえば〈Warp〉は一時期エレクトロ方面でも攻めていましたね。LINK、Jake Slazenger、ドレクシアなど。ダンス・ミュージックとしてチップサウンドを開拓することは可能か? ということに当時心を砕いていたので、そのあたりの音源や、〈Rephlex〉や〈Clear〉といったエレクトロのレーベルにより関心が向くようになりました。チープなエレクトロ、たとえばDMXクルーなどは非常に参考になりましたね。あるいはアタリ・ティーンエイジ・ライオット周辺とか、kid606の〈tigerbeat6〉とか。この時代にはハードコア寄りの音とチップチューンの距離が意外と近くて、〈tigerbeat6〉からコモドール64のコンピレーションが出たりしていたんですよ。
そんな感じで00年代になると〈Warp〉からは耳が遠ざかっていくんですが、それでもプレフューズ73やクリス・クラークなどは折に触れて聴いていましたね。なんだかんだで、ちょっと一筋縄ではいかない感じのエレクトロニカが結構好きなんですよ。「え、こんなのも〈Warp〉から出るの?」という意味では、バトルズにも驚かされました。
2010年代になると〈Warp〉の動向には疎くなるんですが、日本のゲーム音楽のドキュメンタリー『Diggin' in the Carts』(2014)の企画で出演依頼などが来たときに、フライング・ロータスやハドソン・モホークといったゲーム/ゲーム・サウンドに影響を受けたエレクトロニック・ミュージシャンがいることを知りました。ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーも、そんな流れのなかで発見したアーティストです。
既存のジャンルの枠組では表現できないなにかを持っているアーティスト、というのが最初の印象でしたね。そこはとても〈Warp〉らしいなと。2010年代の作品はどれも研ぎ澄まされていますが、個人的にはその前の、アナログ・シンセを主体にしている作品、特に『Rifts』に好きなところが詰まっています。
彼の音楽を聴いて興味深かったのは、映画なども含め、かなりいろんな音楽・音響のありかたを「体験」として積み重ねてきたひとなのだろうなということです。それら多くの体験のひとつにゲーム・サウンドがあった。ゲーム音楽から直接的な影響を受けているというよりも、ゲームをひとつの音響的な体験として吸収しているのだろうなと感じます。
彼は以前のインタヴュー(http://monchicon.jugem.jp/?eid=1891)でゲームの音について言及していました。そこで、ゲームの音楽それ自体についてはそれほど面白いとは思わないけれど、映像と音の(ミス)マッチングという面から独特な体験をゲーム音楽は与えてくれると言っています。普段ゲームにどっぷり浸っているわれわれのような人間からすると、すでに慣れてしまっているのでわかりにくい感覚ではあるのですが、たとえば弾幕シューティングの後ろでフュージョンが流れているというのは、よく考えてみると不思議な組み合わせではありますよね。OPNはそのギャップみたいなところも含めて面白いものとして受けとっているそうです。ゲーム音楽産業の内側からはできない形で、ゲームと音楽の関係の楽しみ方を広げてくれるアーティストとして、彼には注目していますね。
ちなみに、今回の新作では音楽生成AIが使われているようです。ゲーム・サウンドにおけるAIの活用もいままさにスポットライトを浴びつつある領域ですが、実はゲーム音楽とAIの歴史には蓄積があります。古代祐三さんという作曲家がいて、ハドソン・モホークが影響を受けたことを公言している方ですが、彼がメガドライブのゲーム『ベアナックルIII』(1994)──海外で非常に人気のタイトルです──の音楽をつくる際に、早くもAIを利用しているのです。OPNを出発点に、そういった歴史を紐解いてみるのも面白いかもしれませんね。
※当記事は小冊子「ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとエレクトロニック・ミュージックの現在」に掲載された文章の未発表ロング・ヴァージョンです。