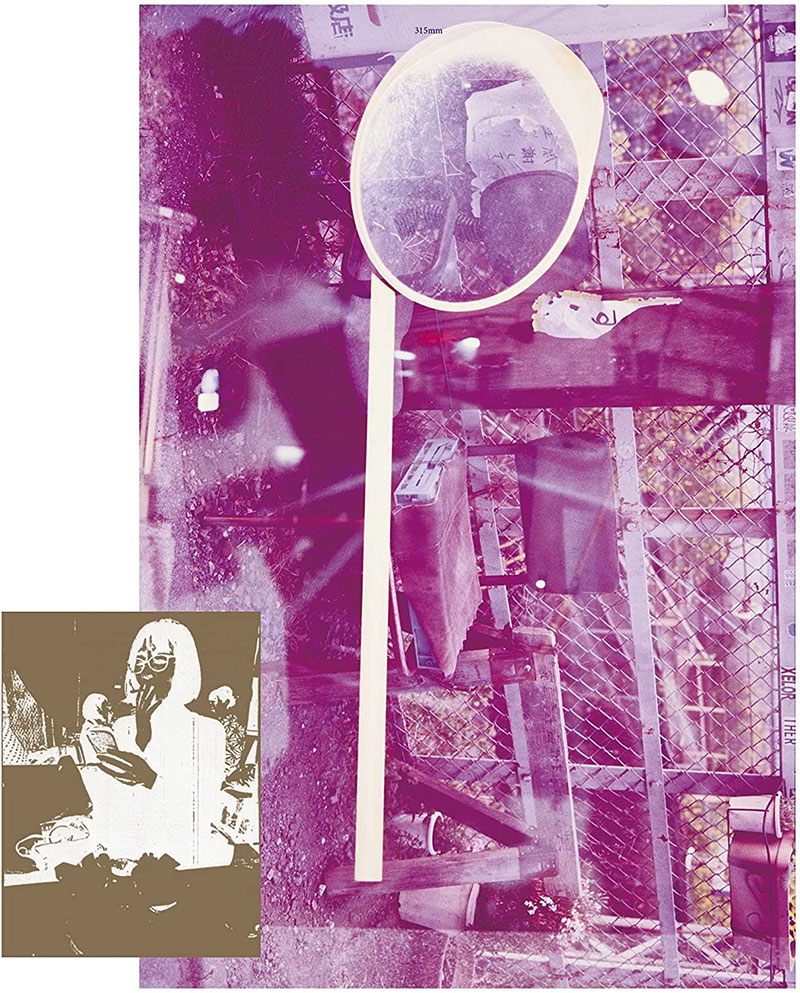ニューヨークのアーティストとは、「生き延びるために創造しないといけない必要性」があるひとたちなんだと思う。競争が激しいし、物価や生活費も高い。だから生き延びるために精力的に活動しないといけない。ニューヨークでアーティストとしてやっていくのは昔から非常に困難なことだった。たくさんの血と汗と涙を流さないとやっていけない。
都市の喧騒が聞こえる。行き交う人びとの姿が見える。彼らはそのテンポを「ダウンタウンのペース」と呼んでいるが、これは、街から生まれたノイズを使って身体を揺らそうとする者たちの音楽だ。
ニューヨークのブルックリンからイキのいいガレージ・バンドとして2010年代初頭に登場し、ぶっきらぼうだがオリジナル・パンク~ポスト・パンクへのたしかな敬意を感じさせた3作目『Sunbathing Animal』で世に知られたパーケイ・コーツは、00年代なかばのディスコ・パンク/ポスト・パンク・リヴァイヴァルにも、00年代後半のブルックリン・シーンにも間に合わなかったからこそ、特定のシーンに絡め取られることなくマイペースに自分たちの音楽を拡張してきた。その間ノイズをやったりヴェルヴェット・アンダーグラウンドっぽいことをやったりハードコアのルーツを意識したことをやったりしているのだが、バンドとしてのまとまりとパフォーマンス性を一段引き上げたのが、いくらかダンス寄りになった前作『Wide Awake!』だった。初期から持っていた猥雑な音の感触は残しつつも、パーカッションや電子音を整頓して配置することでデザイン性を高めたのである。
そして、その路線を推し進めたのが、(変名バンドParkay Quartsやダニエル・ルッピとのコラボレーション作を除いて)通算6作目となる『Sympathy for Life』だ。バンド・メンバーたちはアルバムを作りながら、COVID-19によるロックダウンをまだ知らないニューヨークのインディ・パーティで踊っていたという。ストンプ・ビートとワイルドなベースラインが痛快な “Walking at a Downtown Pace”、ポスト・パンク・バンドがサーフ・ロックをカヴァーしたような “Black Widow Spider”、パルスめいた電子音がユニゾン・コーラスとゆったり絡み合う “Marathon of Anger” と、テンポを変えつつも足腰を動かすロック・チューンが続く。同じくニューヨークのLCDサウンドシステムや!!!のように、ハードコア・パンク育ちのキッズがテクノやハウスに触発されて生み出した音楽の系譜を受け継いでもいるだろう。
アルバムは本格的なパンデミック以前に完成していたというが、ある意味、ロックダウンによってニューヨークが(一時期)失っていたものを封じこめた作品だと言える。人びとが狭い地下やビルに一室や路上に集まって踊ること、そこで交わした社会的/政治的議論を生かし、ともに声を上げること。パーケイ・コーツは以前から歌詞に都市で生きることのジレンマや苛立ちをミックスしてきたが、パンデミックを経たことでその個性がよりクリアに見えることになった。彼らはこのアルバムで、踊って考え、考えて踊っている。以下のインタヴューでヴォーカル/ギターのアンドリュー・サヴェージはパーティ文化をコミュニティと表現しているが、パーティは都市に生きる人間たちにとって考えや価値観をシェアする場としても機能しているのだ。また、ロックダウンによって人びとの集まる機会が失われた2020年のニューヨークにとって、ブラック・ライヴズ・マターが再集結のきっかけだったという証言も興味深い。パーティに通っていたひとたちが、デモの現場で久しぶりに再会するなんてこともあっただろう。
パーケイ・コーツによる「ダンサブルなロック」は、ロック・リスナーがただ気持ち良く踊れるように設計されて提供されたものではない。異なるジャンルの音楽を聴いていたはずの人間たちが一堂に会して同じリズムで踊り、そこにこめられた問題提起と向き合うものとして、『Sympathy for Life』は野性的なグルーヴを展開している。
ブラック・ライヴズ・マターの抗議活動は、人びとを再び集結させる上で非常に重要な出来事だったと思う。怒りが昂っていたし、とても感情的な雰囲気ではあったけれど、同時にポジティヴな空気も感じられた。ニューヨーカーたちの間では「みんないっしょに乗り切ろう」という意気込みがあった。このような団結力は、俺がこの街に10年以上住んでいていままで見たことがないようなものだった。
■いま、海外のミュージシャンのライヴが観られない状況なのでもはや懐かしい気持ちになるのですが、2018年わたしはフジロックであなたたちのステージを観て、すごく踊って最高の気分になりました。『WIDE AWAKE!』、そして本作『Sympathy for Life』とダンサブルなロック・アルバムが続きますが、これはあなたたちにとって自然な流れだったのでしょうか?
アンドリュー・サヴェージ(以下AS):そう思うね。いままでのバンドの進化というものはすべて、自然な流れだったと思う。変化や進化というものを無理に起こそうとしても、それは見え透いたようになるだろうし、もしかしたら気取っていると思われるかもしれない。でも俺たちはそれには当てはまらないと思う。バンドの11年の活動を見れば、バンドの重要な進化に気づいてもらえると思う。俺たちはいま、サウンドもヴィジュアルもファースト・アルバムのときと違うし、5枚目のアルバムのときとも違う。それはつまり俺たちが人間として進化し、俺たちの志向や音楽に対する考え方が進化し、ニューヨーク・シティという俺たちが住んでいる世界で生活していることの意味や、地政学に対する考え方が進化していることが反映されているからだと思う。そういうものの影響は受けているし、世界も進化しているからね。そういう意味で自然な流れだったと思う。それに、バンドとして同じことを繰り返したくないという思いもある。だから意識的に、バンドとしてのコアなアイデンティティを変えずに、どうやったらいままでとは違うことができるかと考えている部分はあるね。
■アルバムはパンデミック前にニューヨークのパーティに通ったことに影響されているとのことですが、どのような音楽がかかるパーティに行っていたのでしょうか?
AS:ロックダウンになる前の話になるけど、俺はレイヴ・カルチャーに興味を持ちはじめた。だからおもにテクノ・ミュージックだ。オースティンは何年も前からディスコ寄りの音楽のDJをしていて、〈ザ・ロフト〉という昔からあるディスコのパーティに行っていたよ。
■あなたたちの音楽は、たとえば70年代のニューヨークのアート・ロックからの影響もありますが、もともと自分たちはニューヨークのバンドだというアイデンティティ意識は強い方ですか?
AS:強いほうだと思う。ただ、「ニューヨークのアーティスト」というものが何なのかということが明確ではないから答えにくい質問ではあるね。たとえば、「70年代のニューヨークのアート・ロック・シーン」など人びとが強いこだわりを持つ分野もあるように、ニューヨークは文化的な文脈で定義されることが多いと思う。つまり、あるひとが想像するニューヨークとは、感情的・文化的な経験がもとになって定義されることが多いと思うんだ。だけど、ニューヨークという街を定義するのは難しい。この街はつねに変化しているという性質を持っていて、静止しているということがない。だから「ニューヨークのアーティスト」が何であるのかを定義することが難しい場合もある。俺が思うにニューヨークのアーティストとは、「生き延びるために創造しないといけない必要性」があるひとたちなんだと思う。ニューヨークは競争が激しいし、物価や生活費も高い。だから生き延びるために精力的に活動しないといけない。それはどんな時代でも、どんな文化的要素に紐つけようとしても共通していることで、ニューヨークでアーティストとしてやっていくのは昔から非常に困難なことだった。たくさんの血と汗と涙を流さないとやっていけない。俺たちには昔からそのメンタルが備わっているからニューヨークのアーティストだと言えると思う。
■ニューヨークはパンデミックの影響をとくに大きく受けた街だと思うのですが、あなたたちの音楽制作やこのアルバムに対して、パンデミックはどのような影響を与えましたか?
AS:パンデミックがはじまる直前のほんの数日前にアルバムの制作を終えていたから、音楽制作には影響を与えなかった。でもアルバムのリリースには影響を与えた。理想としては2020年9月にアルバムをリリースするはずだったんだけど、それは実現されなかった。その代わり、というかそのおかげで、どうやってアルバムをリリースしていくかという方法について考える時間が増えたから、それについてじっくり考えることができた。たとえば、アルバムのすべての曲でミュージック・ヴィデオを作ることにしたから11のミュージック・ヴィデオが公開されるし、アルバムのプロモーション企画として11のイヴェントが予定されている。それから俺はアルバムのアートワークをすべて担当しているんだけど、今回のアルバム・アートワークには制作に手掛けられる時間に1年間の猶予が生まれた。2020年9月にアルバムをリリースしていたら、これらのことはすべて不可能だった。ツアーができなくなってしまったから、従来の方法でアルバム・プロモーションができなくなってしまったから、こういう流れになったんだけれど、このタイミングでアルバムをリリースできたことは良かったとじつは思っている。パンデミック当時、ニューヨークは俺がいままでに見たことのないような状況だった。最初はものすごく静かだった。
そして去年の夏にブラック・ライヴズ・マターの抗議活動が起こり、それは、人びとを再び集結させる上で非常に重要な出来事だったと思う。そのときに人びとは再び外に出るようになった。人びとの怒りが昂っていたし、とても感情的な雰囲気ではあったけれど、同時にポジティヴな空気も感じられた。ニューヨーカーたちの間では「みんないっしょに乗り切ろう」という意気込みがあった。このような団結力は、俺がこの街に10年以上住んでいていままで見たことがないようなものだった。だからパンデミックの影響で世界は大きく変わってしまったけれど、そこからポジティヴなものも生まれたと思う。
■あなたたちのこれまでの楽曲はよくデザインされたものだったように思います。本作では長時間の即興演奏がもとになったそうですが、それはこれまでの方法論とかなり異なるものだったのでしょうか? そして、その方法はこのアルバムにどんな影響を与えましたか?
AS:まったく異なるものだったよ。アルバムの曲のなかでも、従来の作曲方法で作られたものはいくつかある。“Walking at a Downtown Pace”、“Pulcinella”、“Sympathy for Life” などがそうだ。だけど、今回の新しい方法は40分の音源──おもに俺たちが即興演奏をしているもの──をテープに録音して、ロデイド・マクドナルドの協力を得て、それをひとつの曲にエディットしてまとめていくという方法だった。コラージュを作ることをイメージしてもらえればわかりやすいと思う。
■『WIDE AWAKE!』はデンジャー・マウスがプロデュースでしたが、本作でプロデュースに関わったロデイド・マクドナルドとジョン・パリッシュはどのような役割を果たしたのでしょうか?
AS:ロディ(ロデイド)は先ほど話したように、エディットをするというプロセスで重要な役割を担っていた。彼はその方向性にバンドを向かせていってくれた。彼はアルバムの音を操作して様々なテクスチャーを加えてくれた。ギターの音をシンセに通して、アルバムで聴こえるグリッチーでザラザラとしたテクスチャーを表現してくれたんだ。彼は四六時中でも作業したいというひとで、俺たちと作業したときもノンストップでやっていた。そのいっぽうで、ジョンは音の操作や音に介入するということをほとんどしないひとで、とてもクリーンなサウンドを好むんだ。彼はピュアなサウンドを表現する才能に長けていて、マイクを楽器などに近づけて、その音をそっくりそのままテープ・マシーンに直で伝えることが非常に上手い。完璧にそれをやってくれる。素晴らしいよ。非常にプロ意識の強いひとで、ミュージシャンとしても素晴らしい腕の持ち主だ。彼といっしょに録音したものでは、彼はシンセとピアノを弾いてくれている。このふたりの協力がなければ、アルバムはこのような仕上がりにはなっていなかったと思う。
[[SplitPage]]ニューヨークという街はつねに変化している。だからこそ、現状を表現するということが非常に重要だと思うんだ。アルバムとは、どこでレコーディングされて、どこで制作されて、アーティストがどんなマインドでいたのかという、そのときと場所のスナップショットだと俺は考えている。
■本作においてグルーヴが何より重要だったとのことですが、あなたたちの音楽にとって、グルーヴを生み出すためにもっとも重要な要素は何でしょうか?
AS:何だろうな。(考えて)わからない(笑)、良いリズムセクションがあるのに越したことはないね。
Walk at a downtown pace and
Treasure the crowds that once made me act so annoyed
ダウンタウンのペースで歩いて、
イラつかされたこともある群衆を大切にするんだ
(“Walking at a Downtown Pace”)
■リード・シングル “Walking at a Downtown Pace” はワイルドなパーティ・チューンで、街の息使いが伝わってくるミュージック・ヴィデオも印象的です。あなたたちにとって、ダウンタウンはどんなものを象徴する場所なのでしょうか?
AS:それは、ニューヨークのダウンタウンのことかい? それとも曲で歌っているダウンタウンのことかい?
■曲で歌っているダウンタウンは、ニューヨークのダウンタウンではないのでしょうか?
AS:ああ、確かにそうだよ。その両方について話せばいいか。曲のヴィデオは、ニューヨークの現状を非常にうまく切り取っていると思う。先ほども話したようにニューヨークという街はつねに変化している。だからこそ、現状を表現するということが非常に重要だと思うんだ。ニューヨーク出身のアーティストとして俺たちは、そのときの瞬間を定義しようという狙いがある。アルバムとは、どこでレコーディングされて、どこで制作されて、アーティストがどんなマインドでいたのかという、そのときと場所のスナップショットだと俺は考えている。このヴィデオは、制作された2021年夏のニューヨークがどんな感じだというのを非常にうまく伝えている。ニューヨークがかっこよく描かれていると思うし、曲にすごく合っていると思う。ある意味、ニューヨーク・シティに宛てたラヴ・ソングだと言えるね。
■現在のニューヨークのもっとも好きなところと嫌いなところを教えてください。
AS:いまのニューヨークのもっとも嫌いなところは何もかもが高すぎるということ。物価がどんどん上がっているから、ニューヨークで暮らすことが難しくなっていっている。でも(好きなところとして)通常の生活では、ニューヨークでは素晴らしいイヴェントや体験が可能だ。それもじょじょに戻りつつある。音楽イヴェントも再開したし、美術館も再開した。もう少しで通常に戻ると思う。本当にいまの話で答えると、今日はニューヨークでは初めて秋らしい日で、外はすこし肌寒かった。それが良かった。俺は秋が一年で一番好きだから。だから今日のニューヨークにはとても満足している。
■『WIDE AWAKE!』ではジェントリフィケーションで変わる街が一部モチーフになっていましたし、パーケイ・コーツは「考えるバンド(thinking band)」だとしばしば言われてきました。本作において、あなたたちがとくに考えてバンド内で話していたことは何でしょう? 政治でも社会でも哲学でも、はたまたバカバカしいことでも何でも教えてください。
AS:資本主義というテーマが引き続き探求されている。このテーマはパーケイ・コーツの歌詞にかなり頻繁に登場する。“Black Widow Spider”、“Homo Sapien”、“Application/Apparatus”、“Just Shadows” といった曲は資本主義がテーマになっている。資本主義を批判する視点で歌詞を書いていると同時に、資本主義に加担している身として書いているんだ。俺たちはプロのミュージシャンとして資本主義制度の一部になっているし、資本主義の恩恵を受けている身でもある。だけどそれに批判的になりたいという欲求もある。世界の大都市や世界の大部分が資本主義の恩恵を受けていると言える。パーケイ・コーツは、資本主義から逃れられないことや、資本主義が俺たちに与える影響について歌っていることが多い。それから、このアルバムの強いメッセージとして「コミュニティ」というものもあって、それはパーティなどに遊びにいってそこにいるひとたちといっしょに踊るというような一体感や、ひととひとの間にある空間やエネルギーという概念を表している。人びとが集まっている一体感というものがアルバムで感じられるから、今作は、楽しくてダンサブルなアルバムになったんだと思う。それに素敵なラヴ・ソングもアルバムには入っているよ。それにしても「考えるバンド(thinking band)」と言われるのは嬉しいね。
Young people enjoying urban habitation
Headlights beaming with western potential
都市での居住を楽しむ若者たち
西洋文化の可能性とともに輝くヘッドライト
(“Application/Apparatus”)
What a time to be alive
A TV set in the fridge
A voice that recites the news and leaves out the gloomy bits
こんな時代に生きられて最高だ
テレビ画面が埋めこまれた冷蔵庫
憂鬱な部分を避けながら、ニュースを読み上げる声
(“Homo Sapien”)
■“Application/Apparatus” や “Homo Sapien” ではとくに、テクノロジーに対するアイロニカルな視点が提示されているように思います。このアルバムにおいて、現代の都市のライフスタイルはテーマのひとつだと言えますか?
AS:それはバンドにとってのテーマのひとつだと言えると思うよ。でもアイロニカルな視点と言えるかはわからないな。“Homo Sapien” は辛辣な冗談(サーカスティック)と言えるかもしれないけど、“Application/Apparatus” はアイロニーでも辛辣な冗談でもない。そしてどちらともテクノロジーに対する批判ではないんだ。“Application/Apparatus” はテクノロジーに関与することによって生まれる孤立感について歌っている。それは批判と言うよりはむしろ観察だと思う。“Homo Sapien” は批判ではあるんだけど、多少、からかい半分な感じで批判している。
俺たちはプロのミュージシャンとして資本主義制度の一部になっているし、資本主義の恩恵を受けている身でもある。だけどそれに批判的になりたいという欲求もある。世界の大都市や世界の大部分が資本主義の恩恵を受けていると言える。パーケイ・コーツは、資本主義から逃れられないことや、資本主義が俺たちに与える影響について歌っていることが多い。
■“Zoom Out” というタイトルからはどうしてもヴィデオ通話サービスのZoomを連想してしまいますが、歌われていること自体は、かなりぶっ飛んだ無限の可能性が提示されていますよね。これはパーカッションとベースが効いたワイルドなダンス・チューンですが、どういった精神状態を表したものなのでしょうか?
AS:この曲の歌詞を書いたのは俺じゃないんだ。でも俺の予想では、先ほども話した「コミュニティ」という概念に行き着くんだと思う。けど、わからないな、俺たちは自分たちが書いた歌詞の内容についてあまり話さないんだよ。だから俺の予想でしかないんだけどね。いま、歌詞を思い出しているけど、「When you zoom out, the power is now / When you zoom out, together is now」と歌っている。だから一体感(togetherness)についての歌で、ズームアウトするということは、自己という個人のアイデンティティから、コミュニティという、より大きな規模で俯瞰して物事を見るということなんじゃないかなと俺は思う。
■先ほども少し話に出ましたが、本作に併せた企画「The Power of Eleven」が面白いですね(アルバム収録曲に合わせて世界各地で開催されるイヴェント。その第1弾として、Gay & Lesbian Big Apple Corpというマーチングバンドが “Walking at a Downtown Pace” をマンハッタンで演奏した)。これはどのような目的意識で生まれたアイデアだったのでしょうか?
AS:(ロックダウンの最中は)この先、コンサートなどのライヴ・ミュージックが可能かどうかがわからないという状況だった。そこでコンサートなどがなくても人びとが集まることのできるイヴェントを企画することにしたんだ。この企画をしたとき、世界が今後どのようになっていくのかは不明だったけれど、世界がどんな状況になっても、拡張や縮小が可能な企画にしたんだ。何かのファンであると言うことは、コミュニティの一部であることを意味する。長い間、コミュニティから外れていたひとたちを、バンドの宣伝になるようなクールな体験を通して、再びコミュニティ内に戻してあげるというのがこの企画の狙いだった。
■日本ではまだまだ、パンデミック以前のようにライヴでひとが集まって踊ったり歌ったりするのが難しい状況なのですが、このダンサブルなアルバムをどのようなシチュエーションでリスナーに楽しむことを薦めますか?
AS:自分の家に友人を招いたりすればいいんじゃない(笑)? ひとりで踊ってもいいし。わからないよ、日本の状況がよくわからないからね。自分の家に友人を招いたりしているのなら、自分の家で小規模なダンス・パーティをするのがいいと思う。
■最後に遊びの質問です。パーケイ・コーツにとって最高にダンサブルなロック・アルバムを3枚教えてください。
AS:トーキング・ヘッズの『サイコ・キラー'77』。このアルバムを聴いてたくさん踊った覚えがある。ロック・アルバムだよな? それから、ロキシー・ミュージックのファースト・アルバム。セルフ・タイトルだ。あとはなんだろうな……(しばらく考えている)。シルヴァー・アップルズのセルフ・タイトルのアルバム。